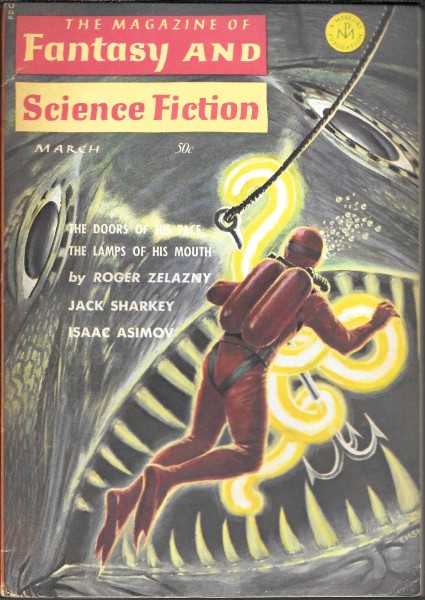ブルーモンスター
原作:フレドリックブラウン
アランフィールド
プロローグ
彼の生涯にスペクトルがあるとすれば、彼の生涯がほとんど怪奇その
ものだったように、それはまさしく、怪奇だった。光のスペクトルが、
赤外線から紫外線に
亙るように、それは、絶望の夜の思考である、ウル
トラブラックから、神が山の上から見おろすように、彼が他人の心、思
考や知識を見おろす、ハイテンションの目覚めや輝きである、インフラ
ホワイトに
亙っていた。しかしその間には、なにかがあって、ブラック
とホワイトの間に、グレーがあるように、単純に接することを拒む、赤
の帯域があった。赤は、激しい
怒りだった。彼の意識が、赤の帯域に差
し掛かると、殺人鬼となり、非常に危険だった。彼はすでに、まったく
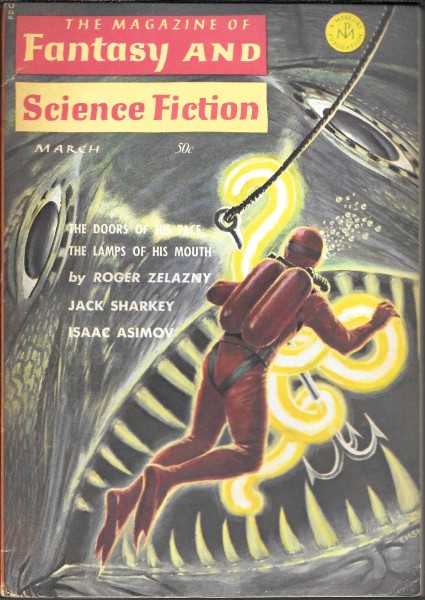
面識のない、ふたりの男とひとりの女を殺していて、捕らえられ、精神
鑑定の結果、ここへ送られてきた。ここは、犯罪的精神疾患リハビリセ
ンターだった。彼はすでにこのリハビリセンターで、彼の名誉のために、
あるいは、不名誉のために、ひとりを殺していた。彼がここへ来て、だ
いたい1年たつ頃、今から3年前のことだが、所員が彼のことを信用し
きっていて、彼の室へひとりで入り、暴行を受けた。彼はその数週間は、
表面上、穏やかで、治療の成果が出ているように見えたので、拘束帯は、
はずされていた。守衛が、彼が集めておいた汚水バケツをあけに行って、
戻ってくるのを、彼は、ぼんやり座って待っていた。すると、立ち上が
り、一瞬の動きで、守衛の背中をフルネルソンで押さえ込んだ。守衛は、
一度だけ助けてと叫んだが、この危険な抱え込みで、壁に打ち付けられ、
意識を失った。助けは1分で来たが、すでに遅かった。その時、彼らが
見たのは、何度も壁や床に打ち付けられたことで血だらけになった守衛
の頭だった。守衛は、一度も意識を回復することなく、数時間後に死亡
した。それ以来だれも、ひとりで彼の室に入ることはなくなった。いつ
もふたりで入り、出るときは、うしろへ下がりながら、常に彼に注意し
ながら出た。殺人の衝動が、いつ彼を襲うのか、前もって分かる者はい
なかった。周期性はなく、識別パターンもなかった。
登場人物
ウォルターフレモント:27才、犯罪的精神疾患収容施設にいる。
クレス医師:フレモント担当の医師。
ブラッドレー:看護婦。
エッシー:看護婦。
1
彼の名前は、ウォルターフレモント、27才だった。23才のときに、
彼は突然、殺人衝動にかられて暴れまわった。大学を卒業して間もない
ときで、それまでは、輝かしい学生で、あらゆる面で将来を期待されて
いた青年だった。確かに、幼年期や少年期を通じて、20代初めにはま
すます、よくある憂鬱な時期や、高揚の時期を過ごした。しかしどちら
も、通常の範囲内で、精神障害が疑われるような過度な緊張に近いもの
は、どこにもなかった。彼は、産業界の精神科医になるべく勉強をした。
その後、数ヶ月間、石油の大手企業の精神科医主任のアシスタントをし
たのが、最初の仕事だった。その時、突然、殺人鬼の赤の帯域が現われ、
彼はそこに入り、意味もなく殺しまくる、殺人マシンとなった。
当然だが、それが、彼のキャリアの終わりとなった。
現在、彼は、明るいグレーの気分にあって、赤の帯域のかなり上で、
ブラックやダークグレイからも、かなり離れていた。廊下を医者と看護
婦が歩いて来る足音がすると、彼は静かに立ち上がり、棒の掛かったド
アのところに行って待った。今日は、医者と話しをするだろう、彼は、
良いモードにあって、その上、欲しいものがあった。ときどき、ダーク
グレイにあるとき、会うのをを避けるために、もっと悪いふりをして、
ときには緊張病のふりをした。腰には、ひもの代わりにゴムを付けて、
フランネルのパジャマに裸足で、棒の内側で腕を組んで立っていた。彼
の場合、パジャマにひもがないことは、重要ではない、それで、だれか
の首を締めてやろうとしない限り。最も悪い抑圧期の底にあっても、人
を殺そうとしたり、殺人衝動に駆られることはなく、反対に、死への恐
怖が、彼の精神が時として下降して、真っ黒な奈落の底へ落ちて行く重
要なファクターだった。自分を傷つけようとしたことは一度もなく、ひ
とりでいるときでも、拘束したり、壁にクッションを入れる必要はなか
った。壁のクッションは、むしろ、守衛が殺されそうになった際に守衛
の命を救うためのものだった。
◇
それで、ふたりは、彼が棒を通して外のふたりを見てるとき、ドアの
外から棒を通して彼を見ていた。大きくてぶっきらぼうなクレス医師は、
ライオンのたてがみのようなくせ毛だらけの厚いグレーの髪に、どおん
という声、笑いながらも注意深く観察する小さな閉じ掛かったブタのよ
うな目にごまかされる笑いの持ち主だった。クレス医師は、自分では、
ぶこつ者と思っていて、実際に知ってるよりも、もっと多くのことを知
ってるふりをしていた。時には、おしゃべりがしたかったが、そのチャ
ンスがなかった。担当は、D病棟で、つまり、ウォルターフレモントの
担当だった。おそらく、死がふたりを別つまで。しかし、彼があり得な
いインフラホワイトのモードにない限り、あなどってるふりをしたり、
少なくとも、協力してるふりをすることは知っていた。たまに、許され
た小さなプレゼントをする必要があった。今日、彼の欲しいものは鉛筆
で、それをすごく欲しがっていた。
「では、フレ〜モント」と、医者。どおんという声を出した。いつもそ
んなふうに、母音を引きずった。「今日は、カネを持ってなさそうだな!
払う用意はある?」
「ええ、ドクター」と、彼。「準備完了」この『準備完了』は必要なか
った。しかし、彼はその鉛筆が欲しかった。もらうためなら、すぐにで
も、おべっかを使い始めるだろう。「ええ、ドクター」そして、頭を振
ることで、約束を思い出させようとした。クレス医師は、いつも、患者
を好いているようにふるまったが、患者との最後の面談から2週間たつ
ので、ウォルターは、そうでないことを知っていた。守衛も、かつては、
彼と友好的におしゃべりしていた、それは、彼の最初の1年間で、守衛
を殺す前、面談について、彼としゃべっていた。クレス医師の雇用の条
件は、2週間に1度、かならず、30分は、患者が状態が不安定であっ
たり、あるいは、緊張状態で聞くことも話すこともできないのでない限
り、1対1で面談をすること、あるいは、個人的に患者をケアすること
であった。しかし、彼は、患者と2週間に1回会うことで好意を持って
いるふうには、ふるまわなかった。なぜなら、保護ケア以上であるかの
ような見せかけは、幻想に過ぎないと事務サイドから抗議が出ていたか
らだった。それは、本人は別に意に介さない、患者のためでなく、患者
の親戚や、センターの支出代金を支える税支払者のためだった。
クレス医師は、看護婦の方を向いた。「ブラッドレー、今日はなにか
約束が入っていた?」
背の高いやせた看護婦は、手にしていたクリップボードを見た。「す
ぐにはないが、ドクター、1つだけ」彼女は、腕時計を見た。「今、1
0時で、最初の約束が、11時に入っている。もしも、最初の見回りを
30分で済ませられるなら、彼とは、10−30から11まで使える」
医者は、オーケーだと言って、ふたりは動き出した。
彼は、うしろに、簡易ベッドまで下がって、待つのは30分だけで、
鉛筆の実験を今日、1時間くらいで始められることが嬉しかった。今日
とにかく、ついにそれが働き出すと信じていいと感じた。
◇
ふたりの守衛がやって来たのは、30分も立たない頃だった。ふたり
とも用心深かった。ひとりは、彼が着なければならない拘束衣を、もう
ひとりは、やわらかいかかとのないスリッパを持っていた。拘束衣を持
つ方は、彼に後ろを向けと命令したが、スリッパの方は、「ヘイ、待っ
て!」と言って、手渡しただけだった。「最初に、それを着て!そうし
ないとオレたちが着せなければならない」
彼は、素直に従って、拘束衣を着て、座り、スリッパをはいた。ゆる
ゆるだったが、はけた。「なぜ、スリッパを?」と、彼。今まで、医者
のオフィスやどこへ行くにも、スリッパをはいたことはなかった。昼間、
外のグラウンドで数時間過ごせる特権のある患者以外は、だれもスリッ
パをはいてなかった。彼には外に出る特権はなく、この4年間、靴やス
リッパをはいたことはなかった。奇妙な感覚だった。
立ち上がり、手首をうしろに回したまま、ぐるりと回った。拘束衣は
機能していて、ベルトと両手首は、腰の高さの下に固定されて、背後か
らは無防備だった。
守衛の返事は、まったく、期待してなかったが、ひとりが答えた。
「新しい決まり」と、守衛。「州の掲示板に、高齢の女教師が、患者が
みな裸足で歩かされていて、そのうちアスリートの足になるか足が悪く
なるかのどちらかだ、と訴えた。それで、新しい決まりができた。へん
てこな決まり」
独房の外に出ると、守衛は別れた。ひとりが、残りの歩きに付き添っ
た。手首は、拘束衣の中で居ごこち良かった。
廊下、廊下、ゆっくりとしたエレベータ、廊下、廊下、それから、ク
レス医師のオフィスのドア。「座って」と、守衛。彼は、クレスのデス
クの前の患者用のイスに座った。守衛は、ドアの内側に寄り掛かってい
たが、足音がしたので、クレスのためにドアをあけた。「11時ちょう
どに」と、クレス。守衛に言い、守衛は出て行った。医者は、座った。
スイベルチェアが、いつものように、キーキー鳴った。医者の小さな目
は、いつものように、なにかを鋭く見るというよりは、いつも、笑いを
誘った。
「では、フレ〜モント」と、医者。「なにか、新しいことは?なければ、
古いうねに新しくわを入れる?」
「うまく、それをやれそう」と、フレモント。「けれど、建設的な提案
がある。あんたがこう主張したのを覚えてる?オレが正気のとき━━━
もっと正確には、比較的正気のとき━━━殺人衝動に駆られていたとき
のことを、覚えていれば、記述してもらえば役に立つと?」
「確かに、そう言った。今までは、殺人者の行動の動機の解明がされて
はなかった。しかし、彼は、そうする理由があって、攻撃なり殺人なり
をしていたはずだ。まったく面識のない者を攻撃する理由は、明らかに、
正気のものではないが、彼は、そのとき、明確な理由に基づいて行動し
ていた。そのようなときに、どんな幻覚を抱いていたか知ることは、活
き活きとした手掛かりをもたらしてくれる。なぜか?あんたは、そのと
きのことを覚えている?」
フレモントは、頭を振った。「いや、そのときのことは、あとで思い
出すと、完全にブラックアウト。オレには、だれかを殺した記憶さえな
い、たとえ、だれかを攻撃したとしても。しかし、オレが考えるのは、
そう、大学で知ったデューンの時間理論に興味があって、特に、彼の命
題、夢は断片の複合体、過去の実際の記憶だけでなく、未来の経験に先
立つ記憶も含まれる、意識が━━━」
「デューン理論については、フレ〜モント、オレは良く知っている、説
明の必要はない。その理論は、まったく、信用されてない。それで?」
「それは、肝心な点でない、オレもそれを信じてなかった━━━ただ、
それを経験しただけ━━━今も、信じてない。肝心な点は、数か月前の
あるとき、オレには夢の記憶があって、それであとで知ったのだが、夢
のいくつかは、その後の経験に、遠方から、影響を及ぼしているかのよ
うだった。今まで、そういうことはなかった。しかし、まだ、それは肝
心な点でなく、肝心な点は━━━」
ひと息入れて、続けた。「肝心な点は、そのときまで、オレは、ほと
んど夢を見たことがない、という印象があった。しかし、そのとき以来、
紙と鉛筆をベッドのすぐ脇に置いて、目覚めた瞬間に、少なくとも、覚
えている夢についてのキーワードなり、フレーズをざっと書き留めるこ
とを眠る前に心に印象づけてからベッドに入った。驚いたことに、オレ
はいつも、不変的に、夢を見ていたことだった。目覚めた瞬間に、いく
つかのキーワードを書き留めることで、完全に目覚めて、意識を持った
あとでも、夢の少なくとも一部を、その結末を、思い出したり、再構築
できるようになった。多くの人々は、オレが思うに、それを見なかった
かのように、夢のほとんどを忘れてしまう。オレについては、覚えてい
る時間は、ほとんどの人よりずっと短かった。しかし、それはあった」
「それで?」
「それで、殺人衝動の方は、夢ではないが、それはある程度━━━その
ような状態のときに、考えたり感じたりした、記憶の最後に1・2秒残
っているものをメモに残そうとするとき、どちらも似ているところがあ
る。それで、オレが赤の帯域から出て来た瞬間に、心に残ったものがあ
れば、メモに残すべきだ━━━そう、それは役に立つ。手掛かりとして
いくつかのワードを残せれば、そのときにオレがしたことだけでなく、
オレの強迫観念がどんなものだったか、そう行動した理由まで思い出せ
るかもしれない」
「しかし、安全確保の問題がある。先がとんがってるものは、一切、禁
止だ。それが規則」
「まともなルール、しかし、それが、鉛筆にも?やわらかい芯で先が丸
くなって、とんがってなくても?あんただって、それが武器とは見なせ
ないのは確かだ━━━素手の方がもっといい。たぶん、賢いやつなら、
自分を傷つける方法を見つけるかもしれない、ただ飲み込むだけで。し
かし、オレに自殺できないことを、あんたは知っている」
医者は、顔をしかめた。「分かった。その所持を許したと、守衛に言
っておく必要があるな、さもないと、守衛に見つかったら、すぐに取り
上げられてしまう」
デスクの引き出しをあけて、やわらかい芯で、6インチくらいの長さ
の鉛筆を捜し出した。それを短剣のように握り、さらに顔をしかめて、
武器として使えるかどうか、テストした。ため息をついて、立ち上がっ
た。「一番短いのを選んだが、まだ、長い。鉛筆削りで短くしないと!
切り株のように!もしもあんたがこれでなにかしたら、オレの仕事に影
響する!」
ため息をついて、立ち上がると、ドアのところへ行って、開けると、
呼んだ。「エッシー、すぐここへ!」
鉛筆をどうして欲しいか説明して、彼女に渡した。「ドアはあけたま
まにしてくから、すぐ、戻って来て!」
彼は、また、座ると、ため息をついた。「最近では、殺人衝動の期間
は、どのくらい続いた?」
「毎回、数日間だと思う。はっきりしない理由は、そう、近くに攻撃対
象がいないと、その衝動があるのかどうか、はっきりしないから。しか
し、そう、それはあったと思う。少なくとも、目覚めていて、ブラック
アウトがあったことは、かなり確かなので。そして、時には、横になっ
ていて、起き上がった記憶がないのに、突然、立ち上がっている。ふつ
うは、そのとき、かすかな、寸前まで赤だった印象がある。メモを残す
ことに成功したら、『赤』の言葉は、最初にたぶん書くだろう、その言
葉が許されていれば」
「その期間の考えは?」
「ない。攻撃を観察してみて、もっといい考えは?」
医者は、うなづいた。「最新の観察から、10分が良い推測値。2か
月前のこと、あんたはオレと話していて、今のようにまともに見えた。
守衛のひとりが、あんたを連れて、室まで戻り、もうひとりの守衛とい
っしょに、拘束衣をはずそうとした。あんたは、ひとりの守衛を攻撃し
て、クビを締めようとした。守衛は、あんたを取り押さえ、拘束衣をま
た着せた。それから、オレに報告に来たので、行ってみたが、あんたは
静かにしていた。なにがあったか訊かれたので、教えた」
「覚えている。つまり、気がつくとオレは拘束衣を着せられていて、あ
んたがいたのでなにがあったのかと訊いた。守衛を攻撃したことは覚え
てなかった。そう、あの時は、鉛筆を持っていてもなんの役にも立たな
かった。気が付くと、手首が後ろできつく縛られていた。しかし、希望
はある━━━」
エッシーが来たので、彼は黙った。彼女はオフィスで鉛筆を削って戻
って来ると、ドクターのデスクに置いて、出て行った。
クレス医師は、その鉛筆を持ち上げて、顔をしかめた。2・5インチ
しかなかったが、先が尖っていた。先を少し折ってから、落書き用の紙
を置いて、先がにぶく丸くなるまで、円を描いた。「これでいいだろう」
と、彼。落書き用の紙を数枚切り取って折りたたむと、フレモントのパ
ジャマの胸ポケットに入れた。
「サンクス」と、フレモント。ほんとうに感謝していたわけでなかった。
クレスの取引の部分が多すぎて、感謝に値しなかった。しかしクレスな
ら許してくれるような、別の楽しみを試してみたかった。
医者はうしろに寄りかかると、スイベルチェアがキーキー鳴った。
「うまく行くことを祈ろう。攻撃の新しい視点を活用できる。あんたの
精神状態の躁うつ病の段階はどう?」
フレモントは、忍耐しながら言った。「前に言ったはず、オレは躁う
つ病の精神状態にはない。ずっと前に終わっている。オレのうつ状態は、
精神状態の1つではあり得るが、逆の端なので、オレは躁状態ではない。
元気でもないし、興奮状態でも、異常にしゃべり好きになってもいない。
ちょうど逆で、3つ目のところにいる。おだやかになるところ。ものが
はっきり見えるし、急がず、よりよく見える」
医者は認めた。「しかし、まだ、あんたの病状は十分診断できていな
い。原因と治療の有益なアドバイスができない」
「その通り、ドクター!治療に関する限り。しかし、その精神状態は、
オレ固有のものだと、まだ、考えている。ある意味、機能的というより
も有機的で、純粋に突然変異」
「ふむふむ、そして、あんたの父が、空飛ぶ円盤からの放射を浴びたの
が原因だと前に言っていたが、まだ、その幻想を?」
それが幻想なら、オレは今も抱いている。可能な答えと考えてるとい
う方が当たっている。それを、空飛ぶ円盤と呼んだことはないが、その
ブームの数年前だった。ブームは、1947年から始まったが、それが
起こったのは1939年、オレが生まれる9か月とちょうど1週間前だ
った。
「前に詳しくあんたに伝えた、オレのオヤジが話してくれたことをその
まま。オヤジはふざけてなかったし、オレもおかしくなかった。『空飛
ぶ円盤』のところは、あんたの脚色だ。オレが言ったことは、父がやけ
どを負ったということ、そのやけどが、ミステリアスな状況下で放射に
よって受けたやけどと思われる。完全に説明不可能な、極度にミステリ
アスな状況で」
クレス医師は、鼻を鳴らした。「その通り!泳ぐ空飛ぶ円盤の排気に
よるやけどだった」
「また、それもあんたの脚色。正確には━━━」
「分かった、分かった」医者は、がまんできなくなって、言った。「あ
んたは話してくれた。ところで、最初のオレの質問に戻ろう、もう一度
訊いていいなら。うつの時期が━━━考えが明晰になる時期に変わると
きは、どんなかんじ?」
「そう、今なら、それをもっとうまく説明できそう。前に言ったように、
完全に黒の時期があったとは信じてない。うつの感覚はあったが、マイ
ルドなものだった。最近は、ずっと上り調子で、それは黒の時期とは違
う、スペクトルの白の端のように感じている。それを躁状態とは呼ばな
い、なぜなら、そうでないから」
「躁状態の時期から、躁うつ病の精神状態に移ったのではない?」
「その考えは間違っている。どちらの時期も互いに反対なら、単に、躁
うつ病の精神状態ではなくて、まったく別のなにかだ。しかし、あんた
がそう呼びたければ、止めることはできそうにない。あんたは、その、
まったく別のなにかに、新しい名前を付けなければならないと思う」
クレスは笑った。フレモントは、目の前の男に、男のアホさ加減に、
突然、怒りの炎を感じた。赤の怒りでなく、ただのふつうの怒りだった。
もしも、と彼は考えた、今までの殺人が、犠牲者を選ばない盲目的な衝
動でなく、冷酷にだれかを殺していたなら、クレス医師は、つぎの犠牲
者となっていただろう。この4年間、ますますそう感じるようになった。
アホになるしかない男には、怒ってもしかたがない。
ドアにノックの音がして、守衛が顔を出して、中を見た。「用意は?」
医者は、うなづいて、立ち上がった。
5分後、独房に戻り、拘束衣をはずされた。守衛が自由にしてくれる
まで待ち、あの鉛筆を取り出して、眺めた。希望よりは短かったが、じ
ゅうぶん使えそうだった。燃えるマッチの方が良かったが、それが必要
だと医者に頼めるいい理由が見つかなかった。頼んでも、断られていた
だろう。クレス医師は、超心理学の実験だとは、信じてなかった。
超心理学にそのようなものがあったとしても。たぶん、いつの日か、
ここでのなん年ものことがすべて価値があったと思われるだろう、たと
え、その年月が、彼の一生をすべて含んでいたとしても、彼に与えられ、
医療オフィスに飾られるような、ただ受け入れるだけの既成事実となる
だろう。たとえば、テレキネシスがそうだ。意志のままにものを動かす
ポルターガイストのような能力。クレスの前に座って、と彼は考えた、
そして拘束衣のままで、そうすることができると言って、証明する、筋
肉を動かすことなく、心だけで持ち上げる、そう、たとえば、デスクの
上の重い灰皿を、壁に向かって投げる。
彼の頭に向かってではない。そのような瞬間に彼を殺すことは、意味
がない。彼の人生で考えもしなかったことを見せ、考え方の前提を引っ
繰り返す方がよい。彼にそれを見せたあとで、好きなときに、殺すこと
も、尻を蹴とばすこともいつでもできる。
それから、と彼は自分に言った、彼を殺せる。殺しのランセンス。正
常なときに、正常な殺人、それに対して、やつらになにができる?
2
有史以前から、人は、魔法による力を使ったり、身を守ったりする方
法を追求してきた。魔法や呪文、儀式を通して、敵の目をあざむいたり、
自分の姿を隠したり、彼の住む社会がどのようなものであれ、自分を進
化させたり、有利な立場になるように。魔法を通じて、病気を治したり、
傷を直したり、生命や男らしさを伸ばしたり、愛する女を獲得したり、
鉛を金に変えることで富を得ようとして来た。
(つづく)