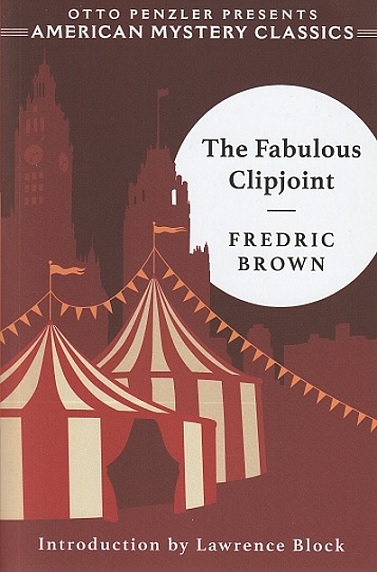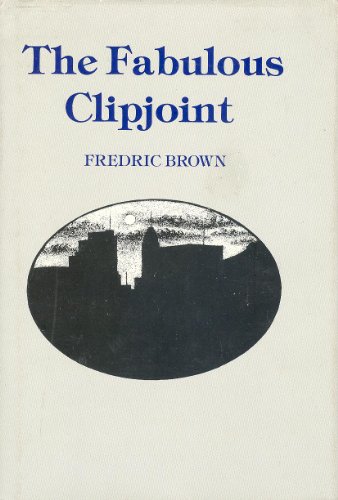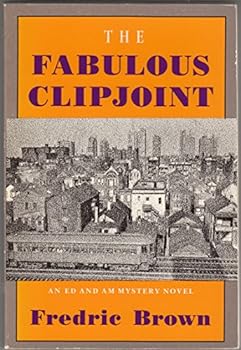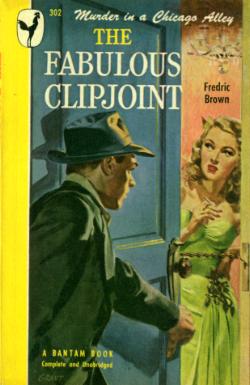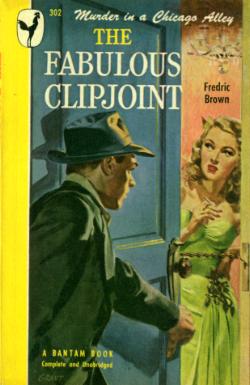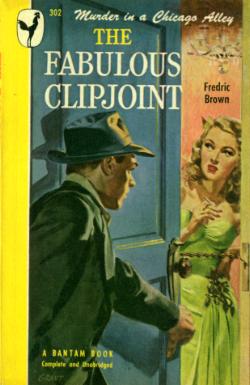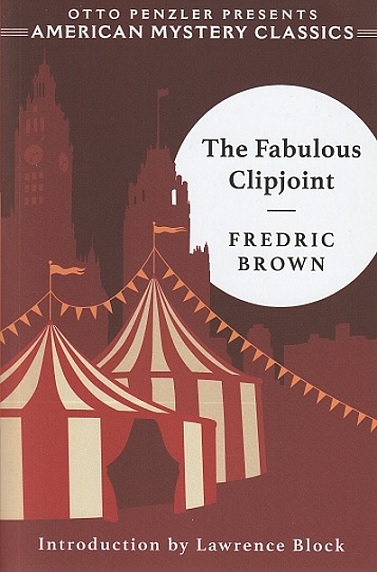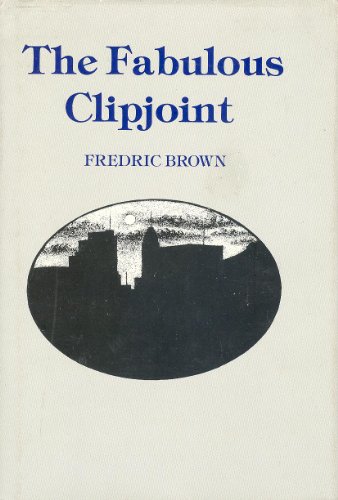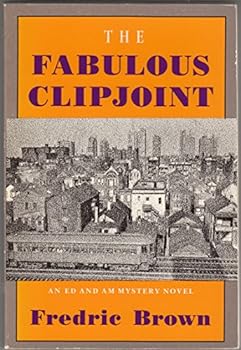ファブクリップ
原作:フレドリックブラウン
アランフィールド
登場人物
エドハンター:父親を殺した犯人を追う。
ウォリーハンター:静かな酔っ払い、静かな男。
マッジハンター:ウォリーの妻、男の敵。義理の息子エドが好き。
ガーディハンター:マッジの娘、男が大好き。
アムハンター:ウォリーの弟、たまに私立探偵をやる。
バニーウィルソン:ウォリーの同僚、友人。マッジに好かれている。
バセット:殺人課の刑事、無口でも正直でもない。
カウフマン:小男、サルより毛深い腕で、バーの経営者。
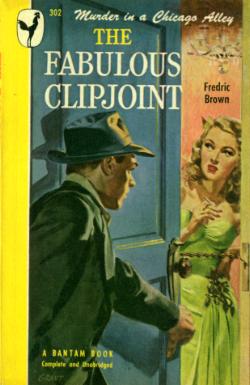
ハリーレーノルズ:ギャングの親分。
ダッチレーガン:どこにでもいるチンピラ、ハリーの子分。
ベニーザトーピード:別のチンピラ、ハリーの子分。
クレアレイモンド:ギャングの女、すぐ電話を教えてしまう、
ウェントウォース、スリーエイトフォーツー。
プロローグ
夢で、オレは、質屋のガラス窓に顔をつけて見ていた。北クラーク通
りの西側の、グランドアベニューを北に1ブロック行ったところにある
質屋だ。シルバーのトロンボーンに手が届きそうだった。窓以外のもの
は、ぼやけてはっきりしなかった。
シルバーのトロンボーンをつかむ前に、歌声がして振り返った。ガー
ディの声だった。
ガーディは、歩道で歌いながら、なわとびをしていた。去年、高校に
進学して男狂いになって顔じゅうに口紅やパウダーを塗る前のガーディ
のようだった。ガーディは、まだ15にもなってなかった。3・5才オ
レより年下だ。夢では、いつもより濃くすでに化粧をしていた。しかし
なわとびもしていた。子どものように歌いながら。
「いち、に、さん、オーレイリー、よん、ご、ろく、オーレイリー、な
な、はち━━━」
しかし、夢を見ながら、オレは目覚めていた。こんなふうにある状態
にあるのに、別の状態でもあるのは分かりにくい。エレベータが動く音
が夢のなかのように聞こえ、だれかが廊下を歩いている音がして、エレ
ベータが下へ降りたあと、ベッドのそばの床に置いた目覚まし時計のチ
ックタック音がして、今にもアラームが鳴りそうな音になった。
1
オレは、アラームを止めて寝返りをうった。しかし、もう目覚めてい
て眠りには戻れなかった。夢は、消えかかっていた。なぜトロンボーン
を手に?それは、オレがずっと夢見てきたからだ。なぜガーディがやっ
て来て、オレを起こした?
もう起きる時間だった。おやじは、昨夜は外で飲んでいて、オレが眠
るときは、まだ帰ってなかった。今朝は起きるのがたいへんだろう。
きょうは仕事に行きたくなかった。オレは、アム叔父さんに会いに、
ジェーンズビル行きの列車に乗りたかった。アムは、サーカスで働いて
いた。オレが8才だったときから、10年会ってなかった。しかしきの
う、おやじが話していたので、アムに会いたかった。おやじの話では、
アムは、J・C・ホバートサーカス団にいて、今週はジェーンズビルで
興行していた。そこは、巡業の場所としてはシカゴからもっとも近い場
所だった。それで、おやじは1日仕事を休んで、ジェーンズビルへ行き
たいと言っていた。
おふくろは、ほんとうの母ではなく義理の母だが、嫌な顔をしておや
じに言った。
「なぜあんたは、あんなろくでなしの弟に会いたいのさ?」
それで、おやじは外へ飲みに行った。
おふくろは、アムが嫌いだった。それで、オレは10年もアムに会っ
てなかった。
オレは行くことはできた。しかしそれはトラブルのもとかもしれなか
った。それで、おやじのするようにしようと考えた。
起きだして、ベッドを出て、シャワー室で顔に水を浴びて完全に目覚
めた。
いつもは、シャワーのあと服を着て、おやじを起こし、朝食をとった。
仕事にはいっしょに出かけ、おやじはエルウッド出版のライノタイプ技
師で、オレは、そこの見習いだった。
その日は、朝の7時には、もう暑かった。窓のカーテンは、微動だに
しなかった。息するのも辛かった。服を着ながら、猛暑日の記録を更新
するだろうと思った。
オレは、廊下をつま先立ちで歩いて、おやじとおふくろの寝室へ向か
った。ガーディの室のドアはあいていて、意味もなく中を見た。ガーデ
ィは、両手を広げて背中を上に寝ていた。顔は、化粧なしで子どものよ
うに見えた。なんとも言えない中途半端な子ども。
ガーディの顔は、そんなふうにからだの残りの部分と不釣り合いだっ
た。つまり、こんな暑い夜には、パジャマの胸も肌けてきっとりっぱな
胸だろう。ガーディがもうすこし大人になったら、すこし大きすぎるだ
ろうが、今は、美しい胸を自分でも誇りに思ってるだろう。きつめのセ
ーターを着ていたら、そう言われそうだ。
ガーディは、ますます早く大人になりつつある。かしこいままでいて
ほしい。そうでなかったら、15にさえなってないのに、妊娠して帰っ
てくることになりかねない。
ガーディは、オレがこんなふうに中を見るように、わざとドアをあけ
っぱなしにしておいたのだ。ガーディは、ほんとうの妹でなかった。義
理の妹だった。義理のおふくろの連れ子だった。おやじが再婚したとき、
オレが8才で、ガーディが4才の鼻水たらしのガキだった。ほんとうの
おふくろはその前に死んだ。
そう、ガーディは、オレの目をすこし楽しませようとしただけだ。ガ
ーディの近くを通りすぎるときに気を引きたかっただけだ。それで、ガ
ーディは大騒ぎすることもできるわけだ。
オレは、ガーディをのろいながら、あけっ放しのドアを通り過ぎた。
オレが気にするようなことはなかった。
オレはキッチンに寄って、コーヒーをいれるために、やかんの下の火
をつけた。それから戻って、おやじとおふくろの寝室をノックして、お
やじが起きてくるのを待った。
おやじは、出てこなかった。室へ入って、おやじを起こさなければな
らなかった。オレは、おやじとおふくろの寝室にはあまり入りたくなか
った。しかしふたたびノックしても返事がないので、ドアをあけた。
おやじはいなかった。
おふくろは、ベッドで眠っていた。靴だけぬいで、服は着たままだっ
た。服は、黒のベルベットのもっともいい服を着ていた。今は服は乱れ
て、着たまま寝ているとかなりきつそうに見えた。それが、おふくろの
もっともいい服だった。髪も乱れ、化粧もしたまま汚れて、枕に口紅が
ついていた。室は酒のにおいがした。鏡の前にほとんどカラで、コルク
栓なしのボトルがあった。
室を見渡してみて、おやじはここにはいないことは確かだった。おふ
くろの靴は、ベッドとは逆の隅に落ちていて、おそらくベッドからぬい
でほうったのだ。
とにかく、おやじはここにはいなかった。
おやじは、まだ家に帰ってなかった。
◇
オレはドアを、あけたときより静かにしめた。立ったまま、なにをし
たらいいのか迷った。おぼれるものはワラをもつかむの心境で、おやじ
をさがし始めた。
「おやじは酔って帰ったから」と、オレは考えた。「イスの上か、どこ
か床の上で寝ているのだろう」
オレは、家じゅうを見てまわった。ベッドの下、クローゼットの中、
すべてを見た。こんなことはムダなことが分かっていたが、見てまわっ
た。おやじがどこにもいないことを確認したかった。たしかに、いなか
った。
コーヒー用のお湯は、沸騰して蒸気をあげていた。火を止めて、立ち
つくした。さがしまわったことで行き詰まり、なにも考えられなくなっ
た。
「だれかといっしょだったはずだ」と、オレは考えた。「印刷工の同僚
とかの家に泊まったのかもしれない。かなり酔って帰れなくなって」
オレは、推理がでたらめなことが分かっていた。おやじは、酒の飲み
方が分かっていた。決して、そんなふうに酔うなんてことはなかった。
「なにかが起こったのかもしれない」と、オレは考えた。「たぶんバニ
ーウィルソン?バニーは、夜勤で働いていて、きのうは休みだった。お
やじはたまにバニーと飲んでいた。2回くらい、バニーはうちに泊まっ
ていた。朝、ソファで寝ていたバニーを見た」
バニーウィルソンの家に電話するべきか?電話しようとして、やめた。
もしも電話をし始めたら、病院にも警察にも可能性のあるところに電話
しつづけなければならない。
もしもここで電話し始めたら、おふくろかガーディが起きてくるだろ
う。まだ、状況が分かってない。それを知るのが先だ。
あるいはオレは、ここから外出したかっただけかもしれない。オレは
マンションをつま先立ちで出て、階段を最初は1段づつ、そのあとは2
段づつ走って降りた。
通りを渡って、立ち止まった。電話するのがイヤだった。もうそろそ
ろ8時で、急がないと仕事に遅れそうだった。そのとき、仕事のことは
重要でないと気づいた。きょうは仕事に行かないだろう。なにが起こっ
てるのか分からなかった。電話ボックスに寄りかかった。ぼんやりした
気分で、頭に日射しがあたって、なにか自分の一部しかここにない気が
した。
こんなことを終わりにしたかった。なにがあったのか知りたかった。
そして、終わりにしたかった。しかし警察に行って聞くのはイヤだった。
あるいは、最初に電話するのは、病院だったかもしれない。
電話だけはしたくなかった。オレは知りたかったが、同時に知りたく
なかった。
通りを走ってきた車が、速度を落とした。ふたりの男が乗っていて、
ひとりが外の通りの番号をチェックしていた。そして、うちのマンショ
ンの前で停まった。ふたりの男が降りてきて、両側に立った。ふたりは
私服刑事だった。制服がなくても警官であることは、見え見えだった。
「このことだ!」と、オレは考えた。「知るときが来た!」
オレは通りを戻り、マンションに入るふたりについて行った。オレは
話しかけなかった。話したくなかった。ふたりが話すのを聞きたいだけ
だった。
ふたりについて、半階分うしろから階段をあがった。3階で、ひとり
が立ち止まり、もうひとりが廊下を歩いて室番号を見てくるまで待って
いた。
「つぎの階に違いない」と、ひとり。
階段を向いていたひとりが、オレの方を見た。オレは、通りすぎよう
とした。
「よう、ぼうや、15号室はなん階だい?」と、ひとり。
「つぎです」と、オレ。「4階です」
ふたりは先を進み、オレは今や数歩うしろからついて行った。オレの
すぐ前のひとりは、太って、ズボンはシートでテカテカになっていた。
一段上がるごとに伸び縮みするのが、おかしかった。ふたりは、でかく
て警官だという以外、ふたりについて覚えていることは、それだけだっ
た。ふたりの顔は見なかった。ふたりを見たのは確かだが、認識はしな
かった。
ふたりは、15号室の前で立ち止まり、ノックした。オレはそのまま
階段を上がり、5階のフロアに着くと、靴をぬいで、階段の踊り場まで
戻った。壁を背にして座った。これで、オレは、ふたりに見つからずに、
会話を聞けた。
すべてが聞けた。おふくろはスリッパをひきずって、ドアまで出てき
た。あくときのドアのきしむ音も聞こえた。つぎに沈黙。あいたドアか
らキッチンの時計のチクタク音が聞こえた。ガーディのはだしの歩く音
も聞こえた。ガーディは、室から出て、バスルームの廊下の曲がり角で
見られないようにして、玄関にだれが来ているのか聞き耳をたてていた。
「ウォリーハンター」と、警官のひとり。古い電車のきしみ音のような
声で。「ウォリーハンターは、ここにお住まいですか?」
おふくろの呼吸が荒くなったのが聞こえた。それが、答えのようなも
ので、おふくろの顔色を見て、こう言うだろうと思った。
「あなたは、ウォリーハンターさんの奥さんですか?」まさに、そう言
った。そしてすぐに続けた。「奥さん、言いにくいのですが━━━」
「事故ですか?」と、おふくろ。「傷は?もしかして━━━」
「彼は死にました、奥さん。発見されたときに、すでに死んでました。
それで、あなたのご主人でしたら、できれば、いっしょにきて確認を。
いえ、まったく急ぎません。奥さんのショックがやわらぐまで、中で待
つことはできます」
「どんなふうに?」おふくろの声は、ヒステリックではなかった。感情
がなくフラットだった。「どんなふうに?」
「ええ」と、もうひとりの警官の声。オレに15号室はどこか聞いた声
だった。
「強盗です、奥さん。撃たれて路地に倒れてました。昨夜の午前2時ご
ろです。財布が盗まれていて、それで今朝まで身元が分かりませんでし
た━━━ハンク、つかまえろ!」
ハンクは、動作がにぶかったらしい。ドタンバタンという音がして、
ガーディの興奮した叫び声もした。警官は中へ入っていった。なにがあ
ったのかは分からない。オレは靴を手にしたまま、ドアに向かった。
ドアは、オレの顔の前でしまった。
◇
オレは階段に戻り、また座った。靴をはき、ただ座っていた。しばら
くして、だれかが上のフロアから階段を降りてきた。家具職人のミスタ
ーフィンクだった。うちの真上に住んでいた。オレは壁側に寄って、横
を通れる余地を作った。彼は4階に降りてから、手を欄干に置いたまま、
オレの方を振り返って見た。オレは、フィンクを見ないで、彼の手を見
ていた。たるんで締まりがない手で、汚いくぎを持っていた。
「エド、どうしたんだい?」と、フィンク。
「別に」と、オレ。
フィンクは、一度欄干から手を離したが、また置いた。
「なぜ、そんなところに座ってる?仕事をクビになったのか?」
「いいえ」と、オレ。「なんでもありません」
「じゃなんで、そんなところに?酔ったおやじさんに蹴られて、追い出
されたのか?」
「ほっといてください」と、オレ。「いいから、ほっといて!」
「オーケー、きみの好きにするさ。いいチャンスかもしれないよ、エド。
きみはりっぱだから、あんな飲んだくれのおやじさんの家から出て」
オレは立ち上がって、フィンクの方へ階段を降り始めた。オレはムカ
ムカしていたので、すごい形相だったのかもしれない。フィンクはオレ
の顔を見て、顔色を一変させた。オレは今まで、相手がそんなに急に恐
怖の顔になったのを見たことなかった。フィンクは体をひるがえして、
急いで階段を降りていった。オレは、フィンクが下の階をすぎるまで、
そこに立っていた。
それから、オレはまた座り、手で頭をおおった。
しばらくして、うちのドアがひらく音がした。オレはじっとしたまま、
顔を向けもしなかった。しかし、声や足音で分かった。4人とも階段を
降りて、どこかへ行った。
物音がしなくなってから、オレは、自分のカギで家に入り、やかんの
下の火をつけた。こんどは、コーヒー沸かし器でコーヒーをいれた。こ
れで、準備はできた。窓に行って、セメントだらけの街のようすを眺め
た。
おやじのことを考えた。もっと、おやじを知りたかった。おやじとは、
うまくいっていた。これからもっとなにかができた。今となっては手遅
れだった。おやじのことは、ほんとうのことはなにも知らなかった。
しかし、今おやじのことをもっと知る長い道のりを前にしている気が
した。ほとんどなにも知らないし、多くのことを誤解していた気がした。
おやじの酒がそうだ。そのことは今、重要ではないと分かった。なぜ
飲むのかは知らないが、理由があったはずだ。たぶん、今、窓の外を眺
めながら、その理由を分かり始めていた。おやじは、静かな酔っ払いで、
静かな男。おこったところを数回しか見たことなかった。おこったとき
は、いつもしらふだった。
◇
「あなたは」と、オレは考えた。「1日じゅうライノタイプの前に座っ
て、手書きの広告原稿や、路上で売られる雑誌記事や、教団の財政報告
の組版をして、家に帰れば、昼間から酔ってからんでくる妻や、ぐれか
かった義理の娘の相手をしなければならなかった。
息子は、おやじよりすこしは頭がよくて成績もいいとうぬぼれた知っ
たかぶりだった。
そうした雑多なものから抜け出るには、あなたはあまりに良心的すぎ
たから、数杯のビールでまぎらわそうとした。酔うつもりでなくても酔
った。たぶん、あなたの意思でなかったのだから、それ以上なにができ
ただろう?」
オレは、おやじとおふくろの寝室に写真があったことを思い出して、
見に行った。10年前に再婚したころのものだった。
立ったまま写真を見た。オレは、この写真の男を知らなかった。オレ
には見知らぬ男だった。今、おやじは死に、オレは、おやじのことを、
真の意味では、知ることはできなかった。
◇
10時半だった。おふくろとガーディは、まだ、帰ってなかった。オ
レは家を出発した。道路はオーブンのようで、太陽はほとんど真上から
照りつけていた。まさに、猛暑だった。
オレは、電車の線路に沿って、グランドアベニューを西に歩いた。ド
ラッグストアを通りすぎた。そこで、エルウッド出版に電話して、きょ
うは行けないと言うべきだったと、オレは考えた。おやじもそこへ行っ
てなかった。8時に電話するべきだった。今では、オレたちが来れない
理由を知ってるだろう。
オレが戻ったとき、みんなになんて言えばいいのか分からなかった。
ただ、だれとも話したくなかった。「おやじは死んだ」と、言えるよう
な気がまったくしなかった。
警察とも話したくなかったし、葬式について考えたくもなかった。お
ふくろとガーディが戻るのを待っていたが、帰ってこないのは好都合だ
った。ふたりとも話したくなかった。
オレはおふくろ宛のメモを残し、アム叔父さんに会いにジェーンズビ
ルへ行くと伝えた。おやじが死んだ今、おふくろもオレがアムに会うこ
とに口出しできないだろう。
オレは、そんなにアムに会いたいわけでもなかった。ジェーンズビル
へ行く口実になるからだ。
オリンズ通りからキンジーに出て、橋を渡って運河の先、シカゴ鉄道
マジソンストリート駅に行った。ジェーンズビルを通るセントポール行
きは、11時20分だった。切符を買って、駅のベンチで待った。
午後の早版の新聞を2部買って、目を通した。おやじのことは、どこ
にものってなかった。
「シカゴでは」と、オレは考えた。「そんなことは1日なん10件も起
こるのだ。大物ギャングだとか重要人物でなければ、インクのムダだ。
酔っ払いが路地に倒れていて、撃ったやつが大麻をやっていて、なん
10発も撃ったとかでなければ、だれも気にしない。
ギャングもなし、色恋もなしなら、インクのムダだ。
死体安置所には、なん100体も運ばれてくる。もちろん、すべてが
殺人ではない。路地のベンチで寝ていた浮浪者が目覚めなかったとか、
安宿の宿泊者が朝ゆすっても起きなかったとか、店員は、そんなやつの
ポケットにある2ドルか4ドルをくすねてから、警察に電話するなり、
店からたたき出すなりするだろう。それが、シカゴだ!」
記事には、南ハルステッド通りのナイフで刺された死体のことや、安
ホテルの1室で麻薬をやっていた女の死体のことがあった。印刷工が、
すこし飲みすぎて食堂から出てきたところをつけられたとしても不思議
はない。きのうは給料日でサイフには緑紙幣がたんまりあっただろう。
そんなことを記事にしても、シカゴの印象が悪くなるだけだ。記事に
できないのは、そんな事件の数が多すぎる理由もあった。重要人物とか、
特殊なやり方で殺されたとか、女性がらみでないと記事にはならない。
昨夜の麻薬をやりすぎた女のように、新聞に歓迎されるやり方をした
場合もあった。それは、窓から飛び降りるそぶりをみせて、十分な見物
人やカメラマンが集まるまで待ってから飛び降りて、いいシャッターチ
ャンスを与えたケースだった。
オレは、新聞をベンチに残して、正面へ歩いていき、立ってままマジ
ソン通りを歩く人々を見ていた。
「新聞の間違いではない」と、オレは考えた。「新聞は人々が欲しがる
ものを与えてるだけだ。そんなゴッダムシティが嫌いなだけだ!」
オレは、通り過ぎる人々を見ていた。嫌悪感を感じた。なかには楽し
そうにしているやつもいたが、オレは、嫌悪感を感じた。
「あいつらは」と、オレは考えた。「だれか他人に起こったことなら、
なんとも思ってないのだ。それが、この街で数杯飲んで帰ろうとした男
でさえ、そのわずかな懐のお金のために殺されなければ歩いて帰れない
理由なのだ。
たぶん、この街だけのことではないのだろう。どこでも、だれにでも
起こることなのだ。この街が、すこし大きいから、その分もっと悪いと
いうだけだ」
通りの向こうの宝石店の時計が、11時7分すぎになった。オレは、
駅に戻った。セントポール行きの列車が入ってきた。オレは、列車に乗
って、席についた。
列車のなかも暑かった。席はすぐにいっぱいになり、隣に太った女性
が座って、オレは窓側に寄った。通路にも人が立った。楽しい旅になり
そうになかった。物理的な息苦しさで、かなり気が滅入った。
「なぜ行かなきゃならない?」と、オレは考えた。「家に帰って、音楽
でも聞こう!走っていけばいい。アムには、電報で知らせればいい!」
立ち上がろうとしたとき、列車は動き出した。
2
サーカスの娯楽施設にあるスロットマシンは、にぎやかな音をたてて
いた。メリーゴーランドの蒸気オルガンは、雷のようなバスドラムを伴
う見世物小屋の呼子のスピーカーの音量と競い合っていた。ビンゴショ
ーでは、番号を読み上げるマイクの声が響いていた。
オレは、それらの音のただなかにたたずんだまま、アム叔父さんを見
つけられるか迷っていた。顔さえよく覚えていなかった。アムがサーカ
スでやっていることは、売店ということしか知らなかった。おやじは、
アムについて多くは語らなかった。
だれかに訊いてみることにした。あたりを見回して、大声を出したり
してないヒマそうな人間をさがした。綿菓子店の男は、イスによりかか
ってボーッとしていたので、近づいて、アム叔父さんについて訊いてみ
た。
「ボールゲームさ。牛乳瓶のやつ!」と、男。親指で方向を指した。
オレは、その方向へ歩いていった。太った小男がカウンター越しに手
をのばし、通行人に3個のボールをさしだしていた。その男は、アムで
はなかった。
さらに、その方向に歩いていった。進めば、アムに近づくはずだった。
「いた!」と、オレは考えた。「アムに違いない!」
顔は、見覚えがあった。しかし、思っていたほど背が高くなかった。
前に会ったのは、オレが8才のときだから、背が高く見えたのだ。体重
も重そうだったが、今見ると、記憶にあるようなデブではなかった。し
かし、アムの目は同じだった。記憶どおりだった。なにか秘密を知られ
ているかのような、キラキラした輝きがあった。
今、オレはアムより背が高かった。
「3つ投げて、25セントだよ!当ててみないか?」と、アム。3個の
ボールをさしだした。
もちろん、アムはオレに気づいていなかった。8才と18才では、見
かけがかなり違うのだから当然だが、オレは気づいてくれなかったこと
ですこしがっかりした。
「アム叔父さん、エドだよ、エドハンター」と、オレ。「シカゴから着
いたばかりだ。おやじが、昨夜、殺されたことを知らせに」
アムの表情は、オレが話し始めたときは輝いたが、話し終わるころに
は、まったく違った。しばらく暗くなって、ふたたび緊張し、まったく
違う表情になった。目にきらめきはなくなった。アムは、まったく違う
ように見えた。オレが知っているアムとは、まったく違うように見えた。
「殺されたって、どういうことだ、エド?」と、アム。
オレはうなづいた。「路地で死んで見つかったんだ。撃たれていた。
給料日で、おやじは飲みに出ていたんだ」それ以上は続ける必要はなか
った。それで、じゅうぶんだった。
アムは、ゆっくりうなづいた。3個のボールをカウンターの上の3角
の枠の1つに置いた。
「ちょっと待っていてくれ!看板を降ろしてくる」と、アム。そうした。
「これでよし!テントは、こっちだ!」
アムは、ボールで倒そうとするダミーの牛乳瓶が後ろの側壁につるさ
れている2つの箱の脇を通って、裏手の方へ行った。
オレは、アムについて店の裏手12ヤードにあるテントへ行った。ア
ムがテントの入り口の布を上げていてくれたので、先にテントへ入った。
テントは、床が6X10フィートの広さで、側面は、垂直部分が3フィ
ートで、あとは先細りになっていた。まん中では、余裕で立っていられ
た。簡易ベッドが1つと、すみに、大きなトランクが1つに折りたたみ
イスが2脚あった。
最初に目に入ったのは、ベッドで眠っている女性だった。彼女は、小
さくやせていて、ブロンドだった。20才か25才くらいで、眠ってい
ても顔はきれいだった。靴は脱ぎ捨ててあって、服は着たままで、綿の
プリントドレス1枚だった。アムは、彼女の肩をゆすって起こした。す
ぐに彼女は目覚め、1秒で完全に目覚め、もう眠たそうでなかった。立
ち上がって、服のシワを伸ばして、オレを見た。
「ハーイ、エド!あなたもハンターでしょう?」
オレは、うなづいた。
「外へ行って」と、アム。「ホーギーを呼んできてくれ!」
彼女は、アムを見て、出て行った。
「ポーズショーの女さ」と、アム。「あいつらは、夜まで仕事がないか
ら、たまにここへ来て寝てるのさ。先週なんか、ベッドにカンガルーが
いたよ!ホントさ、冗談でなく!ピットショーに出ている、ボクシング
するカンガルーさ!カーニバルにいたら、自分のベッドにいろんなもの
に出くわすのさ!」
オレは、イスのひとつに座っていた。アムは、トランクをあけて、中
のものを、ベッドの下から引っ張り出してきた古いスーツケースに移し
変えていた。
「アム、いるかい?」外で、低い声がした。
「ホーギー、入ってくれ!」と、アム。
テントの入り口の布が、ふたたび上がり、背の高いホーギーが入って
きた。ホーギーが立つとテントの入り口はふさがり、頭は支柱のポール
に届きそうだった。顔は平たく、完全に無表情だった。
「やぁ!」と、ホーギー。
「いいかい、ホーギー」と、アム。荷物の移し変えをやめて、スーツケ
ースの横に座った。「これから、シカゴに行ってくる。帰りがいつか、
分からん。留守のあいだ、ボールゲームをやっててくれるか?」
「もちろん、いいさ!オレはここではスローされたんだから、スプリン
グフィールドでもスローされる。ジャックがブローする気なら、あいつ
にやらせりゃいい。カットは、なんパー?」
「カットは、いらない」と、アム。「ただ、モーリーには、今まで通り、
払ってやってくれ!残りは、ぜんぶ取っていい!戻るまで、今のスタッ
フをまとめておいて欲しいんだ。それと、このトランクを見ていてくれ!
シーズンエンドまでに戻らなかったら、預かっておいてくれ!」
「分かった。あんたへの連絡方法は?」
「シカゴの局留が使える。しかし、その必要はない。サーカスが今どこ
か調べれば、また、会える。戻るときには、戻るさ!オーケー?」
「分かった、そう、1杯やってくれ!」ホーギーは、尻ポケットから平
べったい1パイントボトルを出して、アムに手渡してから言った。「こ
れが、甥のエドかい?彼女ががっかりするだろうな。エドが来たら、知
り合いになりたいって言っていたからな。失ったものは、少なくない」
「どうだか?」と、アム。
ホーギーは、笑った。
「いいか、ホーギー」と、アム。「さっきエドと話した。エドの父、オ
レの兄のウォリーが、昨夜、死んだんだ」
「そうだったのか」と、ホーギー。「悪かった、アム」
「いいさ!ボトルはもらっておく。いいだろ?あと、よかったらもう店
をあけてくれ!お客が出てるから、ひと稼ぎできそうだ」
「そうだな。さっきはすまなかった。ああ、言いたいことは分かるな?」
ホーギーは、出て行った。
◇
アムは、座ったまま、オレを見ていた。オレは黙っていた。アムもし
ばらく黙っていた。それから言った。「どうした、エド。なにか引っか
かるのか?」
「分からない」と、オレ。
「ああ、言わなくていい」と、アム。「いいか、エド。オレは、見かけ
ほど無口じゃない。1つだけ言う。一度もゆっくりしてないだろう?泣
いてない、だろ?板のようにかたいままだ。それはよくないな。自分の
ためになにかするといい。にがいままでなく」
「大丈夫!」
「いや、なにかが引っかかってる!」
アムは、ホーギーの1パイントボトルをまだ手にしたままで、キャッ
プをはずしてなかった。オレは、それを見て、言った。「飲んでいいか
い、アム叔父さん?」
アムは、ゆっくり、首を振った。「酒は、救いにはならない。飲むな
ら、ほしくなってからだ。なにかから逃げてはダメだ。今まで逃げてき
たろう?ウォリーのことを知ってから」
「ああ」と、オレ。「酒は飲みたいと思わない。ただ、1口だけさ。そ
れがしたいだけ!」
「なぜ?」
説明は、難しかった。「おやじをよく知らなかった。そのことに、今朝
気づいたんだ。彼には、オレはいい子だった。彼はアル中じゃなかった
と思う。彼もそれは知っていた。オレにとって、おやじはあまりよくな
いことが、分かっていたと思う。お互いに、理解し合うこともなかった。
分かる?」
アムは、なにも言わなかった。ゆっくり、うなづいた。
オレは、続けた。「酒がきらいだ。つまり、味が。ビールは好きだが、
ウィスキーの味はきらいだ。でも、ひと口だけ飲みたい、おやじのため
に。埋め合わせるため、少しだけ、ある意味。彼が知ることがないのは
分かる。でも、そうしたい、彼のためにひと口だけ、ある程度、これ以
上うまく言えない」
「そうか」と、アム。ボトルをベッドの上に投げて、トランクのところ
へ行った。「すずのカップを入れたはずだ。カップボールゲーム用だ。
ボトル以外で飲むのは、カーニバルではまれだが、いっしょに飲もう!
ウォリーのために、オレも飲みたい」
アムは、アルミニウムカップを3つ出してきて、2つに3分の1ずつ
注いで、1つをオレに差し出した。
「ウォリーのために」と、アム。
「おやじのために」と、オレ。
アルミニウムカップでカンパイして、飲み干した。悪魔の火のように
熱かったが、むせなかった。
しばらく、ふたりとも無言だった。それから、アムが言った。「モー
リーに会ってくる。カーニバルのオーナーさ。オレが行くことを知らせ
てくる」
すぐに出て行った。
オレは、そこに座った。ウィスキーの生のまずさを口に感じたが、考
えたのはそのことじゃなかった。おやじのことだった。おやじは死んだ。
2度と会えない。いきなり、オレは泣き叫んだ。ウィスキーのせいじゃ
なかった。ウィスキーの効果は最初のひと口が過ぎてしまえば、なんの
効果もなくなるからだ。もっと、内面から来るものだった。アムは、そ
れが来ることを知っていて、オレをひとりにしてくれたのだ。オレくら
いの若者は、人前で泣き叫びたくないことを知っていたのだ。
泣くのをやめるころには、酔いを感じ始めた。頭ががんがんして、胃
が気持ち悪かった。
アムが戻った。オレの目が赤いのを見て、言った。「そのうち気分が
よくなるよ、エド。だれでも通る道さ。太鼓の皮のように固かったから
な。今はだいぶリラックスしてる!」
オレは、ニヤリとして、言った。「飲みなれてないせいで、倒れそう
だ。カンはあるかな?」
「ここじゃ、公衆トイレだな。宝くじ売り場の向かいだが、きれいじゃ
ない。そこへ行って病気になるか、あるいは、外でするといい」
オレは、外へ出て、テントの裏にまわって済ませた。
戻ると、アムはスーツケースを詰めていた。
「ひと口飲んだだけでは」と、アム。「初めてでも病気にはならないよ!
食事はしたのか?」
「いや」と、オレ。「昨夜の夕食のあと食べてない。思いもつかなかっ
た」
アムは笑った。「無理もない。最初に食い物屋に寄って、エドは食事
して、オレはスーツケースを取りに戻って、そこからいっしょに駅へ行
こう!」
アムは、オレの食事を注文して、オレが食事を始めるまで待った。
「すぐ戻る」と言うと、出ていった。
オレが食事を終えるころに、ちょうど戻ってきた。アムは、テーブル
の向かいに座って、言った。
「駅に問い合わせたが、今夜の6時30分のシカゴ行きがある。あと、
マッジに電話した」マッジは、オレの義理のおふくろだ。「現状が分か
ったが、新しいことはなにもない。検死は、明日の午後で、葬儀屋は、
ウェルズ通りのハイデン、ウォリーは今はそこだ」
「そうじゃないと思っていた、死体仮置き場かないかに」と、オレ。
アムは、頭を振った。「シカゴでは、そういうことはない、エド。遺
体は、特別な人物でない限り、近くの葬儀屋に送られる。親戚が申し出
て別の葬儀屋を手配しない限り、市の方から請求書は送られてくる」
「親戚がなにもしなかったら?」
「共同墓地行きだ。重要なのは、親戚には検死の権利があって、証拠が
新しいあいだに調べられるということだ。必要があれば、その権利を保
留にすることもできる」
オレは、うなづいて、言った。「おふくろは取り乱してた?オレが、
つまり、逃げたから」
「取り乱してはなかった。ただ、この件の担当になった刑事がエドと話
したがっていて、困っていると言っていた。刑事には、エドにすぐ帰る
ように伝えてほしいと頼んだそうだ」
「そんなやつと」と、オレ。「なにも話したくない!」
「それはよくないな、エド。やつを、オレたちの側につけるんだ!」
「オレたちの側?」
アムは、オレを奇妙な目で見た。「そう、エド」と、アム。「オレた
ちの側さ。エドは、オレといっしょだろ、違うか?」
「つまり、これから━━━」
「そう!だから、ホーギーやモーリーにいろいろ頼んで、モーリーは今
シーズン、カーニバルの運営権を買い取っていて、カーニバルの名前は、
ホバートのままだが、とにかく、オレがいくらでも留守にできるように
したのさ。そうさ!ウォリーを殺して逃げている、とんでもないやから
をとっつかまえたくはないのか、どうだエド?」
「サツができないことでも?」と、オレ。
「サツには時間的制約がある。ホットな熱い弾丸でも出てこない限り。
オレたちには、時間を自由に使える。ここが、重要な点だ。オレたちに
は、サツが見逃したものが分かっている。オレたちは、ハンターだ!」
アムがそう言った瞬間、オレは、電気ショックに近いぞくぞく感を感
じた。
「オレたちは、ハンター家だ!」と、オレは考えた。「名前にふさわし
い!暗闇の路地に潜む犯人を狩りにゆくハンターだ!おやじを殺したや
つだ!」
気が高ぶりすぎだったかもしれない。しかし、オレはアムを信じた。
サツが見逃した犯人をつかまえにゆく、ハンターだ!オレは、電報で済
ませなくてよかったと思った。
「オーケー!」と、オレ。「とんでもないやからをとっつかまえにゆこ
う!」
アムの目に輝きが戻った。輝きは戻ったが、なにかがあった。死んだ
ような、なにか。目の輝きにもかかわらず、大きな黒のひげを蓄えた太
った小男のようには見えなかった。トラブルにあったときに、味方でい
て欲しい存在に見えた。
◇
シカゴ行きの列車を逃したとき、アムは言った。「しばらく、別々に
行動しよう!エドは、いったん、家に帰って、マッジと仲直りして、刑
事に会えそうなら彼に会え!オレがどこかは、電話で連絡する」
「そのあとは?」と、オレ。
「まだ、それほど遅くはないし、寝床に入る気もないなら、また落ち合
える。しなきゃならないことを、明確にしよう。つまり、スタートだ!
エドは、刑事やマッジから聞き出すことがあれば整理する」
「オーケー」と、オレ。「でもどうしていっしょに家に来ないんだい?」
アムは、ゆっくり首を振った。「マッジとはあまり近づきすぎない方
が、うまくやっていける。ジェーンズビルから電話したときはマッジと
は話せたが、あまり近づきたくはない」
「分かった」と、オレ。「オレもあの家にはいたくない。なぜ、室を借
りてはダメなんだい?アム叔父さんの近くとか、2室あるところとか。
これから、いっしょに仕事するなら━━━」
「むずかしいんだ、エド。とにかく、すぐはダメだ。エドとマッジのあ
いだにどんなことがあるのか知らないが、エドの家はあそこだから、ど
んなにすぐでも、葬式が済むまではダメだ。葬式のあとで家を出てもす
ぐには見られない。しかし、今、家を出たら、すぐに出たと見られる」
「そうだね、正しいと思う!」
「エドが家を出て、マッジがそれを気に入らなかったら、オレが責めら
れる。オレたちふたりとも、マッジの犬小屋にいるようなもんさ。そう、
もしもオレたちがこの事件を扱うなら、どんな関係者とも仲よくする必
要がある。分かるかい?」
「おふくろは」と、オレ。「やってないさ、もしもそういう意味なら。
ふたりは少し前にケンカしたが、おふくろはおやじを殺してない」
「そういう意味じゃなかった。マッジがやったとは考えたこともない。
エドは、しばらくは、家にいなきゃならない。もしもウォリーが生きて
いたら、そうしていたろう?オレたちはどんな物事だって、中間的な立
場から、いろいろ打ち合わせして進められる。外側からじゃないんだ。
エドは、マッジとも刑事ともいい関係を保って、聞いておくべきことを、
なんでも質問して情報を集められる。これからは、いろいろ乗り越えて
ゆくことが必要になる。オーケー?」
◇
オレが帰ったとき、おふくろはひとりだった。ガーディは出かけてい
た。どこへ行ったかは、きかなかった。おふくろは、見たことない黒の
ドレスを着ていた。目は、かなり泣いたように赤かった。化粧は、すこ
しの口紅以外してなかった。口の片方に口紅がはみ出ていた。
声は、おふくろの声とは思えなかった。平坦で、半分死んだようで、
抑揚がなかった。
見知らぬ者どうしのようだった。
「ハロー、エド」と、おふくろ。「ハロー、ママ」と、オレ。オレは、
居間へ行って、座った。おふくろが入ってきて、やはり、座った。オレ
はラジオのそばで、ダイヤルを意味もなくいじった。
「ママ」と、オレ。「すまなかった。今朝、つまり、逃げて。ここにい
るべきだった」アム叔父さんに会えたのはよかったけれど、オレはあや
まった。
「いいのよ、エド」と、おふくろ。「なぜ出て行きたかったか、分かる
気がする。でも、どうやって事件のことを知ったの?ここへ刑事さんが
来たとき、エドはいなかったし」
「階段にいたんだ」と、オレ。「話し声が聞こえた。それで中へ入りた
くなかった。エルウッド出版に電話して、話した?」
おふくろは、うなづいた。「ええ、葬儀屋から。エドはひとりで勤め
に出たと思って電話したのよ。上司はいい人で、必要なだけ休んでいい
と言ってくれた。準備ができたら、いつでも戻っていいと。エドは、戻
るんでしょう?」
「そう思う」と、オレ。
「いい商売だわ。ウォリーは、エドはよくやっていると言ってた。がん
ばってやるべきよ!」
「そのつもりさ」
「食事は?なにか作ろうか?」
おふくろは、確かに、別人だった。前は、オレが空腹かどうかなんて
気にもしなかった。
「ジェーンズビルで食べた」と、オレ。「アム叔父さんは、ホテルに泊
まるので、電話すると言っていた。室が取れたかどうか知らせるために」
「ここへ来ればよかったのに!」
どう答えたらいいか分からなかった。オレは、また、ラジオのダイヤ
ルをいじって、おふくろを見なかった。おふくろが、みじめに見えて、
顔を見れなかった。
しばらくしてから、おふくろが言った。「聞いて、エド!」
「ああ」
「エドには、そんなに好かれてないことは知ってる。ガーディにも。家
を出てゆきたがってるのも知ってる。エドは、もう18だし、わたしと
は義理の関係だし。エドを責めない。でも、しばらくのあいだだけ、こ
こにいてくれる?
しばらくしたら、始めるつもり。ガーディとわたしはどこかアパート
を捜して、わたしは仕事につく。ガーディも、エドのように高校を出て
ほしいし。家賃は9月初めまで払ってあるから、そのあとは月払いにし
てもらって、翌月分は払わなければならない。ここは、わたしたちだけ
では、広すぎる。なにを言いたいか分かるでしょ?エドは、それまでこ
こにいてもいいし」
「分かった」と、オレ。
「助け合えるわね?しばらくは、いっしょにやってゆける、エド?」
「もちろん」
「葬式が済んだら、仕事を捜す。たぶん、また、ウェイトレスね。ここ
を出る前に家具を売るわ。そんなに高くはないでしょうけど、葬式代く
らいにはなる」
オレは言った。「売るのはいいけど、葬式代の心配はいらない。共済
組合基金が葬式代を出してくれる」
おふくろは、ピンと来ないようだったので、説明した。おやじは、あ
と数年くらいで商売から身を引くつもりだったので、共済組合基金の満
額とまではいかないが、国際や地方も含めると、500ドルくらいの共
済金がもらえる。詳しいところまでは知らないが、そのくらいにはなる」
おふくろはきいた。「確かなの、エド?共済金がもらえるの?」
「確かさ」と、オレ。「ITUは、しっかりした組合で、大丈夫。あて
にしていい。たぶん、エルウッドからも少しは出る」
「それなら、すぐにハイデンに行って来る!」
「なにしに?」
「ウォリーの葬式は、りっぱにあげたいのよ、エド。できるだけりっぱ
に。借金しなきゃできないと思ったから、家具代くらいでお願いした。
出せる額は、200ドルで、これが精一杯だった。2倍にしてもらうよ
う言ってくるわ!」
オレは言った。「おやじは、葬式代だけに使ってほしくはないと思う
よ。スタートには、いろいろかかる。ママとガーディのスタートには。
家賃だって、葬式代以外の費用も、いろいろと。だから、ハイデンの葬
式代はそのままでいいと思う」
おふくろは立ち上がった。「行ってくるわ。みすばらしい葬式なんて」
オレは言った。「葬式は、あさってだ。明日、共済金の正確な額を調
べたあとにすればいい。明日の朝まで待って、ママ!」
おふくろは、ためらっていたが言った。「分かったわ、明日の朝でも
遅くはない。コーヒーをいれるけど、飲む?おなかはすいてなくても、
コーヒーは飲めるわね?」
「いいね」と、オレ。「手伝おうか?」
「そこに座ってて!」おふくろは、時計を見た。「刑事がエドに会いた
いそうよ。名前はバセット。8時にここへ来る」
おふくろはドアの方を向いた。「ありがとう、エド。ここにしばらく
いると決心してくれて。あと、ほかのことにも。わたしは、たぶん」
頬を涙が伝った。
オレも、泣きたかった。だが、ただ、座っていただけだった。なんて
言ったいいか分からなかった。
オレは言った。「ママ━━━」
オレは、腕をおふくろにまわして慰めてあげたかった。しかし、今ま
でそんなことしたこともないのに、できるもんじゃない。10年のあい
だ、一度も。
おふくろは、キッチンへ行った。電気がつく音がした。
オレは、内面に複雑な思いを感じた。
3
バセットは、8時に来た。オレはおふくろとコーヒーを飲んでいた。
おふくろは、もう1杯コーヒーを出して、バセットは、テーブルの斜め
向かいに座った。バセットは、刑事のように見えなかった。背が高くな
く、ふつう、オレと同じくらいで、体重もオレより重くはなかった。色
あせた赤毛で、そばかすがあった。目は、シェルぶちメガネの奥で疲れ
たように見えた。
しかし、バセットは良心的で友好的だった。刑事のようにはまったく
見えなかった。
質問をたくさんする代わりに、バセットは、ただ、こうきいただけだ。
「どうしたんだい、エド?」そして、あとはオレが話すことを、聞いて
いた。オレは、バセットにすべて話した。両親の室をノックしたところ
から、おやじの答えがなかったこと。話さなかったのは、おふくろが、
靴以外は服を着たままだったこと。関係ないことだからだ。おふくろが
どこへ行こうと、今のこととは関係がなかった。
オレの話が終わったとき、バセットは座ったままで、なにも言わずに
コーヒーをすすっていた。オレも黙って、おふくろも黙っていた。電話
が鳴った。たぶんオレにだと言って、居間の電話のところへ行った。
アム叔父さんだった。ノースクラーク通りのワッカー街に室を借りた
そうだ。ここから、数ブロックしか離れてなかった。
「いいね」と、オレ。「すぐにここへ来てくれるよね?刑事のバセット
が来てる!」
「そうだな」と、アム。「マッジは、大丈夫そうか?」
「オーケーさ。すぐに来てくれて大丈夫!」
オレは、キッチンに戻り、アムがこれから来ると話した。
「彼は、カーニバルで働いていると言わなかった?」と、バセット。
オレはうなづいて、言った。「彼はいいやつさ。ところで、バセット
さん、ストレートに聞きたいことがあるんだけど!」
「どうぞ!」
「警察が、つまり、あなたが犯人を見つける可能性はどのくらい?多少
は、あるの?」
「多少もない」と、バセット。「捜査中のものは、なにもない。こうい
う犯行を行う犯人は、犯行時につかまる可能性は高い。パトロールカー
に警戒しなくてはならないし、巡回警官も先に見つけなくてはならない。
犯行時に逆にタックルされたらやり返さなければならない。
しかし、犯行をやり遂げて逃げおおせたら、かなり安全になる。犯人
が口をすべらさない限り、犯人をつかまえるチャンスは、千に1つか、
千に10くらいになる」
オレは言った。「こういう犯行?」オレは一般的な話にしたかった。
おやじのことは触れたくなかった。「つかまえるチャンスがあるとした
ら、なにかな?」
「いろいろありうる。目撃者がいたかもしれない。多くの質屋を見てま
わってるが、犯人が持ち込むかもしれない。それを逆にトレースできる」
「おやじは、時計を持ってなかった」と、オレ。「少し前に修理に出し
たんだ」
「そうだな。別の手もある。彼はつけられていたかもしれない。食い物
屋で、札束を見られて、だれかにつけられたかもしれない。その食い物
屋に、もしかしたら目撃者がいて、犯人の特徴を覚えているかもしれな
い。あるいは、単に、犯人の知り合いとか」
オレはうなづいた。「おやじが昨夜、どこにいたか分かってる?」
「最初は、クラーク通り。そこで、少なくとも2軒の食い物屋に寄って
いる。もっとかもしれない。店では、それぞれ2杯づつビールを飲んで
いる。彼は、ひとりだった。最後にいた店は、分かっている。そこが最
後だと、かなり確信している。シカゴアベニューの西、オルレアンの逆
側。そこでもひとりで、あとをつけたやつはいなかった」
オレはきいた。「そこが最後だと、なぜ分かった?」
「彼は、家に持ち帰るために、ビールを数本買った。それが1時で、彼
が発見されたのが、だいたい2時だった。その場所が、ここと最後の店
の途中だった。そのまま家路についたかのように。そのあいだに、食い
物屋はなかった。店が2軒あったが、それも徹底的に調べた。彼は、立
ち止まったかもしれないが、ビールを持ってたことや、時間とかを考え
て、それ以上寄り道はしてないようだ」
「どこで、どこでおやじは見つかった?」
「オルレアンとフランクリンのあいだの路地、シカゴアベニューの2・
5ブロック南」
「ヒューロンとエリーのあいだ?」
バセットは、うなづいた。
オレは、言った。「それなら、オルレアンの南に歩いて行って、フラ
ンクリンに抜ける路地を近道したんだ。しかし、なんだって、近くなる
わけでもないのに、路地を抜けようとしたんだ!」
バセットは、言った。「ふたつ考えられる。ひとつは、彼はビールを
かなり飲んでいた。分かってるよりずっと飲んでいて、これ以上は飲め
ず、外にいて、時間も9時から1時になろうとしていた。ビールは慣れ
ていて、家からずっと飲んでいるから、安易に路地を抜けようとしたの
さ。エドが言うように、路地を抜けても、近くなるわけでもないのに」
「もうひとつは?」
「今まで路地を抜けたことはなかったということさ。彼は、フランクリ
ンのはずれにいた。つまり、シカゴからフランクリン、そしてフランク
リンの南までずっと歩いていた。路地の入り口で強盗に会い、強盗は彼
を路地に引きずり込んで、撃った。そのあたりの路地は、明け方のその
時間は、かなり人通りがまばらで、フランクリンの高架鉄道の下は、よ
くホールドアップがある」
オレは、考えながら、うなづいた。バセットは、刑事のようには見え
なかったが、にぶいめんどりでもなかった。バセットの言った可能性の
どちらも起こりえた。一方もあるし、他方もある。オッズはイーブンだ
った。
強盗は、かなり手慣れていて、ぬかりなかった。バセットの言うよう
に、だいたい、千に1つだった。
オレは考えた。「バセットは、この件では、アム叔父さんよりできる
かもしれない。おやじの足取りをかなりよく調べていた。このあたりで
は、楽な仕事というのはない。クラーク通りとシカゴアベニューでは、
みんな警官を毛嫌いしている。違法ギリギリの連中ばかりだ」
◇
アム叔父さんが来て、おふくろが出迎えた。ふたりは、ホールでしば
らくおしゃべりした。オレは、声が聞こえたが、話の内容は分からなか
った。キッチンに来たときは、仲がいいようだった。おふくろは、もう
一杯、コーヒーを入れた。
バセットは、アムと握手して、すぐに打ちとけたようだ。バセットは、
少しだけ質問した。オレがジェーンズビルへ行ったかどうかはきかなか
った。ふと思いついたような質問ばかりだった。オレがどの列車で来た
かとか、どんなサービスだったかとか、そのようなことだった。オレが
しゃべった話が本当かどうかをチェックするようなことはきかなかった。
頭のいいアヒルだと、オレは考えた。
しかし、アム叔父さんが捜査について、いくつかきき始めるまで、オ
レはものごとの半分しか見てなかった。バセットは、最初の2つの質問
に答えていると、口のはしがすこしめくれ上がった。
バセットは言った。「エドにきいたらどうだ?そのようなことは、エ
ドに、ぜんぶ話した。ふたりで立ち向かうわけだ。幸運を!」
アムはオレを見た。眉毛がすこし上がった。バセットはオレを見てな
かったので、首をすこし振って、刑事にはべらべらはしゃべってないこ
とを伝えた。頭のいいアヒルだ。なにを考えているのか、オレには分か
らなかった。
ガーディが帰ってきて、アム叔父さんに紹介された。おふくろは、ガ
ーディに映画を見に行かせていた。ガーディは本当に映画を見に行った
らしい。そうでなければ、こんなに早く帰るわけなかった。
アム叔父さんは、ガーディの頭を親しみをこめて軽くつついていた。
子どものように。ガーディはそれを嫌がっていたので、オレをそう言っ
た。ホームドラマの5分間のようなことがあって、ガーディは自分の室
へ行った。
アムはオレにニヤリとした。
コーヒーが冷めたので、おふくろは新しく入れに立った。アムは言っ
た。「外へ出て、今度は、酒にしよう。どうだい、バセット?」
刑事は肩をすくめた。「いいね。今は非番だし」
おふくろは首を振った。「あなたたちだけで、どうぞ」
オレは自分をわきまえていた。「のどがかわいたんで、セブンアップ
かコークが飲みたい」
アムは言った。「いいとも」
おふくろはなにも文句を言わなかった。みんなは外で出た。
◇
オレたちは、グランドアベニューの店に入った。バセットは、ここは
静かでいいと言った。たしかに静かで、客はオレたちだけだった。
ブース席に座って、ビール2杯とコカコーラを注文した。バセットは
電話をしてくると言って、電話ブースへ入った。
オレは言った。「彼はいいやつさ。どちらかというと、オレは好きな
ほうだ」
アムは、ゆっくりうなづいて言った。「彼はのろまじゃないし、正直
でもないし、しらみでもない。医者が推すようなやつだ」
「うん?彼が正直でないと、なぜ分かった?」オレは世間知らずじゃな
いし、多くの警官が正直じゃないことも知っている。ただ、アムがどう
やってそんなにすぐそう確信したのか不思議だった。あるいは、ハッタ
リで言ってるのだろうか?
「彼を見ただけで、そう感じた」と、アム。「なぜかは分かないが、分
かるのさ。カーニバルで野球チームを作ったことがあった。ラケットに
ボールが当たるように、エドも、そのうち人間を見抜けるようになる」
オレは、なにかで読んだことを思い出した。「ロンブロッソの犯罪心
理学」
「ロンブロッソのおかげだな。顔かたちのことじゃない。心で感じるな
にかさ。なぜかは分かない。あの赤毛の刑事は、買収できる」
アムは、財布を取り出して、バーにいるふたりには見えないように、
テーブルの下で、紙幣を1枚出した。財布は尻ポケットに戻した。紙幣
を2つ折にして、手のひらにしまった。チラッと見えたが、100ドル
紙幣だった。
オレは、すこし恐ろしくなった。アムが、なぜバセットを買収する必
要があると思ったのか、まったく分からなかった。アムが間違っていて、
トラブルになったら困る気がした。
バセットは戻ってきて、座った。
アムは言った。「バセット、聞いてくれ!このような事件では、警察
はお手上げなのは分かる。しかし、ウォリーは、オレの兄だ。ウォリー
を殺したやつが、捕まるのを見たい。コテンパンにされるのを見たい!」
バセットは言った。「ベストを尽くしてる」
「それは分かっている。しかし、警察には、捜査にあてられる時間は、
そう多くはないだろう。オレは、できるだけのことをしたい。1つのこ
とだけだが。つまり、わずかだが、心付けがある。歌いたくない者に歌
わせることはできない。言いたいことは分かるだろ?」
「ああ、分かる。助けにはなる」
アムは、手のひらを下にして手を差し出した。「これを取っておいて
くれ。オレたちのためになりそうなら、どんどん使ってほしい」
バセットは紙幣を受け取った。テーブルの下で紙幣の角を確認するの
が、見えた。紙幣をポケットにしまった。顔色ひとつ変えなかった。な
にも言わなかった。
飲み物のお代わりを注文した。つまり、ふたりは。オレはコークの半
分も飲んでなかった。
バセットの目は、シェルぶちメガネの奥でもっと疲れたように、もっ
とベールがかったように見えた。「聞き込みでは」と、バセット。「そ
れ以上は聞き出せなかったが、クラーク通りでは、2軒の店にそれぞれ
30分くらいづつ立ち寄った。グランドアベニューでは、ひとつの店に
立ち寄った。そこで、ビールを買った。おそらく、それが最後の店だっ
た。ほかになにかあるとしたら、そこだが、まだなにも」
「そのあいだは?」と、アム。
バセットは、肩をすくめた。「酔っ払いには、2つのタイプがある。
ひとつは、どこかに座って、酒を飲むタイプ。もうひとつは、ぶらぶら
するタイプ。ウォリーハンターは、ぶらぶらするタイプだった。4時間
外出していたが、3つの店に寄るのは、それぞれ30分くらいで2・3
杯のビールを飲んだ。それが平均ということなら、歩きを考えても、も
しかしたら6から7つの店に寄ったのかもしれない」
「飲んだのはビールだけ?」
「だいたいは。ある店では、バーテンダーが覚えてなかった。シカゴア
ベニューで最後の一杯を飲み干すと、持ち帰りのビールを買った。カウ
フマンの店だ。主人の話では、ウォリーは静かにビールを飲んでいたそ
うだ。酔ったふうでなく、きちんとしていた」
「カウフマンは、なにを?つまり、バーの主人という以外で」
「だれも多くは知らない。違法なことをしてないかどうかも、分からな
い。なにかあったとして、つかんでないだけかもしれない。シカゴアベ
ニュー駅周辺の聞き込みでは、なにも出なかった。知る限り、クリーン
さ」
「カウフマンと話したときは、どうだった?」
バセットは言った。「隠すことはできただろうが、オレは、この事件
とは無関係だと思う。すぐに、写真のウォリーを認めたし、店をあとに
した時間も覚えていた。ほかの人と同じラインだ。つまり、そこにいた
ことを覚えていて、出て行った時間も覚えていた。なにかトラブルがあ
ったようには見えなかった、と言っていた。絵描きからメガネを取り上
げて、それで見てみたが、返したってかんじだ」
「みんな、そんなふう?」
「そうだな」と、バセット。「明日の検死のあと、彼に会って聞いてみ
ればいい」
「そりゃいい」と、アム。オレに。「明日の検死では、オレを知らない
ことにしてくれ!一番後ろの席に座るから、だれもオレを知らないこと
に。だれも聞きにこないだろう」
バセットの目が少しきらめいた。ほんの少し。
「なにか策でも?」と、バセット。
「たぶん」と、アム。
ふたりは、互いに了解したようだった。ふたりには分かっていたが、
オレは分からなかった。
◇
テントでホーギーが、アムと話していたときのように。あのときは、
カーニバルのことで、オレが知る必要はなかったが、今は違った。ふた
りが話しているワードは分かるが、意味が分からなかった。
オレは気にしなかった。
バセットは言った。「切り口はいい。確かじゃないが」
オレにはピンと来なかった。オレは言った。「おふくろはやってない」
バセットはオレを見た。オレは思っていたほど、彼を好きでない気が
した。
アムが言った。「エドが正しい。マッジは」少し間をおいた。「マッ
ジはウォリーを殺してない」
「そうだな。似たような事件があって」
「ああ、100万に1つのまれなケースだ。それでも、マッジはウォリ
ーを殺してない。たしかにマッジは、ウォリーが帰宅するまで待ってか
ら、包丁かなにかを持って、いっしょに外出することもできた。しかし
この事件は違った。ウォリーのあとをつけて、路地でこん棒で殴ったわ
けじゃない。ところで、凶器はこん棒?」
「いや、もっと硬いなにかだ」
「どんな?」
「もっと硬くて、振り回せる重さのあるものだ。先がとがってないもの、
鋭いエッジのないもの。ゴルフクラブとか鉄パイプ、空のボトルといっ
たような」
鈍器だ、とオレは考えた。新聞記事でよく見かける凶器だ。記事にさ
れたとしてだが。
1匹のゴキブリが、バーカウンターから床をはってきた。黒くて大き
いやつだ。床のつなぎまで来ると、少しうろうろして止まった。そして
10インチ走り、止まって、また10インチ走った。
バーの従業員が見つけて、歩いてきて踏みつけようとしたが、ゴキブ
リはぎりぎりかわして逃げた。
しかし2回目はラッキーはなかった。クチャッという音がした。
「そろそろ」と、バセット。「家に帰る時間だ。さっき電話したが、妻
が病気らしい。重くはないが、薬を買ってきてほしいそうだ。それじゃ、
明日の検死でまた」
「オーケー」と、アム。「さっきの計画で、検死では話はできない。そ
のあと、ここでまた落ち合うというのはどうだい?」
「そうしよう。じゃ、また。エドもまた」
バセットは帰った。
◇
オレは考えた。100ドルといえば、大金だ。したくもない仕事をさ
せるために、オレに100ドルくれるような奴のいる仕事でなくてよか
った。
しかしよく考えてみると、バセットは、悪事をしろと言われたわけで
はなく、単に、オレたちの仲間になって、協力してほしいと言われただ
けだ。いろいろと役立つ情報がほしいと。そのことは正しい。ただ、そ
れに対して金をもらうのは悪かった。しかし、バセットには病気の妻が
いる。
ただ、とオレは考えた。アムは、バセットに病気の妻がいることを知
らなかった。しかし、バセットが100ドル受け取ることは知っていた。
アムは言った。「いい投資さ!」
「たぶんね」と、オレ。「でも、バセットが正直でないなら、正しい情
報をくれたのかどうか、どうやって分かる?100ドルもらっても、な
にもしてくれないかもしれない。100ドルといえば、大金だ!」
アムは言った。「10セントが大金なこともある。100ドルが大金
でないことも。オレは、100ドルに値する情報が得られると考えてい
る。どうだい、これから現場を見てまわるというのは?1つチェックし
ておきたいことがある。その気になれるか?」
「いいとも!」と、オレ。「どうせ帰っても眠れない。まだ、11時だ
し!」
アムはオレを見た。アムは言った。「エドは21才で通ると思う。聞
かれたら、オレは父親だと言えば疑われない。同じ苗字だし、家族のよ
うにふるまった方がいい」
「つまり、正体を明かす必要はないということ?」
「そう。店に入ったら、それぞれビールを注文する。オレは、すぐに飲
んでしまうが、エドは、なめる程度にする。それから、オレがグラスを
交換する」
「すこしなら大丈夫!」と、オレ。「もう18だし」
「すこしなら大丈夫!だが、その程度でいい。グラスを交換するってこ
とでいいか?」
オレはうなづいた。議論の余地はなかった。とりわけ、アムが正しい
場合は。
◇
オレたちは、グランドアベニューからクラーク通りへ北に向かって歩
いた。オンタリオの角で立ち止まった。
「おやじが歩いた道順に近い」と、オレ。「つまり、ウェルズ通りから
オンタリオへ、北に向かっていたんだと思う」
オレは、そこに立った。オンタリオを見てるうちに、おやじが歩いて
くる気がした。
すごくつらかった。おやじはハイデンの厚板の上に横たわっているの
だ、と考えた。葬儀屋は、血を抜いて、防腐剤の液体をつめたのだろう。
暑いから、手早くしなくてはならなかったのだろう。
おやじは、もう、父ではなかった。おやじは、暑い日なんて気にもし
なかった。おやじは、冷たくなった。寒い日には、おやじは外出したく
なかった。たった1ブロックや2ブロックでさえ、イヤだった。しかし、
暑い日は気にもかけなかった。
アムは言った。「ビアバレルとコールドスポット、この2つで間違い
はない?」
オレは言った。「オレが聞いてなかったときに、バセットがなにか言
ったのかもしれないが、聞き逃した」
「聞いてなかった?」
「ゴキブリを見ていた」と、オレ。
アムは、なにも言わなかった。また、歩き出し、通り過ぎた店名を見
ながら歩いた。北クラーク通りをループノースからバグハウス広場にか
けて、食い物屋は、1ブロックにだいたい3・4軒あった。安く飲み食
いできる通りだった。
ヒューロンの北にあるコールドスポットに来た。オレたちは、店に入
り、バーカウンターに立った。奥のギリシア人たちは、オレにはほとん
ど見えなかった。
バーカウンターに数人の男たちがいるだけだった。女はいなかった。
後ろの方のテーブルで酔っぱらいが眠っていた。オレたちは、それぞれ
ビールを注文した。アムがオレの分の大半を飲んだ。
ビアバレルでも、同じことをした。シカゴの近くの、通りの逆側を上
がったところにあった。そこも同じかんじで、少し広く、客も少し多く、
バーテンダーもひとりでなくふたり、テーブルで眠っている酔っぱらい
も、ひとりでなく3人だった。
オレたちの近くに客はいなかったので、自由に話せた。
オレは言った。「これから誰かにきくつもり?おやじがなにをしてい
たかとか、なにか?」
アムは首を振った。
オレは、知りたかった。「なにを見つける?」
「なにをしていたか。なにを捜していたか」
オレは、そんなことできないと思った。聞き込みもしないで、なにか
を見つけることなんて、できるはずなかった。
アムは言った。「よし、見せてあげる!」
オレたちは外へ出た。来た道を1ブロック戻り、別の店に入った。
「分かった」と、オレ。「どういうことか分かった」
しばらく口がきけなかった。ここは、まったく違った。音楽があって、
そう呼ぼうとすればだが。そして、男より女が多かった。ほとんどは若
くはないが、数人は若かった。ほとんどみんな酔っていた。
売春婦ではない。すこしはそうかもしれないが、多くはない。ただの
女たちだった。
オレたちは、また、それぞれビールを注文した。
オレは考えた。おやじがこの店に、ビアバレルやコールドスポットの
代わりに、こんなかんじの店に、来なかったことがうれしかった。おや
じは、ただ酒を飲みたかっただけだった。酒だけだった。
◇
オレたちは、また北へ向かい、通りの西の側に戻って、シカゴアベニ
ューの角をまわった。
警察署の前を通り、ラサラを過ぎ、ウェルズも過ぎた。おやじは、こ
こで南に向かうこともできた、とオレは考えた。12時半で、おやじも
だいたい同じ時間にここにいた。
昨夜だ。オレは考えた。まだ、昨夜だ。おやじもここにいたのだ。通
りの同じ側を、今のように歩いていたのだ。ほんの昨夜のことだ。だい
たい同じ時間に。ちょうど12時半。オレは考えた。
オレたちは、フランクリンの高架鉄道の下に出た。
列車が頭上で轟音をたて、夜を引き裂いた。夜中だと、こんなに高架
鉄道がうるさいのが不思議だった。ウェルズまで1ブロックで同じ高さ
なので、夜ならだれでも音が聞こえるだろう。オレでも目が覚めてれば。
あるいは、朝早く、最初に目覚めるとき、まだ、ベッドにいるときとか、
でなければ、聞こえないだろう。
オレたちは、オリンズ通りの角まで歩いて、そこで立ち止まった。道
に交差して、トパーズビールのネオンサインがあった。シカゴアベニュ
ーの北の端だった。角に2つのドアがあった。カウフマンの店だった。
ここは、行ってみるべきだった。このブロックで、唯一の店だったから
だ。
おやじの最後の立ち寄り場所。
オレはきいた。「あそこへ行かないの?」
アムは、ゆっくり首を振った。
オレたちは5分くらいそこで立っていた。なにもせず、話もせずに。
なぜカウフマンの店へ行かないのか、オレはきかなかった。
それから、アムが言った。「そろそろ?」
オレは言った。「そうだね」
オレたちは、向きを変えて、オリンズ通りを南に歩き始めた。
今からそこへ向かった。その路地へ向かった。
4
その路地は、ただの路地だった。オリンズ通りの端は、一方が駐車場、
他方が菓子工場になっていた。工場に沿って、運搬用のプラットフォー
ムがあった。
路地は、粗い赤のレンガで舗装されていた。ふち石はなかった。
街灯が1つあって、オリンズ通りの街灯より小さかった。
フランクリン地区へ降りてゆくと、坂の下に、もうひとつ街灯があっ
て、路地の入り口の左を照らしていた。特に暗くはなかった。オリンズ
通りに立っていても、見えた。
路地の真ん中は薄暗いが、見ることはできて、もしもだれかが立って
いたら、フランクリン地区をバックに、人影のシルエットが見えただろ
う。
今は、そこにはだれもいなかった。
路地の真ん中あたりは、ぼろぼろの古くて低いビルの裏で、ヒューロ
ンとエリーに面していた。エリー側は、線路に沿った木のバックポーチ
と同じ階のバックドアに通じる木の階段だった。ヒューロン側は、同じ
高さで路地につながっていた。
アムは言った。「ウォリーがここへ来たなら、つけられていたに違い
ない。路地にだれかいたら、気づいていただろう」
オレは、ポーチを指さして言った。「ポーチのどこかに何人かいたの
かもしれない。酔っ払いが路地をよろよろ歩いてきて、通りすぎたので、
階段を降りてあとをつけて、路地の奥で━━━」
「ありえなくはないが、可能性はゼロに近い。ポーチにいたのなら、そ
いつらはそこの住民ということになる。自分の家の裏で、すこしは離れ
ていても、そういうことはしないだろう。ウォリーは、足がふらつくく
らい酔っていたかどうか、怪しい。店を出るとき、どのくらい酔ってい
たかというバーテンダーの話は、割り引いて考えるべきだ。トラブルに
巻き込まれたくない気持ちから言ったことだから」
「ありえなくはない」と、オレ。「可能性は低いが、ありえなくはない」
「確かに。そこを調べよう。このあたりのアパートのだれでもいいから、
話してみよう。可能性を逃すべきでない。オレの言ったことは、絶対な
いということではないんだ」
夜中の路地でしゃべる音量くらい静かに、オレたちは話していた。路
地の半分は過ぎて、アパートもいくつか過ぎていた。フランクリン通り
に面した低いビルの裏にいた。両側とも3階建てで、1階が店で、上が
アパートだった。
アムは立ち止まって、腰をかがめた。「ビール瓶のガラス片だ。ここ
が事件現場だ」
オレは、おかしな気分になった。ほとんどめまいに近かった。ここが、
その場所だった。今、オレが立っている、ちょうどここが、その場所だ
った。
それ以上、考えたくなかった。それで、オレも腰をかがめて、見始め
た。琥珀色のガラス片だった。数ヤードにわたって広がっていた。ビー
ル瓶2・3本の量に十分だった。
それは、落ちてそのままだったわけでは、もちろんなかった。路地を
歩く人々に蹴られたり、トラックにひかれたりしていた。もっと細かく
なっていて、もっと広がっていた。しかし、円のままで、ガラスが散ら
ばった円の中心が、ビール瓶が落ちた場所だった。
アムは言った。「ラベルの一部がある。カウフマンが売ったブランド
か分かる」
オレは、それを拾って、路地の端の電灯まで歩いていった。オレは言
った。「トパーズビールのラベルの一部だ。おやじが買ってきたビール
で、何千回も見ている。カウフマンの店にトパーズのネオンサインがあ
る。しかし、このへんではよく売られているビールだ。確かなことは言
えない」
アムはやって来て、オレたちは、フランクリン通りの両方向を眺めた。
貨物列車が、頭のすぐ上を通過していった。長い貨物列車で、ノースシ
ョア鉄道に違いなかった。まるで世界の終わりが来たかのように、騒々
しかった。
◇
騒音は、かなり大きかった。銃声を消すのにじゅうぶんだと、オレは
考えた。ビール瓶を落とした騒音を加えても。この騒音が、もっと暗い
路地の真ん中でなく、それよりも明るい路地の端で起こったことを説明
していた。犯人は、ここへ来たときにおやじを背後から襲い、高架鉄道
が通過した。おやじが大声で叫んだとしても、高架鉄道の騒音が、口笛
のようにしてしまった。
路地の両側には、店があった。1つは、水道の配管部品を売る店だっ
た。もう1つは、空き家だった。長い間、空き家だったようで、ガラス
が曇って中が見えなかった。
アムは言った。「そろそろ、エド」
「分かった。今夜やれることは、こんなところだと思う」
オレたちは、フランクリン通りをエリーへ下り、ウェルズを渡った。
アムは言った。「なにが悪いか、分かった。腹が減ったのだ。お昼か
らなにも食べてない。エドも2時から食べてない。クラーク通りでなに
か食おう!」
オレたちは、24時間営業の焼肉店に入った。
オレは、ポーク焼肉サンドを一口食べるまでは、空腹は感じなかった
が、これをたいらげると、フレンチフライにサラダも食べた。さらに、
ふたりとも、おかわりを注文した。
おかわりが来るのを待っているとき、アムがきいた。「エド、なにを
目指してる?」
「どういうこと?」
アムは言った。「つまり、この先50年あまりで、なにをする?」
答えは、考えるまでもなく、明らかだった。オレは言った。「たいし
たことじゃない。オレは見習いの印刷工で、見習い期間中に習ったライ
ノタイプを多少は動かせる。職人にもなれる。印刷というのは、将来性
のある職業だ」
「そうだろうと思った。シカゴにずっと?」
「そこは考えてなかった」と、オレ。「すぐには出ていかない。見習い
期間が終わったら、旅が好きだから、どこか別の場所で仕事をみつける」
アムは言った。「商売はいい。しかし、一度商売を始めると、離れら
れなくなる。同じように━━━おっと、オレは、オランダ人じゃないの
に、オランダ人のオジのようにしゃべっている!」
アムは、歯を見せて笑った。アムは、女性に話すかように、なにかし
ゃべろうとしていた。オレがそれを分かっていることも、分かっていた
し、話す必要もなかった。そんなふうにきいてくれたことが、うれしか
った。
その代わりに、アムはきいた。「エド、夢は?」
オレは、アムを見た。アムはまじめだった。オレはきいた。「これっ
て、修学旅行の夜?あるいは、精神分析かなにか?」
「その中間だ」
オレは言った。「今朝、夢で、質屋の窓に見えるトロンボーンに、手
を伸ばしていた。ガーディは、歩道でなわとびをしていた。トロンボー
ンに触れる前に目が覚めた。これで、オレのすべてが分かったんじゃな
い?」
アムは、声に出さずに笑った。「それは、エド、止まっているあひる
を撃つようなもんだ。1発で2羽。2羽のうち1羽だけを見るべきだと
言ったら、どっちのことだか、分かる?」
「分かると思う」
「彼女は、毒だ。エドのような若者にとっては。マッジがそうなように
━━━ここは省くとして、トロンボーンはどう?吹いたことは?」
「言葉通りでは、ない。高校2年のときに、学校のトロンボーンを借り
られたので、バンドで演奏するくらいまで練習するつもりだった。しか
し近所から苦情が来て、かなりな騒音だったようだ。アパートに住んで
れば分かると思う。それに、おふくろが音が嫌いだった」
カウンターにいた店員が、サンドイッチのお代わりを持ってきた。も
うそれほど空腹ではなかった。横からみると、すごく大きく見えた。オ
レは、フレンチフライを最初に少しだけ食べた。
それから、バーベキューサンドのパンのふたを持ち上げて、ケチャッ
プを分厚くかけた。
それは、まるで━━━。
サンドのふたをピチャっと乗せた。そして、それがなにに見えたか考
えまいとした。しかし、オレは、ふたたび路地に戻っていた。出血があ
ったのかさえ知らないし、おそらく、なかった。出血させずに殺すこと
は、いくらでもできる。
しかし、オレは、昨夜、血だらけになったおやじの頭や、路地の粗い
レンガの上に、血がしたたるさまを想像した。今、血は洗われたのか、
きれいになっていた。誰かが、洗ったのだろうか?いや、たぶん血なん
か出なかったのだ。
しかし、サンドイッチは、気持ち悪くなった。すべて忘れてしまわな
い限り。オレは目を閉じて、今の想像は最初からナンセンスだったと心
に繰り返した。いち、に、さん、オーレイリー、よん、ご、ろく、オー
レイリー。
すぐにオレは、勝った。気分の悪さは回復した。オレは、アムから視
線をはずして、カウンターの方を見た。
オレは言った。「たぶん、おふくろがオレを待っている。まだ、おふ
くろに遅くなると言ってなかった。もう1時すぎだ」
アムは言った。「なんてこった!オレも忘れていた。エドはすぐ帰っ
た方がいい」
サンドイッチの残りは食べたくないと、オレは言った。アムは自分の
分は食べ終わっていた。オレたちは店の外で別れ、アムはワッカー街の
ある北へ、オレは、ウェルズ通りの自宅へ急いだ。
おふくろは、オレのために玄関の明かりをつけっ放しにしていたが、
待ってはいなかった。おふくろの室のドアは暗かった。オレは、ほっと
した。説明したり謝ったりしたくなかった。もしも、待っていて心配し
ていたら、アムをとがめただろう。
オレは、すぐに静かにベッドに入った。目を閉じた瞬間に、眠ってし
まった。
◇
目が覚めたとき、室のなにかが違っていた。なにかが違う。いつも通
りの朝で、室は暑く、閉め切っていた。横になったまま、違いに気づく
まで1・2分かかった。目覚まし時計が止まっていたのだ。巻いてセッ
トするのを忘れていた。
今の時間が重要かどうか分からなかったが、知りたかった。起き上が
り、キッチンへ時計を見に行った。7時1分だった。
奇妙だと思った。自分の室の時計が止まっていても、いつも通りに目
覚めた。
ほかにだれも起きていなかった。ガーディの室のドアはあいて、パジ
ャマの胸元もあいていたので、急いで通り過ぎた。
自分の目覚まし時計を巻いてセットし、ふたたび横になった。できれ
ば、あと1・2時間は眠るべきだった。しかし、眠りに戻れなかった。
眠気さえなくなった。
アパートは、おそろしく静かだった。今朝は、外も大きな物音はしな
かった。ただし、数分ごとに、フランクリン駅を通過する高架鉄道の音
を除いて。
時計のチックタックいう音が、だんだん大きくなった。
今朝は、おやじを起こしに行く必要はない、とオレは考えた。もう2
度とおやじを起こす必要はないのだ。だれも。
起き上がって、服を着た。
キッチンへ行く途中、ガーディの室の前で立ち止まって、中を見た。
ガーディは、オレに見てもらいたいのだ、とオレは考えた。オレも見た
かった。なぜ、だめなんだ?答えは、オレが一番よく分かっていた。た
ぶん、オレは、おやじを起こしに行く必要がなくなったとか風邪気味で
イライラするはけ口が欲しかったのだ。正確にはそれも違う。30秒で、
オレは自分を軽べつして、キッチンへ行った。
コーヒーをいれて、座って飲んだ。今朝は、なにをしようとしていた
のか考えた。アムは、遅くまで眠っているだろう。カーニバルにいたと
きは、いつも遅くまで寝ていただろうから。とにかく、検死が終わるま
では、調査することはあまりない。そして、葬式が終わるまでは。
それに、今のような朝の時間、少し悲しかった。口ひげのある太った
小男と、耳の後ろが濡れた少年が、シカゴじゅうから、失業中の泥棒を
見つけようとしていた。
オレは、くすんだ赤毛の疲れた目をした犯人を思い描いた。オレたち
は、100ドルで買収した。あるいは、アムはそう考えた。ある面では、
アムは正しかった。バセットは、カネを受け取ったからだ。
パタパタという足音が聞こえて、ガーディがパジャマ姿でキッチンに
入ってきた。胸元もいっしょに。はだしの足先は、マネキュアで塗られ
ていた。
彼女は言った。「おはよう、エド。それ、コーヒー?」
彼女は、あくびをした。しなやかな子猫のようにのびをした。指のツ
メは隠れていた。
オレは、カップをもうひとつ出して、注いだ。彼女はテーブルの向か
いに座った。
彼女は言った。「ゲーッ!今日は、検死よ!」わくわくしてるかのよ
うに。まるで、「ゲーッ!今日は、フットボールの試合よ!」と言って
いるかのように。
オレは言った。「オレも検死させられるかな?やり方が分からない」
「エドは、させられないと思う。ママとわたしだけって、言っていたわ」
「なぜ、おまえが?」
「本人確認よ。わたしが最初に確認したの。ママは、葬儀屋でほとんど
気を失いかけていて、刑事さんたちは気を失われると困るようだったの
で、わたしが見たいと言ったの。あとでママが落ち着いてきて、刑事さ
んのバセット氏がママに話して、ママも見たいと言ったので、見させた
のよ」
オレは言った。「刑事たちは、おやじの身元をどうやって調べたのか
な?つまり、おやじは身分証明証を身に着けてなかったし、発見された
のが深夜だったから」
「ボビーが知っていたのよ。ボビーレインハート」
「ボビーレインハートって、だれ?」
「ハイデンで働いている男よ。まだ、見習い。何回か、わたしといっし
ょにでかけたことがあって、パパのことも見て知っていた。7時に出勤
したので、遺体を見てすぐに、刑事さんたちに誰なのかしゃべったの」
「そう」と、オレ。その若者は、今、思い出した。16か17くらいの、
青白い顔したヨタ者で、髪はいつもグリースでべったりで、いつも一番
いい服を着て高校に来ていた。自分で、自分のことを、女にもてる女た
らしと思っていた。
あいつが、おやじの体の処置を手伝ったかと思うと、イヤな気分にな
った。
コーヒーを飲み終えると、ガーディはカップを洗って自分の室へ着替
えに戻った。おふくろが起きて来る音がした。
オレは、居間へ行って、雑誌を手にした。外は雨が降り始めた。静か
な、しとしと雨だった。
探偵雑誌だった。ストーリーを読み始めた。ホテルのスイートルーム
で死体で見つかったのは、金持ちの男で、首に黄のシルクのロープが巻
かれていたが、毒殺だった。
多くの容疑者がいた。みんな、それぞれに動機があった。彼の秘書は、
彼に言い寄られていた。未亡人は、相続するという動機があった。秘書
のフィアンセは、死んだ男の金をゆすっていた。3章では、このゆすり
の男に焦点があてられ、犯人だったことが判明する。首に黄のシルクの
ロープがあって絞殺されたが、凶器は、このシルクのロープではなかっ
た。
オレは、雑誌を置いた。オレは考えた。実際の殺人は、そんなものじ
ゃない。
殺人は、今の事件のようなものだ。
おやじが水族館へ連れていってくれたことを思い出していた。なぜ、
思い出したのか分からない。6才くらいで、たぶん、5才だった。ママ
も生きていたころだったが、ママは行かなかった。おやじとオレは、よ
く笑った。あるさかなの顔がおかしかった。口をあけてビックリしたよ
うなさかなの顔も、おかしかった。
今思うと、おやじは、そのころは、よく笑っていた。
ガーディは、おふくろに、友人の家へ行って正午ごろ帰ると言った。
午前中は、ずっと雨だった。
◇
検死法廷では、ずっと座ったまま、始まるのを待っていた。ハイデン
葬儀屋のメインホールだった。「本日、検死法廷」という掲示はなかっ
た。しかし、出席者には伝わっていたようだ。席は40あって、ほとん
どふさがっていた。
金ぶちメガネの小男が、大声で文句を言っていた。検死官代理だった。
名前はあとで知ったが、ヒーラーだった。文句ばかり言う男で、早く始
めようと騒いでいた。
バセットと数人の刑事が来ていた。ひとりだけ制服の警官もいた。長
い薄い鼻で、プロのギャンブラーのような男がいた。ホールの最前列に、
6人の男たちが座っていた。
そしていよいよ、なにがあろうとも、すべて解決してしまいそうな、
検死官代理が槌で机をたたいた。みんな静まり返った。最前列の6人は、
陪審員で、代理は、なにか異論があるかどうかきいた。異論はなかった。
さらに代理は、ウォリーハンターや彼の死の経緯を知っているかどうか、
そのことをだれかと議論したかどうか、なぜ公平で正当な証拠や証人を
見つけられないのか尋ねた。返答は否定的で、法廷じゅうが納得した。
代理は、6人に仮置き場の死者を見せ、宣誓させた。
それは、形式を逸脱したなかでも、形式的だった。
それは、陳腐で、つまらぬ映画のようだった。
検視の進行中、代理は、死者の家族の者がいるかきいた。おふくろが
立ち上がり、進み出た。なにかをもぐもぐ言われて、なにかをもぐもぐ
言った。
名前と住所、職業、死者との関係。死者を見せられ、本人であること
を確認して、夫であると認めた。
おやじについての多くの質問。職業、勤め先、住所、どのくらい住ん
でいたか、といったようなこと。
「ハンター夫人、生きてる夫を最後に見たのは?」
「木曜の夜、9時ごろ。外出しました」
「どこへ行くと言って?」
「なにも。ビールを飲みに出かけてくる、とだけ。たぶん、クラーク通
りだと」
「彼は、たびたびそこへ?」
「ええ」
「週に?」
「1・2度」
「ふだんはどのくらいまで?」
「真夜中くらい。たまに、遅く、1時か2時」
「木曜の夜、お金は?」
「正確には分かりません。20ドルか30ドル。水曜が給料日だったの
で」
「もっと正確なことは?」
「なにも。水曜の夜に、25ドルくれました。生活費として。残りの家
賃や光熱費、その他もろもろを夫が」
「ハンター夫人、彼に敵は?」
「だれも」
「もっとよく考えて!彼を憎んでた者は?」
おふくろは言った。「いいえ、だれも」
「彼の死によって、利益を得るのは?」
「どういう?」
「つまり、お金は?ビジネスかなにかで利益は?」
「なにも」
「保険には?あるいは、保険をかけられて?」
「いいえ。自分から言ったことは一度。しかし、断った。その分、預金
した方がいいと。結局、どちらもしなかった」
「木曜の夜、ハンター夫人、帰りを待って?」
「ええ、しばらくは。しかし遅くなりそうで、先に寝た」
「ハンター夫人、夫が酔って、路地やらで危険な目にあったことは?」
「ええ、なんどか。2度ホールドアップがあった。最近では、1年前」
「負傷は?自己防衛は?」
「なにも。ホールドアップされただけ」
オレは、注意して聞いた。初耳だった。ホールドアップのことは、だ
れも話してくれなかった。しかも、1度ではなかった。思い出した。1
年前、財布をなくしたと言っていた。社会保障カードと組合カードを、
新しく作った。たぶん、おやじは、オレに話すことでもないと考えたの
だろう。
◇
代理は、出席している警察関係者に、質問したい者がいるか尋ねた。
だれもいなかった。代理は、おふくろに、もう席に戻っていいと言った。
「本人確認した者が、ほかにいたと聞いている。ミスハンター、ここに
いますか?」
ガーディが立ち上がって、もぐもぐをやった。そして、イスに座って、
足を組んだ。スカートのすそを直す必要はなかった。短かったからだ。
おやじを本人確認したこと以外のことは、聞かれなかった。おふくろ
のとなりの席に戻ったとき、ガーディはがっかりしたように見えた。
つぎに、普段着の男たちのひとりを立たせた。彼は、パトカーの警官
で、ふたり一組で巡回中に、死体を発見したのだ。
パトカーで、ゆっくり南へ走っていて、フランクリン通りの高架鉄道
の下で、2時ごろ暗い路地をサーチライトで照らすと、彼が倒れている
のを見つけた。
「発見されたとき、彼はすでに死んでいた?」
「はい。死んでから、おそろく1時間は」
「身分証は?」
「はい。持ってなかった。財布も、時計もなにもかも。なにもなくなっ
て、ポケットも。65セントだけ」
「倒れていた場所は、暗く、だれか通っても見つけられなかった?」
「いいえ。路地の突き当たりに、フランクリン通りの街灯があったが、
電球が切れていた。そのことは後で報告して、新しい電球がついた。あ
るいは、つける予定だと言われた」
「ほかに特別なことは?」
「顔に引っかき傷があった。落ちたときにできるような。撃たれたとき
に、顔から倒れた」
「それは分からない」と、代理。鋭く言った。「彼を発見したとき、顔
から倒れていた?」
「ええ。ビール瓶が割れたガラス片があった。そこはビールのにおいが
した。路地と彼の服が、濡れていた。彼は、ビール瓶を運んで━━━え
え、ここも推測です。こぼれたビールとビール瓶の破片があった」
「死体に、帽子は?」
「そばに1つ。かたい麦わらの帽子。いわゆるセイラーストロー。つぶ
れてなかったので、撃たれたときに、かぶってなかったらしい。彼が倒
れていた様子から、背後から撃たれたと思われる。犯人が追いついて、
片手で帽子をぬがせ、別の手でこん棒で殴るような。正面から撃って、
気づかれずに帽子をぬがせることはできない、彼が自分から帽子を取ら
ない限り」
「事実だけを述べてください、ミスターホーバース」
「はい、質問はなんです?」
「死体に、帽子は?これが、今の質問です」
「いいえ。かぶってなかった。近くにひとつ落ちてた」
「ありがとう、ミスターホーバース。終わりです」
警官は、証人席から降りた。オレは、昨夜、ものごとを間違えてとら
えていたと考えた。街灯がついていたからだ。事件当時は、消えていた。
路地のフランクリン地区の突き当たりは、かなり暗かっただろう。
◇
代理は、ノートを見てから言った。「カウフマン氏はいますか?」
背の低い太った男が、足をひきずりながら進み出た。厚いレンズのメ
ガネをして、奥の目がフードをかぶってるように見えた。
名前は、と彼は証言した。ジョージカウフマン。シカゴアベニューで、
カウフマンという店を持っていた。
はい、ウォリーハンターは、木曜の夜に、カウフマンの店に寄った。
30分ほど店にいて、それより長いとしてもたいした時間ではなかった。
それから、家に帰ると言って店を出た。カウフマンの店では、ウィスキ
ー1杯に、2・3杯のビールを飲んだ。質問されて、3・4杯だったか
もしれないと認めた。しかし、ウィスキーについては、1杯だけだった
と断言した。
「彼は、ひとりでしたか?」
「はい。ひとりで店に来て、ひとりで出ていった」
「店を出るとき、家に帰ると言いましたか?」
「はい。バーカウンターで立って飲んでいた。しゃべった言葉を忘れた
が、家に帰ると言った。ビール4本買って、支払いを済ませ、店を出た」
「彼を知ってましたか?前からの知り合い?」
「何回かは。顔見知りだった。名前は知らなかった。刑事さんに写真を
見せられて、教えられるまでは」
「その当時、店の客は、ほかになん人?」
「彼が店に来たとき、入れ違いに帰ろうとしていた若者がふたりいて、
そのまま帰った。ほかに誰も店に来なかった」
「彼は、唯一の客だった?」
「彼は、ずっと、ひとりだった。ヒマな夜で、彼が帰ってから少しして
から、店を閉めた」
「どのくらいあとに?」
「そうじを始めて、閉店まで20分。もしかしたら30分」
「彼がいくら持っていたか見ましたか?」
「財布から、5ドル出して支払った。財布の中まで見なかった。いくら
持っていたのか知らない」
「彼が来たときに帰った、ふたりを知っていたか?」
「少しだけ。ひとりは、ウェルズ通りのレストランの店員で、ユダヤ人
だが、名前は知らない。もうひとりは、いつもいっしょに来た」
「死んだときの酩酊状態を、言えますか?」
「飲んではいたが、酔っていたかどうか分からない」
「まっすぐ歩けましたか?」
「ええ。声は少し太く、おかしなことも言ったが、酔ってはいなかった」
「これで終わりです。ありがとう」
つぎに検死の医者が、宣誓した。長い薄い鼻で背が高く、プロのギャ
ンブラーのように見えた男だった。
名前は、ドクターウィリアムハートレイ。医院はワバッシュで、ディ
ビジョン通りに住んでいた。そう、彼が、死体を検死したのだ。
彼の言葉は、技術的なことばかりだった。手に持った鈍器で頭部を殴
打されたことによる死亡。立ったまま、背後から殴られたように見えた。
「検死は、何時ごろ?」
「24時5分」
「死んだのは?」
「その1・2時間前。たぶん、2時間近く前」
◇
ハイデンを出るとき、おずおずと肩に手を置かれた。周りを見てから、
オレは言った。
「ハロー、バニー!」
バニーは、いつもよりずっと、おびえたウサギのように見えた。
オレたちは、ほかの人が通れるように、出口の脇に寄った。
バニーは言った。「エド、なんて言ったらいいか。できることがあっ
たら、なんでも言ってくれ!」
オレは言った。「ありがとう、バニー。でも、なんとか済んでいる」
「マッジは?どんなぐあい?」
「あまりよくはないが━━━」
「いいかい、エド!なにかできることがあったら、電話してくれ!少し
は貯金もある」
オレは言った。「ありがとう、バニー。しかし、大丈夫」
オレは、バニーが、おふくろでなく、オレに声をかけてくれたことが
うれしかった。おふくろだったら、バニーからお金を借りたかもしれな
い。そして、たぶん、オレが返すことになっただろう。借りたりしなく
ても、なんとかできるはずだった。
それに、バニーは、返ってこないようなカネを貸せる余裕はなかった。
オレは、なんのためにバニーが貯金しているのか知っていた。小さな印
刷ショップを持つことが、バニーウィルソンの夢だった。しかし、始め
るには多額のカネが必要だった。店を始めるのは、タフなゲームで、資
本が必要だった。
バニーは言った。「ふと立ち寄ってもいいかな?エドやマッジと話す
ために。マッジも話したがるかな?」
「もちろん!」と、オレ。「マッジも話したがるさ!おやじの友人のな
かで一番、バニーのことが好きなくらいさ!」
「来週、立ち寄るよ!仕事帰りに、たぶん、水曜の夜に!きみのお父さ
んは、いいやつだった、エド!」
オレは、バニーが好きだった。しかし、それだけだ。バニーと別れて、
オレは家に帰った。
5
電話で、アムは言った。「ガンマンになるのは、どうだ?」
オレは言った。「どういうこと?」
「ガンマン用ハットをかぶれば、そうなれる!」
「銃もないし、パンクでもない」
アムは言った。「半分は正しい。しかし、銃は必要ない。やることは、
ある男を正気を失うほどこわがらせることだ」
「オレの方がこわがるかも?」
「こわければ、こわがればいい。その方がぎこちなくなって本物らしく
なる。オレが鍛え上げる。やり方を教える」
オレは言った。「本気で?」
アムは言った。「そうさ」淡々としていた。オレは、アムが本気だと
分かった。
「いつから?」と、オレ。
「あさって、葬式が終わるまで待とう」
「分かった」と、オレ。
電話を切ってから、オレは、自分がどう変身するんだろうと考えた。
居間へ行って、ラジオをつけた。ギャングものだった。すぐにラジオを
切った。
オレは、ガンマンになった自分を考えた。考える時間はあった。アム
が言った意味は分かった。少し、こわくなった。
検死が終わった、金曜の夜だった。おふくろは、最後の葬式の打ち合
わせでハイデンにいた。ガーディがどこかは知らない。たぶん、映画だ。
窓際に行って、外を見た。まだ、雨が降っていた。
◇
朝、雨は止んだ。
まだ、じめじめとしめっぽく、むし暑かった。葬式用に、一番いい服
を着たが、にかわかなにかで体にピッタリくっついている気がした。コ
ートも着てみたが、また脱いだり、なんども、着たり脱いだりしていた。
ガンマンについて考えた。アムは、少しからかったのかもしれない。
よし、そうだとしても、ガンマンになれと言うなら、なってみよう。
おふくろが起き出した音がした。オレは、外へ出た。
ハイデン葬儀屋の前まで来て、立って見ていた。
しばらくして、中へ入った。ハイデン氏はオフィスで、ワイシャツ姿
で書類を整理していた。タバコを置いて言った。
「やぁ、エドハンターだね?」
「はい」と、オレ。「なにかお手伝いすることは?」
ハイデンは頭を振った。「すべて準備済みで、することはない!」
「棺を持つ者とかは?」
「仕事仲間の者たちが数人。ここにリストがある」
オレは、リストの名前を見た。主任のジェイクランシーがリストの先
頭で、3人のライノタイプ工にふたりの職人。オレは、印刷所のことを
まったく考えてなかった。彼らが来ることをを知って、おかしな気にな
った。
ハイデンは言った。「葬式は、2時。すべて準備済み。オルガン奏者
も来る」
オレはうなづいた。「父は、オルガン音楽が好きだった」
ハイデンは言った。「家族の者は、葬式の前に、ひとりで最後の姿を
見て、お別れが言いたいものだ。エドは、それで来たんだね?」
そうだった。オレはうなづいた。
バイデンは、メイン通路の逆側にある、検死の行われたメインホール
とは別の同じ広さのホールに、オレを案内した。そこに、棺架台の上に
棺があった。美しい棺だった。クロムトリミングがほどこされて、グレ
ーのビロードでおおわれていた。
バイデンは、上体が見えるように、フタの一部を上げて、なにも言わ
ずに静かに出て行った。
オレは、おやじを立ったまま見下ろした。
しばらくして、そっとフタを下げて出た。背後にあった小さな室のド
アもしめた。バイデンやほかのだれにも会わないようにして、外へ出た。
気楽に歩きはじめて、南に向かった。ループ街を過ぎて、南ステート
通りから完全にそれた。
それから歩くスピードを下げて、立ち止まった。そして戻り始めた。
ループ街には、多くの花屋があった。オレは、花についてはなにもし
てないことに気づいた。使えるカネは、まだあった。花屋のひとつに入
って、数時間後の葬式に間に合うように、赤のバラを用意できるかきい
た。店の者は、できると言った。
そのあと、コーヒーショップに立ち寄ってから、家に帰った。だいた
い11時だった。
玄関のドアをあけてすぐ、オレは、なにかがおかしいことに気づいた。
においだった。閉め切った暑い空気は、ウィスキーのにおいで満ちて
いた。土曜の夜の西マジソン通りのようなにおいだった。
まいったな、とオレは考えた。葬式まであと3時間。後ろ手にドアを
しめて、なぜかカギもしめた。おふくろの寝室まで行った。ノックはし
なかった。ドアをあけて、中を見た。
おふくろはドレスを着ていた。きのう買ったらしい新しい黒のドレス
だった。ベッドのへりに座って、手には、ウィスキーボトル。目はうつ
ろで、ぼーとして、オレを見ようとしていた。
おふくろは髪をかき上げようとしたが、すぐに片側に落ちた。顔の筋
肉はゆるんで、年取ったようにみえた。浴びるほど飲んだのだ。
彼女は、前後にすこしゆれていた。
オレは室に入って、おふくろが気づく前に、ウィスキーボトルを取り
上げた。しかし、彼女はボトルを、また、つかもうとした。起き上がっ
て、ボトルに向かってきて、倒れそうになった。オレは、彼女を押して、
彼女はベッドの上に背中から倒れた。オレをののしり始め、また、起き
上がろうとした。
オレは、ドアのところへ行き、カギを抜いて、外側からさして、彼女
がドアノブをつかむ前に、外側からドアにカギをかけた。
オレは、ガーディがいることを望んだ。ガーディは家にいて、オレを
助けるべきだった。オレより、おふくろの扱いがうまいし、オレには助
けが必要だった。
◇
オレは、キッチンに走った。ウィスキーボトルを逆さにしてシンクに、
ごぼごぼと流した。最初にしなければいけなかったことは、これだった。
ウィスキーを流してしまうことだった。
おふくろの声が、カギをかけたドアの向こうから聞こえた。ののしっ
たり叫んだり、ドアノブをがちゃがちゃさせた。しかし、大声は出さず、
ハンマーでたたいたりしなかった。大声でなかったことは幸運だった。
空になったボトルをシンクに置いたときも、ドアノブをがちゃがちゃ
させていた。
オレは、ガーディの室へ向かいかけた。そのとき、別の音がしてオレ
を凍らせた。
それは、窓をあける音だった。おふくろの窓は、通風坑に向かってい
た。
おふくろは、ジャンプしようとしていた。
オレは戻って、ドアをあけるためにキーを差し込んだ。キーはすこし
引っかかった。窓も引っかかった。窓はいつも引っかかって、あけるの
に苦労した。おふくろが苦労しているのが聞こえた。彼女は、今はただ、
すすり泣いていて、ののしったり叫んだりしなかった。
ドアはあけっぱなしにして、おふくろが出ようとするときだけ、見る
ことにした。窓はひざより少し高いところまであいて、引っかかってい
た。おふくろは、そこからはい出ようとはしなかった。
オレは、おふくろの背中を引っぱった。おふくろは、オレの顔を引っ
かこうと手を伸ばしてきた。
1回だけ、おふくろの頬を強くたたいた。彼女が倒れる前につかまえ
てベッドに寝かせた。おふくろは気を失っていた。
オレは、呼吸を整えるために、そこに1分間立っていた。暑く悪臭の
する室で、べたつく汗にぬれて、寒気がして震えていた。
それから、ガーディを捜しに行った。
ガーディは、その間も眠っていた。かなりよく眠っていた。11時だ
ったが、いびきをかいて眠っていた。
ガーディをゆすると、目をあけて、座った。急なことで慎み深さを見
せて、腕を胸の前で組んでいたが、よく目覚めてなくて、みだらなふう
に。目は完全にひらいた。
オレは言った。「おふくろは酔っている。葬式まで3時間。急いで!」
イスの背にかけてあった、シャツかバスローブを手渡して、急いで出
ていった。ガーディの足音がすぐ後ろに聞こえた。
オレは言った。「おふくろの室へ先に行って!オレは、水を用意する」
オレは、バスルームに行って、バスタブに水を出した。水を全開にす
ると、バスタブがカラの間はあたりに飛び散った。しばらくして、水が
溜まり出した。
おふくろの室に戻ると、ガーディは手際よく仕事をしていた。おふく
ろの靴とストッキングを脱がせていた。
ガーディは言った。「どうしてこうなったの?エドはどこにいたの?」
オレは言った。「8時から今まで外出していた。おふくろは、オレが
外出するころ起きだして、近くまで出て、ウィスを買ったようだ。飲み
始めてから3時間たつ」
オレは、おふくろの肩を持ち、ガーディはひざを持って、ベッドの上
に座らせて、ドレスを頭から脱がせ始めた。
心配なことがあって、オレはきいた。「おふくろのスリップは、今の
と別のものはあるかな?」
「あるわ。時間に間に合うようにしらふに戻せるかしら?」
「間に合わせよう!スリップはそのままにして、バスルームまで歩かせ
ないと!」
おふくろはぐったりして重く、歩かせることはできなかった。半分運
び、半分引きずって、なんとかバスルームまで来た。
そのときには、バスタブは水でいっぱいだった。おふくろをバスタブ
に入れるのが、もっとも難しかった。ガーディもオレも、ふたりともび
しょ濡れになったが、なんとかできた。
オレは言った。「おふくろの頭は、支えておいて!オレは、コーヒー
を沸かしてくる。スープのように濃くして!」
ガーディは言った。「ママの寝室の窓をあけて、悪臭を外に出して」
オレは言った。「それはやってある。換気して、窓はあけた」
やかんを火にかけて、上からお湯を注げるように、挽いたコーヒー豆
をポットに入れた。できるだけ多く、上からあふれるくらいに。
バスルームに走って戻った。ガーディは、タオルをおふくろの髪に巻
いて、顔に冷たい水を浴びせていた。おふくろは目が覚めた。少しうな
り声を上げ、浴びせられる水から逃れようと頭を動かした。震えていて、
冷たい水に、腕と肩は鳥肌立っていた。
ガーディは言った。「回復しそう、でも、分からない。ああ、あと3
時間━━━」
「ぎりぎりだ」と、オレ。「いいかい、おふくろが回復したら、手伝っ
て、バスタブから出して、乾かしてあげて!オレは、薬局まで行ってく
る。なにかある。なんていう薬か知らないけど」
オレは自分の室に戻ると、乾いたシャツとパンツに着替えた。葬式に
は、普段着のスーツで行くことになるが、仕方がないだろう。
バスルームの前を通るとき、ドアは閉まっていて、ガーディとおふく
ろの声が聞こえた。低く、ぼやけていたが、ヒステリーではなかった。
ののしったりもなかった。たぶん、間に合うだろうと、オレは思った。
コーヒー用のお湯は沸いていた。コーヒー沸かし器にお湯を注ぎ、冷
めないように保温にした。
クラッセンの薬局へ行った。話しているうちに、いい方法が見つかる
と思った。店長とは知り合いで、秘密は守ってくれるので、なんでもほ
んとうのことを話せた。
「ちょうど良い薬がある」と、店長。「それはど強い薬ではないが、き
みの役に立つと思う」
「おふくろの息にもね」と、オレ。「もうすぐ葬式で、多くの人に接し
なくてはならない。おふくろを元気にしてくれるものが欲しい」
オレたちは、そうした、おふくろをなんとかまっすぐ立てるようにで
きた。
◇
葬式は、美しかった。
ほんとうは、そう思ってなかった。正確にはそれは、おやじの葬式で
はなかった。オレにとって。小さな室で、ひとりでおやじに会ったとき
が、オレにとってのほんとうの葬式だった。オレは、おやじにさよなら
を言えたし、それ以外のことも。
これは、だれもが通り過ぎなければならないなにかというだけだった。
他人を思いやる気持ち。おやじを尊敬する念からの旅たち。
オレは、おふくろの左側に、ガーディは右側に座っていた。アムはオ
レの左に。
葬式のあと、印刷所の上司のジェイクが、オレのところに来た。ジェ
イクは言った。
「仕事には戻ってくるだろ、エド?」
「ええ」と、オレ。「戻ります」
「好きなだけ休んでいい。今の時期は、それほど忙しくはない」
オレは言った。「ジェイク、今やりたいことがあるので、1・2週間
もらいたいのですが?」
「いいとも。今は、ヒマだ。しかし、戻りたい気持ちを変えないように!
おやじさんがいなくなって、働く意味が変わる。でも、いいスタートが
切れる。ぜひ、戻ってきてくれ!」
「ええ」と、オレ。「戻ります」
「おやじさんのロッカーに物が残っている。送ることもできるし、ある
いは、取りに来るかい?」
「取りに行きます」と、オレ。「清算分もあるし、3日以内に行きます。
父の分も。月曜から水曜の間に行きます」
「事務所に、準備しておくように言っておく」と、ジェイク。
葬式が終わって、棺に土をかけたあと、アムは、いっしょに家に来た。
オレたちは、輪になって座っていた。話すことは、多くはなかった。
アムがトランプをしようと言って、アムとおふくろと、オレがしばらく
遊んでいた。ラミーだった。
アムが帰るとき、オレもいっしょに廊下に出た。アムは言った。
「今夜は、ゆっくり休め!じゅうぶん休んでから、行動開始だ。明日の
午後、ホテルに来てくれ」
「オーケー」と、オレ。「今夜じゅうに、やっておかなければならない
ことは?」
「なにもない」と、アム。「バセットに会いにゆくが、エドも来る必要
はない。路地に裏庭で接しているアパートにどんな連中が住んでるのか
調べるために、耳飾りでも贈るつもりだ。そういう仕事は、オレたちよ
りバセットの方が手際がよい。もし弾丸が出てきたら、オレたちがそこ
も掘る」
「も、というと、カウフマンのこと?」
「そう、やつは探れば、なにか出てくる。分かってただろう?」
「確信はなかった」と、オレ。
「オレはあった。バセットが見逃した点だ。しかし、慎重にことを進め
なくてはならない。明日の午後なかばに会いに来てくれ。室で待ってい
る」
7時近くだった。おふくろは、オレが、ループ街まで下りて、ガーデ
ィを映画に連れてゆくのはいい考えだと言った。
オレもそう思った。ダメな理由でも?
たぶん、おふくろはひとりになりたかったのだろう。オレは、ガーデ
ィが新聞の映画欄を見ているあいだ、おふくろを観察していた。おふく
ろには、また、酔いつぶれてやろうとする意思もそぶりも見えなかった。
おふくろは、今朝のことのあと、もう酔ったりすべきでないと自覚し
ているように、オレには思えた。今朝のことは、見苦しかった。しかし、
おふくろはそれをみごとにもみ消した。葬式では、だれとでも話して、
だれにも気づかれなかった。アムさえ、そんなことがあったとは気づか
なかったろう。オレとガーディと薬局のクラッセン以外、だれにもバレ
なかった。
おふくろの目は赤く、顔は、はれぼったかったが、みんなからは、泣
いたあとだからだと思われていただろう。
おふくろは、おやじを本当に愛していた、とオレは思う。
ガーディは、オレにはグチャグチャとしか思えない音楽のライブショ
ーを見に行きたがった。そこには有名なスウィングオーケストラも出る
ので、オレは反対しなかった。
オレが正しかった。ショーはつまらなかった。しかし、ブラスセクシ
ョンだけは、すばらしかった。ずば抜けていた。ふたりのトロンボーン
がはっきり聞き取れた。ソロパート担当は、ティーガーデンのようによ
かった、と思う。すぐにでなく、しばらくしてから、からだに染み込ん
でくるような音色だった。
もしもあんなふうに演奏できたら、100万ドル払ってもいいと、オ
レは考えた。100万ドル持っていればの話だが。
最後の曲は、ジャンプナンバーで、ガーディは、足を動かしっぱなし
だった。ガーディは、どこかダンスへ行きたがったが、オレはだめだと
言った。ライブショーへ行ったこともよくなかった。葬式のあった日の
夜としては。
家に戻ったとき、おふくろは外出していた。
しばらく雑誌を読んでから、眠った。
◇
目が覚めたときは、真夜中だった。声がした。おふくろの声で、かな
り酔っていた。もうひとりの声は、よく知っている声だったが、だれか
思い出せなかった。
オレとは関係ないことだったが、だれだか知りたくなった。ようやく
ベッドから出て、少しあいているドアのところへ行った。しかし、しゃ
べり声は止んで、ドアが閉まった。
声は聞こえたが、ワードが聞き取れなかった。
おふくろが自分の室へ行って、ドアを閉めた音がした。歩き方から、
かなり酔っていたが、今朝よりはちゃんとコントロールされていた。ヒ
ステリックな声は出さずに、友好的な声だった。
窓のことは心配しないことにした。
オレは、ベッドに戻って、横になって、あの声がだれだったか思い出
そうとしながら、ずっと考え事をしていた。
それから、分かった。バセットだった。色あせた赤毛で、くすんだ目
をした殺人課の刑事。
たぶん、バセットは、おふくろがやったと考えて、酔わせて自白させ
ようとしたのだ。そのやり方は、オレは好きではなかった。
まったく別の理由があったのかもしれない。そうだとしても、よくな
かった。そのとき、バセットが病気の妻がいると言ったことを思い出し
た。
いずれにしても、そのやり方は好きではなかった。もしもバセットが
仕事と趣味を混同するなら、それぞれ単独であるよりも、もっと悪い。
オレは、バセットが好きだったのだ。アムから賄賂をもらったあとでも、
好きだったのだ。
少しも眠れなかった。思いつくことが、なにからなにまで気に入らな
かった。
朝起きたとき、口にイヤな味がした。
空気が蒸し暑い湿気を含んでるせいだと、オレは考えた。目覚ましを
セットしていてもしてなくても、毎朝7時に起きる気がした。
バセットは、最終的には悪気はなかったのだと考えて、起き上がって
服を着た。どちらも悪く考えすぎていたのかもしれない。おふくろは、
クラーク通りまで出て、バセットは、偶然会って、家まで送ったのだ。
おふくろのためを考えてだ。
オレは服を着た。なにをすればいいか、分からなかった。
コーヒーを飲んでいると、ガーディがキッチンに入ってきた。
「ハイ、エド!」と、ガーディ。「眠れなかったわ。エドも?」
「ああ」と、オレ。
「熱いコーヒー、入れておいてくれる?」
「いいよ」
ガーディは、室に戻り、服を着て、テーブルのななめ向かいに座った。
オレは、ガーディにコーヒーを注いた。ガーディは、パンのバスケット
から、甘いロールパンを取った。
「エド」と、ガーディ。
「なに?」
「ママは、昨夜、何時に帰った?」
「知らない」
「帰った音を、ぜんぜん聞いてないということ?」ガーディは立ち上が
って、おふくろの室を見に行こうとした。
「帰っている」と、オレ。「帰ったのは聞いた。それが何時だったかは、
時計を見てなかったので、分からない」
「かなり遅かった?」
「そう思う。オレは眠っていた。おふくろは、昼まで寝てるだろう」
ガーディは、考え事をしながら、ロールパンをかじった。パンをかじ
るたびに、リップスチックの跡がついてるだろう。なぜ朝食の前は、リ
ップスチックを控えようとしないのか不思議だった。
「エド」と、ガーディ。「いい考えがある」
「なに?」
「ママは飲みすぎよ。これを続けていたら━━━」
そのあとを、言おうとしなかった。オレは、続きを待っていた。続き
がないなら、具体的な考えではないということだ。つまり、おふくろの
酒に対して、なにもできない。
ガーディは、目を見開いて、オレを見た。「エド、2日前に、ママの
洋服タンスにパイント瓶を見つけた。それを取り上げて、隠したけど、
ママはぜんぜん気づかなかった。そんなことお覚えてないのよ」
「流しにあけてしまえばいい」と、オレ。
「ママはまた買うわ。1ドル49セントで買える。そしてもっと買う」
「もっと買う」と、オレ。「だから?」
「エド、わたしも飲むようになる」
「どうかしてる!まだ14なのに!」
「15よ、来月で。15だけど、デートでよく飲む。酔ったことはない。
聞いてるの、エド?」
「望遠鏡で見たわけでないけど」と、オレ。「どうかしてる!」
「パパだって、よく飲んでた」
「おやじのことは、別にしよう」と、オレ。「もう、行ってしまったん
だから。おまえが飲むこととどう関係する?家の伝統だから飲むのか?
あるいは、別の理由で?」
「話をそらさないで!パパが酒をやめなかった理由は、なんだと思う?」
同じことを繰り返すガーディに腹が立った。おやじはもういない。地
面の下6フィートだ。
ガーディは言った。「パパの酒をやめさせられなかったのがなにか、
分かる。もしもエドがパパと同じことを始めたら、パパは酒をやめられ
たわ。エドはいつもいい子だった。パパは、エドが、自分のようにデタ
ラメなことをすることはないと分かっていた。もしも、エドが酔ったり、
悪い仲間に入ったりしたら、パパは酒をやめたわ。パパはエドのことを
愛していた。だから、なにがエドを夢中にさせるのか、知りたいと思っ
ていたのよ」
「ありえるね」と、オレ。「しかし、おやじは死んだんだ。なぜ、そん
なことを今考える?」
「ママは死んでないわ。エドはママのことをあまり考えないけど、わた
しのママなのよ」
確かにそうだった。なにがおふくろを酔わせるのか、今になってやっ
と気がついたのだから。
◇
オレは、ただ座って、ガーディを見ていた。まだ、チャンスがあった。
そうならないための、最後のチャンスだった。ガーディがそんなふうに
ハメをはずし始めたら、おふくろを目覚めさせることになるだろう。お
ふくろは、おやじを失った。しかし、まだ、ガーディがいるのに、15
才の酒のにおいがプンプンするわが子を見たくはないだろう。
オレは、その地獄を考えた。そうはならない気がした。
ガーディが自分で考えるよう、オレは仕向けた。ちゃんと自分で考え
ると思った。
「いや、おまえはそうはならない!」
「なぜ、そう思うの?なってやるわ!」
「いや、ならない!」
しかし、オレはガーディを止めることもできないと、思った。ガーデ
ィは、よく考えて、そうするつもりなら、オレは今は止められても、つ
いて歩くこともできないし、ずっと見ていることもできない。
「今がその時よ、エド!」と、ガーディ。「ママがお昼に二日酔いで目
覚めたとき、しっかりと見るわ。ママが気に入ると思ってるの?」
「おふくろは、おまえをぶつだろうな」
「どうしてそんなことが?自分が酔っ払いなのに。ママはわたしをぶた
ない。決して!」
たぶん、とオレは考えた。ぶった方がいい結果になるだろう。
オレは言った。「どれも、そうなって欲しくない」
オレがガーディをそうさせたのかもしれない、と思った。
オレは言った。「そんなのただのギャグだ。どんなものか知るために、
酔っ払いになろうとしているなんて!」
ガーディは、イスを後ろに引いた。「これからボトルを買ってくる。
エドがいい子ぶってるなら、取り上げて、流しなさいよ。そしたら、わ
たしは、クラーク通りに行って、酔っ払ってやる!年齢より上に見られ
るし、若い女に酒をおごってくれる店は、たくさんある。みんな気前の
いい酔っ払いでいたいのよ!」
ヒールの足音が、ガーディの室へ向かった。
ここから地獄が始まる、エド。オレは自分に言った。「どれも現実に
なって欲しくない。しかし、オレがオールで阻止しようとしても、ガー
ディはやるだろうし、クラーク通りで酔っ払うだろう。行き着くところ
は、たぶん、シセロ街の売春宿。そんなもんだ」
オレは立ち上がったが、外には出なかった。
困っていた。酒を飲むのを止められないが、トラブルに会わないよう
に、そばを離れないでいることはできる。ある段階まで行ったら、地獄
のように感じて、逃げ出したいと思うだろう。しかし、そう仕向けるこ
とはできない。
オレは、がまんした。
ガーディは、ボトルを持って戻った。すでに栓は抜かれていた。ガー
ディは、一杯注いだ。
ガーディは言った。「エドも飲む?」
オレは言った。「気がすすまない」
「社交的でしょ?」
「いいや」と、オレ。
ガーディは笑って、飲み干した。チェイサー用の水のグラスをつかん
だが、むせたりはしなかった。
もう一杯注ぎ、座った。
こっちを見て、ニヤニヤした。「いっしょに飲めないの?」
「飲めない」と、オレ。
ガーディは笑って、また飲み干した。居間へ行って、ラジオをつけ、
ダイヤルをまわして、音楽にした。朝なら、いい音楽だった。
ガーディは言った。「エド、踊らない?ダンスすれば、仕事もはかど
るわ」
「踊りたくない」
「いい子ぶって!」
「いや」と、オレ。
オレは、どうなるか分かっていた。
ガーディは、音楽に合わせて、くるくる回ったりして戻り、座った。
3杯目を注いだ。
「早く飲みすぎ」と、オレ。「酒に慣れてないのに、ガブ飲みするのは
よくない!」
「前にも飲んだわ。多くはないけど、多少は」別のグラスにウィスキー
を注いだ。「エドもどう?ひとりで飲むのは、楽しくない」
「分かった」と、オレ。「一杯だけなら」
ガーディは、グラスをかかげて言った。「幸せな日々に!」
オレは自分のを持ち上げて、ふちに口をつけて、少しだけすすった。
しかし、ガーディは飲み干した。
ガーディはラジオに戻り、言った。「エド、ここへグラスとボトルを
持って来て!」
オレは居間に入って、座った。ガーディは、オレのイスの肘掛に座っ
た。
「エド、もう一杯注いで!楽しいわ!」
「ああ」と、オレ。自分のを少しすすった。ガーディは、4杯目を飲み
干した。少しむせた。
「エド」と、ガーディ。「踊って!」
音楽は、良かった。
オレは言った。「いい加減にしろ、ガーディ!」
ガーディは立ち上がり、音楽に合わせて、踊り始めた。スウィングし
たり、軽くヒザを曲げたり、体をゆさぶったり。
ガーディは言った。「いつかステージで踊るわ!どう、うまい?」
「うまいね」と、オレ。
「ジプシーローズのようにも踊れるわ!見てて!」ガーディは踊りなが
ら、腕を後ろにまわして、ドレスのファスナーをつかんだ。
オレは言った。「やめろ、ガーディ!オレはおまえの兄だということ
を忘れたのか?」
「兄ではない。とにかく、踊ることとは関係ない!」
ガーディは、足元がおぼつかなくなった。すぐ近くで踊っていた。オ
レは手を伸ばして、ガーディの手をつかんで言った。
「もう十分さ、ガーディ!」
ガーディは笑って、もたれかかってきた。手首をオレのひざの上に。
ガーディは言った。「キスして、エド!」ガーディの唇は明るい赤で、
からだは熱かった。急に唇を重ねてきたので、なにもできなかった。
オレは立ち上がって言った。
「やめろ、ガーディ!おまえは子どもじゃないか!」
ガーディはからだを引いて、笑った。
「いいわ、エド!もう一杯、飲みましょ!」
オレは、2杯注ぎ、1杯をガーディに渡して言った。
「おふくろにかんばい!」
ガーディは言った。「オーケー、エド。ほかに言うことは?」
今度は、オレがむせて、ガーディは笑った。
ガーディは、ダンスを数ステップしてから言った。
「もう一杯ついでおいて!すぐ戻る!」
ガーディは、居間を出るとき、少しよろめいた。
オレは、2杯ついで、ラジオのところへ行って、ダイヤルをまわした。
別の番組にして、また、戻した。音楽以外はなにもなかった。
ガーディが戻って、「エド」と言うまで気づかなかった。
音がしなかったのは、ガーディは裸足だったからだ。服は着てなかっ
た。
ガーディは言った。「わたしは子ども?」少し笑った。「子どもかし
ら?」
オレは、ラジオをいじくるのをやめて、消した。
オレは言った。「子どもじゃない。おかわりをついで来よう!おまえ
のぶんは、ここにある」
オレは、ガーディのぶんを手渡して、チェイサー用の水をくみにボト
ルを持ってキッチンへ行った。そして自分のぶんを飲むふりをして、シ
ンクに流した。2杯ぶんを持って戻った。
ガーディは言った。「酔ったみたい」
「さぁ!」と、オレ。「もう一杯飲もう、ガーディ!カンパーイ!」
もう一杯を、いっしょに飲んだ。ボトルには、まだ一杯ぶん残ってい
た。最後の一杯分で、ぎりぎり2杯を分け合うことになる。
ガーディは、また、ダンスステップを踏んだ。そして、よろめいた。
オレは抱きとめて、ソファに座らせた。ボトルを取りに戻ろうとすると、
ガーディは言った。
「エド、座って!」
「ああ」と、オレ。「いいけど、まだ、一杯ぶん残っている、取ってき
ても?」
ほとんどはガーディの口から外へこぼれたが、少しは飲めた。オレが
ハンカチで口をぬぐうと、ガーディは笑った。
「いい気分だわ、エド!」
「1分だけ、目を閉じて!」と、オレ。「ゆっくり休める!」
1分で十分だった。ガーディは眠った。
オレはガーディを抱きかかえて、彼女の室へ運んだ。パジャマのズボ
ンがあったのではかせて寝かせ、ドアを閉めた。
グラスをすべて洗って、ボトルを見えないところ、ゴミの缶の中へ入
れた。
オレは、やっと地獄から抜け出た。
6
ワッカー街の12階でエレベータを降りたのは、だいたい2時だった。
アムの室を見つけて、ノックした。
アムは、オレを招き入れるとき、顔をじろじろ見た。
「なにかあったのか?」と、アム。「なにをしていた?」
「なにも」と、オレ。「ただ、歩いていた。長い散歩」
「なにか、まずいことは?どこへ行った?」
「どこへも」と、オレ。「ただ、歩いただけ」
「運動で?」
「やめてくれ!」と、オレ。「オレの勝手!」
「そりゃそうだ!文句があるわけでない!座ってリラックスしてくれ!」
「これから、なにかをさがしに外出は?」
「あるが、それほど急ぎでない」アムは、しわくちゃのタバコの箱を出
した。「1本いるか?」
「いいね」
オレたちは、タバコに火をつけた。
アムは、煙の向こうからオレを見た。アムは言った。「なにか食べつ
くしたっていうかんじだ。それがなにか正確には分からない。単なる推
測だが。女性のひとりが乱痴気騒ぎをやらかした?あるいは、ふたりと
も?葬式に出られるように、マッジの酔いを覚ました?」
オレは言った。「アム叔父さんには、メガネはいらないね?」
アムは言った。「マッジとガーディは、あのまま。おまえが変えよう
としても、なにもできない」
「すべてが、おふくろのせいではない」と、オレ。「おふくろにもどう
しようもなかったのだと思う」
「誰かのせいということはないさ。そのうちだんだん分かってくるだろ
う。ウォリーにとってもそうだし、エドにとってもそうだ。エドがそう
なのは、エドのせいではない」
「オレは、なに?」
「コショウだな。黒コショウ。ウォリーのせいばかりではない。それは、
もっと前からだと思う。窓のところへ行って、しばらく、外を眺めてみ
れば分かる」
室は、ホテルの南はじだった。オレはそこへ行って、外をながめた。
外は、まだ湿っぽく、グレイだった。町の南は、巨大な商業ビルが立っ
ていて、ワッカー街の隣だった。そこは、北西側で汚い側だった。汚れ
た古いビルが汚い生活を隠していた。
「汚いながめだ」と、オレ。
「それが、オレが言いたかったことだ。窓から眺めているとき、それが
なんであれ、見ているものがなにか分かるか?エド自身さ!ものごとは、
美しく見えたり、ロマンティックだったり、思いがけなかったりするの
は、エドの中で、美しかったり、ロマンティックだったり、思いがけな
かったりするからさ。今、エドが見ているものは、エドの頭の中さ!」
オレは言った。「アムは、詩人のように話す。カーニバルの人間じゃ
ない」
アムは声を出さずに笑った。「本で読んだことはある」と、アム。
「いいか、エド。ものにラベルを付けるんじゃない!ワードは、人をバ
カにしてしまう。もしも人を、印刷工だとか、酔っ払いや、オカマやト
ラック運転手だとか呼べば、そいつにラベルを貼り付けてしまう。人は
複雑だ。たった一つのワードで、人をラベル付けることはできない」
オレは、まだ、窓のところに立っていたが、アムの方に振り向こうと
した。アムはベッドから出て、オレのそばに来て、また、窓の方を向か
せた。オレの肩に手を置いて、立っていた。
アムは言った。「もう一度見てくれ。別の見方を教えたい。今より少
しましになるような」
オレたちは、あいた窓から、湿っぽい通りを見下ろした。
アムは言った。「そう、本で読んだことはある。エドも読んだだろう。
しかし、知っていたことでさえ、本に書かれていることを、本当には見
抜けてない。ものは、ちゃんとそこにあるように見えるだろう?ものは
固く、隣りのものとは区別されるかたまりで、あいだには空間もある。
だが、そうじゃない。それは、そのあたりに漂う原子のただのあつま
りだし、原子は、そのあたりに漂う電荷と電子からできていて、星々の
あいだに空間があるように、互いのあいだに空間もある。それは、ほと
んどなにもないものの、大きなかたまりさ。ただそれだけ。空間が終わ
って、ビルが始まる場所に、明確な線などない。原子が、もっと離れば
なれになって、ちょっと少ないだけ。
それに、漂うだけでなく、原子は前後に振動もしている。ただの雑音
に聞こえるものは、ひどく離れた原子が、すこし激しく振動しているか
らさ。
さて、クラーク通りを歩く男がいたとしよう。彼は、ほかのなにもの
でもない。だたのダンスする原子のかたまりの一部さ。彼は、よろめい
ては、下や周りの原子や空間をかき混ぜているだけ」
アムは戻って、ベッドに座った。アムは言った。「見ることを続けろ!
絵を描け!分かってることは、ただの見せかけ。トリックの裏にある隠
されたものを暴け!
ほとんどなにもないもののかたまりが続いている。それが真の姿だ。
分子間には空間がある。かなり固い物質でできた高いビルであっても、
まとめてしまえば、サッカーボールくらいになってしまう!」
アムは声を出さずに笑った。「分かるか?」と、アム。「エドの周り
は、実際には、サッカーボールで囲まれている!」
オレは、立ったまま、しばらく町を見下ろしていた。振り返ると、ア
ムは笑っていた。オレも、歯を出して笑った。
「オーケー!」と、オレ。「下へ行って、クラーク通りを蹴っ飛ばそう!
なにか出てくるかもしれない」
「むしろ、シカゴアベニューだ。オリンズ近くの店。これから行って、
カウフマンを心の底から怖がらせてやろう!」
オレは言った。「やつは、長年のあいだ、タフな町でバーを経営して
いる。どう脅したら、震え上がる?」
「なにも。いっさい脅したりしない。それが、やつを怖がらせる。それ
が、唯一の方法だ」
「よく分からない」と、オレ。「たぶん、オレがニブいからだろうが、
ピンと来ない!」
「カモ〜ン!」と、アム。
「なにをするんだい?」
「なにも。なにもしない。やつの店で座ってるだけ」
まだ分からなかったが、待つことはできた。オレたちは、エレベータ
で降りた。
◇
ロビーを横切るとき、アムがきいた。「エド、新しいスーツは?」
「そうだね、でも、買わない方がいい。時間のロスになる」
「それは、オレの責任だ。エドには、ダークブルーのピンストライプの
入ったスーツがいる。少し年上に見せてくれる。ある種のハットも必要
だ。これも仕事の一部だ。文句を言うな。エドは、ガンマンのように見
せなけりゃならない」
「オーケー」と、オレ。「これはあくまで借り。いつか返済する」
オレたちは、スーツを買った。40ドルした。最近買ったスーツの、
2倍だった。アムは、特にスタイルにこだわった。ふさわしいスーツが
見つかるまで、いくつか見て回った。
アムは言った。「そんなにいいスーツじゃない。長持ちはしない。し
かし、ブランドも新しいし、ドライクリーニング前なら、高いスーツに
見える。よし、つぎはハットだ!」
オレたちは、両端を反対側に折り曲げられる、スナップブリムのハッ
トを買った。アムは靴も買いたいと言ったが、磨けばいいからと言って
やめてもらった。今はいているのは、比較的新しいし、磨けば、新品に
見える。オレたちは、絹のように見える、レイヨンのシャツに、すばら
しいネクタイも買った。
ホテルに戻って着替えると、オレは、バスルームの鏡で、全身を映し
てみた。
アムは言った。「ニヤけているような歯は、絶対見せるな!かわいい
坊やに見える」
オレは、顔をシャキッとさせた。「ハットはどう?」
「どこで買った?」
「ヘルツヘルドの店」
「本当か?よく思い出せ!オレといっしょにズラかった、ジェネバ湖で
手に入れたんだろ?あれは、かなりやばかった。ブレインがもう大丈夫
と知らせて来るまでは、一週間、身を隠していた。ホテルの受付の女を
覚えているか?」
「小柄のブルネット?」
アムはうなづいた。「また、よりを戻したらどうだ?あの夜、車から
降りるときに風で飛ばされたハットの代わりに、彼女がそのハットを買
ってくれたんだ。なぜ、彼女かは、あの一週間でエドは300ドルも彼
女につぎ込んだからだ。エドはシカゴへいっしょに連れて来たかったん
だろ?」
オレは言った。「ああ、今でもそう思っている。なぜ、そうしなかっ
たんだろう?」
「オレがだめだって言ったからだ。オレがボス。そこんとこをよく頭に
叩き込んでおけ!もしもオレが手を回してなきゃ、おまえは3年前に電
気イスで黒こげになっていたところだぞ!やい、あんまりつけあがるな
よ!なにを、ニヤニヤしている?」
オレは言った。「分かったよ、ボス!なんでオレが黒こげになるんだ
い?」
「1つは、バートン銀行の仕事さ。すぐに引き金を引きすぎる!出納係
がボタンに手を伸ばしたとき、すぐに殺すことはなかった。近くにいた
んだから、腕でも撃っておけばよかったんだ」
オレは言った。「ボタンに手を伸ばすからだ!」
「スワンが勝手なまねをして、オレがこらしめてやれと言ったときもそ
うだ。おまえはなにをした?撃っただけか?いいや、おまえは面白半分
に余計なことをしてくれた。覚えてるか?」
「おかしなまねをしたからさ。自分のせいだ!」
アムはオレを見て、頭を振った。声が変わった。アムは言った。「悪
くはねぇが、エド、リラックスしすぎだ。もっとからだをこわばらせて、
神経が張り詰めるようにやってもらいてぇな!脇のホルスターに実弾入
りの銃を収めたら、その重さで、忘れようにも、忘れられねぇ!一瞬た
りとも、そのことを忘れるな!」
「分かった」と、オレ。
「それと、目だが、ずっと、やつの目を見ていろ!やつが、タバコを2
本吸おうが、もっと吸おうが、ずっとだ!」
オレは、ゆっくり、うなづいた。
アムは言った。「そうすれば、オレが言ってることが分かる。やつは、
世界の王で、G弦のようにホットだとしても、細い糸で留められたコイ
ルのようになっていて、やがて、静かに座っていられなくなる。エドの
ことをおそれていて、さわっただけで、10フィートの棒でつつかれた
ようになる」
「そうだろうな」と、オレ。
「目は、やつからそらすな!しかし、殺意をもって見てはだめだ。殺意
は、やつを元気づけてしまう。やつが、そこにいないかのように、やつ
を撃とうが撃つまいがどうでもいいように、ただ、見てるだけでいい。
電柱を見るのと同じだ」
「声の調子は?」と、オレ。
「声は出さないでいい。口を閉じておけ!オレが問いかけるまで、話し
かけるな!オレがずっと、しゃべってるから、めったにしゃべるな!」
アムは、腕時計を見て、ベッドから立ち上がった。アムは言った。
「今、5時だ。すっかり時間を食った。出かけるぞ!」
「一晩じゅうかかりそう?」
「たぶん」
オレは言った。「電話を借りていいかな?ちょっと用があって。先に
下へ行って、ロビーで待っていて!」
アムは言った。「いいとも!」そして、出て行った。
◇
オレは、家に電話した。もしもおふくろが出たら、電話を切るつもり
だった。ガーディがおふくろに言ったことを確かめるまで、おふくろと
は話したくなかった。
しかし、出たのはガーディだった。
オレは言った。「エドだ、ガーディ。おふくろは近くにいる?」
「ママは、買い物に行っている。エド、わたし、なにかバカなことをし
た?」
大丈夫そうだった。
オレは言った。「ああ、少しは。けど、忘れよう!すごく、がんこだ
った。それだけさ。それ以上でもない。分かった?今度そんなことをし
たら、ヘアブラシをかけてやる!」
ガーディは、くすくす笑った。あるいは、そう聞こえた。
オレは言った。「おふくろは、ガーディがあのウィスキーを飲んだこ
とを知ってる?」
「知らないわ。わたしが先に起きて、気持ち悪くて、今も、まだ、そう。
でも、酒のビンは片付けてママに見せないようにした。ママは起きて、
気持ちが悪いようで、わたしのことは悟られないようにした。頭痛だっ
て、言っておいたの」
「それは、いい思いつきだ」
「わたし、忘れたわ、エド。きれいに忘れた。ママに見つからないよう
にずっと気を使っていた。怒鳴られたり、泣かれたりするのがイヤだっ
たので、ずっと気をつけていた」
「そう」と、オレ。「思いつきを忘れたんなら、ずっと忘れていればい
い。オレの言ってる意味が分かるなら、どちらの思いつきも。ガーディ
が酔っ払ってなにをしたか覚えているんだろ?」
「ぜんぜん、記憶がない。わたし、なにをしたの?」
「からかわないでくれ!」と、オレ。「すべて覚えているはずだ」
今度は間違いなく、くすくす笑いだった。
あきらめた。オレは言った。「いいかい、おふくろに言っておいてく
れ。オレは、遅くならないと家に帰れない。たぶん。けれど、心配はい
らない。アム叔父さんといっしょだ。ひと晩中いっしょだと思う。では、
また」
オレは、ガーディが質問する前に、電話を切った。
エレベータで下へ降りた。オレは、気持ちを引き締めようとした。ア
ムが服とハットを選んだのは、正解だった。エレベータの鏡には、オレ
は22か23くらいに見えた。オレは、そのようにふるまった。
心を堅くして、目を鋭くした。
ロビーを横切って歩いてゆくと、アムはOKと言うようにうなづいた。
アムは言った。「いいね。そこまでできるとは、思ってもいなかった」
◇
オレたちは、シカゴアベニューまで北へ歩いてから、西に折れた。警
察署の前を通りすぎた。そこは正面を向いたまま、歩き続けた。シカゴ
アベニューからオーリーンズ街へ斜めに横断したとき、トパーズビール
のネオンサインが輝いていた。アムは言った。「やって欲しいことは、
すべてここだ。エドは口をきくな。カウフマンを見ていろ!オレがリー
ドする」
「分かった」と、オレ。
オレたちは、飲み屋に入った。カウフマンは、バーカウンターにいる
ふたり連れの男にビールをついでいた。横のブース席に、男女の連れが
いた。夫婦に見えた。バーの男は、昼間からビールを飲み続けているか
のように、眠たそうに少し飲んだ。男は、連れとしゃべってはいなかっ
た。
アムは、テーブルに背中を向けて、バーカウンターが見えるように座
った。オレも同じ方向に顔が向くように、テーブルの片方にイスを引い
た。
オレは、カウフマンを見た。
カウフマンは、オレが思うに、とりわけ見て楽しいというわけでなか
った。背が低く、体重があって、長い腕で、見るからに力がありそうだ
った。だいたい40か45才くらいに見えた。洗ったばかりのシャツを
着て、ひじまで腕まくりをしていた。腕は、猿のように、毛むくじゃら
だった。髪はうしろに撫で付けられ、つややかだった。ヒゲはそる必要
があった。度の強いメガネをしていた。
カウフマンは、今出したビール2杯分、20セントをレジに収めると、
バーカウンターのすみを回って、オレたちのテーブルにやってきた。
オレは、やつを見続けて、観察して、やつに圧をかけた。
やつは、トラブルがあっても自分で解決できそうなほど、タフに見え
た。しかし、この町のバーテンダーは、みんなそうだ。そうでなければ、
バーテンダーになんかならない。
やつは言った。「なんにします?」
やつの目がたまたまオレを見た。オレは、見返した。オレは、命令を
思い出した。筋肉1つ動かさなかった。顔の筋肉でさえ。オレは考えた。
「よう、娼婦の息子、すぐにでも殺せるんだぜ」
アムが言った。「ホワイトソーダ。グラスで2つ」
やつの目が、オレからそれて、アムを見た。疑わしそうに、ジョーク
なのかどうか分からず、笑おうかどうしようか迷ってるように見えた。
アムは笑わずに言った。「グラスで、ホワイトソーダ2つ」
アムはテーブルに紙幣を置いた。
カウフマンは、肩をすくめたいように見えたが、実際にはしなかった。
紙幣を受け取り、バーに行った。2つのグラスとおつりを持って戻って
きた。
「ほかには?」やつは、知りたがった。
アムは無表情のまま言った。「ほかに注文があれば、知らせる」
カウフマンは、バーに戻った。
オレたちは、そこに座ったまま、なにもせず、しゃべりもしなかった。
かなりの間を置いてから、アムがホワイトソーダをひとすすりした。
バーにいた男たちは出て行って、別のグループ、今度は3人が入って
きた。オレたちは彼らになんの注意も払わなかった。カウフマンを見て
いた。1秒たりとも目を離さなかったというわけではなかったが、だい
たいは、カウフマンを見ていた。
すぐ分かるように、やがてそれが、カウフマンを戸惑わせ、少し嫌な
気分にさせた。
2人の男たちが入ってきて、ブース席にいた夫婦が出ていった。
7時に、もうひとりのバーテンダーが出勤してきた。背が高く、やせ
ていて、よく笑い、笑うと金歯がたくさん見えた。彼がバーにつくと、
カウフマンがオレたちのテーブルにきた。
「ホワイトソーダを、2杯おかわり」と、アム。
カウフマンは、アムを一瞬見てから、テーブルに置かれた代金を拾っ
て、グラスにおかわりを入れるために、バーへ行った。戻ってくると、
一言もしゃべらずにグラスを置いた。それから、エプロンをはずしてフ
ックに掛けると、飲み屋の裏口から出ていった。
「やつは、警察へ行ったのかな?」
アムは頭を振った。「やつはまだ、心配はしてない。食事に行ったん
だ。それって、いいアイデアかも?」
「いいね」と、オレ。前に空腹のまま気分が悪くなったことを思い出し
た。食事のことを考えたら、牛一頭丸ごと食えそうなくらい空腹を感じ
た。
オレたちは、数分待ってから、店を出た。クラーク通りを歩いて、シ
カゴアベニューから1ブロック南の小さなチリ料理屋で食事した。この
町で最もうまいチリ料理が食える店だった。
食事の時間を楽しんだ。コーヒーを飲んでいるときに、オレはきいた。
「これから戻る?」
「ああ。9時に戻って、12時までいる。やつは、そのころにはイライ
ラし始める」
「それから、なにを?」
「やつのイライラを手助けする」
「聞いてもいいかな?」と、オレ。「もしもやつが警察を呼んだら、ど
うなる?今のところ、座ってホワイトソーダを飲んでも、違法じゃない。
でも、呼ばれた警官は、いろいろ質問してくる」
「警察の方は、手を打ってある。シカゴアベニューからの電話を受ける
警官には、バセットから話が通してあって、呼び出しに応じて派遣する
警官には、ちゃんと言い含めておいてくれるようになっている。もしも
派遣することになればだが」
オレは言った。「ああ」100ドル紙幣のことを思い出した。これは、
バセットからの最初の配当だった。路地で裏庭のあるビルを調べると言
ったことをカウントしなければだが。バセットは、そのくらいのことは
しただろうが、警官に話を通すことは、明らかに、特別なはからいだっ
た。
食べ終わると、オレたちは、クラーク通りからオンタリオへ少しはず
れた静かな店で、ビールを飲んで、たくさんしゃべった。
おもに、おやじのことだった。
「ウォリーは、変な子どもだった」と、アム。「知ってるように、オレ
より2つ下だった。子馬のようにむちゃをした。オレだって歩きたくて
むずむずしていた。今でもそうさ。だからカーニバルにいる。エドは、
旅は好きか?」
「旅はしたいと思ってる」と、オレ。「でも、今までそのチャンスがな
かった」
「今まで?へっ、まだ、子どもじゃないか!しかし、ウォリーは、16
才のときに家出した。その年は、オレたちの父親が心臓麻痺で突然死ん
だ年だった。母親は、その3年前に死んでいた。
オレは、ウォリーはそのうち手紙をくれると思っていた。それで、手
紙が来るまで、セントポールからなるべく離れないようにしていた。手
紙は、オレと父宛てだった。カルフォルニアのペタルナにいて、小さな
新聞社のオーナーをしているとあった。ポーカーで勝ったらしい」
「そんなこと一言も聞いてなかった」と、オレ。
アムは、声に出さずに笑った。「それを長くは続けなかった。手紙の
返事で電報を打ったが、届く前に、ウォリーは去っていた。すぐに行く
と伝えたが、そこに行ってみると、ウォリーはお尋ね者になっていた。
重大な犯罪ではなく、名誉毀損で訴えられていた。ウォリーは、新聞社
をやってゆくにはあまりに正直すぎた。ペタルナの有力市民のひとりに
ついて、うそ偽りのない暴露記事を書いた。ただそれだけのことだった
と、あとでウォリーが話してくれた。そう信じている」
アムは、歯を見せて笑った。「ウォリーを捜すためというのが、その
まま旅を続けるためのスマートな言い訳になった。ウォリーはカリフォ
ルニアを出ているだろうと思った。名誉毀損は、犯人引渡しが行われる
ほど重大な犯罪ではなかったが、おそらく、それ以外の容疑もあって、
州を出ていた。フェニックスで、ウォリーの足取りを見つけた。いくつ
かの場所であと少しで追いつけそうになりながら、ついに、メキシコの
ファレスにあるエルパソ国境付近のギャンブル場まで来た。ファレスは、
当時はワイルドで荒っぽい場所だった。エドも一度見ておくといい」
「新聞社でもうけたカネを、みんな失ったのかな」
「そうだな、ウォリーは、もっと前に、すべて使っていた。ウォリーは、
ギャンブル場で働いていた。ブラックジャックのディーラーとして。オ
レがそこに着くころには、ウォリーは、ファレスにはあきあきしていた。
それで、オレが着くとディーラーをやめた。どうやら言葉がしゃべれる
ようになっていて、いっしょにベラクルスへ行かないかと誘われた。
これは愉快な旅だった。ベラクルスはファレスから1200から13
00マイルの距離だった。そこに着くまで4ヶ月かかった。ファレスを
出発したとき、オレたちの手持ちは85ドルだった。しかしメキシコド
ルに両替すると、400ドルくらいになった。国境付近ではたいしたこ
とないが、メキシコへ100マイルも入れば、金持ちになれる。ただし、
言葉が話せて、インチキ賭け事に引っ掛からなければだが。
オレたちは4ヶ月のうち、半分は金持ちだった。モンテリーでは、オ
レたちより頭のいい連中といっしょだった。あのとき国境に向けてラレ
ドへ戻ればよかったが、オレたちはベラクルスへの旅を続けることにし
た。徒歩でメキシコの服を着て、3週間1ペソもない日が続いた。英語
さえ忘れかけて、言葉に慣れるため、オレたち同士でも現地の言葉でし
ゃべっていた。
ベラクルスで仕事を見つけて、無一文を脱した。そこが、ウォリーが
初めてライノタイプに出会った場所だった。スペイン語の新聞を出して
いたのはドイツ人で、スウェーデン人の妻がいて、生まれはビルマだっ
た。英語とスペイン語、両方に達者な者を捜していて、彼自身は英語が
よくしゃべれなかった。それで、ウォリーにライノタイプの使い方を教
えて、平台印刷機で新聞の発行を続けた」
オレは言った。「そうだったのか」
「なに?」
オレは少し笑った。「高校ではラテン語を選んだ。外国語を選ぶとき、
おやじはスペイン語なら教えられると言ったが、学校で習った程度だと
思っていた。まさか、話せるとは思いもしなかった」
アムは、とてもまじめな顔でオレを見た。なにかを考えているように、
黙っていた。
しばらくして、オレはきいた。「ベラクルスのあとは、どこへ?」
「オレはパナマへ行った。ウォリーはしばらくベラクルスにとどまって
いた。ウォリーのお気に入りが、ベラクルスにはあった」
「長くそこに?」
「いや」と、アム。短く言った。時計を見上げた。「行こう、エド。カ
ウフマンの店に戻った方がよさそうだ」
オレも時計を見上げた。「まだ時間がある。戻るのは、9時。ウォリ
ーのお気に入りが、ベラクルスにはあったのなら、なぜ、長くいなかっ
た?」
アムは、一瞬オレを見て、目が瞬いた。「エドに教えても、ウォリー
は、もう気にしないだろう」
「そう、教えて!」
「ウォリーは、決闘して勝った。ベラクルスのお気に入りは、新聞社を
やっているドイツ人の妻だった。ドイツ人からモーゼル銃で決闘を挑ま
れ、逃げられなかった。決闘には勝って、ドイツ人の肩を撃って病院送
りにした。しかしすぐにウォリーはベラクルスから出た。ひそかに、不
定期貨物船の積み荷にもぐりこんだ。あとで、なにがあったか話してく
れた。4日目につかまって、乗船代としてデッキをそうじしたり働かな
くてはならなかった。そのとき立っていられないほど船酔いになった。
ウォリーは海が苦手だったようだ。しかし、最初の寄港地に着くまで船
から降りられなかった。そこがリスボンだった」
「冗談でしょ?」と、オレ。
「いや、本当だ。しばらくスペインにいた。マタドールになるために学
びたいという、変な考えを持った。しかし、どこにも入れてもらえなか
った。若いうちから、訓練を始めなけりゃならないし、伝がなければだ
めだ。そのうえ、ピカドールの役はまっぴらだった」
「ピカドールって?」と、オレ。
「馬に乗って槍で牛を刺激する役。馬は、ほとんどの戦いで角で刺され
る。傷口におがくずをかぶせておいて、あとで縫うが、深く刺されれば、
生きてはいられない━━━やめよう。この部分はスキップする。オレも
闘牛のこの部分はいつも嫌だった。オレが見た最後の試合では、数年前
のファレスだが、馬にパッドを当てていて、そこは刺されても馬は大丈
夫だった。闘牛は剣できれいに殺された。屠殺場で行われることよりそ
の点ではずっとよかった。そこでは━━━」
「おやじのことは?」オレは提案した。「スペインのあと」
「ああ、また戻った。オレたちは、セントポールにいた友人を通じて、
手紙でやり取りした。オレは、ロサンジェルスのホイーラ探偵事務所に
いた。ウォリーはボードヴィル一座にいた。かなりうまくジャグリング
ができた。トップスターではなかった。ジャグリングのなかでさえ。し
かし、インドの棒はうまかった。有名な一座にも出られるくらいだった。
ウォリーはジャグリングは?」
「いや」と、オレ。「やったことはなかった」
「そういったことは、よく覚えておくといい。さもないと、忘れてしま
う。ウォリーは手でやることが上手だった。ライノタイプも素早かった。
そうだった?」
「すべて普通のスピードだった」と、オレ。なにかが気になった。「た
ぶん、それは、数年前にわずらった、腕の関節炎のせいだ。数ヶ月仕事
ができなかった。そのあと、スピードが落ちて、その後も続いた。シカ
ゴに移る前のゲーリーにいたころ」
アムは言った。「オレには一度も言わなかった」
オレはきいた。「アムとおやじは、いっしょにまた、なにかやったこ
とは?お互いを訪ねる以外に」
「そうだな。オレが警察の手先になって、探偵事務所にいたことは話し
たが、やめて、ウォリーとオレは薬のショーの一座について、いっしょ
に旅した。ウォリーは、黒人の顔で、ジャグリングやいろんなことをし
た」
「アムは、ジャグリングは?」
「オレはできない。ウォリーは、手でするショーはすべてできた。オレ
は口の方。呼び込みや、腹芸とか」
オレは分からないという顔をしたらしい。
アムは、歯を見せて笑った。「つまり、腹話術。さぁ、行こう!もう
ほんとうに行く時間だ。もしもオレやウォリーの物語を聞きたければ、
仕事の前のひとやすみくらいでは話しきれない。そろそろ9時だ」
オレはカウフマンの店まで、ぼーとしながら歩いた。
オレは、おやじがライノタイプのオペレータだったことも知らなかっ
た。おやじがワイルドな若者だったとは、考えもしなかった。メキシコ
を無一文で旅したり、決闘をしたり、スペインでマタドールになろうと
したり、薬のショーでジャグリングしたり、ボードヴィルの一座にいた
り。
そのすべてとともに、とオレは考えた。彼は酔って路地で死んだ。
7
カウフマンの店は、前より混んでいた。バーカウンターには6人の男
と2人の女、2つのブース席にカップル、後ろのテーブルのカードゲー
ムにもいた。ジュークボックスは鳴り響いていた。
しかし、オレたちのテーブルには誰もいなかった。オレたちは、前と
同じように座った。カウフマンは、バーで忙しく、オレたちが来て座っ
たのを見てなかった。
1分以上してから、こっちを見て、カウフマンを見つめるオレたちと
目が合った。バーカウンターの目の前の男のグラスにウィスキーを注い
でいた。グラスのふちまで酒があふれ、磨いたカウンターに小さな水た
まりができた。
レジを鳴らし、カウンターの端をまわってオレたちの前に立つと、手
を尻にあて、好戦的に見えて、同時に決めかねている様子だった。
カウフマンは低い声で言った。「なにが欲しい?」
アムは無表情だった。顔にユーモアのかけらもなかった。声にも。
「ホワイトソーダ、2つ」
カウフマンは手を尻から出して、エプロンでゆっくりふいた。目をア
ムからオレに移した。オレは、平坦にじっと彼を見た。
長くはオレを見てなかった。アムに目を戻した。
イスを引いて座った。彼は言った。「ここで、トラブルはごめんだ」
アムは言った。「オレたちも、トラブルは好きじゃない。巻き込まれ
るのはごめんだし、こちらから起こすつもりもない」
「なにか言いことがあるなら、言ってしまえば、もっと楽になるんじゃ
ないか?」
「なにを?」と、アム。
飲み屋のオーナーの唇は、一瞬こわばった。怒り出しそうに見えた。
声が前より静かになった。彼は言った。「あんたらをどこで見たか思
い出した。路地で撃たれた男の検死法廷に来ていた」
アムはきいた。「どの男?」
カウフマンは深く息をしてゆっくり吐いた。彼は言った。「そう、確
かだ。あんたらは、後ろの席で人目をはばかるように座っていた。あん
たらは、あのハンターの友人かなにかか?」
「どのハンター?」
カウフマンは、また、怒り出しそうに見えた。それから、低姿勢にな
った。
彼は言った。「あんたらの手間を省いてやろう。欲しいものがなんで
あれ、ここにはない。オレはなにもしてない。知ってることはすべて、
検死法廷で警官に話した。あの件についてはなにも知らないし、すべて
話した。あんたらはそれを聞いたはずだ、あそこにいたんだから」
アムはなにも言わなかった。タバコのケースを出すと、オレに差し出
した。オレは1本取った。それをカウフマンにも差し出したが、カウフ
マンは無視した。
カウフマンは言った。「話したことがすべてだ。あんたらはなにしに
ここへ来たんだ?いったいなにが欲しいんだ?」
アムは顔色一つ変えなかった。アムは言った。「ホワイトソーダ。グ
ラスで2つ」
カウフマンは急に立ち上がったので、座っていたイスが後ろへひっく
り返った。首から上が赤くなった。彼は振り返って、イスをつかみ、テ
ーブルの下に注意深く戻した。元あった位置に正確に戻すことが重要で
あるかのように。
それ以上なにもしゃべらず、バーカウンターに戻った。
数分してから、背の高い、子どもっぽい顔をしたバーテンダーが、ホ
ワイトソーダを運んできた。陽気に歯を見せて笑い、アムも笑い返した。
アムの目のすみに、小さなきらめきがあって、本当の笑いのようだった。
カウフマンはこちらを見なかった。バーカウンターの反対側の客の相
手をしていた。
「嫌な客を追い返すミッキーは入れてない?」と、アム。
「ミッキーはなし」と、バーテンダー。「ホワイトソーダにミッキーを
入れたら味で分かってしまうから、入れない」
「そう、それ!」と、アム。スリムなバーテンダーに1ドル紙幣を手渡
した。「釣りは取っておいて、スリムくん!息子の貯金箱に」
「どうも。店長があんたのことを気にしてる、アム。いつ帰るか知りた
がってる」
「すぐだ、スリムくん。話しているのを見られる前に、行った方がいい」
バーテンダーは、カードゲームテーブルの客の注文を聞きに戻ってい
った。
オレはきいた。「彼といつ知り合いに?」
「昨夜だ。彼の仕事のあと。彼の名前と住所をバセットに教えてもらっ
て、電話した。彼はもう、味方さ」
「100ドル渡して?」
アムは頭を振った。「買収できる人間もいれば、できない人間もいる。
オレは彼の息子の貯金箱に、わずかな銀貨を入れただけ」
「彼の息子の貯金箱は、ジョークでなかったんだ。つまり、釣り銭のこ
と」
「ジョークじゃない。釣り銭が、どこに行くかの話」
「そうだったのか」と、オレ。
カウフマンは、また、バーカウンターのこちら側の端に来たので、オ
レはしゃべるのをやめて、彼を見る仕事に戻った。彼は、再びこちらを
見ることはしなかった。
オレたちは、真夜中少し過ぎまで店にいた。それから立ち上がり、店
を出た。
◇
家に帰ると、おふくろとガーディは寝ていた。おふくろのメモに、仕
事探しを始めたいから、起きたら何時でもいいから自分も起こしてくれ
とあった。
オレは疲れていたが、なかなか眠れなかった。おやじについて聞いた
ことを考えていた。
おやじはオレの年で、と考えた。新聞社のオーナーになって新聞を出
していた。決闘をして男を撃った。既婚の女性と関係を持った。メキシ
コを徒歩で旅して、メキシコ人のようにスペイン語をしゃべった。大西
洋を横断して、スペインに住んだ。国境の町で、ブラックジャックのデ
ィーラーをしていた。
おやじはオレの年で、と考えた。ボードヴィルの一座にいて、薬のシ
ョーで旅をしていた。
黒人の顔をしたおやじを、想像できなかった。それ以外のことも、想
像できなかった。おやじはその頃、どんな顔をしていたんだろう?
しかし、オレは、そのうち眠った。おやじの夢は見なかった。自分の
夢を見た。オレはマタドールで、スペインの闘牛場にいた。顔に黒いド
ーランをぬって、手には細長い剣を持っていた。夢は、混ざり合って、
さらに、混ざり合った。闘牛の牛は、本物の巨大な黒い牛だった。だが、
少し変わり、なにか、それは飲み屋のオーナーのカウフマンになった。
そいつはオレに向かって突進してきた、角は1ヤードもあって、先端
が針のように尖って、太陽を反射してギラギラ光った。オレは、恐ろし
く、すごく、恐ろしく━━━。
◇
オレたちは、次の日の午後3時に飲み屋に戻った。アムの調べでは、
それがだいだい、カウフマンが店に出てくる時間だった。スリムくんは、
昼は休みで、2人では手が回らないほど忙しくなる夜から、出てくるこ
とになっていた。
オレたちが店に入ると、カウフマンはエプロンをつけていて、スリム
くんは、ちょうど帰ったばかりだった。
カウフマンは、オレたちが来るのを予想していたように、注意深くこ
っちを見た。カウフマンとオレたち以外、店には誰もいなかった。しか
し、ビールやウィスキーの臭い以外のなにかが、空中を漂っていた。
トラブルになりそうだ、とオレは考えた。
オレは、昨夜見た夢と同じくらい恐ろしかった。夢を見ているようだ
った。
オレたちはテーブルについた。同じテーブルに。
カウフマンは戻ってきた。彼は言った。「トラブルはごめんだ。なぜ
他の席に行かない?」
アムは言った。「ここが好きなんだ」
「オーケー」と、カウフマン。バーカウンターに行って、ホワイトソー
ダのグラスを2つ持って戻ってきた。アムは20セントを渡した。
カウフマンはバーカウンターに戻り、グラスを磨き始めた。オレたち
の方は見なかった。一度、グラスを落として割った。
少しして、ドアがあいて、ふたりの男が入ってきた。
ふたりとも大きく、タフそうに見えた。ひとりは、もとボクサーだっ
た。耳を見ればすぐ分かった。頭はつるっぱげで、肩は猿のように盛り
上がり、目は小さく、ブタの目のようだった。
もうひとりは、大きな男のとなりでは小さく見えた。しかし、よく見
ると、5フィート11インチはありそうだった。体重も裸でも180ポ
ンドありそうだった。顔は馬づらだった。
ふたりは店を入ったところで立ち止まり、まわりを見渡した。ブース
席をすべて見て、誰もいないことを確かめた。オレたちを除いて、すべ
てチェックした。アムはイスを動かして、足の位置を変えた。
ふたりはバーカウンターへ行った。
カウフマンは、ふたりの前にグラスを2つ置いて、なにも言われない
のに、酒を注いだ。
いずれ分かるにしても、これですっかり読めた。
胃のくぼみにあった、冷たい感覚が広がりつつあった。立ち上がった
ときに、足がぐらぐらしそうで心配だった。
オレは目の端で、アムを見た。アムの顔は完全に冷静だった。唇は動
いていなかったが、オレが聞こえる音量以上の大声で話した。口が動か
ないことに一瞬驚いたが、腹話術のことを思い出した。
アムは言った。「エド、ここはひとりの方が、うまく切り抜けられそ
うだ。トイレへ行け!そこに窓があるから、外へ出て逃げろ!今すぐに!
やつらは飲んだらすぐ始める」
アムが嘘をついているのが、オレには分かった。アムが悪役を演じな
ければ、ここを乗り切る道はどこを捜してもなかった。オレが悪役でな
い以上に、アムも悪役でなかった。
オレは自分が、悪役だと考えた。オレはガンマン。100ドルに見え
るスーツを着て、スナップブリムのハットをかぶっている。しかも安全
装置をはずした、仮想の38口径も。それは、左肩に吊るしたホルスタ
ーに収めてある。
オレは立ち上がった。足はゴムではなかった。
アムのイスの後ろを回ってから、男たちの室のドアに向かって歩いた。
しかしそこまでは行かず、バーカウンターの端の手前で止まった。そし
て、カウンターの前と後ろを見渡せるところに立った。
右手を持ち上げて、今はないが38口径の台尻に触れているあたりの
コートの内側に、指を休ませた。
オレはなにもしゃべらなかった。やつらを見ていただけだ。手をカウ
ンターの上に置いておけと言わなかったが、やつらはそうしていた。
オレは3人とも見ていた、中でも、カウフマンの目を見ていた。カウ
ンターの後ろのどこかに銃を置いてあるはずだ。それがどこか分かるま
で、カウフマンの目を見ていた。立っているところからは見えなかった
が、それを隠してある場所が、今、分かった。
「おまえらはなにしに来た?」と、オレ。
馬づらが答えた。「なんでもない、ダンナ。なんでもない」
頭をカウフマンに向けた。馬づらが言った。「たった10ドルで、ジ
ョージ。危ない橋を渡らせようってのか?」
オレはカウフマンを見た。オレは言った。「汚い手を使ったな、ジョ
ージ。カウンターから数歩下がったらどうだ?」
カウフマンは、ためらった。オレはコートの中へ1インチ手を滑らし
た。
カウフマンは、3歩後ろへゆっくり下がった。
オレはカウンターを回って、先に、やつの銃を取り上げた。それは、
38口径のフレームを使った、短銃身の32口径リボルバーだった。い
い銃だ。
シリンダーをあけて、カートリッジを、カウンターの後ろの2つある
シンクの一方の皿洗い用の汚れた水へ落とした。そのあとで、銃も水の
中へ落とした。
後ろの棚からボトルを取るために、カウンターを回った。鏡でアムと
目が合った。アムは同じテーブルに座って、チェシャネコのように歯を
見せてニヤニヤしていた。オレにウィンクした。
オレが見て一番高いボトルは、ティーチャーズのハイランドクリーム
だった。
「これは店のおごりだ!」と、オレ。ふたりのグラスについだ。
馬づらはオレに笑いかけて言った。「レジからオレたちに10ドル出
してくれないか、ダンナ?ジョージが仕掛けた汚い手でもらえるはずな
んだが」
アムは立ち上がり、バーカウンターへ歩いてきた。馬づらと巨漢の間
に来た。ふたりの間にいると、立っていても小さく見えた。
アムは言った。「オレに払わせてくれ」財布を出した。10ドル紙幣
を2枚出して、両側の男たちにそれぞれ渡した。「その通り!今回のこ
とでペテンにかけられるのを見たくない」
馬づらは紙幣をポケットにしまった。「あんたが正しい。オレたちは
それだけのことはしないとな、ダンナ?」
馬づらはカウフマンを見た。巨漢もカウフマンを見た。カウフマンは
真っ青になって、もう一歩後ろに下がった。
「いや」と、アム。「オレたちはジョージが好きだ。ジョージになにか
あって欲しくない。エド、みんなにもう一杯ついでくれ!」
オレは、ふたりのグラスにハイランドクリームをついだ。さらにグラ
スを2つ出して、ホワイトソーダを3/4クォータづつ注いだ。
「ジョージを忘れないでくれ!」と、アム。「ジョージもいっしょに飲
みたいはず」
「そうだった」と、オレ。
オレは5つ目のグラスを出して、注意深く、ホワイトソーダを注いだ。
それを、カウフマンの前までカウンターをすべらした。
カウフマンはグラスを取らなかった。
それ以外の4人は、飲んだ。
馬づらは言った。「やらないでいいのか?」
「ああ」と、アム。「オレたちはジョージが好きだ。知り合いになれば
いいやつ。今のままでいい。このあたりを見回ってる警官が、もうすぐ
来る。顔を見せるかもしれない」
馬づらは言った。「ジョージは不平を言わないだろう」そして、カウ
フマンを見た。
みんなはもう一杯づつ飲んだ。それから、2人の巨漢は出て行った。
とてもなごやかだった。
アムは、歯を見せて笑った。アムは言った。「エド、ジョージのレジ
に入れといてくれ。スコッチを6杯、1杯50セントと計算して。あと、
5杯のホワイトソーダもレジに」カウンターの上に5ドル紙幣を置いた。
「3ドル50セントを会計してくれ!」
「分かった」と、オレ。「ジョージにおごられたくない」
オレはレジを鳴らして、アムに1ドルと50セントの釣りを渡し、5
ドルをレジに入れた。
オレたちはテーブルに戻って、座った。
たっぷり5分間座っていた。その間に、カウフマンは、みんなすべて
終わったことだし、なにも起こらなかったことにしようとするだろう。
5分間の終わりに、男がひとり入ってきて、ビールを注文した。カウ
フマンはビールを注いだ。
それから、オレたちのテーブルに来た。まだ、アゴのあたりが少し青
くなっていた。
カウフマンは言った。「神に誓って、ハンターが撃たれたことについ
ては、なにも知らない。検死法廷で言ったことが、すべてだ」
オレたちは、なにも言わなかった。
カウフマンはしばらくそこに立っていた。それから、バーカウンター
へ戻って行った。タンブラーに、指2本分ウィスキーをついで飲んだ。
オレたちが見始めてから、最初の飲酒だった。
オレたちは、ぶっとうしで、夜8時半まで、そこに座っていた。
多くの客が、来ては出て行った。カウフマンは、それ以上ウィスキー
を飲まなかったが、2つグラスを落として、割った。
◇
シカゴアベニューに向かって歩くあいだ、あまりしゃべらなかった。
食事のとき、アムは言った。「エド、今日は上出来だった。いや、正直
に言おう。まさかエドにあんな才能があるとは、思いもしなかった」
オレは、歯を見せて笑った。オレは言った。「オレも正直に言うが、
自分でも思いもしなかった。今夜はあそこに戻る?」
「いや。やつは、すぐにでも口を割りそうだが、明日まで待とう。違う
角度から攻めて、明日の夜までに、口を割らそう」
「やつは、まだ、口を割るところまでいってないというわけだ。なにか
を隠しているということ?」
「やつは、なにかを恐れている。検死法廷でも、なにかを恐れていた。
オレが思うに、やつはなにかを知っている。とにかく、すぐにでも、口
を割りそうなところまで来ている。今日はすぐ帰って、明日、早く来れ
ばいい。気分転換に、睡眠が必要だ」
「あんたはなにを?」
「11時にバセットに会う。それまではなにも」
「それまで待てるし、バセットにも会いたい。オレは眠くない」
「ああ、余波ということもある。緊張の場面に自分を置いた。手は震え
てない?」
オレはうなづいて、言った。「大丈夫だが、胃が葉っぱのように揺れ
ている。悪役を演じてるあいだ、すごく恐怖を感じた。バーカウンター
に寄りかかったら、そのまま倒れてしまいそうだった」
「眠らないのは正解かもしれない」と、アム。「しかし11時まで2時
間ある。どう時間潰しする?」
オレは言った。「エルウッド出版に立ち寄ってみる。おやじとオレの
給与の小切手をもらいたい。週の半分、それ以上ではないが、週の5日
のうち、3日分はある」
「夜中にもらえるのか?」
「もらえる。小切手は、上司のデスクの中で、夜は夜間の上司がキーを
持っている。あと、おやじのロッカーからものを出して、家に持ち帰り
たい」
「そうか。あと、教えて欲しいのは、ウォリーが殺された原因となるも
のは、会社にはなかった?」
オレは言った。「よく分からない。ただの、印刷会社だ。つまり、金
目なものは扱ってはいない」
「ああ。とにかく、いろいろな方向に、目や脳を向けておくことだ。敵
はいなかった?みんなが味方だった?」
「そうだと思う。みんなに好かれていた。本当に親しい友人はいなかっ
たが、誰とでもうまくやっていた。おやじとバニーウィルソンは、互い
によく会っていた。バニーは夜勤で、おやじは昼間なので、それほど多
くはなかったが。ほかにジェイクという昼間の上司がいた。ジェイクと
おやじは、かなり仲がよかった」
「そうか。オレはバセットに、グランドアベニューの店で会う。別の日
の夜中、オレたちがバセットに会った店だ。エドも来るなら、11時前
後に来てくれ!」
「そうする」と、オレ。
◇
オレは、オーク近くのステート通りを上がって、エルウッドに向けて
歩いた。暗くなってから、仕事に行くわけではないのにそこへ行くのが、
おかしな気がした。
薄暗い階段を3階まで上がり、校正室の入り口で立ち止まり、中をの
ぞいた。西側に6台のライノタイプが並んでいた。バニーが一番近くの
台で活字を組んでいた。それ以外の3台にも、オペレーターがいた。
おやじの台には誰もいなかった。おやじがいなくて使われてない台が
あるからというよりは、単に夜中でオペレーターが少ないからだ。オレ
は入り口で数分立っていた。誰にも声をかけられなかった。
夜間の上司のレイメッツナーがデスクを横切って歩いてきたので、オ
レはついて歩いて、席の近くに立った。
彼は見上げて言った。「やぁ、エド」そして、「ハイ」と、オレ。そ
れから、オレたちは言葉に詰まった。
バニーウィルソンがオレを見て、歩いて来て、言った。「仕事に戻る
のか、エド?」
「もう少ししたら」と、オレ。バニーに言った。
レイメッツナーは、デスクの鍵の掛かった引き出しをあけて、小切手
を見つけた。オレは受け取ってポケットに入れた。彼は言った。「エド
は、百万長者の身なりだな」
オレは自分の身なりを、すっかり忘れていた。少しきまり悪い気がし
た。
バニーは言った。「エド、仕事に戻る準備ができたら、昼間の勤務の
代わりに、夜の勤務にしたらどうだ?レイ、エドは夜でも勤務できる?」
メッツナーはうなづいて、言った。「いいアイデアだ。夜間は働きや
すいし、給与も少しいい。植字を習ってるところだろ?」
オレはうなづいた。
彼は言った。「夜勤だともっと学ぶ時間がある。2台のマシンがいつ
も空いている。自由に時間を使って練習できるし、オレたちも30分く
らい教えられる」
「考えてみる」と、オレ。「たぶん、そうする」
彼らの言う意味は分かった。昼間の勤務でいっしょに働いていた、お
やじがいなくなったのだ。たぶん彼らが正しい、とオレは考えた。とに
かく、いい人たちだった。
「そう」と、オレ。「これからロッカーに行ってみる。レイは、おやじ
のロッカーをあけるマスターキーを持ってる?」
「ああ」と、レイメッツナー。自分の鍵束からマスターキーをはずして、
渡してくれた。
バニーは言った。「ランチタイムまで15分だ、エド。オレは外へ行
って、サンドウィッチとコーヒーのランチを食べる。少し待っててくれ
たら、いっしょに行かないか?」
「ちょうど食事してきたところ」と、オレ。「しかし、ジャバコーヒー
ならつきあいたい」
メッツナーは言った。「もう行ってきていいよ、バニー。オレがパン
チカードを打っておく。オレもいっしょに行きたいが、弁当がある」
オレたちはロッカー室へ行った。オレのロッカーから取り出すものは
なかった。おやじのロッカーをあけた。古いセーターに定規に小さな黒
のスーツケース以外なにもなかった。セーターは家に持ち帰る価値はな
かったが、捨てる気にもなれなかった。セーターと定規はオレのロッカ
ーにしまった。小さなスーツケースはロックされていて、すぐに中を見
ることはできなかった。
家に向かっているとき、中になにがあるか分かった。いつも少し気に
なっていたのだ。スーツケースは、厚さが4インチ、縦横がだいたい1
2X18インチでどこにでも売ってるものだった。オレがエルウッドで
働き始めたときから、おやじのロッカーの隅にいつもあった。
一度おやじにきくと、こう言った。「ただの古い私物さ。家には置い
ときたくない。貴重品はない」それ以上しゃべることはなく、オレも尋
ねなかった。
オレたちは外へ出て、ステート通りとオーク通りの角の小さな食い物
屋に入った。バニーがサンドウィッチとパイを食べているとき、オレは
ほとんどしゃべらなかった。
それから、オレたちはタバコに火をつけ、バニーは言った。「警察は
まだ、犯人を捕まえてない?ウォリーを殺した犯人」
オレは首を振った。
「容疑者は誰かいる?」
オレはバニーを見た。
バニーがそういうことを言うのが、おかしい気がした。一瞬、バニー
が言ったことがオレから離れて、向こうが透けて見えた。
オレは言った。「警察は、おふくろを疑ってはいない、あんたの言う
意味がそうなら」
「オレは別に━━━」
「隠さないで、バニー!あんたの言ったことは、そのことだった。そう、
おふくろはまったく無関係だった」
「ああ、分かってる、エド。オレが言いたかったのは、そう、いらんこ
とに口を挟んで、自分のわなに掛かっちまった!微妙な問題に首を突っ
込むべきでなかった。情報を与えもしないで、エドから情報を得ようと
していた。ほかの手がありそうだ」
「分かった。それで」と、オレ。「情報は?」
「考えてもみろ、エド。男が殺された。警察は、妻が完全にシロでなけ
れば、いつも妻を疑う。理由はきかないでくれ!警察はいつもそうだ。
同様に、女が殺されたら、警察は自動的に夫を最初に疑う」
オレは言った。「オレもたぶんそう思う。しかし今回は違っていて、
完全なホールドアップだった」
「確かに。しかし、別のアングルでの調査も行う。事件が、そのように
見えるものとは本当は違っているかもしれない。エドの母親のマッジが、
12時と30分過ぎのあいだにどこにいたか知っている。よって、彼女
はシロだ。アリバイが必要なら、あげられる。彼女はやってないという
オレの根拠は、これだ」
「どこで見たの?」
バニーは言った。「水曜は、非番だったので、1・2杯飲んでいた。
そして、10時くらいにエドの家に電話して、ウォリーがいるかどうか
きいた。そしたら、ウォリーは━━━」
「思い出した」と、オレ。「電話に出て、おやじはもう外出したと答え
た」
「そう。それで、ウォリーに出くわさないかと、何軒か店をまわった。
真夜中近く、グランドアベニュー近くの1軒の店で、店の名前は知らな
いが、マッジが入ってきた。寝る前に一杯やりに出てきたと言った。ウ
ォリーはまだ帰ってないとも言った」
オレはきいた。「腹を立てていた?」
「それは分からない。そうでないように見えた。しかし、本心は分から
ない。女は奇妙。とにかく、オレたちは少し飲んで、話した。マッジが
店を出たのは1時半すぎで、オレも家に帰った。家に着いたのは2時少
し前だったから、分かる」
オレは言った。「おふくろにとっては、アリバイが必要なら、いいア
リバイになる。ただ、おふくろには必要ない。バニー、教えてくれない
か?なぜ、検死法廷に来たんだ?あそこでは、それが不思議だった」
「たしかに。オレは何時に起きたことなのか、知りたかった。あと、す
べてを。検死法廷では、マッジがあの夜、外出したのかどうか聞かれな
かった。それで、マッジは大丈夫だと知った。そのときまで。彼女は聞
かれた?」
「オレの知る限り。聞かれてない」と、オレ。「そんなことは全く問題
とならなかった。オレがおやじを起こしに行ったとき、おふくろはまだ
ドレスのままだったので、外出したことは知っている」
「まだ、ドレスのまま?なんてことだ、エド。なぜそんな━━━」
オレはしゃべるべきでなかったと思った。こうなったら、すべて話さ
ないわけにゆかない。「おふくろは、酒のボトルを持ち帰ってて、おや
じが帰ってくるのを待ちながら、飲み続けていた。着替えないで、その
まま眠った」
「警察は知らない?」
「分からない、バニー」と、オレ。あの朝に起きたことを話した。「オ
レが家を出るとき、おふくろは起き始めた。おふくろは服を変えたり、
バスローブに着替えたりしていれば、警察は来たとき気づいてない。オ
レが家を出たあとで、おふくろはドアで警察に答えているので、知れな
かったとしても、不思議はない」
「それなら良かった」と、バニー。「マッジが外出していたことを警察
が知らないなら、大丈夫だ。どういう意味か分かるはず」
「ああ」と、オレ。
おふくろが、あの夜、どこにいたのか分かって、心配するようなこと
はなにもなかったことを知って、オレは少しホッとした。
バニーは、別れ際にまた、オレにカネを貸そうとした。
◇
オレが食い物屋に着いたとき、アムは、数日前と同じブース席にひと
りで座っていた。11時まで数分あった。
アムはオレを見て、それからスーツケースを見た。質問したい目をし
ていたので、オレはなんなのか話した。
アムはスーツケースを目の前のテーブルの上に置くと、ポケットの中
をさがし回った。ペーパークリップを見つけると、まっすぐに伸ばし、
先端を少し曲げた。
「あけていいのか、エド?」
「もちろん、いい」と、オレ。「やってくれ!」
ロックは簡単にあいて、ふたを持ち上げた。
「びっくりするかも」と、オレ。
ちょっと見ると、それは、奇妙なごちゃまぜだった。それから、1つ
のアイテムが、もう1つと意味を持ち始めた。それらは、おやじが若い
ころにやっていたことを、アムが話してくれていなかったら、なんの意
味もなさなかっただろう。
黒の毛ばだったかつらがあった。それは、貴族が黒く化粧してつける
もののようだった。直径がだいたい2・5インチの明るい赤のボールが
6つあって、ジャグリング用だった。鞘にスペイン船が描かれた短剣。
美しいバランスの単発のターゲットピストル。黒のマフラー。メキシコ
原住民の子どもの小さな土の人形。
ほかにもあった。すべてを一度に見ることはできない。
手書きの紙の束。ティッシュで包まれたなにか。壊れたハーモニカ。
それは、おやじの生涯だ、とオレは考えた。それが、小さなスーツケ
ースの中に詰め込まれていた。とにかく、おやじの生涯の一面ではある。
それらは、おやじが保存したいと思ったものだが、家には置いておきた
くないもの、誰かが蹴っ飛ばしたりしてなくなったり、あるいは質問さ
れて答えなくてはならない家には置いておきたくないものだった。
音がしたので見上げると、バセットが立ったまま見下ろしていた。
「このガラクタはどこから?」と、バセット。
「座れ!」と、アム。バセットに。アムは、明るい赤のジャグリングボ
ールを1つ拾い上げ、水晶のように、覗き込んだ。目に奇妙な輝きがあ
った。泣くわけでもなく、いや、まったくそうでもないような。
オレもバセットも見ないで、アムは言った。「話してやれ!」オレは
バセットにスーツケースについて話した。それがどこにあったかを。
バセットは手を伸ばして、紙の束を拾い上げた。それを引っくり返し
て、言った。「なんてこった!スペイン語だ」
「詩のようだ」と、オレ。「改行の仕方がまるで。アム、おやじはスペ
イン語で詩が書けたの?」
アムは赤いボールから目を離すことなく、うなづいた。
バセットは、中のものをかき混ぜて小さな紙を見つけた。新しいパリ
パリの紙で、3×4インチくらいの大きさだった。印刷された書式に、
タイプライターで欄が埋められ、インクでサインがあった。
バセットはオレの隣りに座っていたので、彼が読む間にオレも読んだ。
それは、セントラル相互保険会社に払い込んだ保険料の領収書だった。
日付は2ヶ月たってなかった。ウォレスハンター名義の保険証書の年4
回払いの1回目を払い込んだ保険料の領収書だった。
金額を見て、オレは口笛を吹いた。5千ドルの保険証書だった。『終
身生命保険証書』の下の注意書きに、『倍額支払』とあった。つまり、
1000ドルだ。殺人は事故死といえるだろうか?
受取人の名前は、ウァレスハンター夫人となっていた。
バセットは咳払いをした。アムは見上げた。バセットは保険料の領収
書を、正面のアムに差し出した。
「捜していたものだ」と、バセット。「動機だ。彼女は保険を掛けてな
かったと言っていた」
アムは領収書をゆっくり読んだ。アムは言った。「あんたはどうかし
ている。マッジはやってない」
「彼女はあの夜外出していた。彼女は動機があった。彼女は2回ウソを
ついた。悪いが、ハンター、残念ながら━━━」
バーテンダーは、テーブルの脇に立っていた。「ご注文は?」
8
「聞いてくれ!」と、オレ。バーテンダーが注文を取って戻って行くと
言った。「おふくろはやってない。アリバイがある」
ふたりはオレを見た。アムは、まゆげを半パイカ分上げた。
オレはバニーのことを話した。話しているあいだ、バセットの表情を
見ていたが、なにも読み取れなかった。バセットは言った。「たぶん、
やつに会っておく。どこに住んでる?」
「ああ」と、オレ。バニーウィルソンの住所を教えた。「今夜は、朝1
時半に仕事があける。家にまっすぐ帰るのか帰らないのか、知らない」
「分かった」と、バセット。「このバニーというやつと話すまでは、動
かない。だが、あまり意味ないかも。彼は家族の友人だし、つまり、マ
ッジの友人で、好意から時間を伸ばしたりするかもしれない」
「なぜ、彼がそんなことを?」
バセットは肩をすくめた。知らないという肩のすくめでなく、話した
いことはなにもないという肩のすくめだった。
多くの意味があった。オレは言った。「聞いてくれ!あんたは━━━」
アムがオレの腕に手をのせて、つかんだ。
アムは言った。「もういい、エド。1ブロック歩いてきて、頭を冷や
せ!」
アムの握りは強くなって、痛かった。
「今すぐだ!」と、アム。
バセットがオレをブース席から出させるために、立ち上がったので、
オレは立ち上がって、急いで外へ出た。そのときは地獄のように感じた。
◇
外に出ると、グランドアベニューまで歩いた。
手になにかあると気づいたのは、タバコを取り出そうとしたときだっ
た。それは、丸い赤のラバーボールだった。明るく輝く赤の、スーツケ
ースにあった6このうちの1こだった。
オレは、高架鉄道へ上がる階段の前で立ち止まり、手の中のボールを
見つめた。なにかが背後に来た。ぼんやりした男の影で、ボールをジャ
グリングしていた。当時オレは赤ん坊だった。男は笑い、明るいボール
は、ゲーリーのアパートの揺りかごの室のランプの光に輝いた。オレは
回転する球体を見て、泣くのをやめた。
一度だけでなく何度もあった。オレはいくつだったのだろう?覚えて
いるのは、歩いたこと、少なくとも1度は、歩いて、明るいボールに手
がとどいて、男が1こを遊び用にくれて、オレがそれを口でチューチュ
ー吸うと男は笑った。
3才は過ぎてなかった、とにかくそれほどは過ぎてなかった。最後に
見たとき以来、完全に忘れていた。
オレの手の中のこのボールは、サイズも感覚も輝きもそのまま、失わ
れた記憶に戻してくれた。
しかし、ジャグリングしていた男の顔は、まったく思い出せなかった。
笑い声だけ、あとは明るく輝く球体。
ボールを上に投げて、受け止めた。いい感覚だった。6このジャグリ
ングを習うかもしれない。また、上に投げてみた。
誰かが笑って、言った。「ジャグしたいか?」
オレはボールをつかんで、ポケットにしまうと、振り返った。
ボビーレインハートだった。ハイデン葬儀店の店員、木曜の朝、出勤
してきて、おやじの遺体を見て誰だか伝えた男だ。日焼けした肌とグリ
ースを塗った黒髪に似合ってない、白のパームビーチスーツを着ていた。
歯を見せて笑っていたが、さわやかさに欠けて、好きになれなかった。
「なんだと?」と、オレ。
笑いが消えて、険悪な表情になった。
もってこいだった。やつがなにか言うのを期待した。やつの顔を見て、
ガーディといっしょのところを想像した。葬儀店に安置されたおやじを
やつが見て、そしてたぶん、おやじのからだを処置していることを考え
た。ああ、ひどい!別のだれかであってくれれば、もっと違うふうに思
えたはずだった。しかしそれを始める人間を好きではないとき、そのよ
うなことが起これば、やつを憎むだろう。
やつは言った。「なんだとはなんだ?」そして、右手をパームビーチ
コートの脇のポケットに入れた。
たぶん、タバコかなにかを出そうとしたのだろうが、オレには分から
なかった。やつは銃に手を伸ばしたように見えた。半ブロック先にだれ
もいないような、外の場所で。確かめるまで待っていられなかった。た
ぶん、理由が欲しかったのだ。
オレはやつの肩をつかみ、後ろ向きにすると、右手の手首を逆にねじ
上げた。やつは、半分ののしり、半分ぎゃあぎゃあいう声を上げて、な
にかがコンクリに当たってカチンと鳴った。
やつの手首を離して、エリの後ろをつかんだ。やつは身をかがもうと
したが、ぐいと引き上げたとき、オレたちの影が動いて、歩道に落ちた
ものが見えた。金属製の武器のナックルだった。
やつはオレの手から逃げようとしてもがき、オレの手にはコートの切
れ端が残った。コートの背中部分を引き裂き、やつの肩の右側にあるも
の、ノートやポケットの中の財布とかが落ちた。
やつはビルと背中合わせに下がって、ためらっているように見えた。
オレから逃れたかったが、金属製のナックルなしではどうしようもない
ことが分かっていた。引き裂かれたコートは下に落ちていた。
やつはそこに立ったままあえぎ、オレが向かってきたときに備えてい
たが、コートから落ちたものを、それなしでは逃げる気はなかったが、
あえて拾おうとはしなかった。
オレは金属製のナックルを、通りの中間あたりまで蹴って、後ろへ下
がった。オレは言った。「オーケー、おまえの大事なものを拾いな!叫
んだりしたら、歯を蹴っとばすからな!」
やつの目は多くを語っていたが、なにも言わなかった。やつはものを
拾うために前に出てきた。オレは下を見て言った。「ちょっと待て!」
かがんで、やつが拾う前に、財布を拾った。
それは、おやじの財布だった。
なめし皮で、高級な財布、ほとんど新品だった。しかし、磨いた皮に
対角線状に斜めの引っかき傷があった。この傷は、ライノタイプの硬い
金属製のスラッグの鋭利な角でついたものだった。
車がカーブを曲がってやって来る音が聞こえた。ボビーはこちらを見
てから走り出した。オレは財布をポケットに入れてから、やつを追った。
声が叫んだ。「ヘイ!」車がまた走り出した。
空き地を突っ切ろうとしているところを捕まえて、やつを殴っている
ところへ、車からふたりの警官がやって来て、オレたちをとらえた。ひ
とりは、オレのコートを後ろから引っ張って、ボビーレインハートから
引き剥がし、平手でオレの顔を叩いた。
「離れな、チンピラ!」と、警官。「署へ来るんだ!」
オレは後ろに向かって蹴り上げたかったが、そんなことをしても無駄
だった。
パトカーの方へ歩かされている間、オレはハーハー息をしていたが、
話せるようになると、急いでしゃべった。
「ケンカじゃない!」と、オレ。「殺人事件の捜査の一部だ。殺人課の
バセットが、ここから2ブロック先の食い物屋にいる。オレたちをそこ
へ連れて行ってくれ。バセットは、こいつに会いたいはずだ」
オレを捕まえていた警官は。オレのポケットの外側を手で触って、武
器を調べた。「署で話すんだな」
もうひとりの警官は言った。「殺人課にバセットという刑事がいる。
どの事件だ?」
「オレの父が」と、オレ。「ウォレスハンターが先週フランクリン通り
の路地で殺された事件」
彼は言った。「ここで殺された男がいた」こちらの警官を見て、肩を
すくめた。「そこへ行ってみよう。2ブロックだけだ。もしも殺人事件
なら━━━」
オレたちはパトカーに乗せられたが、気を許されたわけでなく、食い
物屋に入るときには、襟首をつかまれた。たいしたパレードだった。
◇
バセットとアムは、まだ、ブース席にいた。ふたりは見上げたが、ま
ったく驚いた様子はなかった。
バセットを知ってる警官が、オレより先にしゃべり出した。「このふ
たりのチンピラがケンカしているのを見つけた。ひとりは、あんたが興
味を持つそうだ」
バセットは言った。「さぁ。そいつを離してやれ!どうした、エド?」
オレはポケットから財布を出して、ブース席のテーブルの上に置いた。
オレは言った。「おやじの財布だ。こいつが持っていた」
バセットは財布を拾い上げると中味を調べた。お札が少しあった。5
ドル紙幣1枚に、1ドル紙幣が数枚。セルロイドの下のIDカードを見
て、ボビーの顔を見上げた。
「どこでこれを、レインハート?」彼の声は、とてもやさしく静かだっ
た。
「ガーディハンター。彼女がオレにくれた」
オレは、アムがずっと息をとめていて、それから長い息を吐いたのが
聞こえた。彼はオレを見なかった。バセットの手の中の財布を見ていた。
バセットは言った。「いつ?」
「昨夜。彼女が言うには、おやじのものだったそうだ」
バセットは財布を2つ折りにして、注意深くポケットにしまった。タ
バコを取り出して火をつけた。
バセットは警官ふたりにうなづいて言った。「ごくろうさん。オレは
これからボビーの言ったことが本当か調べる。ボビーを署へ連れて行っ
て公務執行妨害で留置しておいてくれ!」
「オーケー」
「今夜の当直は?」
「ノーバルト」
バセットはうなづいた。「彼なら知っている。彼に伝えてくれないか?
オレがしばらくしたら電話して、レインハートを釈放させるようにする
と」バセットは、財布をまた取り出し、紙幣とIDを中から抜き出して
ボビーに渡した。「中味は必要ないだろう。財布は証拠として、しばら
く預かる」
ボビーは警官に連れてゆかれるときに、ドアの手前でオレの方を見た。
オレは言った。「いつでも相手になるぜ!」
彼はそのまま外へ連れ出された。
◇
バセットは立ち上がって、アムに言った。「ナイストライだった」
アムは言った。「その財布だけでは、なんの証拠にもならないだろう」
バセットは肩をすくめた。
彼はオレに向かって言った。「家に帰って眠れるわけにいかなくなっ
た。アムに泊めてもらうか?」
「なぜ?」と、オレ。
「今夜、やらなくてはならないことがある。家宅捜査。保険証書とか、
なにか出てくるかもしれない」
アムはうなづいた。「エドは、オレのとこへ泊るだろう」
バセットは出て行った。アムは座ったまま、なにも言わなかった。
オレは言った。「中途半端なことをした。台無しにしてしまった?」
アムはオレの方を向いて、言った。「薄汚い顔をしてる。顔を洗って、
もっとしゃきっとしてこい!これから彼女ができるんだから」
オレは言った。「別のやつと張り合って?」
その言葉で、アムは蒸気機関車のようにシュッシュッとなった。これ
は、元気いっぱいだというアムのサインだった。オレは洗面所で顔を洗
った。
アムは訊いた。「気分は?」
「最高!」と、オレ。
「体調のことだ。一晩じゅう起きていられる?」
「起きていられれば、一晩じゅうでもいける」
アムは言った。「まだ、つまらぬ仕事しかしてない。調査しているも
のにからかわれている。森の中の赤ん坊だ。そろそろ、森の木を切り倒
し始めていい」
「そうさ!」と、オレ。「バセットはなにを?おふくろを逮捕?」
「マッジを尋問のため呼び出すつもりだ。財布が出てきた以上、ガーデ
ィも尋問するつもりだ。だが、オレが頼んでやめてもらった。オレたち
がカウフマンに口を割らせるために、数日待ってくれるそうだ」
「尋問が済んだら、おふくろとガーディを帰してくれる?」
「分からない、エド。分からない。もしも保険証書が出てきたら、帰さ
ないかもしれない。オレたちは今夜、2つの歯を蹴られた。保険の領収
書と財布だ。その2つは、今のところ、間違った方向を指している。バ
セットに、そのことを言っておくべきだ」
オレは、また、赤のラバーボールを手に取って遊んだ。アムは手を伸
ばしてボールを奪い取ると、押しつぶし始めた。すぐに、ボールはぺち
ゃんこになった。かなりの手の力だった。
アムは言った。「こんなものを見つけなけりゃよかった。う、うまく
説明できないが、ウォリーは、これをとっておかなければよかったのに」
オレは言った。「言ってる意味が分かる気がする」
「ウォリーは、たいへんなことになってしまった。エド、オレは10年
ウォリーと会ってなかった。この10年で、なにが起こったのだ?」
「聞いて、アム!」と、オレ。「おやじが自分で仕組んだということは?
自分で殴ったとか。たとえば、あのボトルの1つで。変な考えかもしれ
ないけど、インドの棒でジャグリングしていたから、高く投げて落ちて
くるところにいれば?変な考えなことは分かるが、しかし━━━」
「ありえないな。エドにひとつ、言ってなかったことがある。ウォリー
は、決して自殺はできなかった。恐怖症のような、一種の心理的ブロッ
クがあった。死は恐れてなかったし、死にたかったかもしれない。一度
死のうとしたことがあった」
オレは言った。「どの程度、ほんとうなのかな?そのときは、ほんと
うに死ぬ気はなかったんでは?」
アムは言った。「それは、メキシコ横断の旅で、チワワの南にいた時
だった。ウォリーは、カグラという毒ヘビにかまれた。荒野を横断する
人気のない道で、オレたちだけだった。道といっても、踏みならされた
道以上のものでなかった。応急処置の道具もなかった。あったとしても、
どうしようもなかった。カグラ用の血清はなかった。2時間以内に死ぬ。
この世における最悪の、最も苦痛を伴う死のひとつだった。
足は、すぐにはれ始め、地獄のような痛みが襲った。ふたりのあいだ
で、銃を持っていたのはウォリーだけだった。オレたちは別れを告げ、
彼は自分を撃とうとした。彼は、単純に、撃てなかった。彼の反射神経
は、反応しなかった。彼は、オレに撃ってくれるよう頼んだ。オレは━
━━分からない。事態がもっと悪くなったら、やったかもしれない。し
かし、誰かが来るのが見えた。ロバに乗ったメキシコ人だった。
彼が言うには、ヘビはカグラでなかったという━━━ヘビは、オレた
ちに撃ち殺されて道にころがっていた。カグラとほとんど見分けのつか
ないくらいに、よく似たその土地のヘビだという。毒はあるが、大丈夫
だという。しかし、痛みは本物と同じだった。オレたちは、ウォリーを
ロバに縛り付けて、隣りの村の医者まで3マイル運んだ。それで、彼を
助けた。あるいは、その医者が助けた」
オレは言った。「しかし━━━」
「オレたちは、そこで1ヶ月、とどまらなければならなかった。医者は
しゃれた男だった。オレは、医者の手助けをして、ウォリーが回復する
あいだ、滞在費のために働かなくてはならなかった。夜、オレは医者の
本を読んだ。ほとんどは、心理学や精神医学に関する本だった。医者は
そうした英語やスペイン語の本をたくさん持っていた。
オレに多少そうした知識があるのは、そこが学ぶ最初のスタートにな
ったからだ。占い師の仕事で実際上のことを見聞きする以外に、それ以
来、多くの本を読んだ。ウォリーを精神分析すると、彼にはそれがあっ
た。自殺できない人間がいて、どうであろうと、肉体的にも精神的にも
不可能なのだ。普通によくあるのではないが、ごくまれというわけでも
ない。アンチ自殺症候群。それは、年月がたったから、なくせるとか変
えられるといったものではない」
オレは訊いた。「ストレートだ。からかってない?」
「いささかも!」
アムは、ラバーボールをもういくつか、ぺちゃんこにした。
アムは言った。「中に入ったら、ドアの内側にもたれて、なにも言う
な!」
「どこの中?」
「カウフマンの室。やつは結婚してない。オークの少し北、ラサラ通り
のアパートに住んでいる。歩いて家に帰る。オレは一度行って、アパー
トのレイアウトを調べた。オレたちは、かなり長い間、やつをからかっ
た。事態が深刻になるまえに、今夜、やつを解放してやろう」
「オーケー」と、オレ。「いつ始める?」
「やつは月曜の夜は、かなり早く店を閉める。1時を過ぎたら、いつで
も。オレたちは、すぐに出なければ。真夜中過ぎの今」
◇
オレたちはお代わりを飲んでから、店を出た。ワッカー街まで行って、
おやじのスーツケースをそこに置いた。それから、クラーク通りを北へ
オークまで行き、ラサラ通りへ出た。
アムは、ラサラ通りの西側、角の北に、奥まったアパートを見つけた。
オレたちはそこに立ち、待った。1時間近く待っていた。通り過ぎたの
は、2・3人だった。
カウフマンが通り過ぎた。彼はアパートの方を見なかった。
オレたちは完全に通り過ぎるまで待ってから、歩き出し、彼と並んで
歩いた。ひとりづつ、両側に。
カウフマンは、壁にぶつかるようにさえぎって立ち止まった。しかし、
オレたちは、彼の腕をそれそれつかんで、また、歩かせた。オレはやつ
の顔を一度見たが、2度と見なかった。見るに耐えない顔だった。死に
たくないのに、死を覚悟した顔だった。下の歩道と同じ色だった。
やつは言った。「聞いてくれ!あんたたちは、オレを━━━」
「室で話そう」と、アム。
オレたちはアパートの前まで来た。
アムは、カウフマンの腕を離し、先にアパートに入った。
廊下がどこにつながっているのか分かってるかのように、自信を持っ
て歩いた。オレは、アムが以前ここへ来たと言ったことを思い出した。
オレは、カウフマンに続いて、3番目で歩いた。廊下はホールにつな
がっていた。やつは少し遅れた。オレは人差し指の先で、やつの背中に
軽く触れると、やつは跳び上がった。やつは、階段を上がりながら、ア
ムにすがりつきそうになった。
3階で、アムは彼のポケットから鍵を取り出し、室のドアをあけた。
室に入ると、電気をつけた。
オレたちは彼に続き、オレはドアを閉めると、そこにもたれた。
ここでのオレの役目は終わった。ドアにもたれ続けることを除いて。
カウフマンは言った。「聞いてくれ!オレは━━━」
「静かに!」と、アム。カウフマンに。「座れ!」アムが食い物屋の店
主を軽く押すと、彼はベッドの端に座った。
アムは、カウフマンにぜんぜん注意を払ってなかった。窓際のドレッ
サーまで行って、カーテンを窓の端まで下ろした。
ドレッサーの上の目覚まし時計を持ち上げた。大きな音でチックタッ
ク言って、2時9分前を指していた。自分の腕時計を見て、2時15分
前に合わせた。ぜんまいのねじを数回巻いて、アラームボタンのアラー
ム時刻を調整した。2時にセットし、アラームが鳴るようにボタンを引
っ張った。
「いい時計だ」と、アム。「2時に鳴ったとしても、近隣に迷惑になら
ないことを祈る。列車に乗らなければならない」
アムは、ドレッサーの一番上の左の引き出しをあけて手を入れた。手
を出すと、ニッケルめっきされた小さな32口径リボルバーをつかんで
いた。
アムは言った。「この銃を少しの間、借りてもいいかな、ジョージ?」
室を横切って、オレを見た。「危ないものは、銃なんかは、持ってなか
ったし、これからも持たないことにしている。そういうものがあると、
トラブルを招くのも早くなる」
「その通り!」と、オレ。
アムはシリンダーをまわし、銃を折り、また、ピシャと元に戻した。
「枕を投げてくれ!」
オレはベッドから枕をつかんで、アムに投げた。
アムは右手で銃をかかえて、左手の枕で包んだ。
ドレッサーを背中にして寄りかかった。
目覚まし時計が、チックタック言った。
カウフマンは、汗をかいた。額から、大きな玉の汗が落ちた。彼は言
った。「もう、やめてくれ!」
「なにを?」と、アム。オレを見て、ニヤリとした。「こいつがなにを
言ってるのか、分かるか?」
オレは言った。「たぶん、オレたちに脅されていると思っているので
は?」
アムは驚いたように見せた。「なぜ、そんなことをする?オレたちは、
ジョージが好きなのに」
目覚まし時計が、また、チックタック言った。
カウフマンは、ポケットからハンカチを出して、額をぬぐった。
彼は言った。「分かった!その目覚まし時計を止めてくれ!なにが知
りたいんだ?」
オレは、アムの体から緊張が逃げてゆくのが見えた。それが出てゆく
まで、そこにあったことに気づかなかった。アムは言った。「こっちが
知りたいものがなにか、分かってるはずだ、友よ。それを自分流にしゃ
べってくれればいい」
「ハリーレーノルズという名から思うことは?」
アムは言った。「話を続けて!話すだけでいい」
「ハリーレーノルズは、ギャングだ。ダイナマイトだ。3週間前、やつ
はオレの店に来た。ふたりの男たちといっしょで後ろの方に座っていた。
ウォリーハンターが一杯やりに来ていたときだった。ハンターもふたり
の男たちといっしょだった」
「どんな男たち?」
「普通の男たちで、印刷工だった。太ったのと背が低いやつ。オレの知
らないひとりを、ハンターはジェイと呼んでいた。もうひとりは以前に
もハンターといっしょで、名前はバニー」
アムはオレを見た。オレはうなづいた。ジェイが誰だか、オレは知っ
ていた。
カウフマンは言った。「彼らは一杯だけ飲むと、出て行った。レーノ
ルズといっしょだったひとりは立ち上がると、彼らに続いて出て行った。
まるで、後を追うように。すると、レーノルズがバーカウンターに来て、
3人の真ん中にいたやつの名前を訊いた。オレは、ウォリーハンターだ
と答えた」
アムは訊いた。「やつは名前を知っていた?」
「そう。オレから名前を聞くまで、不確かで、名前を聞いて、確信した
様子だった。やつは、ハンターがどこに住んでるか訊いたが、オレは、
知らないと答えた。それは本当だった。ハンターは定期的に来る、たぶ
ん、週1回のペースで。しかし、どこに住んでるかは知らなかった。
それだけ聞くと、そのあと数杯飲んでから帰っていった。
次の日、彼はまた来た。なにかの用事でハンターに会いたいので、住
所を知りたいと言った。次に来たとき、どこに住んでるか調べておいて
くれと言った。そして電話番号を渡されて、ハンターが来たら電話して、
ハンターがいると伝えてくれと言った。しかし、ハンターにはこのこと
についてはなにも言うなと」
「どんな電話番号?」
カウフマンは言った。「ウェントウォース、スリーエイトフォーツー。
ハンターが来なかったら、そうメッセージを残せと。同様に、ハンター
の住所を聞いて分かったら、電話して、そうメッセージを残せと」
「それは、翌日のことだな?」
カウフマンはうなづいて言った。「たぶん、手下のひとりにハンター
をつけさせて、家を突き止めようとしたが、見失ったようだ。それで、
レーノルズは戻ってきて、オレを通じて突き止めようとした。彼はオレ
がもしも従わなかったらどうなるかを、教えてくれた。つまり、ハンタ
ーが来たのに、オレが知らせなかったらどうなるかを」
アムは言った。「ハンターは、殺された日までに、また来た?」
「いや。そのあと、2週間、来なかった。彼が殺された日まで。その夜
は、オレが検死法廷で話したすべてが起こった。電話したことを除いて。
そう、オレは電話しなけりゃならなかった。もししなかったら、レーノ
ルズに殺されていた」
「レーノルズとは、電話で話した?」
「いや。オレが掛けた電話には、誰も出なかった。2度電話した。1回
目は、ハンターが来て2分たったとき、2回目はそれから10分後。誰
も答えなかった。オレはホッとした。オレはそれ以上巻き込まれたくな
かった。レーノルズの言ったことに従って、自分を守ること以外は。こ
のことに、あんたたちはどんな関わりが?」
アムは言った。「どんな関わりがあろうと気にしないでいい。レーノ
ルズとのトラブルだけは避けてほしい。レーノルズと、その後会って、
なんと言った?」
「それ以来、彼とは会ってない。一度も来店してない。来るはずもなか
った。別の方法でハンターに接触したのだろう。彼か手下のひとりが、
あの夜、店の前で待ち伏せして、ハンターをつけていったのだろう、彼
は、おそらく━━━」
目覚まし時計が鳴り出して、3人とも跳び上がった。アムは後ろ手を
伸ばして、音を止めた。枕をベッドに投げて戻し、32口径をドレッサ
ーの上に置いた。
アムは訊いた。「ハリーレーノルズはどこに住んでる?」
「知らない。オレが知ってることは、電話番号だけ」
「仕事は?」
「でかい仕事のみ。銀行とか給料とか、そんなとこ。弟が刑務所にいる、
銀行強盗で終身刑」
アムは悲しそうに頭を振って、言った。「ジョージ、あんたはそんな
連中と付き合ってはだめだ。レーノルズとあの夜、ウォリーハンターが
来ていた夜にいっしょだった、ほかのふたりは?」
「ひとりはダッチと呼ばれていた。大柄なやつだ。もうひとりは、小柄
のトーピード。名前は知らない。ダッチは、ハンターの後をつけて見失
ったやつだ。見失ったと思うのは、翌日にレーノルズが来店したからだ」
アムは言った。「オレたちにしゃべることは、それですべてか、ジョ
ージ?ほかにあるなら今しゃべっちまった方がいい。しゃべればその分、
気が楽になる。言ってる意味分かるな?」
カウフマンは言った。「意味は分かってる。もっと思い出せば、大丈
夫、きっと伝える。やつを見つけられることを、願ってる。電話番号は
言った。それをどこで知ったかは、やつにしゃべらないでくれ!」
「しゃべらない、ジョージ。だれにもしゃべらない。オレたちはもう行
く。眠るといい」アムはドアの方に歩き始めた。オレはドアノブを回し
た。
アムは一瞬立ち止まって、カウフマンに言った。「いいか、ジョージ。
オレはこの件で警察に協力しているようにふるまってるので、やつらに
なにか伝えなければならないかもしれない。電話番号があれば、やつら
の方がオレよりももっと簡単にレーノルズを見つけられるかもしれない。
しかし、電話番号は秘密にしておいてくれ!もしもバセットがたずねて
来ても、すべてしゃべっていいが、電話番号だけはしゃべるな!ハンタ
ーの住所を調べろと言われただけで、レーノルズがそれを聞きに店に来
るはずだった。しかし、彼は来なかったと」
◇
オレたちは外に出て、階段を降りた。外は澄んだ夜の空気だった。
オレたちは今、名前が分かった、とオレは考えた。オレたちが捜して
いる名前だ。名前と電話番号だ。そして、今度の相手は、ギャングの親
玉だ。カウフマンのような小物じゃない。
そして、オレたちだけで立ち向かわなければならない。アムは、バセ
ットにこの電話番号を教えないだろう。
オーク通りの街灯の下で、アムはオレを見て言った。「怖いか、エド
?」
オレの喉は少しカラカラだった。オレはうなづいた。
アムは言った。「オレもだ。怖くて口がカラカラだ。バセットに協力
してもらう?それとも、オレたちで楽しんでみる?」
オレは言った。「オレたちで楽しんでみよう」
9
夜の冷気が、今は気持ちよかった。アセをかいていた。えりのカラー
を緩めて、ハットも頭の後ろに押しやった。
それはまた反動だったが、前とは違っていた。オレは背が高いように
感じ、食い物屋にいたときのようなイライラ感はなかった。
オレたちはウェルズ通りを南に向かい、なにもしゃべらなかった。し
ゃべる必要はなかった。あのようなことの後では、アムはオレのパート
ナーだし、オレはアムのパートナーという気がした。
そして、「オレたちは、ハンター家だ!」というフレーズを思い出し
た。オレは考えた。これからそうするのだ。警察ができないことでも、
オレたちならできる。前はそれほど信じてはいなかったが、今は信じて
いた。今それが分かった。
そう、オレは怖かった。しかし、いい意味での怖さだった。まるで、
幽霊小説の怖さを棘のように感じて、やがてそれを自分の棘として快く
感じてしまうように。
オレたちはシカゴアベニューを東に渡って、ドアに2本の青の光のあ
る警察署の前を通り過ぎた。前に歩いた階段を見上げた。さっきまでの
快さは消えた。おふくろとガーディは、あそこできつい尋問を受けてい
るだろう、あるいは、ダウンタウンの殺人課オフィスにいるのだろうか?
おふくろがやったことではなかった。バセットには分かってないのだ。
クラーク通りの角を曲がった。アムは訊いた。「コーヒーはどうだ、
エド?」
「いいね」と、オレ。「しかし、あの電話番号に今夜掛ける?あとにす
る?」
「今から掛ける、早い方がいい」と、アム。「数分したら」
スペリオルの北にある店で、チリを一皿に、それぞれにコーヒーを注
文した。カウンターの端に座った。逆側の端に大声をあげてるふたりの
女がいた。カーリーという人物について言い合いをしていた。
チリはうまそうだったが、おいしく感じなかった。オレはおふくろの
ことを考えていた。警察は女をゴムホースで殴るようなことはしないだ
ろうが。
アムは言った。「なにを考えてる、エド?」
「なにって?」
「なにか、よくないこと?」アムはあたりを見渡して、カウンターの上
に置いた女のハンドバッグに目をとめた。「ハンドバッグのことを考え
ろ!ずっと、そのことを!」
「なぜ?」と、オレ。「なぜそんなことを?」
「自分が皮細工職人だと思え!そうすれば、興味が沸いてくる。ハンド
バッグは何の役に立つ?ポケットの代わりだ。男にはポケットがあるが、
女にはない。なぜか?それは、ポケットが、物を入れれば、女の体形を
損なうからだ。まずいところが膨らんで、あるいは場所はよくても膨ら
みすぎてしまう。彼女はどうだ?」
「そう思う」と、オレ。
「なぜ、ハンカチを?女はハンカチを時々ポケットに、たいていは、小
さいものを持ち歩く。男は大きいものを。それは、女が男より鼻水が出
ないからではない。大きなハンカチは膨らむからだ。女が大きなハンカ
チを持ち歩いたとしたら━━━しかし、ハンドバッグに戻そう!」
「そう」と、オレ。「ハンドバッグの方がいい」
「ハンドバッグは、ものがたくさん入った方がいい。また、小さく見え
た方がいい。さて、大きいけど見た目が小さいハンドバッグを、どうデ
ザインする?女に『あら、見た目よりたくさん入るわ!』と言わせるよ
うな?」
「分からない。どうやって?」
「アプローチは経験的に行うしかない。見た目の異なる多くのバッグを
製作して、誰かがそのひとつを、思ったよりたくさん入ると言ってくれ
るのを待つ。それから、なぜそれが見た目よりたくさん入るのかを調べ
る。同じことを、別のバッグにも行う。すると、最終的にひとつの方程
式にたどり着く。代数って知ってるか、エド?」
「あまり身近に感じたことはない」と、オレ。「ハンドバッグのことを
考えると、財布のことが思い浮かぶ。ボビーレインハートが言っていた、
ガーディにもらったって、本当かな?」
「本当さ。もしもウソだったら、すぐにバレてしまうようなウソはつか
ないだろう。どこかで拾ったとか言うだろう。しかし、それは気にしな
いでいい」
「けど、気になる」
「なぜ?ガーディが殺して、財布を盗み、ボビーに渡したとでも?ある
いは、マッジが殺して、財布をその辺に落とすか、ガーディにあげたと
でも?」
オレは言った。「誰もそんなことしてないことは分かる。しかし、状
況は悪い。ガーディは、財布をどうやって手に入れた?」
「財布を持ってかなかったのさ。それだけのこと。多くの男は、飲み会
に行くとき財布を家に置いてゆく。ポケットに数枚の硬貨だけ持って、
財布は安全な家に置いてゆく。ガーディはそれを見つけて、中のカネを
もらって黙っていた。財布を人にあげてしまったのはよくなかった。も
っと悪いことになると分かっていたら、焼却炉に捨てただろう」
「ガーディはとにかく」と、オレ。「まずいことをしてくれた。かなり
まずい」
アムは言った。「そうでもないよ、エド。彼女は前々からしたかった
ことをしただけ。多くの者もしただろう。全部ではないが、多くの者は」
「おやじはしなかった」と、オレ。
「そうだな」と、アム。「ウォリーはしなかった」言葉を選ぶように、
ゆっくりと。「しかし違いはある。ガーディは利己的で、そのため自分
の人生を失敗させたくなかった。ウォリーは、自分の人生を失敗させた。
ガーディはもしも間違った男と結婚したら、すぐに別れるだけだ。
ウォリーは、たとえ失敗しても、志を貫く男だった。また、決して結
婚してはならない男だった。しかし、エドの母親は本当の女で、エドと
彼は幸せだった。しかし、彼女が死んでしまってから、ウォリーの暮ら
しはすさんでしまった。これは、エドにも分かるだろう。そこで、マッ
ジはうまく反動で彼をつかまえた」
オレは言った。「おふくろは━━━いや、ここはスキップしてくれ!」
気づいたのは、オレが、義理からのみ、おふくろを助けようとしている
ということだった。おふくろとおやじの関係を振り返れば、いろいろな
ことがあった。アムが正しかった。オレは気持ちが折れかかっていた。
それは、おふくろが今困難に直面していて、おふくろが変わったからだ。
おやじが死んでから、大きく変わった。しかし、それが長続きすると甘
く見てはいけないと思った。
おふくろはオレにとっての毒だった。おやじと同じくらいまともな男
たちにも、毒だった。だから、おやじは酒を飲むようになってしまった。
酒を飲むにしても、おやじは静かに酒を飲み、トラブルを起こすような
ことはなかった。
オレはチリを食べ終わり、皿を脇にどけた。
アムは言った。「まだだ、エド。コーヒーのお代わりがある」アムは
お代わりを注文して、言った。「その電話番号に掛けたら、なんて言お
うか考えている。なにか別のことをしゃべったらいいと思う。どんなこ
とがいい?」
「女のハンドバッグは?」と、オレ。
アムは笑った。「退屈な話題だったろ?それは、エドがよく知らない
話題だからだ。よく知ってれば、興味も増す。オレは前に皮細工職人を
知っていた。やつはハンドバッグについて、一晩中しゃべれた。カーニ
バルが好きなら、カーニバルについてよくしゃべれる」
「続けて!」と、オレ。「ハンドバッグよりカーニバルについて聞きた
い。ブローってなに?」
「ブローオフの略。追加料金を取るショー、ふつうは、フリークショー
でやる。つまり、フリークショーに25セント払ったとする。呼子は、
舞台裏に連れて来て、あと25セントで追加のショー、もっと払えば追
加のスペシャルショーを見せると言う。テントの端で。なぜ?」
オレは言った。「カーニバルで、アムがホーギーにボールゲームをや
ってくれるよう頼んでいたのを思いだしたんだ。ホーギーはスローを食
らって、ジャックがスプリングフィールドのあとブローする気なら、あ
いつにやらせりゃいい。それって、なんの話?」
アムは笑った。「記憶力がいいね」
「ああ」と、オレ。「今夜の話からも覚えている。ウェントウォース、
スリーエイトフォーツー。いつ電話する?」
「あと数分したら。ホーギーに戻ろう。ホーギーは、色ものの呼子で、
フリークショートップの追加のショーは、男客限定の、生身のモデルの
セックス講義で、それぞれ25セント、もし不満があればお代は返す」
「生身のモデルとは?」と、オレ。
「それが、冷やかし客の気を引くものだ。知りたがってくる。そこが、
あいつのうまいところで、若者の心得を読めばすぐ分かることを、水着
のふたりの女を生身のモデルとして使う。どんなタイプか話すときに使
うだけ」
「ひやかし客たちは、カネを返してほしがる?」
「まれに、すごくまれだ。返したとしてどうなる?いい夜に、まだ10
0ドル儲かってれば、ナッツ以上だ」
「ナッツって?」
「費用のこと。たとえば、使用権として一日30ドルかかったとする。
そのナッツをかけて、それ以上儲かれば、利益。つまり、ナッツの元手
をとった」
オレはコーヒーの残りを飲んで、訊いた。「銀行強盗がなぜおやじを
捜していたのかな?」
「知らない。それを見つけなけりゃならない」アムはため息をついて立
ち上がった。「行こう!始めよう!」
◇
クラーク通りをワッカー街へ下って、アムの室へ行った。
アムは、座る前に壁際にあったイスを動かして、言った。「エド、後
ろに立って、耳を受話器に当てろ!オレは受話器を少しだけ耳から離し
て持つので、エドもよく聞こえるはずだ。エドの記憶力を、会話に傾け
ろ!」
「オーケー!」と、オレ。「どんなアングルで?」
「さぁ、知らない。アドリブでゆく。なにをしゃべるかは、相手次第だ」
「相手がハローと言ったら?」と、オレ。
アムはくすくす笑った。「そこまで考えてない。待ってから判断する」
アムは受話器を持ち上げ、オペレータに番号を告げた。声が違ってい
た。ゆっくりと、がさつで、完全に違うイントネーションだった。前に
どこかで聞いていた。しばらく考えて、分かった。ホーギーの声をマネ
していたのだ。ホーギーの話をしていたから、マネしようと最初に思い
ついた声がホーギーだったのだ。完璧だった。
呼び出し音が聞こえた。オレはもっと近くに寄り掛かり、体重をイス
の背に乗せて、耳を受話器の端にできるだけ近づけた。
呼び出し音が3回鳴ったあとで、女の声で言った。「ハロー?」
ひと言から、どれだけのことが分かるのか━━━推測できるのかとい
うのは、おもしろい。ひと言だけで、彼女が若く、きれいで、スマート
なことが分かる。「スマート」のあらゆる意味において。彼女がそのひ
と言を放つ仕草だけで、好きになってしまうのだ。
アムは言った。「だれ?」
「クレア。ウェントウォース、スリーエイトフォーツー」
「どうしてる、ベイビー?」と、アム。「覚えてる?サミーだよ」酔っ
たふうに。
「残念ながら、ノー」と、声。かなり冷たい感じで。「サミーなに?」
「ジーワン、覚えてるはず!」と、アム。「サミー。この前の夜、バー
で会った。クレア、聞いて!電話には深夜すぎることは分かってる。で
も、ハニー、ビリヤードで大儲けしたとこ。みんなから2千ドル勝った。
そいつを一気に使おうということ。町じゅうを買占めだ!シェパレーや
メドッククラブやいろいろ。シカゴで一番の美人といっしょに。大当た
りだ。ウサギがよければ、ウサギの毛皮のコートを買ってやる。これか
ら、オレがタクシーで迎えにゆくから━━━」
「ノー」と、声。電話が切れた。
「チェッ!」と、アム。
「ナイストライ!」と、オレ。
アムは受話器を電話に戻して、言った。「ナイストライでもこれ以上
の結果は望めない。それは、オレがロメオのようにホットになれないか
ら。エドがやるべき」
「オレ?とんでもない!女のことなんか、なにも知らない!」
「そこさ!エドなら、望む女を誰でもものにできる。鏡を見てみろ!」
オレは笑った。しかしドレッサーの鏡に振り返った。
オレは言った。「目の周りが青アザになりそうだ。ボビーレインハー
トめ!」
アムは鏡の中のオレに向かって、ニヤリとして言った。「青アザも魅
力的だ。そのままにしておけ!生肉なんかで冷やすな!さて、ムダかも
しれんが、もう一度トライしてみよう!」
アムはある番号にダイヤルして、ウェントウォースの交換手に、スリ
ーエイトフォーツーが登録されているか訊いた。少し待ってから、「ど
うも」と言って、がっかりしたように電話を切った。
「登録されてない番号だ」と、アム。「そうではないかとは思った」
「これから、なにを?」
アムはため息をついた。「別の方向から攻めよう。ハリーレーノルズ
の名前から調べよう。バセットはなにか知ってるかもしれないし、資料
室から調べられるかもしれない。この電話番号で、バセットを出し抜け
ると思っていたのだが。あした、あと2つくらい、どんちゃん騒ぎをや
ってみよう。電話クイズ番組で、アトランダムに番号に電話して、もし
もイリノイ州の州都を当てられたら、100ドル送るというのはどうだ?
あるいは━━━」
「聞いて!」と、オレ。「電話番号リストなら手に入れられる」
「え?どうやって、エド?登録されてない番号は、入手が難しい」
「バニーウィルソンの義理の妹━━━バニーの弟の妻が、電話局で働い
ていて、そういう番号を扱っている。前に一度、主任のジェイクのため
に未登録番号を見つけた。彼の義理の妹が、そのためにトラブルになら
ないようにすれば、オレたちにも見つけてくれる」
「エド、それは朗報だ。すぐにでもやれるのか?」
「バニーに今夜でも会えれば」と、オレ。「明日の昼にでも分かると思
う。バニーが義理の妹に出勤前に会えれば、昼休みに出たときにバニー
に電話できる。仕事場からはそんな電話はできない」
「バニーは電話がある?」
「大家の電話がある。昼間だけ使える。けど、今からそこへ行かなけれ
ばならない。バニーは、ハルステッド通りに住んでる」
「バニーは、もう家に帰っている?」
「帰ってる頃だ。もしもまだなら、待ってる」
「オーケー、エド。しばらくの間、分かれよう。ここに10ドルある。
これをバニーに渡して、義理の妹にあげて新しい帽子でもなんでも買っ
てもらう。オレはバセットを捜し出して、尋問でなにが分かったか訊く。
オレたちがカウフマンに口を割らせたと知ったら、バセットはやりやす
くなるだろう。少なくとも、今までは間違った推理をしていたと気づく
だろう」
「オレたちは、どこで会う?」
「ここに戻って来い。オレがいないときにエドが来たら、オレの鍵を渡
してくれるよう、管理人に頼んでおく。では、すぐに行け。オレは、バ
セットを捜しに出る前に、電話で捜してみる」
◇
オレは、グランドアベニューまで下ると、パトカーが来るのが見えて
ラッキーだった。それで、ハルステッドまで数分で行けて、バニーのア
パートまで歩いて行けた。
室の電気は消えていた。それは、外出してるか眠っているか、どちら
かを意味する。オレは階段を上がった。これは、バニーを起こすに十分
な重要な用だった。
彼は外出していた。それが確認できるまで、ノックした。
オレは階段に座って、待った。そのとき、バニーがよく鍵を掛け忘れ
て出かけることがあることを思い出した。確かめてみると、やはり鍵は
掛かってなかった。それで、中に入って、雑誌を見つけて読んだ。
4時の時報が鳴って、キッチンで、コーヒーをいれた。かなり強くし
た。
コーヒーができたときに、バニーが階段でつまづきながら帰ってきた。
すごく酔っていたわけでなく、酔いかけのところだった。しかしオレは、
やって欲しいことを話す前に、2杯のコーヒーをいれた。全部の話はし
なかったが、電話番号の登録リストがなぜ必要なのかが分かる程度には
話した。
バニーは言った。「分かった、エド。10ドルのことも。彼女は少し
は好感を持ってくれる」
オレはそれをバニーのポケットに入れて、彼女にとにかく渡してと言
った。
「彼女が今朝仕事に行く前に話してもらえるかな?」と、オレは訊いた。
「ああ、簡単さ。彼女は家が遠いので、5時半に起きる。オレは電話す
るまで起きていて、そのあと11時に目覚ましを掛けておけば、彼女が
電話してくる頃には起きていられる。エドは正午過ぎならいつでもオレ
に電話してくれればいい。エドが電話してくるまで、オレは起きている」
「助かる、バニー、サンクス!」
「いいって!エドはこれから家に?」
「ワッカー街に戻る」
「途中までいっしょに歩こう」バニーは時計を見た。「それから時間ま
でにここに戻れる。時間になったら、角の終夜営業のドラッグストアで
電話すればいい」
オレたちは、橋を渡って、グランドアベニューまで歩いた。
バニーは言った。「エドは最近変わったな。なにがあったんだい?別
人になった」
「さぁ、分からない」と、オレ。「たぶん、新しいスーツのせい」
「いや、違う。大人になったか、なにかだ。なんにしても、いいね。エ
ドが望んだことなら、いい方向に向かっている。オレのように、わだち
にはまるな!」
「あんたは、わだちにはまってない」と、オレ。「あんたはそのうち、
自分の店を開くと思う」
「どうかな、エド。設備代だけでたいへんだ。貯金も少ないし。しかし、
いつかはやりたいと思う。だが、しらふでいられるなら、貯金ももっと
できるだろうが、それができないんだ。もうオレは40だ。必要な資金
の半分も貯金できてない。がんばっても、店を出す前に年寄りになっち
まう」
バニーは苦々しそうに少し笑った。「オレはときどき、大きなギャン
ブルゲームをやってみたいと思うようになった。エドも聞いたことがあ
るだろう、賭け金は制限なしの、オレのわずかな預金全部をブラックジ
ャックに賭けて、勝つか負けるか1発勝負。それで、オレは十分な資金
を得るか、なにもなくなるか。すべてなくなっても、半分のままでいる
よりましな気がする。もっといいかも」
「もっといいって、どんなふうに?」
「そうなれば、心配するのをやめられる。いつもオレはウィスキー1杯
に25セント使ったり、ビール1杯に10セント使ったりしている。そ
のことで心を痛める必要はなくなる。地獄へ行くことを心配してないが、
飲み代はケチってるんだ」
しばらくは黙って歩いていた。それから、バニーが言った。「これは
オレの間違いだった。実際、何もできてない。どんなやつでも、自分の
望むもの、それに近いものを得ることができる。それをすごく欲しがっ
て、そのために他のことをがまんすれば。しかしオレは、ひとりで暮ら
しながら、自分の収入から週30ドルは貯金できたはずだった。1年前
に十分な資金を作れたはずだった。しかしオレは生活も楽しみたかった。
そうしたのだから、なにをぎゃあぎゃあ言う必要がある?」
オレたちは高架鉄道の下まで来た。バニーは言った。「よし、ここか
らオレは戻る」
立ち止まって、オレは言った。「うちのアパートにも遊びに来てくれ!
昼間とか次のオフの夜にでも。おふくろは、あまり友人がいないから、
バニーに会えたら喜ぶ」
「そうするよ、エド。サンクス。ところでいっしょに一杯どうだい?通
りの向こうで」
オレは少し考えてから、言った。「いいとも、バニー」
本当は飲みたくなかったが、なにか表に出せない理由で、バニーがい
っしょに飲みたがっていると感じた。彼の言い方にもなにかあった。
◇
オレたちは一杯だけやって、そして食べ物屋の前で別れた。オレは高
架鉄道の下を抜けて、クラーク通りへ歩いた。
あふくろとガーディのことが心配だった。家に帰ってるかどうか。そ
れで、路地を家のアパートの方へ抜けて歩いた。キッチンの窓の見える
路地に来ると、キッチンの明かりが見えた。
その明かりが警察がまだ捜索している明かりなのか、おふくろが戻っ
た明かりなのか分からなかったので、立ってしばらく見ていた。すると、
おふくろが窓を横切った。おふくろはまだ、ドレスを着ていたので、帰
って間もないことが分かった、ガーディも見えた。おふくろはガスレン
ジを行ったり来たりしていたので、帰ったばかりで、寝る前になにか食
べるものを作っているのだろうと思った。
オレは階段を上がりたくなかった。バセットが、オレはアムのところ
に泊まると言ってあって、オレのことは心配してないだろう。もしもオ
レがまだうろうろしていると知ったら、もっと心配するだろう。
オレは、路地を抜けて、クラーク通りを過ぎて歩いた。空は、夜明け
の明るさが始まっていた。
◇
ワッカー街で、アパートの管理人に鍵を預かってるか訊いた。預かっ
てなかったので、アムは帰っていることが分かった。
バセットがいっしょだった。ふたりはそれぞれテーブルの両端に座っ
て、大きな身振りでカードゲームをしていた。ふたりの間に酒のボトル
があって、バセットは虚ろな目をしていた。
アムは言った。「エド、おなかいっぱい食ったかい?」
バセットにはオレがどこか言ってないことを、アムはこっそりオレに
伝えていたのだ。それで、電話番号のことはまだ秘密だと分かった。
オレは言った。「朝食3回分食べた。これで、1日じゅう過ごせる」
「ジンラミーさ!」と、アム。「1ポイントに1ペニー。静かに!」
オレはベッドの端に座って、ゲームを眺めた。アムは勝っていて、3
0ポイント、リードしていた。スコアの書かれた紙を見て、これが3回
目のゲームだと分かった。アムは、最初の2ゲームを取っていた。
しかし、バセットはこの回は勝った。彼はボトルから長い一口を飲む
と、アムが次の手を考えている間、オレの方に顔を向けた。彼は目をふ
くろうのように広げて、言った。「エド、あんたの妹は、誰かがアドバ
イスを━━━」
「フランク、あんたの番だ」と、アム。「次で最後だ。オレはエドに用
事がある」
バセットはカードを手にした。1枚落としたので、オレは拾ってあげ
た。なんとかカードを切り、ボトルから一口飲んだ。1クォートビンで、
ほとんどカラだった。
バセットはこの回も勝った。しかしアムは次の回ではジンを作って、
結局100ポイント勝った。
バセットは言った。「もう十分だ。終わりにしよう。疲れた」財布を
出した。
アムは言った。「しまってくれ!3ゲームで10ドルくらいだが、必
要経費に入れてくれ。フランク、これからなにか食いにゆく。少し休ん
だらどうだ?エドを家まで送ってくるから、戻ってあんたが寝てたら、
起こしてあげる」
バセットの目はほとんど閉じかかって、半分閉じた。ウィスキーをが
ぶ飲みしたのが効いて、かなり酔っていた。ベッドの端に座って、揺れ
ていた。
アムはテーブルを元の場所に戻して、バセットを見て、ニヤリとした。
左の肩を少し押すと、バセットは後ろに横になって、枕の上に頭を乗せ
た。
アムはバセットの足をかかえて、ベッドの上に乗せた。バセットの靴
ヒモをゆるめて脱がせた。シェルぶちメガネとハットも取って、ドレッ
サーの上に乗せた。ネクタイをゆるめて、えりのボタンをはずした。
バセットは目をあけて、言った。「ソノファビッチ!」
「ああ」と、アム。なだめるように。「ああ、フランク」
オレたちは、室の電気を消して、外へ出た。
◇
エレベータを降りると、バニーと電話番号のことを話した。登録リス
トを正午過ぎならもらえると。
アムはうなづいて言った。「バセットは、オレたちがなにか隠してい
ることに気づいている。頭がいいやつだ。自分でカウフマンに会いに行
って、締め上げないとも限らない」
オレは言った。「あんたはカウフマンをかなり怖がらせてる。少しく
らい締め上げられても口を割らないだろう。やつはハリーレーノルズよ
りも、今のオレたちを怖がっている」オレは少し考えてから、訊いた。
「もしも目覚まし時計が、やつが吐く前に鳴り出したら、どうしてた?」
アムは肩をすくめた。「仮定の話はバカげてる。それより、現実の朝
食は?」
「ウシ1頭でも食える!」と、オレ。
オレたちは、クラーク通りとシカゴアベニューの角のトンプソンの店
へ行った。テラス席でハムエッグを食べながら、バセットから聞いたこ
とを話してくれた。
ガーディは、財布をレインハートへ渡したことを認めた。彼女の説明
は、アムが推測したものと同じだった。おやじは別の古い財布を持って
いた。そのことは知っていた。オレが知らずにガーディが知っていたこ
とは、最近飲みに行くときは、新しい財布とカネは家に置いていたこと
だった。本棚のある段の後ろに落として、カネの一部だけ古い財布に入
れて出かけていた。
オレは言った。「それは、前にホールドアップにあった時からだと思
う。その時、社会保障カードや組合証やらすべてに、新しい財布も取ら
れた。おやじはたぶん、今度ホールドアップやスリにあっても、カネ以
外に失うものはないと考えたのだと思う。クラーク通りを酔って歩いて
いたら簡単にありうる」
「ああ」と、アム。「ガーディは一度財布を隠すのを見て、知っていた。
実際に、本棚に20ドル入った財布があった。もらっておいても、誰も
損しないと考えたのだろう」
オレは言った。「まさに、見つけたもの勝ち。そのことは別に気にな
らない。彼女がやりそうなことだ。しかしなんだって、財布を持ち歩い
て、イヤなやつにあげたりしたのだろう?ここはやめよう。レインハー
トが財布を持っていたのを見つけたのがすごい偶然だった。バセットは
彼女を信じた?」
「本棚を調べたあとで。本の後ろのほこりが、彼女の言った、財布があ
ったところだけ跡があった」
「おふくろは?」
「バセットはマッジが犯人でないことはかなり確信しているようだ。オ
レからレーノルズの線を聞く前から。また、警察はアパートを徹底的に
調べた。しかし、保険証書や興味あるものはなにも見つからなかった」
「バセットはレーノルズのことをなにか知っている?」
「バセットは彼のことを知っていた。そのようなやつがいて、カウフマ
ンが話したことはすべて、バセットが知っていることと一致する。バセ
ットは3人の関心度にランクを付けていて、ハリーレーノルズ、ダッチ、
トーピードの順、そのうち彼らに注目して、名前と経歴を調べるだろう。
彼は、3人がウィスコン州での銀行強盗で指名手配されていると考えて
いる。最近のだ。とにかく、マッジを尋問するより、この線にずっと興
味を持った」
「今夜はわざと、バセットを酔わせようとした?」
「男は馬と同じ。男をウィスキーのところまで連れてくることはできる
が、酔わせることはできない。一度でも、オレがウイスキーをついでい
るのを見たか?」
「見てない」オレは認めた。「ビンをつかんでるとこも見てない」
「エドは、ぞっとする猜疑心を持った」と、アム。「しかし同時に、オ
レたちは朝まで自由だ。彼は正午まで寝ている。オレたちは、彼を差し
置いて、保険会社に向かう」
「レーノルズの線があるのに、なぜ、保険会社?」
「いいか、オレたちは、レーノルズがなぜエドのおやじに興味があった
のか、まだ分かってない。なぜウォリーが高額の保険に入って、そのこ
とをバッグに入れて秘密にしていたのか、その裏ストーリーが分かった
ら、前進になる。思いつきが必要だ。レーノルズの線が出てくる前から
抱いていたあるアイデアがある。電話番号のリストを入手するまでは、
1手も進められない。つまり、眠ることから失うものは何もない」
「眠りが必要だ」と、オレ。
「オーケー!エドは若い。若さで生きている。オレはもっとセンスがい
るが、ないようだ。もっとコーヒーを飲まないか?」
トンプソンの店員を見て、オレは言った。「ダウンタウンのオフィス
が始まるまで、あと1時間ある。オレはコーヒーを飲んで、アムはもっ
と、おやじといっしょだった頃の話ができる」
時間は、あっという間に過ぎた。
10
セントラル相互保険会社は、セントルイスに本店を置く保険会社の広
くもない支店だった。期待されるのは、オフィスが小さければ小さいほ
ど、おやじのことを覚えている可能性が高いということだった。
オレたちは支配人を訪ね、彼のオフィスに通された。アムが話して、
オレたちが何者か説明した。
支配人は言った。「彼のことは思い出せないが、記録をたどることは
できる。保険証書が見つかってないそうだが、問題ない。こちらの記録
にあれば、支払える」反対を唱えるように、少し笑った。「うちはラケ
ットではない。保険証書は、そのコピーが無くなっていようと、契約が
あって続いているということを示す、ただのレシートに過ぎない」
アムは言った。「分かった。オレたちが知りたいのは、保険が契約さ
れたときの状況を覚えているかどうか、ということ。たとえば、保険の
ことをなぜ家族に秘密にしようとしたのか。保険を契約した外交員に理
由を、なにか理由を言ったはずだ」
支配人は言った。「少しお待ちを」彼は出て行って、事務室へ行き、
数分後に戻ってきて、言った。「主任がファイルを捜している。彼は捜
したあと、自分で持ってくる。おそらく契約時のことを思い出せる」
アムは訊いた。「保険を秘密にするのは、めったにないこと?」
「初めてではないが、かなり珍しい。ある男性は被害妄想があって、保
険のことが知られると、親類から殺されると思い込んでいた。しかし、
逆に、親類を愛していて、死後みんなに残したかった。ただこのケース
が、今回当てはまるかどうかは分からない」
「もちろん」と、アム。
背の高い銀髪の男が、手にファイルを持ってオフィスに入ってきて、
言った。「ブラッドリー支配人、これが、ウォレスハンターのファイル。
彼のことは覚えている。支払いはいつもオフィスでしていた。このファ
イルにはクリップで注意書きが留められていて、支払い確認書を郵送し
ないように書かれている」
支配人はファイルを受け取って、訊いた。「いつも彼と話していたの
かね、ヘンリー?支払い確認書を郵送しない理由を尋ねた?」
ヘンリーは首を振った。「いいえ、支配人」
「分かった、ヘンリー」
ヘンリーは出て行った。
支配人はページをめくって、言った。「そう、支払いは済んでいる。
2つのローンが組まれて、保険料の支払いに当てられた。その分は保険
証書の額面から差し引かれるが、たいした金額でない」別の2つのペー
ジも開いた。「この保険証書は、この支店で販売されたものでない。イ
ンディアナのゲーリーから移管されてきた」
「そこでの記録はある?」
「ない。セントルイスの本店にあるこのファイルのコピーを除いて、他
に記録はない。ハンター氏がシカゴに引越した時に、ゲーリーからここ
へ送られた。日付から分かることは、移管されたのは、保険が契約され
てから、わずか数週間後だということ」
アムは訊いた。「保険証書には、ファイルにない詳細がある?」
「ない。保険証書は、標準終身保険フォームで、名前と金額、作成され
た日付が書かれている。その内側には、保険申込書のフォトコピーが貼
り付けてある。フォトコピーのオリジナルは、このファイルにある。ご
希望があれば、お見せできる」
アムは、ペンとインクで書かれた申込書のページを開いてファイルを
渡された。オレは歩いて行って、アムのイスの後ろから肩越しに読んだ。
申込書の日付と、保険を販売した外交員の名前を、心に留めた━━━ポ
ールB・アンダーズ。
アムは訊いた。「外交員のアンダーズ氏が、まだゲーリー支店で働い
ているかどうか分かる?」
「いや、分からない。手紙で問い合わせれば分かる」
アムは言った。「お構いなく。死亡証明書のコピーは?」
「必要。受取人に小切手を郵送する前に。この若い方のお母さんで?」
「義理の母」と、アム。ファイルを返しながら、立ち上がった。「いろ
いろどうも。ついでに、保険の支払いは、3ヶ月ごと?」
支配人はファイルのページをめくった。
「そう、1回目の支払いのあとは3ヶ月ごと。申し込み書を出す際に、
1年分の保険料を前もって支払った」
アムはまた礼を述べて、オレたちは外へ出た。
◇
「ゲーリーへ?」と、オレ。
「ああ、あの高架鉄道で行ける?」
「1時間かからないと思う」オレは少し考えた。「ループから1時間か
からないのに、引越ししてから1度もゲーリーへ行ってない」
「ウォリーかマッジは、戻ったことは?訪問でもなんでも?」
オレは考えてから、頭を振った。「記憶にはない。誰かがあそこへ戻
ったとは思えない。もちろん、ゲーリーからシカゴに引越したのはまだ
13の時だったが、記憶はしっかりしている」
「話してくれ、いや、待って。列車に乗るまで、待って!」
オレたちがゲーリー行きの急行のシートに座るまで、アムはなにもし
ゃべらなかった。それから、言った。「よし、エド、リラックスして、
ゲーリーについて思い出せることをすべて話して!」
オレは言った。「オレは12番通りの学校に行った。ガーディも。オ
レは8年生で、彼女は4年生、引越した時は。家族は、学校から3ブロ
ックのホルマン通りの小さな木造の家に住んだ。学校には演奏クラブが
あって、オレは入った。楽器を貸してくれて、オレはトロンボーンを借
りた。オレは簡単な曲なら譜面を見て吹けるようになったが、おふくろ
は嫌っていて、『このいやなホーン』と呼んでいた。それで、まき小屋
で練習しなきゃならなかった。シカゴではアパートに住んでるので、お
ふくろがトロンボーンを好きになってくれても練習ができない、それか
ら」
「トロンボーンの話はもういい」と、アム。「ゲーリーに戻ろう」
オレは言った。「家族は、ある時は車があり、ある時は車がなかった。
おやじは、一度に2つか3つの印刷所で働いた。しばらく、腕の関節炎
で働けない時期があって、借金することになった。あれはまだ全部返し
てないと思う。いつか突然引越すんじゃないかという気がした。なぜな
ら、今も残る借金の一部に追い回されていたから」
「突然引越した?」
「オレにはそう思えた。引越しのことを聞いた覚えはない。トラックが
突然やって来て、家具を積み始めた。おやじはシカゴに仕事を見つけて、
家族はすぐに━━━いや、ちょっと待って」
「時間を使っていい、エド。なにか思い出せるはず。おっと、オレはな
んてまぬけだったんだ!」
「なんのこと?」
アムは笑った。「あまりに近くにい過ぎて、見逃していた!まぁいい。
ゲーリーに戻ろう」
オレは言った。「今、思い出した。なにかが引っかかっていた。引越
しの話をするまで完全に忘れていた。シカゴに引越すことを、シカゴに
着くまで知らなかった。おやじは、ジョリーに引越すと言っていた。ゲ
ーリーからだいたい25マイルでシカゴと同じ。しかし、北西ではなく
西だった。友人たちには、ジョリーに引越すと伝えた。おやじは、シカ
ゴにいい仕事が見つかったので、ジョリーの仕事はやめたと言っていた。
当時のオレでさえ、変な気がした」
アムは目を閉じて、言った。「続けて、エド。思い出せる限り、深く!
なかなかいい」
「シカゴに着いて、引越しは今いるところで正しかったが、おやじはシ
カゴの仕事について、本当のことをなかなか話してくれなかった。とい
うのも、シカゴに来て数週間は、おやじは家でブラブラしていた。全部
というのではないが、ほとんどを。それでオレは、おやじが仕事をして
いないと分かった。それから、エルウッド出版の仕事を見つけた」
「ゲーリーに戻ろう。シカゴはいったん置いておこう」
「いいよ」と、オレ。「なにが知りたい?ガーディがおたふくかぜにな
ったこととか?」
「それはなくても大丈夫だ。いろいろ試してみて、もっと深く」
オレは言った。「あいまいに覚えているのは、法廷の場面かなにか。
なんなのか思い出せない」
「ある債権者たちが家族を訴えたとか?」
「ありうる。思い出せない。ゲーリーにいた最後の1・2週間はおやじ
は働いているようには見えなかった。しかし、クビになったのか、一時
解雇なのか、あるいは別のことなのか覚えてない。そう、それは、おや
じがみんなをサーカスに連れて行ってくれた週だった」
アムはうなづいた。「家族は予約席に座った」
「そう、なんで分かった?」
「今まで話してくれたことから、分からないか?今朝、保険会社でなに
を学んだ?それをジグソーパズルの1ピースにして、そしていろいろ話
してくれたことを別のピースにして、なにが描かれた?」
オレは言った。「オレたちはゲーリーから突然撤退した。どこへ行く
のか誰にも話さずに、突然、引越した。引越し先さえ誤魔化した。それ
は家族が多くの借金を負っていたからではないか?」
「そう、オレはエドに1ドル賭ける。ゲーリーにいたときによく買い物
した店を思い出して!雑貨店は覚えているだろう?今日歩き回って、そ
こで訊いてみよう。引越す前にウォリーは支払いはすべて現金で済ませ
たのかどうか」
「仕事もないのに、どうやって支払いができた?オレたちは、破産寸前
だった。まさか━━━」
「見えてきた、エド?」
「保険証書」と、オレ。「保険の契約をしたのは、そのころのことだ。
しかも、1年分の支払いは、前もって現金で済ませていた。5千ドルの
保険なら、100ドルを越える支払いになる。シカゴへの引越し費用や
新しいアパートの室代の支払いもあった」
「さらに」と、アム。「ゲーリーで数週間、働いていなかった。シカゴ
で働き始めたのも数週間たってからだった。さらにみんなをサーカスへ
連れていった。この件で、ほかに付け加えることは?」
オレは言った。「ガーディとオレは、シカゴの学校生活のために、新
しい服を何着が買ってもらった。アムは1ドルの賭けに買った。おやじ
はなんらかの臨時収入があって、それはゲーリーを出る少なくとも3週
間前のことだった。アムの勝ちだ。それでおやじは、すべてのつけの支
払いを済ませたんだ。額は、う〜ん、少なくとも500ドル、たぶん、
1000ドルにも」
アムは言った。「それは1000ドルだったとしよう。ウォリーはそ
れまでの借金を払った。そんなふうに妙だった。さて、ゲーリーに着い
た。なにが分かるか見てみよう!」
駅の電話帳のところへ行って、最初に見つけたのは、セントラル相互
保険会社のオフィス。アムは電話ブースへ入って電話した。
彼はがっかりして出てきて、言った。「アンダーズはもういなかった。
だいたい3年前にやめた。彼の足取りは、イリノイのスプリングフィー
ルドまでしか知らないそうだ」
オレは言った。「かなり遠いね。150マイルはある。けど、彼は電
話を自分の名前で契約しているだろうから、珍しい名前だから、見つか
るかも」
アムは言った。「これ以上追わない方がいい。彼に関われば関わるほ
ど、関わりが薄くなる。つまり、ウォリーは彼になにもしゃべってない
だろう、臨時収入がどこからとか。支払い確認書を郵送しないようにし
てもらう理由は言ったかもしれないが、本当の理由でないことに、10
ドル賭けてもいい。もっといい人物がいる」
「だれ?」
「エドだよ。もっと考えてほしい。住んでいた場所は、どうやって行く
んだ?覚えてるか?」
オレはうなづいた。「イーストエンド行きの電車。ここから1ブロッ
ク先で乗れる」
オレたちは電車に乗って、見覚えのある角で降りた。そこはほとんど
変わってなかった。同じドラッグストアが角にあった。そこから1・5
ブロックのところに、よくみんなで車から降りて歩いたビルがあった。
ビルはほとんど変わってなかった。
◇
家は、通りを渡ったところだった。思っていたより、小さかった。と
ころどころ痛んでいて、ペンキを塗る必要があった。住んでいた頃から
一度もペンキを塗り替えてなかった。
オレは言った。「フェンスが違う。もっと高かった」
アムは声を出さずに笑って、言った。「もう一度見てみろ!」
もう一度見てみると、古いままだった。違うように見えたのは、前は
フェンスの高さが肩まであったからだ。変化したのはフェンスではなく、
オレだった。
オレたちは、通りを渡った。
フェンスに手を置くと、大きな警察犬が家の方から走ってきた。吠え
てはなかった。本気で跳びかかるつもりらしい。手を戻すと、犬はフェ
ンスを跳び越えるのをやめて、うなった。
オレは言った。「ここでは歓迎されてないようだ」
オレたちが歩き出すと、犬もフェンスの内側を同じペースで歩いた。
家をずっと見ていた。かなり痛んでいて、ポーチは垂れ下がり、木の階
段は曲がり、一段は壊れていた。庭はゴミが散らかっていた。
オレたちは歩き続けた。角のドラッグストアは、前と同じ店名だった。
オレは言った。「入ってみよう!」
店主は、見慣れた顔だったが、変な気がした。彼は背が低かった。も
っと大きい人だと思っていた。それを除けば、よく知っていた。
オレはタバコの場所を訊いて、言った。「ハーゲンドルフさん、覚え
てる?1ブロック先に住んでた」
彼はオレの顔を近くで見て、少しして言った。「ハンター少年?きみ
か?」
「そう」と、オレ。「エドハンターだ」
彼は言った。「見間違えるところだった」手を差し出した。「近くに
引越してきた?」
「いや」と、オレ。「しかし、おじが近くに引越してくる。これがおじ
で、ハーゲンドルフさんに、アムハンター。この近くに住む予定。おじ
を案内して、紹介したかった」
アムは店主の手を握り、言った。「エドがここで買うといいと言って
くれた。できれば、あとでまとめて払いようにできる?」
ハーゲンドルフは言った。「つけ払いはしてないのだが、しかし、オ
ーケーだ」オレに歯を見せて笑った。「おやじさんはつけが溜まってい
たが、引越す前に払ってくれた」
オレは言った。「かなりの額?」
「高かった。100ドル以上。正確には覚えてない。しかしすべて払っ
てくれた。ジョリーはどうだい?」
「いいとこだよ」と、オレ。「また、いつか、ハーゲンドルフさん」
オレたちは店を出た。オレは言った。「アムの言う通りだった。額ま
でも。店でうまく調子を合わせてくれて、助かった。こちらから切り出
さないでも済んだ」
「確かに。さて」
オレは言った。「路上電車まで行って、ドラッグストアの近くで待っ
ていて!」
ひとりで、オレはこの1ブロックを2回歩いた。家を通り過ぎる時は
通りを横断した。それで犬はフェンス沿いのオレとの距離を保てなかっ
た。オレは立ち止まって、木に寄りかかり、そこからは家が見えて、オ
レが寝室にしていた上の室、ダイニングルームの窓が見えた。
少し泣きそうになったが、のどにかたまりを飲み込んでがまんした。
その頃に戻って、思い出そうとした。そこにいた最後の1ヶ月の心の状
態でいようとした。
その数週間のある週に、それはやってきた。おやじは、確かに働いて
いなかった。だが、どこかへ行っていた。数日間、昼も夜もなにかをし
ていた。町の外へ出るのでなく、あるいは、出たのか?いや、出てない。
それは確かにあったが、なぜ、今まで思い出さなかったのだろう?た
ぶん、いくつかの理由による。あとで話されることがなかった。おやじ
は、彼のやり方でしていたのであって、しゃべるほどのことはなかった。
そんなふうに今は思える。
オレは、アムがドラッグストアの日よけの下で待っているところへ戻
った。路上電車が来るところだったので、アムに合図して、いっしょに
乗り込んだ。
ダウンタウンに向かってる時に言った。「陪審員の義務があった。お
やじは、引越す前のしばらくの間、陪審員だった」
「どんな事件?」
「知らない。おやじは一度もそれについて話さなかった。新聞のファイ
ルを捜して、どんなことがあったのか調べることはできる。忘れていた
のは、一度もそのことを話したりしてなかったからだ」
アムは腕時計を見た。「ダウンタウンには正午頃に着く。エドはバニ
ーウィルソンに電話リストについて電話できる」
多めに両替して、硬貨をたくさん持ってバニーに電話した。静かなホ
テルのロビーで電話ブースのドアは、アムに聞こえるようにあけていた。
バニーは言った。「分かったよ、エド。契約はレイモンドで、ミラン
タワーのアパート43。ミシガンブルバードと湖を結ぶオンタリオ通り
のアパートホテルだ」
オレは言った。「分かった。サンクス、バニー」
「気にするなって、エド!もっとして欲しいことがあったら、また、言
ってくれ!夜でも仕事がないことがあるし、いつでもいい。どこから電
話してる?ホース夫人が長距離だって言っていた。どこから?」
「ゲーリー」と、オレ。「アンダーズという人に会いに。保険証書をお
やじに売った」
「保険って?」
そのことを話してなかったことを忘れていた。それで手短に話すと、
バニーは言った。「なんだそうか。マッジにとってはいいニュースだな。
マッジがどうやって暮らしてゆくか心配だったが、それがあれば、彼女
の助けになる。捜していた男は見つかった?」
「いや。アンダーズはスプリングフィールドに引越していた。もうこれ
以上は追わない。たぶん、なにも出てこないだろう。オレたちはもうす
ぐ戻る。もう一度サンクス!じゃ、また」
◇
ゲーリータイムズのオフィスで、捜している日付を含む新聞の製本さ
れたバックナンバーを見せてもらった。
捜すまでもなかった。一面に出ていた。スティーブレーノルズが銀行
強盗で裁判が開かれた週だった。裁判は3日続き、有罪の判決で結審し
た。終身刑だった。ハリーレーノルズは、スティーブの兄で、弁護側の
唯一の証人だった。アリバイを主張したが、明らかに信憑性がなかった。
ある理由から新聞にも書かれることはなく、偽証罪で告発されることも
なかった。
弁護側の弁護士はシュバインバーグだった。1年前に弁護士資格を失
って、復帰した、事実を湾曲させるのにたけた名うての弁護士だった。
日ごとに法廷を撮った写真があった。あるものはスティーブレーノル
ズ、別のはハリーだった。オレは、ふたりとも、特にハリーはよく知っ
ていると言えるまで覚えた。
オレたちは仕事を終え、バックナンバーを返した。お礼を言って、オ
フィスを後にした。
アムは言った。「もう、シカゴに戻れる。詳細までは分からないが、
十分やった。あとは推理でほとんど分かる」
オレは訊いた。「推理できない部分とは?」
「裁判のあと、引越すまで、なぜ3週間待ったのか?オレの推理はこう
だ。ウォリーは、レーノルズの裁判の陪審員になった。シュバインバー
グは、陪審員を買収して弁護士資格を失っていた。これが彼のやり方だ
った。なんらかの方法で、ウォリーに近づき、1000ドル渡し、とに
かく無罪に投票するよう頼んだ。証拠から見て、陪審員の意見を2分し
て、無効審理にさせることしかできなかった。
ウォリーはカネを受け取った。そして、シュバインバーグを裏切った。
ウォリーは度胸があったから、やったかも。そう、やったに違いない。
裁判直後に保険証書をカネの一部で契約した。マッジが子どもたちの卒
業までやってゆくに十分な額で。それから、突然ゲーリーから引越し、
やつらに見つからないように行方をくらました。なぜ、3週間待ったの
かは分からない。たぶん、自分を守るためになにかに時間をとられたに
違いない。たぶん、警察はハリーレーノルズを偽証か共犯で逮捕するた
めにしばらく拘束していた。それから釈放した。ハリーが出てきたら、
ウォリーはつけねらわれると思ったのだろう」
オレは訊いた。「マッジは知っていたと思う?」
アムは肩をすくめた。「一部は知っていたに違いない。オレの推理で
は、ほとんどは知らなかった。保険証書のことは話さなかったことは、
すでに分かってる。たぶんマッジは、それについてはなにも知らなかっ
た。思いがけないカネが入ったことは、宝くじでも当たったように思わ
せた。ゲーリーから引越したことは、借金から逃げたように見せて、裏
でこっそり借金は支払っていた」
オレは言った。「それは辻褄が合わない。おやじは逃げることもでき
たのに、借金はすべて正直に支払った。でも、ギャングからは賄賂のカ
ネをもらっている」
「そこがちょっと違う。ウォリーの考えでは、泥棒を裏切るのは、不正
直ではない。その考えが正しいのか間違ってるのかは知らないが、どう
でもいい。そのようなカネを受け取っておきながら、裏切るというのは、
かなりガッツがないとできない」
◇
シカゴに戻る列車では、あまりしゃべらなかった。
ループでハワード急行に乗り換えた。グランドに着いて、オレは言っ
た。「家に帰って風呂に入って、新しい服に着替えたい。体がにおう」
アムはうなづいて、言った。「そう、オレたちはどちらも、眠らずに
続けることはできない。家で、ついでに少し昼寝するといい。今だいた
い2時だ。少し眠って、7時か8時くらいにホテルへ来てくれ。今夜ミ
ランタワーを見に行くが、そのとき意識がもうろうとしていたらまずい」
家に着いて、オレは階段を上った。アムは歩き続けて、ワッカー街へ
向かった。
ドアは鍵が掛かっていたので、自分の鍵で入った。誰もいなかったの
はよかった。風呂へ入り、20分もかからずにベッドに入った。7時に
目覚まし時計をセットした。
目覚ましが鳴って起きたとき、居間の方で声がした。服を着て居間へ
行くと、おふくろとガーディが帰っていて、バニーもいた。みんな食事
をしたところで、おふくろが「ハロー」と言って、オレが食事したいか
訊いた。オレはコーヒーだけ飲みたいと言った。
オレはコーヒーカップを出して、テーブルについた。おふくろを直視
できなかった。美容院へ行って、違って見えた。新しい黒のドレスを着
ていた。それが今までよりもきれいに見せていた。少し化粧もしていた
が、厚化粧ではなかった。
なんと、とオレは考えた。おふくろは化粧していると、ほんとうにき
れいに見える。
ガーディもかなりきれいに見えた。しかしオレを見るときの顔は、す
こし不機嫌そうだった。財布とボビーレインハートとのいざこざの件で、
オレに対してしこりを持ってるのだ。
バニーは言った。「ふたりは保険金が入ったら、フロリダへ引越した
いそうだ。知り合いのいるここにとどまるべきだって言ったんだが」
「友人なんか」と、おふくろ。「バニー以外に誰がいるのさ?エドは、
今朝、ゲーリーへ行ったそうね。前の家を見に行ったの?」
オレはうなづいた。「外から見ただけ」
おふくろは言った。「あそこはオンボロだったね。このアパートも良
くないけど、ゲーリーの家は、もっとオンボロだった」
オレはなにも言わなかった。
おふくろが入れてくれたコーヒーに、砂糖とクリームを入れた。それ
ほど熱くなかったので、すぐ飲んでから言った。「アムに会うので、こ
こにいられない」
バニーは言った。「いっしょにトランプをしようと思っていたんだ。
エドが帰っていたので、マッジが目覚まし時計を見て、7時に起きると
分かって、いっしょに遊べると思った」
オレは言った。「たぶんアムを連れて戻ってくるから、また会える」
オレは立ち上がった。ガーディが訊いた。「これからどうするつもり、
エド?今というのでなく、将来は。仕事には戻る?」
「もちろん」と、オレ。「仕事に戻るよ。なぜ?」
「エドはいっしょにフロリダへ来たいと思ってた。それだけ。フロリダ
へは来ない?」
オレは言った。「たぶん、行かない」
彼女は言った。「お金はママのもの。エドが知ってるか分からないけ
ど、保険証書はママ宛てだから、ママのもの」
おふくろは言った。「ガーディ!」
「知ってるよ」と、オレ。「1セントも欲しくない」
おふくろは言った。「ガーディはそんなふうに言うつもりじゃないの
よ。彼女が言ってるのは、エドは仕事もしてなんでもできるが、ママは
ガーディが卒業するまで面倒みなきゃならないし━━━」
「よく分かってるよ」と、オレ。「正直言って、お金はまったく欲しく
ない。オレはちゃんとやって行ける。じゃ、バニー、また!」
バニーは呼び止めた。「ちょっと待って、エド」そしてドアを出たロ
ーカで5ドル紙幣を差し出して、言った。「アムも連れて来て!彼にも
会いたい。ついでに、これでビールを買って来てくれ!」
オレは紙幣を受け取らなかった。オレは言った。「ほんとうを言うと、
バニー、できないんだ。アムに会わせたいが、別のときに。今夜これか
らしなきゃならないことがある。なにかしようとしていたことは、知っ
てるよね?」
彼は頭をゆっくり振って、言った。「それは、1パーセントもうまく
ゆかない。なにもすべきでない」
「たぶん」と、オレ。「バニーが正しい。しかし、もう始めてしまった。
それがどうなるか見ていてほしい。ダメだろうが、それがオレたちのや
り方だから」
「手助けできることは?」
「もうしてくれた。電話リストだけで、とても助けになった。他に助け
てほしいことがあったら、知らせる。サンクス、バニー!」
◇
ホテルでは、アムは、鏡の横のプラグにつないで、電気ヒゲソリでヒ
ゲをそっていた
アムは言った。「眠れた?」
「ああ、よく眠れた」オレは鏡の中のアムの顔を見た。はれぼったく、
目は少し充血していた。オレは言った。「よく眠れなかった?」
「眠り始めたが、バセットが来て、起こされた。いっしょに飲みに連れ
出され、カマの掛け合いだった」
「うまくいった?」
「うまく聞き出せたのか分かん。なにかを投げて寄こしたが、なんなの
か分からん。実際、やつがオレたちにネコの鈴を付けてたとしても、驚
かない。どこに仕掛けられたのかも分からん」
「どんなふうにやられた?」
「それほどはやられてない。オレはやつに、ゲーリーのことを試しに話
してみた。ウォリーが得た臨時収入のことも、ミランタワーと電話番号
以外、すべて話した。それらよりもっと重要ななにかを、やつは返して
きた手ごたえがあった」
「たとえば?」
「オレも知りたいよ、エド。マッジには会った?」
「フロリダへ引越すそうだ」と、オレ。「ガーディもいっしょに。保険
金が入り次第すぐに」
アムは言った。「彼女たちの幸運を祈る。彼女はうまくやってゆく。
あのカネは1年以上は持たないだろうが、新しい夫を見つけるだろう。
まだ美貌を保っている。ウォリーより6か7若い、オレの記憶が正しけ
れば」
「36だと思う」
アムは言った。「バセットとは1・2杯飲んで、別れた。それで、エ
ドが来るまで眠る時間がなかった。それで出かけていって、ミランタワ
ーを調べてきた。オレたちの仕事の手始めに」
アムは歩いて来て、ベッドに座り、枕に寄りかかった。「アパート4
3には若い女がひとりで住んでいる。名前は、クレアレイモンド。バー
テンダーが言うには、美しいそうだ。夫は出て行った。バーテンダーに
よると、別居してるそうだ。捨てられたようだ。しかし室代は月末まで
払ってあって、それまでは、彼女はひとりでいるそうだ」
「もしかして」
「そう、レイモンドはレーノルズのこと。人相が一致する。彼は。ダッ
チとベニーという仲間とバーによく来るそうだ」
「ベニー?」
「トーピード。バセットから同じ名前を聞いた。バセットは警察が持っ
ている情報をすべて見ていて、いくつかは教えてくれた。ベニーロッソ。
ダッチの苗字はレーガン。この1週間、どちらもミランに姿を見せてな
い。ウォリーの死ぬ1・2日前には来ていたが」
「そこからなにが?」
アムはあくびをした。「分からない。やつらにいつか、訊いてみなき
ゃならない。そろそろ行くとするか」
オレは言った。「少し休んでて!ローカへ出てくるから」
「ああ、分かった」
ローカに出て、戻ったとき、アムはいびきをかいて眠っていた。
オレは考えながら、少し立っていた。今までアムは、自分で10分の
9くらいまでやってしまった。オレは、ただくっついていただけだ。一
度でも頭を使ったり、神経を使って自分でやったことがあったか?しか
も、アムは今、眠りが必要で、オレは必要ない。
オレは深く息を吸い込んで、吐き出して、自分に言った。「どうとい
うことはない」そして室の電気を消した。
アムを起こさずに外へ出ると、ミランタワーに向かった。
11
オレは、歩くペースをスローダウンさせた。これからなにをどうする
のか、分からなかったからだ。夜は、まだかなり早い時間だったし、腹
が減っていて、立ち止まり、食った。食べている間も、なんのアイデア
も浮かばなかった。
しかし、ミランタワーに着いた。
ビルの一角にカクテルバーがあって、ロビーに通じていた。オレはバ
ーに入り、カウンターに座った。シャレたバーだった。ビールを注文し
ようとしたが、このようなところでビールを注文するのはヤボな気がし
た。
オレはハットを後ろへ傾けて、タフに見せようとした。
「ライ!」オレはバーテンダーに言った。映画『ガラスの鍵』で、ジョ
ージラフト演じるネッドボーモンドがいつもライウィスキーを注文して
いたのを思い出した。ジョージラフトになったつもりで演じた。
バテンダーは慣れた手つきでカウンターの上をショットグラスをすべ
らして、オールドオバーホルトのボトルを注いだ。「チェイサーは?」
「プレインウォーター」と、オレ。
カウンターの上に置いた1ドル紙幣から、35セントの釣りをもらっ
た。
急いで飲む必要はない、と考えて、後ろを振り返らずに、バーの後ろ
の鏡を使って、バーの様子を観察した。バーにはなぜいつも鏡がある?
疑問に思った。男が追い詰められたとき、最後に見たい顔は鏡の中の自
分だろう。少なくとも、逃げるために飲む連中にとっては。
鏡に映った、ドア越しにホテルのロビーに入ってくる連中を見れた。
うしろの時計の文字盤も見れた。9時15分過ぎだと教えてくれた。
9時半になったら、とオレは考えた。なにかしよう。なにをするか分
からなかった。始める準備だけした。
最初にするのは、バーを出て、上の階に電話すること。だが、なにを
言おう?
望むべきは、アムがすでに起きていて、彼を待ってみることだ。オレ
はたぶんヘマをやらかすだろう。レインハートとケンカした時みたいに。
オレはまた、鏡の中から、周りを観察した。バーカウンターの反対側
の端に、男がひとりで座っていた。成功したビジネスマンに見えた。ほ
んとにそうなのか?とオレは考えた。もしかしたら、ギャングかもしれ
ない。背が低くて、黒の服を着たイタリア野郎がブース席にひとりで座
っていた。セールスマンだろうが、トーピードのように見えた。ベニー
ロッソかもしれなかった。訊くことはできるが、銃があるかもしれない。
オレは丸腰だ。たぶん、教えてはくれないだろう。
ライを、ひと口すすった。まずい味だったので、いそいで飲み込んだ。
つやつやしたバーカウンターの上に吐いてしまう前に、チェイサーをつ
かんだ。水を思わずつかんだ、みっともないかっこうを誰にも見られて
ないことを祈った。
後ろの時計を鏡で見ると、2時31分に見えた。とういことは、9時
29分だった。
バーテンダーがオレの前に戻ってきたが、オレは頭を振った。酒にむ
せそうになったのを見られたかもしれなかった。自分がおろかに感じた
が、もう1分間、そこに座っていた。それから立ち上がり、ロビーのド
アに向かった。シャツの裾がはみ出ていて、みんなに見られている気が
した。
電話でどもったりしたら、すべてをぶちこわすしそうだった。
ジュークボックスが、オレを救ってくれた。バーカウンターとドアの
間で、中央の柱とは逆にあった。キラキラ輝いて、シャレたバーにあっ
ても、やたら派手だった。立ち止まって、曲目を見ながら、ポケットか
ら硬貨を出した。
ベニーグッドマンを選び、硬貨を入れた。機械がレコードをスライド
させて取り出し、針を落とすのを立って見ていた。
目を閉じて、演奏が始まるのを聴いていた。筋肉は動かさなかったが、
音楽が体じゅうに満ちて、内へと流れた。
そして目をあけて、ロビーの方へ歩いていった。クラリネットが高音
で泣き叫び、支配者のように酔った。ライのせいではない。
気分が良くなった。子どものようにも、おろかにも感じない。シャツ
の裾は入れた。どんなことにも対応できる。ありそうもないことが起こ
ったとしても。
◇
電話ブースに入るとウェントウォース、スリーエイトフォーツーにダ
イヤルした。電話が鳴ってるのが聞こえた。
受話器を持ち上げるクリック音がして、若い女の声。「ハロー?」昨
夜、気に入っていた声だ。
「エドだよ、クレア」と、オレ。
「エドって、誰?」
「オレのことは知らない。まだ、会ってないから。下のロビーから電話
してる、ひとり?」
「ええ。誰なの?」
オレは訊いた。「ハンターという名前からなにか知らない?」
「ハンター?知らない」
オレは訊いた。「レーノルズという名前からは?」
「誰、それ?」
「説明したい」と、オレ。「上へ行ってもいい?それとも、下へ降りて
きて、バーで1杯やる?」
「ハリーの仲間?」
「いや」
「あなたを知らない」と、クレア。「なぜ会わなきゃいけない?」
オレは言った。「それしか、オレを知ってもらう方法がない」
「ハリーを知ってる?」
オレは言った。「オレは、ハリーの敵!」
「・・・」息を呑む声。しばらくの間。
オレは言った。「上に行く。ドアはあけて、チェーンは付けたまま。
狼男のように見えなかったら━━━ほかの
狼でも━━━チェーンをはず
して!」
彼女が答える前に電話を切った。興味を持ったら室に入れてくれるだ
ろう。
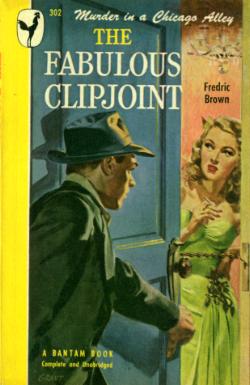
考える時間を与えたくなかった。ほかに電話する時間も。エレベータ
を待たずに、階段を3階まで駆け上がった。
◇
彼女は誰にも電話してなかった。ドアのところで待っていたからだ。
ドアにチェーンを掛けていた。チェーンのまま、4インチだけドアをあ
けて、そこに立って外を見ていた。廊下を歩いてくるオレを見ることが
できて、ノックの後でドアをあけて見るより、よく見れる方法だった。
彼女は若かった。そして、ノックアウト級の美人だった。ドアが4イ
ンチしかあいてなくても、それが分かった。どんな男でも、2回は口笛
を吹いてしまうような女だった。
じゅうたんにつまづくことなく、廊下を歩いてゆけた。
彼女の目は無表情のまま、オレがドアまで来ると、チェーンをはずし
た。彼女はドアをあけて、オレは中へ入った。ドアの後ろで誰もサンド
バッグで待ち構えてなかったので、オレは居間へ行った。そこは、小さ
な映画セットのようなことを除けば、いい室だった。金属製の薪乗せ台
のある暖炉があって、珍しい形の磨かれた火かき棒とシャベルがあった
が、火は燃えてなかった。正面に座り心地の良さそうなソファがあった。
ランプがあって、掛け布があってカーテンがあって、その他いろいろ。
うまく描写できないが、いい室だった。
オレは正面のソファに行って、座った。なにもない暖炉にかざして、
温まるように両手をこすった。
オレは言った。「豪華な夜だね。ブルバードでは雪が7インチ積もっ
て、ハスキー犬たちはオンタリオに着く前にギブアップさ!最後は自分
の手とヒザで雪をかく始末」さらに手をこすり合わせた。
彼女はソファの端に立って、オレを見下ろしていた。ひじを腰に当て
て。スリーブのないドレスに似合いそうな腕だった。そして、彼女はノ
ースリーブのドレスを着ていた。
彼女は言った。「急いでる様子はなさそうね?」
オレは言った。「水曜から1週間後には列車に乗らなきゃならない」
彼女は、風邪が良くなったときのような音を出して、言った。「それ
なら、1杯くらい飲んでいられそうね」
彼女は腰を曲げて、暖炉の左にあるキャビネットをあけた。そこには
ボトルの列とグラスの列があった。計量グラスにかきまぜ用スプーンに
シェーカーがあった。そして、ウィットに富んだ言い方をすれば、ミニ
チュアの冷蔵庫になっていて、一方にアイスキューブの乗ったゴムのト
レイが3つあった。
オレは言った。「ラジオはないの?」
「暖炉の反対側がオーディオセット」
オレはその方を見て言った。「レコードは1枚もない方に賭ける」
「1杯やるの、やらないの?」
オレはボトルの列を振り返って、カクテルはやめておこうと決心した。
もしも自分で作ってと言われたら、作り方が分からない。オレは言った。
「バーガンディがいい。くり色のカーペットに合う。こぼしても目立た
ない」
「そんなこと気にしないで!クリームデメントはどう?家具はわたしの
じゃない」
「でも住んでるのでは?」
「来週以降はもういない」
オレは言った。「それなら、バーガンディはやめて、クリームデメン
トを飲もう。とにかく、オレはそうする」
彼女は一番上の棚から小さなグラスを2つ出すと、クリームデメント
のボトルから注いだ。1つをオレに手渡した。
暖炉棚の上に、チーク材のタバコケースがあった。オレは彼女に1本
取って、火をつけ、オレ用にも1本火をつけた。それからソファに座っ
て、酒をすすった。ペパーミントキャンディの味がした。色はグリーン
のインク。これはオレのお気に入りにした。
彼女は座らず、立ったまま暖炉棚に寄りかかって、オレを見ていた。
彼女はまだ、無表情だった。
彼女は髪は黒で、なめらかにウェーブさせていた。スレンダーな体、
背丈はオレと同じくらい。澄んで落ち着いた目。
オレは言った。「あんたは美人」
彼女の口の端が少し引きつった。彼女は訊いた。「それが電話して来
た理由?」
オレは言った。「あのときは知らなかった。あんたを見たことなかっ
たから。それは話したかった理由じゃない」
「あなたにしゃべらせるには、どうすればいい?」
「酒はいつも助けになる」と、オレ。「音楽も好き。レコードは?」
彼女はタバコの煙を深く吸い込んで、鼻からゆっくり出して、言った。
「もしもわたしが、その目のあざはどうしたの?と訊いたら、セントバ
ーナードにかまれたと言うんでしょ?」
オレは言った。「ほんとうのことを言うと、男に殴られた」
「なぜ?」
「オレが嫌い」
「殴り返したんでしょ?」
オレは言った。「そう」
彼女は笑った。それは素直な大笑いだった。彼女は言った。「あなた
が気違いなのかどうか分からなかった。決められなかった。ほんとうは
なにをして欲しいの?」
オレは言った。「ハリーレーノルズの住所」
彼女は顔をしかめた。「分からない。どこに住んでるのか知らない。
気にもしてない」
オレは言った。「さっきレコードの話をしていた。なにかあるなら」
「やめて!なぜハリーを捜しているのか知りたい」
オレは深く息をしてから、前にからだを傾けて、言った。「先週、あ
る男が路地で殺された。オレの父で、印刷工だった。オレは印刷見習い
工。オレは見かけほど年上じゃない。おじは、カーニバルで働いている。
おじとオレは、父を殺した犯人として警察に突き出すために、ハリーレ
ーノルズを捜している。おじはオレといっしょにここへ来るはずだった
が、今、眠っている。おじはいいやつだ。きっと好きになる」
彼女は言った。「1音節にうまくまとめた。その黒の目は、真実を言
っている」
オレは言った。「これから、1音節で行こう!」
彼女は酒をまたすすって、小さなグラスの縁越しにオレを見た。
「いいわ」と、彼女。「名前は?」
「エド」
「それだけ?残りは?」
「ハンター」と、オレ。「これは2音節になる。エドなら1音節。あん
たの負け!」
「ハリーを本気で捜してるの?それがここへ来た理由?」
「そう」
「彼をどうするつもり?」
「3音節になる」
「続けて」
「やつを、殺す、ため」
「誰に雇われて?」
「ある男。名前は聞いてもあんたは知らない。時期が来たら、話せる」
彼女は言った。「舌がまだスムーズでないようね。もっと酒がいる」
おかわりをついだ。
「それと音楽は」と、オレ。「苛立った胸を癒してくれる。そんなレコ
ードは?もしもあるなら」
彼女はまた笑い、室を横切って、さらさのカーテンの横の引き出しを
あけた。レコードの棚があった。「なにが聴きたい?たいていのはある」
「ドーシーは?」
「両方ある。どっちのドーシー?」
「トロンボーンのドーシー」
彼女は、トミードーシーのことだと知っていて、棚のアルバムから数
枚のレコードを取り出して、ターンテーブルに乗せて自動再生にセット
した。
戻ってくると、オレの前に立った。「誰に送り込まれたの?」
オレは言った。「ベニーに送り込まれたと言えれば、かっこがいいが、
そうじゃなかった。ベニーもダッチも好きじゃない。ハリーと同じくら
い。誰にも送り込まれてないよ、クレア。自分で来た」
彼女は前かがみになって、オレのコートの両側の肩ホルスターのあた
りを触った。背筋を伸ばすと、顔をしかめて、言った。「あなたは拳銃
もなしに━━━」
「静かに!」と、オレ。「ドーシーが聞きたい」
彼女は肩をすくめた。暖炉棚からグラスを取って、オレから十分な距
離にあるソファに座った。オレは別になにもしなかった。したい気もあ
ったが、しなかった。
4枚目のレコードが終わって再生が止まるまで待った。
それから、言った。「いくらか払うとしたら?つまり、ハリーの住所
に」
彼女は言った。「住所は知らないのよ、エド」
こちらに振り返ってオレを見て、言った。「聞いて!ほんとうなの。
信じるかどうか分からないけど。ハリーとはもう終わってる。ハリーと
関係のあるすべてと。ここに2年間住んでいた。そのあいだに得たもの
といえば、故郷に帰るためのカネくらいよ。故郷はインディアナポリス。
ここを出て、インディアナポリスに帰るつもり。仕事を得て、アパー
トに住む。ベッドに枕はひとつ。週25ドルでどうやって生きてゆくか、
といったことを、またすべてを学び直す。たぶん変に聞こえるでしょう
けど」
「特に変でない」と、オレ。「銀行に少し預けておけば、もっといい未
来が」
「それはノー、エド。理由は2つある。1つ目、裏切りはいいスタート
にならない。2つ目、ハリーがどこか知らない。1週間、ほとんど2週
間、会ってない。シカゴにいるのかさえ知らない。気にしてない」
オレは言った。「そういうことなら」
オレは立ち上がって、レコード棚へ行った。そこには、ジミーヌーン
がフューチャーした古いアルバムがあった。ワンワンブルースにワバッ
シュブルース━━━ジミーヌーンのうわさはたくさん聞いたが、レコー
ドは1枚も聴いてなかった。アルバムを手に取り、ターンテーブルに乗
せて再生の仕方を思い描いて、最初のレコードが始まるまで立って見て
いた。始まると、実に実にいい曲だった。
クレアに手を差し出すと、彼女は立ち上がりこちらに来た。いっしょ
にダンスをした。音楽は、クリームデメントがグリーンだったように、
ブルーだった。深い、深いブルーだ。こんなふうに演奏されることはも
うないだろう。演奏は、オレをとらえた。
曲が終わってない時だった。腕の中にクレアがいると感じた。彼女は
腕から逃れようとはしなかった。彼女にキスすることが、この世でもっ
とも自然なことのようになりつつあった。
そうなった。レコード同士の静けさに、それはあった。キスの静けさ
に。ドアで鍵が回される音がした。
その音がなんなのか気づく前に、彼女はオレの腕から出た。
◇
彼女はすばやい静かな動作で唇に1本指を当てて、キャビネットのす
ぐ左の半開きのドアを指差した。それからすばやく動いて、アパートの
外のドアへ向かった、鍵が回されたドア━━━今にも開きつつあるドア
へ。
オレもゆっくりしてなかった。暖炉棚の自分のグラスとタバコに、ソ
ファの上のハットを取り、彼女が指差したドアを抜けた。彼女が玄関の
ドアに行く前に。
暗い室にいた。ドアを少し後ろへ引いて、数インチ半開きにした。
彼女の声が聞こえた。「あら!ここへ来るとは、どういうつもり?」
レコードがまた始まった。ジミーヌーンの2枚目。残りを聞けなかっ
た。レコードはマーギーだった。「マーギー、いつもきみのことを思っ
てる、マーギー━━━」
ドアがガチャリとして、クレアはそれを閉めようとして、室を横切っ
た。顔は怒りでまっ白だった。目は━━━良かった、オレを見てなかっ
た。
ドアをバタンと閉めた。彼女は言った。「ダッチ!なにしに来たの?
ハリーが鍵をくれたの、それとも?」
「クレア、落ち着いて!いいや、ハリーがくれたんじゃない。そんなこ
としやしない。オレが自分で作ったのさ、ベイビー。1週間前に型をと
って」
「なんの型?あ、言わないで!どうでもいいから、もう、出て行って!」
「今かい、ベイビー?」ダッチは室の中へ入ってきた。オレは初めてや
つの顔を見た。その声は、ソプラノではないということ以外はなにも言
えない。オレはやつを見た。室の幅くらいあった。
もしも彼が、オランダ人かアイルランド人だったら、オレはホッテン
トットだろう。オレには、ギリシア人に見えた。ギリシア人かシリア人
かアルメニア人。もしかしたら、トルコ人かペルシア人かなにか。しか
し、レーガンという苗字やダッチというあだ名をどうやってもらったの
だろう?推測はやめた。肌は浅黒く、皮をはいだら、何エーカーにも広
がりそうだ。レスラーのような体で、筋肉のかたまりのように歩いた。
「それじゃあ、ベイビー」と、ダッチ。「ほかには漏らさないでくれ。
気を楽にして。おしゃべりしよう!」
「ここから出て行って!」
彼は立ったままニヤニヤして、手に持ったハットをまわしていた。声
はもっとソフトになった。
彼は言った。「ハリーがオレを裏切ったことに気づいてないと、思っ
てる?オレとベニーが?ベニーのことは知らないが、オレは裏切られる
のが、好きじゃない。そのことをハリーに話すつもりだ」
「なんの話をしてるのか、分からない」
「分からない?」胸ポケットから太い葉巻を出すと、ふっくらした唇に
くわえ、シルバーのライターで時間をかけてゆっくり火をつけた。ハッ
トを頭の後ろにかぶった。もう一度、「分からない?」と言った。
クレアは言った。「そう、もしもここから出て行かないなら━━━」
「なにするつもり?」彼はくすくす笑った。「警察を呼ぶ?ワウパカか
ら持ち込んだばかりのGが40個あるのに?笑わせないでくれ!注意し
て聞いてくれよ、ベイビー。1つ、オレは核心に気づいている。ハリー
はオレと手を切ったふりをした。やつはアタマがいい。ワウパカの仕事
の前にそうした。しかしシュレミエルのように、ハリーと手を切ったと
き、ハリーにブツをつかませた。さて、ハリーはどこに?オレは知らな
い。しかし見つけ出す。そしてオレは、ここにGが40個あることを知
っている」
「あなたはどうかしてる!あなたは━━━」
ダッチが筋肉のかたまりだと考えたのは間違いだった。単に、そのよ
うに歩いただけだ。やつの手がヘビのように伸びて、クレアの手首をつ
かんだ。ぐいと引き寄せ、後ろを向かせて、彼女の両腕を下げさせ、胸
の前に押さえつけた。
もう一方の手で、彼女の口をふさいた。
やつの背中は、ほとんどオレの前にあった。自分がなにをしようとし
てるのか、分からなかった。筋肉の山のような相手になにができるのか、
分からなかった。しかしオレはドアをあけた。なにかないか、あたりを
見回した。唯一見えたのは、にせの暖炉にある火かき棒だった。
そこへ向かって、静かに歩いた。
やつの声のピッチは、いささかも変わらなかった。天気のことをしゃ
べっているかのようだった。やつは言った。「ちょい待ち、ベイビー。
イエスかノーを言えるように手をゆるめるからな。分け前を得られる唯
一の方法は、あんたとオレが、ベイビー、ハリーはもうここにゃ住んで
ない。もうひとつは、そうだな、やりたくはないが」
オレは火かき棒を手にした。足音はまったくさせなかった。ただ、こ
れはおもちゃの火かき棒だった。実際に火をかきまぜたり、山のような
巨体を殴るようにはできてない。ぜんぜん重くなかった。やつを怒らせ
るだけかもしれない。
薪乗せ台は金属製だが、ネジで留められていて動かせなかった。
前になにかで読んだことを思い出した。首の横を叩く柔術があるそう
だ。水平にあご骨のちょうど下を。手のひらの端で叩いても、気絶させ
るか、あるいは命を奪えるそうだ。
やってみる価値はあった。ちょどよい場所に移動して、うまくスイン
グできるように火かき棒を構えた。
オレは言った。「そこまでだ、ダッチ!」
多くのことが起こった。やつはクレアを両手でつかんだまま、頭を予
想した通りの角度で振り返った。オレは火かき棒をフルスウィングした。
火かき棒は、もしもやつの首にメモリが描かれていたら点線で示された
ところにヒットした。
クレアは倒れ、ダッチも倒れた。どすんどすんという振動がミランタ
ワーに響いた。すごい振動だった。暖炉棚のクレアのクリームデメント
のグラスを揺らし、暖炉のタイルに当たってチリンチリンと鳴らし、し
ぶきを上げた。くり色のカーペットは、やはり、しみになるだろう。
最初に考えたのは、やつの拳銃だった。ほんとうに気絶してるのか、
いつまでなのか分からなかった。ホルスターには無かった。それは、し
し鼻のポリスポジティブリボルバーで、コートのサイドポケットにあっ
た。
そいつを手にしてから気分がよくなった。なにが起こっていたかとい
うと、笑い声だった。クレアは手をついて、ひざで立ち上がろうとして
いた。そして、悪魔のように笑っていた。ちょっと酔ったかんじの笑い
声だった。
理解できなかった。彼女は酔ってはなかった。ヒステリーのようでも
なかった。
そう、オレと目が合うと笑うのをやめて、言った。「また、レコード
を掛けて、すぐに!」
それからまた、笑い出した。笑っているのは口だけだった。顔は蒼白
で、目は怯えていた。自分の足で立ち上がり、ゆっくりと室を横切って
行った。
オレは理解できなかったが、命令されたことはやった。またレコード
を掛けた。彼女はソファに崩れるように座って、すすり泣いた。静かに
すすり泣いた。とても静かに。
「マーギー」と、レコード。「いつもきみのことを思ってる、マーギー、
世界はいつか━━━」
さらに、彼女は言った。「エド、しゃべるのよ!大声で!歩いて!そ
うすれば、みんなに聞こえる」彼女は泣くのをやめて、声のピッチを上
げた。「見てなかったの?そんなふうに倒れたのよ!そんな音?殺人か
事故かも?あるいは、ただの酔っ払ってころんだけ?音の後で、話し声
や歩いたり笑ったりすれば、みんなはこう言う。ただの酔っ払いだった。
もしもドスンが殺人だと思ったら、警察を呼ぶ━━━」
「たしかに!」と、オレ。ささやき声だった。のどを広げて、言った。
「たしかに!」大声で。あまりに大声だったので、3回目はやめた。
手にまだ拳銃を持っていた。それが元あったようなオレのポケットに
押し込んだ。それから、ダッチが大の字に倒れているところへ行って、
考えた。なんてことだ、なぜやつはまだ倒れている?あんなことで死ぬ
はずはない。
だが、やつは死んでいた。やつのコートに手を入れて捜したが、脈は
なかった。捜し続けながら、信じられなかった。本で読んだトリックブ
ローで、まさか本当に効くとは思いもしないだろう。普通人でないエキ
スパートだからこそ使える柔術であって、普通人が使えるはずがない。
怖くなって、やつの上に馬乗りになって困らせてやる気にもならなか
った。やつは、サバのように死んでいた。
オレは笑い始めた。しかし、ご近所さんを安心させるためじゃない。
クレアが歩いてきて、オレの顔を叩いたので、笑うのをやめた。
オレたちはソファまで行って、座った。気を落ち着かせ、タバコを取
って、また気を落ち着かせ、マッチをすって、タバコを渡した。手の震
えは収まった。
彼女は訊いた。「なにか飲みものは、エド?」
「いらない」と、オレ。
彼女は言った。「わたしもいらない」
レコードはまた切り替わった。ワンワンブルースが始まった。オレは
立ち上がり、レコードを止めた。もしもご近所さんが、階下でも両隣り
でも、警察を呼ぶなり管理人を呼ぶなりしていたら、すでに到着してい
る頃だ。
オレはソファに深く座った。クレアは手をオレにゆだねたまま、オレ
たちは互いを見ずに、黙って、火のついてない、これから先も決して火
のつかない暖炉を見つめて、座っていた。
とにかく、暖炉を見つめながら、後ろで床に倒れているダッチを見る
必要はなかった。
しかし、やつはそこにいた。起き上がることもなく、去ることもなか
った。ずっとしないだろう。ずっと、なにもしないだろう。やつは死ん
だのだ。
そして、やつの巨体は、そこでだんだん大きくなっていった。室がい
っぱいになるまで。
クレアは、オレの手の中で自分の手をきつく握って、また、しくしく
泣き出した。とても静かに。
12
彼女が泣き止むのを待ってから、オレは言った。「なにかしなけりゃ
ならない。警察を呼んで、本当のことを話す。それがひとつ。別のやり
方は、ここから逃げ出して、彼らが見つけるのに任せる。3番目が一番
やっかいだが、どこか別の場所に移して、そこで見つかるようにする」
「警察を呼ぶことはできない、エド。彼らはハリーがここに住んでいた
ことを突き止める。すべてを突き止めて、ハリーがやったすべての事件
の証人として、わたしをねじ上げる。彼らは━━━」彼女の顔は紙のよ
うに白くなった。「なにかの事件でも、わたしを連れ出して、車で待た
せたり見張らせたりする。なんてことかしら!わたしは、ハリーがゆっ
くりとわたしを教育したのを気づかないふりをしていた。だからしゃべ
ることはできない。警察はダッチが事件に関わったのを知っている。も
しも━━━」
オレは言った。「警察はあんたをマークして、ハリーの事件に結びつ
けるかな?」
「そう、たぶん、そうする」
オレは言った。「なら、警察は呼ばない方がいい。しかし、とにかく、
あんたはここから出て行って、インディアナポリスへ戻った方がいい。
今夜、発てる?」
「ええ、でも、わたしは指名手配される。ダッチの死体がここで見つか
れば、わたしを追ってくる。わたしが誰か突き止められ、出身地も調べ
られる。インディアナポリスへは戻れない。どこか別の場所へ行かなき
ゃならない。ずっと身を隠して逃げなきゃならない。残りの人生がすべ
て逃亡者に━━━」
彼女の話をさえぎった。「オーケー!警官は呼べない。やつを置いて
いくこともできない。ここからどう連れ出す?」
「あいつはすごく重い。どうしたらいいか分からないけど、廊下から見
えないうしろのドアの先に業務用のエレベータがある。深夜過ぎでも動
いている。廊下へ運んだあとは車がいる。あいつはすごく重い。エド、
どうしたらいい?」
オレは立ち上がった。周りを見回して、電話が目について、言った。
「どうしたらいいか、分かった。クレア、少し待っていて!」
オレは電話のところへ行って、ワッカー街を呼び出し、アムの室番号
を告げた。
アムの声が聞こえてきて、ガクガクしていたヒザが楽になった。電話
の横のイスに座った。
オレは言った。「エドだよ、アム」
「若さいっぱいのエドが、オレを置いて、どこでなにしてる?電話が来
るのを待っていた。たぶん、まずいことになったんでは?ふん?」
オレは言った。「そのようだ。今電話してる番号は、例の電話番号か
らだ」
「へぇ!うまくいったのか、それとも?」
「分からない。どっちなのかは、あんたの見方による。聞いて!オレた
ちには車がいる、あるいは━━━」
アムはさえぎった。「オレたちって?」
「クレアとオレ」と、オレ。「聞いて!この電話はホテルの切り替えボ
ードを経由してない?」
「分かった、折り返し電話する」
「その方がいい」と、オレ。
5分で電話が鳴った。「電話ボックスからだ」と、アム。「続けて、
エド!」
オレは言った。「クレアとオレは、うまく行っていたんだが、飛び入
りしてきたやつがいる。ダッチというやつだ。ダッチはちょっと飲みす
ぎで、でかくて手に負えない。フロントロビーを通らないでやつを家に
帰したい。発見されなければいい。誰か車があれば、裏の業務用出入り
口に停めてほしい。あと、やつを業務用エレべータで下に降ろすのを手
伝ってほしい」
「オーケー、エド。タクシーでもいい?」
オレは言った。「運転手はダッチのことを気にするかもしれない。や
つはちょっと堅くなって、う〜ん、分かるよね」
アムは言った。「たぶん、分かる。オーケー、エド。砦を守ってろ!
すぐに応援に駆けつける!」
電話を置いたとき、ずいぶん気が楽になったように感じた。戻って、
クレアの横のソファに座った。
彼女はおかしな顔でオレを見て、言った。「アムおじさんに電話した
の?ほんとうのおじ?」
オレはうなづいた。
彼女は言った。「あなたが編み出した妙な作り話にみえる。先週父が
ハリーに殺されて、あなたとおじがハリーを追って、おじだけが眠くて
━━━これって、ミシガンブルバードで7フィートの雪で犬たちがギブ
アップした話と同じでは?」
オレは言った。「同じではない。そのままの話だ。最初の話は、信じ
ないと分かっていたから、そう言っただけ。あんたの立ち位置が分から
なかったから」
彼女はまた手をオレの手の中に置いて、言った。「話してみて!」
「話したよ。聞いて、クレア!よく考えて!今までに、ハリーが、ダッ
チでもベニーでも、ハンターという名前といっしょに話されてるのを聞
いたことは?」
「ないわ、エド。思い出す限り、ない」
「やつらとは、どのくらい知り合い?」
「2年。話した通り」
彼女を信じたかった。彼女の話すべてを信じたかった。しかし、確か
める必要があった。
オレは訊いた。「カウフマンという名前を聞いたことは?ジョージカ
ウフマン?」
彼女はためらいなく言った。「ええ、聞いたわ。たぶん2・3週間前
に。ハリーがわたしに、カウフマンという名前の男が電話してきてメッ
セージを伝えると。メッセージは住所らしくて、書き写したら、ハリー
に渡してと。あるいは、カウフマンの店で誰かと会うことかもしれない
と。それがもしも男が店にいるということなら、ハリーの居場所が分か
るならすぐに伝えてと」
「カウフマンから電話は?」
「なかった。わたしがいるときには、とにかくなかった」
「別の誰かがメッセージを受けることは可能?」
「ハリーならできたかも。1週間以上前なら。なんどか彼がここにいて、
わたしがいないことがあった。ハリー以外はだれもいない。ハリーが会
いたがっていた男、カウフマンの店に来てるというのは、エドのお父さ
ん?」
オレはうなづいた。チェックはできた。カウフマンの話とグローブの
ようにぴったり合う。彼とクレアとが、このことについて本当のことを
言っていることが証明された。
オレは訊いた。「ハリーの弟のスティーブについては?」
「刑務所にいることだけ。インディアナだと思う。しかしそれは、ハリ
ーに会う前のこと。エド、今なにか飲みたい。あなたは?マティーニを
作ろうか?あるいは、なにか別のもの?」
オレは言った。「マティーニがいい」
彼女が立ち上がったとき、暖炉の上の鏡に自分の姿が映った。小さな
悲鳴を上げて、言った。「わたし、すぐ戻るわ、エド」
彼女は、オレが少し前に隠れていたところの後ろにドアから出て行っ
た。別のドアが開いて閉まり、水が流れる音がした。彼女は気分がよく
なったのだ。娘が自分がどう見えるか気にし出したら、かなり気分はよ
くなっている。
彼女は、ピン札で100万ドルの姿で戻ってきた。
角氷のグラスとベルモットのボトルを持って来たとき、ドアチャイム
が鳴った。
オレは言った。「きっとアムだ。オレが出る」
しかし、コートのポケットのリボルバーに手を置いて、ドアをあけた。
チェーンのまま。
アムだった。キャブドライバーのキャップをかぶって、歯を見せて笑
っていた。
アムは言った。「タクシーをお呼びで?」
オレはチェーンをはずして、言った。「ええ。入って!小さな荷物が
あるので」
オレは彼のうしろでドアを閉めて、鍵を掛けた。アムは言った。「う
まくやってるようだな。エドの唇の上のリップスティックをぬぐえば、
もっと男前だ。どこだ?」
オレたちは居間へ行った。クレアを見て、アムの眉毛は少し上がった。
アムの唇は、クレアのようなものを見たときによく男がするように、口
笛の形に少しとんがった。
それから後ろを振り返って、ダッチを見て、少したじろいだ。
アムは言った。「エド、起重機を持って来いと言ってくれるべきだっ
た」歩いて行って、立ったまま見下ろした。「血はなし。傷もなし。こ
れは都合がいい。どうやったんだ?死ぬほど怖がらしたのか?」
オレは言った。「怖かったのはこっちだ。アム、こちらクレア」
彼女は手を差し出した。彼は手を取って言った。「このような状況で
も、うれしいね」
彼女は言った。「サンクス、アム。マティーニは?」
すでに3つ目のグラスを出していた。アムは振り返って、オレを見た。
なにを考えているのか分かったので、オレは言った。「大丈夫だよ。グ
リーンインクを2杯飲んだが、数週間前だ。下のバーでライを飲んだが、
去年のことだ」
彼女はカクテルを作り終え、それぞれ手渡した。オレは自分のグラス
をすすった。うまかった。お気に入りにした。
アムは言った。「どのくらい話した、エド?」
「じゅうぶん話した」と、オレ。「クレアは現在のスコアを知ってる。
彼女は、オレたちのチームだ」
アムは言った。「なにをしてるのか分かってることを望む、エド」
「オレもそう望む」と、オレ。
「さて、エドはあした、すべて話してくれ。いつも、あしたはある」
オレは言った。「今夜の残りもある」
彼は歯を見せて笑って、言った。「それは疑わしいが、始めよう!酔
っ払いの友人の半分は持てそうか?」
「やってみる」
それから、クレアに。「キャブは裏の業務用出入り口に停めてある。
ただ、鍵が掛かっていた。オレは正面入り口から入った。鍵はある?」
「内側からはあく。ドアにカードボードを挟んでおけば、鍵が掛からな
いようにできるから、また入れる。エレベータは1階で止まっているだ
ろうから、走って下まで行って、4階に上げられる」
「いや」と、アム。「エレベータは音がする。特に、使われてない深夜
には。オレたちは裏の階段でやつを降ろす。あんたは先頭にいて、オレ
たちが誰かと出くわさないようにする。もしも誰かがいたら、なにかし
ゃべって!その声を聞いて、オレたちは止まって待つ」
彼女はうなづいた。
アムはダッチの肩を持って、オレは両足を持った。やつはあまりに重
かったので、ふたりの間に挟んで酔っ払いのように移動させることはで
きなかった。いちかばちか、運んでみるしかなかった。
ホールを抜けて、階段を降ろした。毎日やりたいような仕事ではなか
った。
毎回休憩をとりながら運んだ。ドアはクレアが言った通りだった。裏
の路地には誰もいなかった。やつをキャブに乗せ、後ろの座席の床にジ
ャックナイフのように折り曲げて、クレアがそのために持ってきてくれ
た毛布を掛けた。
オレは座り込んで、額をぬぐった。アムもそうした。
それからアムが運転席に座り、クレアとオレは後ろの席に座った。
アムは言った。「最後の休憩場所は?」
オレは言った。「フランクリン通りの路地━━━いや、忘れて!あそ
こにだけは、こいつを置きたくない」
クレアは言った。「数週間前まで住んでいた場所を知っている。ディ
ビジョン通りのアパート。その裏の路地に置いておけば━━━」
「頭がいい」と、アム。「やつとやつが見つかった場所につながりがあ
れば、そこで捨てられたようには見えない。ミランから離れたところに
調査が集中する」
アムは車のギアを入れた。
フェアバンクスの路地を出て、エリーの北を通って、ブルバードへ抜
けた。ブルバード北からディビジョン通りまではかなり渋滞していた。
クレアは住所を言って、10分後にはダッチを降ろした。そこではい
ささかも時間を無駄にしなかった。
オレたちは全くしゃべらなかった。ブルバードの渋滞にはまってもな
にもしゃべらず、南に向かった。どこかの大時計が2時を打った。
◇
クレアは後ろの席で、オレの腕の中で静かにしていた。
アムは言った。「まだ銃はあるか、エド?」
「ああ、ある」
路地に入ると、前にキャブが停めてあった同じ場所に停めて、言った。
「ふたりともここに、しばらくいてくれ!あの室をもう一度よく見てく
る。前にも仲間がいたなら、あそこで誰か待っているかもしれない。ク
レア、鍵をかして!」
オレはいっしょに上に行きたかったが、行かせてくれなかった。
とてもとても静かだった。
クレアが言った。「キスミー、エド!」
しばらくしてから、彼女が言った。「あす、早い列車に乗る。エド、
あそこにひとりでいたくない。列車に乗るまで、いっしょにいてくれな
い?」
オレは言った。「シカゴは広い。しばらくの間、シカゴのどこかにい
ることはできない?この件がすべて終わるまで」
「それはできない、エド。インディアナポリスでわたしを捜さないと約
束して!住所も教えない。あすの朝でお別れ。それがベスト」
オレは反対したかったが、心の底で彼女が正しいと分かっていた。な
ぜそう分かったのか知らないが、分かっていた。
◇
アムがタクシーのドアをあけて、言った。「ふたりとも分かれて!こ
れが銃で鍵だ。聞いて、エド。エドはこの銃がどこにあったか知らない
ことにする。今夜は持っていて、ワッカー街に戻る前に捨てて!自分の
指紋は消して!」
オレは言った。「そんなドジは踏まない」
「ときどき心配になる。エドはそのうち成長してゆく。今度はいつ会う?
お昼か?」
「たぶん」
クレアは言った。「上で飲み物でも?」
オレたちはキャブを降りた。アムは前のドアをあけて、運転席につい
て、言った。「それができない。このキャブとキャップは1時間で25
ドルかかっていて、すでに2時間たつ。オレの稼ぎでは少し贅沢」
クレアは言った。「グッバイ、アム!」
彼は車のエンジンを掛けた。窓をあけて、言った。「幸運を、子ども
たち!オレが望まないことはしないように!」
車は走り去った。
オレたちはしばらくの間、そこに立っていた。手と手をつないで、暖
かい夏の夜、路地の暗闇で。
クレアが言った。「ステキな夜ね」
オレは言った。「もっとよくなる」
「そうね、もっとよくなる、エド」
彼女は少し、オレにもたれかかった。彼女の腕を取り、オレの腕を体
に回して、キスした。
しばらくして、彼女は言った。「雪から出ない?」
オレたちは、雪から出て、中へ入った。
◇
オレが目覚めたとき、クレアはすでにドレスを着て、スーツケースを
詰めていた。ベッドサイドテーブルの電子時計を見るとまだ、10時だ
った。
彼女は微笑んで言った。「おはよう、エド」
オレは訊いた。「外はまだ、雪?」
「いいえ、ずっと止んでいた。起こそうとしていたところ。11時15
分の列車がある。もしもどこかで朝食を食べるなら、急がないと!」
彼女は、もうひとつのスーツケースを出しにクローゼットへ行った。
オレは起き上がり、急いでシャワーを浴びて、服を着た。彼女はそれ
までに、荷物を詰め終わっていた。彼女は言った。「駅でコーヒーとド
ーナッツを食べるなら、出発しないと!もう1時間しかない」
「タクシーを呼ぼうか?」
「正面にタクシー乗り場があって、朝のこの時間はすぐに乗れる」
オレはスーツケースを2つ持って、彼女は小さなバッグと切手の貼ら
れた小包を持っていた。彼女はそれを見ているオレに気づいて、言った。
「友人へのバースデイプレゼント。2日前に郵送するのを忘れていた。
途中忘れていたら、声を掛けて!」
バースデイプレゼントはどうでもよかった。ドアまで行くと、振り返
って、ドアを背にしてスーツケースを下に置いた。
オレは腕を広げたが、彼女は来なかった。彼女は頭をゆっくり振った。
「だめよ、エド。さよならは終わり。昨夜がわたしたちのお別れ。もう、
わたしを見ないで!もう、わたしを追って来ないで!」
「なぜ、ダメ?クレア」
「なぜかは分かってるはずよ、エド。十分考える時間があったときに。
エドはわたしが正しいって分かってる。おじさんも知ってる。たぶん、
言ってくれる。わたしは言えない」
「しかし━━━」
「あなたはいくつ、エド?ほんとうは?20?」
「ほとんど19だ」
「わたしは29よ、エド。つまり━━━」
オレは言った。「ああ、あんたは老いてもうすぐ死にかかってる。動
脈は硬くなって、やがて━━━」
「エド、わたしの言う意味が分かってない。29は老いてはない。しか
し、女にとって、もう若くはない。そして、エド、昨夜はあの仕事のた
めに、ずっといっしょだった。女は一度いい生活につかってしまうと、
おカネもそうだし、2度と前の生活には戻れない。わたしよりもっと強
い女であっても、戻れない。わたしは、そこへは戻れない、エド」
「あんたの言ってるのは、ハリーのような別の男を見つけるということ」
「ハリーのような男じゃない。違う。かなり頼ってはいた。おカネのあ
る男。でも、あんな方法で稼ぐのではない。シカゴでは、かなり人に頼
っていた。特に、昨夜は、ダッチが来て━━━エドがいてくれてとても
感謝している」
オレは言った。「少しは理解できた。しかし、なぜ━━━」
「エドは印刷工として、どのくらい稼げるの?分かった?」
「オーケー」と、オレ。
オレはスーツケースを持って、出て行った。ホテルの正面のタクシー
乗り場で1台ひろって、ディアボーン駅へ向かった。
タクシーの中でクレアは正面を向いて座っていた。しかしたまたま、
彼女の目に涙が浮かんでいるのに気づいた。
そのことが、オレをうれしくさせるのか、悲しくさせるのか分からな
かった。昨夜については、うれしく、彼女については、悲しくだと思う。
オレの中ではすべてがごっちゃになっていた。アムに会いにカーニバル
へ行って帰ってきたとき、オレにとってはすごく良かったことなのに、
おふくろがそれでオレをバカにしたときのように。
オレは考えた。なぜ、女は首尾一貫性がないのか?なぜ、女は良かっ
たりあるいは悪かったりのどちらかになれないか?心をどちらかに決め
られないか?たぶん、オレたちはほとんどがそんなふうで、良いことと
悪いことがごっちゃになっている。しかし、女は、悪い状態から、すぐ
に良い状態にすぐに切り変われるのだ。女は、おそろしく長い間、良い
状態にとどまれるのだ。あるいは、ずるくいられるのだ。
クレアは言った。「今から5年後には、わたしのことなんてまったく
思い出さないわ、エド」
「いつも思い出す」と、オレ。
高架鉄道の下のバンボーレンを過ぎ、ループ街を通って、駅まで2ブ
ロックのところに来た。
彼女は言った。「もう一度キスして、エド。ほんとうのことを聞いた
あとでも、まだ、したければ」
まだしたかったので、そうした。キャブが停まったときにも、まだ腕
は彼女に回したままだった。彼女が動いたとき、持っていた小さな小包
が床に落ちた。オレは拾って彼女に手渡した。そのとき、住所と名前を
覚えた。
オレは言った。「もしも100万ドルの宝くじに当たったら、マイア
ミのあんたのガールフレンドを通じて、連絡するよ!」
「しないで、エド。わたしにも、宝くじにも。自分の仕事をしっかりや
って、自分のままに生きて!駅にも来ないで、ここで赤帽に荷物を渡し
て!」
「しかし━━━」
「もう出発の時間よ、エド。キャブから降りないで!それがベスト、グ
ッバイ」
赤帽は、荷物を持って、ふたりは歩き出した。
「グッバイ」と、オレ。
運転手が訊いた。「ミランタワーへ戻る?」オレは言った。「ああ」
クレアがオレから離れてゆくのを見ていた。彼女は振り返らなかった。
駅の入り口の脇のポストに立ち止まって、小包を投函した。まったく周
りを見ることなく、ディアボーン駅へ入って行った。
◇
キャブはカーブを曲がったが、オレはまだ外を見ていた。それで、右
後方からカーブに入って来たキャブから、黒っぽい服の小さな男が降り
て、急ぎ足で駅へ入って行くのが見えた。
なにかが引っかかった。見覚えのある顔に見えたが、どこで見たのか
思い出せなかった。
通りを横切り、ディアボーン駅を北に向かった。運転手に言った。
「ミランへ戻ってという意味じゃない。クラーク通りのワッカー街へ行
って欲しい」
運転手は車を走らせながらうなづいた。
次の交差点で赤信号につかまった。そして突然、背後のキャブから降
りた男をどこで見たか思い出した。きのうの夜、ミランタワーのバーで
見たのだ。イタリア人のようで、オレはトーピードのように見えると考
えた。やつがベニーロッソだったのだろうか?
「停めて!」オレは運転手に言った。「ここで降ろして!すぐに!」
運転手は交差点を渡り終え、カーブの車の停止線に停めて、言った。
「急に、気が変わった?」
財布からドル紙幣を2枚渡して、釣りをもらわずに、キャブを降りて、
走って駅へ向かった。キャブで1ブロック遠回りして赤信号で止まって
戻るよりも、自分の足で走って戻った方が早く戻れるはずだった。
しかし、ハリソン街からポーク街に戻るのは、ぞっとする長い道のり
だった。駅前を横切る車の前に立ち止まりそうになったが、駅の入り口
を入るまで走り続けた。
駅に入って走るのをやめて歩いた。まわりを見回しながら。ここがこ
んなに広い場所だったとは思いもしなかった。クレアの姿はなく、彼女
を追っているかもしれない男の姿もなかった。
駅内に2つの人の流れがあって、どちらにもふたりはいなかった。ふ
たりのどちらも。案内所へ急いだ。オレは訊いた。「インディアナポリ
ス行きは何番線?まだ、出発してないなら」
「まだ、着いてない。12時15分まで入って来ない」
「11時15分の列車は?」と、オレ。「もう、出発した?」
「インディアナポリス行きで、11時15分発はない」
オレは時計を見上げた。すでに11時14分だった。オレは訊いた。
「11時15分発は、どこ行き?」
「2つある。セントルイス行き急行が6番線。1番線の19号列車は、
フォートウェイン、コロンバス、チャールストン━━━」
オレは振り向いて出て行った。
望みはなかった。2つの長い列車が1分の間に出てゆく。2つのうち
1つの列車にもたどり着けない。どちらもダメだ。フォートウェインま
での乗車券を買うカネも残ってなかった。
オレは見上げた。係員が5番線と書かれた鉄のゲートを閉めようとし
ていた。
まだ、とオレは考えた。絶望的だが、チャンスが1つある。赤帽だ。
さっきの赤帽を見つけることができたら━━━見える範囲に12人の赤
帽がいた。それぞれ別のホームに。みんな同じ顔ではなかった。ただ、
クレアの荷物を持った赤帽をよく見てなかったことに気づいた。クレア
ばかり見ていたからだ。
オレを追い越した赤帽がいた。オレは彼の腕をつかんで、訊いた。
「2つのスーツケースと小さなバッグを、女性のために運んだ?」
彼はキャップを後ろにずらして、頭をかいて、言った。「ええ、運ん
だかも。どの列車?」
「それを知りたい。15分前のこと」
「セントルイス行きに女性を乗せた。たぶんずいぶん前に。2つのスー
ツケースとバッグだけだったかは、正確に覚えてない。バイオリンケー
スもあったような気も」
オレは言った。「オーケー、忘れて!」そして10セント硬貨を渡し
た。ここにいる赤帽全員と話してみても、ムダだろう。さっきの赤帽を
つかまえたとしても、よく覚えていないのだから。
オレは考えた。たぶん、彼女は最初からどの列車に乗るつもりもなか
ったのだ。いっしょに駅へついて来させないようにした。彼女は行き先
を偽っていた。残りの話も偽っていたのだ。たぶん、駅の別の出口から
出て行ったかなにかだろう。
ベンチに座って、心配する代わりに、腹を立てろと自分に言い聞かせ
た。ミランで見たと同じ男がキャブから降りてきた、それはとんでもな
い思い違いだったかもしれない。キャブがあとをつけられていたことに
気づかなかった。それが同じ男で、彼がキャブのあとをつけて、ロッソ
だというのは、でたらめの推測だったかもしれない。シカゴにいるすべ
てのイタリア人がロッソという名前の殺し屋ではありえない。
ただ、オレはクレアに腹を立てる気になれなかった。
たしかに、彼女はオレを避けた。しかしそうすると言ったし、理由ま
で言った。
昨夜のあとでは、とオレは考えた。クレアに本気で腹を立てる気にな
れなかった。そして、オレが結婚し、どこかに住んで、子どもや孫がで
きたら、とオレは考えた。彼女との記憶は、ただの、愛の小さな思い出
に、なってしまうだろうと。
叫び出したりする前に、オレは駅を出た。南クラーク通りまで歩いて、
北クラーク行きの路面電車に乗った。
13
アムの室をノックした。「入って」と、声が聞こえた。オレはそうし
た。
彼はまだベッドにいた。
オレは訊いた。「起こしてしまった、アム?」
「いや、エド。30分前には起きていた。考えていた」
「クレアは行ったよ」と、オレ。「町を出て行った、たぶん」
「どういう意味だ、たぶんって?」
オレはベッドの端に座った。アムは頭の下に枕をふたつ置いて半分起
き上がって、言った。「それについて話してくれ!プライベートのこと
は省いて、あの娘がハリーレーノルズについて言ったことを、正確に話
してくれ!それに、昨夜ダッチになにがあったのか、今朝なにがあった
のか。最初から、エドが昨夜ここを出たときから順に」
オレは話した。すべて聞いて、アムは言った。「なんてすばらしい!
エドの記憶力には感心する。しかし、ストーリーにおかしな点があるこ
とに気づかない?」
「おかしな点?クレアが話した内容を変えたってこと?確かにそうだが、
オレたちが進めていた仕事とは、なにも関係しないのでは?」
「分からない。関係は、なにもないかもしれない。今朝、そして午後も、
オレは老いぼれて記憶力が悪くなったようだ。自分のしっぽを追う犬の
ように、どこにもたどり着けない気がする。たぶん、オレよりもエドの
方が意味が分かってる。オレはバセットを心配している」
「彼はどのあたりにいる?」
「心配なのはそのことでない。なにかが引っ掛かってる。なにかよくな
いことが。それがなにか分からない」
「どういう意味、アム?」
「どういうことなのか、分からない。エドは音楽に詳しい。音楽で言う
と、和音にいやな音があるのに、見つけられない。ひとつひとつの音を
弾いても正しいのだが、和音で弾くといやな音がある。その音はマイナ
ーとかメジャーとかディミニッシングセブンとかではない。雑音だ」
「楽器で言うと?」
「トロンボーンではない。だから、エドには分からない。しかし、聞い
てくれ!それはオレの内部にあって、誰かが、オレたちの上からなにか
を押しているが、なんなのか分からない。バセットだと思うが、なんな
のか分からない」
オレは言った。「それなら心配はやめよう!先に進もう!」
「先に進んで、なにをする?」
オレは口を開こうとして、また、閉じた。彼はオレに歯を見せて笑っ
た。
彼は言った。「エドは成長を始めている。なにかを学ぶ時だ」
「何を?」と、オレ。
「女とキスしたら、リップスティックをぬぐえ!」
それを拭いて、歯を見せて笑い返した。オレは言った。「思い出して
みる、アム。きょうは何をする?」
「アイデアは?」
「たぶん、ない」
「オレもない。1日休みを取って、ループ街に繰り出すか?映画を見て、
うまいディナーでも食べて、フロアショーを見よう!なにかいいバンド
の演奏を。昼も夜も休んで、オレたちの展望を取り戻そう!」
楽しい時間だった。昼も夜も。街に繰り出して、楽しんだ。しかし、
だめだった。なにかの感覚があって、それは、嵐の前に気圧計が下がる、
大気の静けさのようだった。オレでさえ、それを感じた。アムは、なに
かを待っているのだが、なんなのか分からない男のように、落ち着かな
かった。彼を知って初めてだが、少し気難しそうだった。3回殺人課の
バセットに電話したが、バセットはいなかった。
しかし、その話はしなかった。今見たショーやバンドの話をした。カ
ーニバルのことももっと話してくれた。おやじのことは全くしゃべらな
かった。
真夜中近くに、今日はここまでと言って、別れて家に帰った。オレは
まだ落ち着かなかった。たぶん、ひとつは暑さのせいだった。熱波が戻
ってきた。蒸し暑い夜で、明日はもっと暑くなりそうだった。
◇
おふくろが自分の室から呼んだ。「あんたなの、エド?」オレが答え
ると、バスローブを引っ掛けて出てきた。おふくろは室に入ったばかり
に違いない。まだ寝てなかった。
彼女は言った。「たまに、家に帰って来てくれて嬉しい。エドと話が
したかった」
「なに、マム?」
「今日、保険会社に行ってきた。死亡証明書を持って。保険会社は通し
てくれたけど、小切手はセントルイス支店から出るので、あと2・3日
かかるの。わたしはおカネがないの。エド、いくらか貸してくれる?」
「手持ちが2ドルしかない。銀行預金には20ドル少しある」
「少し貸してくれる、エド?保険の小切手が入り次第、返すから」
「いいよ、マム。とにかく、20ドル貸せる。数ドルは自分のために必
要なので。もっと必要なら、バニーに言って、いくらか貸してもらえる
ようにはできる」
「バニーは、今夜、しばらく来ていたわ。彼を煩わしたくない。心配ご
とがあって、スプリングフィールドの妹さんが、来週早々、手術するそ
うよ。少し悪い。来週仕事を休んで行ってあげるらしい」
「そう」と、オレ。
「でも、エドが20ドル貸してくれるなら、それで大丈夫。小切手は数
日しかかからないと言っていたから」
「分かった、マム。明日一番に銀行へ行ってくる。おやすみ!」
オレは自分の室へ入って、ベッドに行った。おかしな気がした。つま
り、何年もたってからそこへ戻ってきた気がした。自分の家みたいな気
がしなかった。ただ、見たことのある室というだけだった。時計は巻い
たが、目覚ましはセットしなかった。
どこか外で、時計が1時を打ったので、水曜の夜だと気づいた。おや
じが殺されてから、ちょうど1週間だ。
ある意味、それからずいぶん長かった気がした。ほとんど1年にも思
えた。それ以来、多くのことがあった。たったの1週間に。しかしほか
のこともあった。仕事に戻らなければならない。あまり長くは、仕事な
しではいられない。もう1週間だ。次の月曜には仕事に戻らなければな
らないだろう。だが、仕事に戻ることは、とオレは考えた。この室で眠
りにつくことよりも、もっと馴染みのないことだった。
クレアのことは考えないようにした。やがて、眠りに落ちた。
◇
目覚めたのは、11時近くだった。服を着て、キッチンへ行った。ガ
ーディはどこかへ行っていた。おふくろはコーヒーを入れていた。起き
たばかりのように見えた。
彼女は言った。「家にはなにもないのよ。もしも今から銀行へ行くな
ら、卵とベーコンを買ってきてくれない?」
オレは言った。「いいよ」そして、銀行へ行って、朝食用になにか買
って戻った。おふくろは料理して、食事が済むと、電話が鳴った。出る
と、アムだった。
「エドか?」
「朝食を食べたところ」
彼は言った。「やっと、バセットがつかまった。あるいは、彼がオレ
を。数分前に電話してきた。彼はうまくやったようだ。なにかが動いた。
彼は、焼き魚を盗んだネコのような声だった」
「すぐに行く」と、オレ。「少し、待っていて」
オレはテーブルに戻り、コーヒーカップを持ち上げて、立ったまま飲
み終えた。おふくろに、今からアムに会うと言った。
彼女は言った。「忘れていたわ、エド。昨夜、バニーが来ていたとき、
エドに会いたがっていた。エドに連絡しようがないので、メモを置いて
いった。来週、出かけることと関係あるらしい」
「メモはどこ?」
「居間のサイドボードだったと思うわ」
オレは途中でそれを取り、階段を降りながら読んだ。バニーは書いて
いた。「今週末にスプリングフィールドに行く理由は、マッジが話した
と思う。エドは、ゲーリーで保険を売ったアンダーズがスプリングフィ
ールドに引っ越して、彼を捜していると言っていた。オレがそこにいる
間に彼を捜して、なにか質問をしてもらいたければ、日曜の前に知らせ
て!どんな質問をして欲しいかも!」
メモをポケットにしまった。アムに訊いても、保険エージェントはた
いしたことをしゃべらないというだろう。それでも、バニーがそこへ行
くならやってみる価値はあるかもしれない。
◇
オレが着いたとき、バセットは少し先に来ていた。ベッドに座って、
目は前に見たときより疲れ、色あせていた。服は、そのまま寝ていたよ
うに見えた。ポケットに平たいボトルを入れて、茶の紙で包んで、コル
クの上でねじっていた。
アムはオレに歯を見せて笑った。陽気に見えた。
アムは言った。「ハイ、エド!ドアを閉めて!フランクはこれからビ
ックリニュースを言う。エドが来るまで待つよう言ったんだ」
ホテルの室は、暑く、風通しが悪かった。オレはハットをベッドにほ
うり投げて、カラーをゆるめ、ライティングデスクに座った。
バセットは言った。「警察は、あんたらが捜していたギャングを捕ま
えた。ハリーレーノルズ。ベニーロッソ。ダッチレーガンは死んでいた。
ただ━━━」
「ただ」と、アムが口を挟んだ。「彼らのだれも、ウォリーハンターを
殺してなかった」
バセットは続けようと口を開いていたが、閉じて、アムを見た。アム
は歯を見せて笑って、言った。「明らかだ、ディアバセット。明るく陽
気なあんたがその声の調子とおかしな口の形で言いそうなことは、そん
なことぐらいだ。オレたちに火中の栗を拾わせたのさ」
「なんだって?」と、バセット。「あんたらはハリーレーノルズの近く
にいたことも、会ったこともないだろう?」
アムは頭を振った。「そう、オレたちは会ったことない」
バセットは言った。「オレに借りを作ったな、アム。あんたはもっと
頭がいいと思っていた。ハリーがあんたの兄に興味があることを突き止
めて、ハリーを捜し始めたとき、あんたに手綱を預けた。いつかハリー
のところへ導いてくれると思ったからだ」
「しかし、そうしなかった」
「まったく、しなかった。オレを失望させたな、アム。あんたは1塁に
も達してない。警察は彼を捕まえた。あんたがギャングのことを言い出
した時から、彼らは無実だと分かっていた。あんたに言わなかったこと
は卑怯だったが、彼らはウィスコンシン州のワウパカの銀行強盗で指名
手配されていたんだ。ワウパカの住人たちによって、彼らは犯人と特定
された。報酬は住人たちのものだ。そして、ワウパカの犯行は、あんた
の兄が殺された夜だった」
アムは言った。「ひどいな、フランク。オレから何百ドルもせしめて
おいて、賞金ももらうつもりか?」
「いや、捕まえたやつのもんだ。喜びたいんなら、オレもしてやられて
る。コールドミートのダッチの賞金は誰ももらえない。ベニーは州外で
捕まった。誰がレーノルズを?巡回おまわりだ!」
「望みたいところだが、どのくらい損した?」
「彼らそれぞれにGの半分、500ドル。ワウパカで盗まれたカネは行
方不明。Gが40個、4万ドル。それには10パーセントの賞金が付い
ている。つまり、Gが4個、4千ドルだ」舌なめずりした。「しかし、
それは、どこかの預り金庫から、定期チェックかなにかで出てくるんだ
ろう。手の出しようがない」
「そりゃ、よかった!」と、アム。「オレの数百ドルは戻ってくる?キ
ャッシュならまけておく」財布をあけて、中を見た。「ここに来たとき
の400ドルは、今100ドルしか残ってない」
「とんでもない!」と、バセット。「あんたの誘いに乗って、もらった
カネに見合うものは出した。オレが知っていることはすべてしゃべった」
アムは言った。「あんたが返してくれる方に、賭ける!」
「賭けるだと?」
「20ドル!」と、アム。財布をまたあけて、20ドル紙幣を出した。
それをオレに手渡して、言った。「エドが賭け金を預かってる。賭けは、
数百ドルを、あんたがオレに自発的に、自分の意志で、今日中にオレに
返すというものだ」
バセットはアムを見て、それからオレを見た。目は、半分閉じてぼや
っとしていた。彼は言った。「オレは、そのような独りよがりの賭けに
は乗らないのだが」20ドル紙幣を出して、オレに手渡した。
アムは歯を見せて笑って、言った。「さて、ボトルで一杯やろう!」
バセットはポケットからボトルを出して、開けた。アムは長いひと口
を飲み、オレは付き合い程度でひと舐めした。バセットは長く飲むと、
ベッドの脇の床にボトルを置いた。
アムは、オレが座っているデスクの隣の壁に寄りかかって、言った。
「ギャングたちはどんなふうに捕まった?」
「違いって?」と、バセット。「まだなにもしゃべってない」
「そうだが、興味がある。話してくれ!」
バセットは肩をすくめた。「ダッチは今朝早く、夜明けに、ディビジ
ョン通りの路地で、死体で発見された。警察は、ダッチが裏で死んでい
たビルで、浅い眠りについていたレーノルズを捕まえた。ちょうど窓の
下でダッチが死んでいた」
オレは前にかがんだ。アムはオレの腕をとり、オレを後ろに引いた。
腕を取ったまま。
「どう思う?」と、アム。バセットに。
「レーノルズはやってないのは、確かだ。たぶん、ベニーだろう。レー
ノルズは、自分の窓の下に死体を置いたりはしない。しかし、ギャング
たちは互いに裏切り合っている。レーノルズの女━━━彼女がミランタ
ワーに住んでたことを警察は突き止めた━━━は、彼らの全員を裏切っ
ていた」
「その女は?」と、アム。
「シカゴではクレアレイモンドという名前で通していた。本名は、エル
シーコールマン。出身地はインディアナポリス。レポートによると、か
なり美人だった」
アムは、オレの腕を強くつねった。こう言っていた。「落ち着け、エ
ド!」不用意に大声で、訊いた。「だった?」
「彼女も殺された」と、バセット。「ベニーが昨夜彼女を殺して、現場
で捕まった。ジョージア行きの列車で。今朝、そこから長距離電話が入
った。ベニーは、女をナイフでひと突きしたところを捕まった。多くを
供述した」
「供述の内容は?」
バセットは言った。「シカゴから後をつけていた。ベニーとダッチは、
それぞれ、彼女がカネを持っていて、彼女とハリーがふたりを裏切って
ると考えていた。一方、彼らも、互いを裏切っていた。ベニーはダッチ
を殺したに違いない。なぜなら、ダッチの死体を、ハリーレーノルズが
すぐに捕まるところに置いたからだ。ベニーはまだ認めてない。つまり、
認めなかった」
「話はそれるが、フランク」と、アム。「なぜ、彼は、エルシークレア
コールマンレイモンドをナイフで?」
「現金を持って逃げていると考えた。たぶん、正しい。知らないが。と
にかく、後をつけた。彼女は列車のコンパートメントにいた。夜のあい
だに忍び込んで、カネを捜した。彼女は目覚め、叫び声を上げ、ナイフ
で刺された。しかしたまたま、ふたりの保安官が列車に乗っていて、コ
ンパートメントから出る前に捕まった。カネはそこにはなかった」
アムは言った。「ボトルを取って、フランク!もうひと口、密造酒を
味わいたい!」
バセットは拾い上げて手渡して、言った。「密造酒だと?高級スコッ
チだぞ!」
アムは飲んでから戻して、言った。「それで、今は、フランク?今は
なにを?」
バセットは肩をすくめた。「分からない。調書を書いたり、どこかへ
出かけたり。あんたはどうなんだ、アム?結局、あの事件は、ただのホ
ールドアップ殺人で、やった犯人を捕まえられないんじゃないか?」
アムは言った。「いや、フランク。そんなことにはならない」
バセットは、もうひと口、ボトルから飲んだ。ボトルの半分は無くな
った。彼は言った。「もうどうしようもない、アム、聞いて!もしもこ
れ以上なにもないなら、マッジがやったことになる。結局、オレが青信
号を出すまでは、保険会社は小切手を出さないだろう。しかしオレがぐ
ずぐずしている唯一の理由は、ウィルソンにまだ会ってないことなんだ。
たぶん、今から彼にあって、この件は終わりにする」
彼は起き上がって、洗面所へ行って言った。「ブタのように汚れた。
外出する前に、少し洗いたい」
蛇口をひねった。オレはアムに言った。「バニーはメモを残した。日
曜にスプリングフィールドに行くので、こう言っている」オレはメモを
出して、彼に手渡した。彼は読んで戻した。
オレは言った。「保険エージェントに会ってもらう?」
アムは首をゆっくり振った。
彼はバセットを見て、長く息を吸い込んで、ゆっくり吐いた。バセッ
トはタオルで手を拭いていた。メガネをポケットのケースに入れていて、
目がむき出しだった。
彼は言った。「さて━━━」
「数百ドルのことだが」と、アム。「ワウパカの4万ドルに手を乗せら
れる場所を知りたい?知るには100ドルかかる。そのために町の外へ
行かなければならないとしても?」
「4万ドルのためなら、100ドル払うよ!オレをかついでるのでは?
どうやって知った?」
「100ドル払って!」と、アム。
「どうかしてる!どうやって知った?」
「オレは知らない」と、アム。「しかし、知ってるやつがいる。それは
保証する」
バセットは彼をしばらく見ていた。それから、財布をゆっくりポケッ
トから出した。5枚の20ドル紙幣をアムに渡して、言った。「もしも
イカサマだったら━━━」
アムは言った。「話してやれ、エド!」
バセットの目はオレに向いた。オレは言った。「カネはきのうの11
時数分過ぎに、シカゴで投函された。クレアは自分宛てに送った。マイ
アミの局留めエルシーコール宛てに」
バセットの唇が動いたが、なにを言ってるのか全く聞こえなかった。
オレは言った。「あんたは自分の賭けに勝った、アム」預かっていた
2枚の20ドル紙幣を手渡した。彼はそれをバセットからもらった紙幣
といっしょに自分の財布にしまった。
アムは言った。「そんな深刻になるな、フランク!オレたちは、また
ひとつあんたが好きになった。今度は、バニーウィルソンにいっしょに
会いにゆこう!オレもまだなんだ」
バセットはゆっくり出て行った。
14
サハラ砂漠のように暑い日だった。グランドアベニューを歩いている
と、分ごとに暑くなった。オレはコートを脱ぎ、手に持った。それから
ハットを脱ぎ、手に持った。横にいるアムは、暑そうにさえ見えなかっ
た。スーツコートを着て、ベストもハットもつけていた。涼しそうに見
せるトリックがあるに違いない、とオレは考えた。
橋を渡った。水上のそよ風さえなかった。
ハルステッドでは、1・5ブロック南から、バニーのアパートに向か
った。階段を上り、室のドアをノックした。
中でベッドのきしむ音が聞こえた。スリッパでドアまで足を引きずっ
て歩き、ドアを少しあけた。オレだと分かると、大きくあけた。
「ハイ!」と、バニー。「今起きようとしていたところ。入って!」み
んな中へ入った。
バセットは、ドアの内側に寄りかかった。アムとオレは、歩いて行っ
てベッドに座った。室はオーブンのようだった。オレはネクタイをゆる
め、シャツの一番上のボタンをはずした。ここに長くいないことを望ん
だ。
アムは、おかしな表情を浮かべてバニーを見ていた。途方にくれて、
ほとんどうろたえているように見えた。
オレは言った。「バニー、こちらは叔父のアム。そして、こちらは、
おやじの件を担当している刑事のミスターバセット」
バニーを見ると、なにかに当惑しているようには見えなかった。なに
かあったとしても、くるまって寝ていたものといっしょに、ガウンに隠
れて見えなかった。ヒゲを剃る必要があった。髪はくしゃくしゃだった。
昨夜明らかに何杯か飲んでいたが、ひどい二日酔いではなかった。
バニーは言った。「会えてうれしい、バセット。あんたも、アム。エ
ドからたくさん聞いている」
オレは言った。「叔父は少し変わっているが、いいやつ」
バニーは起き上がって、ドレッサーのところへ行った。そこにボトル
といくつかグラスがあった。彼は言った。「みんな、一杯どう?」
バセットがさえぎって、言った。「あとにしよう、ウィルソン。座っ
てくれ!最初に、マッジハンターのアリバイの話を調べたい。別の角度
から見てみた。しかしどうも分からないのは、あんたが言っていた時間
が━━━」
アムは言った。「口を閉じてろ、バセット!」
バセットは彼に顔を向けた。目を怒りでギラつかせて、言った。「な
んだって、ハンター!オレのやり方に口を出すのか━━━」
彼はベッドに向かって一歩踏み出したが、アムが自分のことをいささ
かも気にしてないの見て、止まった。アムはまだバニーを見ていた。お
かしな表情を浮かべて。
アムは言った。「よく分からん、バニー。オレが考えていたやつとは
違う。人を殺すように見えない。しかし、ウォリーを殺したんだろ?」
◇
沈黙があった。薪に切り出せるほどの、沈黙があった。
長い沈黙。
沈黙はのびて、それ自身が、1つの答えになるまで続いた。
◇
アムは静かに訊いた。「保険証書は、ここに?」
バニーはうなづいて、言った。「ああ。そこの引き出しの一番上」
バセットは、ハッと目が覚めたようだ。ドレッサーまで行き、引き出
しをあけた。シャツの下に手を入れてなにかをつかんだ。手を引くと保
険証書在中とタイプされた、ぶ厚い封筒が出てきた。
彼はそれを見て、言った。「あたまがかすんで、どうもよく分からん。
なぜ、これがここに?保険の受取人は、マッジだろ?」
アムは言った。「彼はマッジと結婚する予定だった。彼女に好かれて
いて、彼女がすぐにつぎの夫を捜していることを知っていた。彼女のよ
うなタイプは、いつも結婚することを考えている。バニーのようないい
仕事を持つ男性が、彼女をサポートしてくれるなら、ウェイトレスの仕
事に戻りたくはなかった。彼女はもう若くはないし━━━そう、オレが
ダイヤグラムを説明する必要はないだろ?」
バセットは言った。「つまりこういうことか?彼は領収書のことを知
らなかった。マッジも保険証書のことは知らないだろう、と考えた。結
婚するまでは。しかし、なぜ保険証書を隠そうとしたんだ?」
アムは言った。「隠す必要はなかった。結婚したあとで、それがどこ
からか、ウォリーの持ち物の間からでも見つかるようにすればよかった。
マッジは、それを彼自身の印刷ショップを始めるのに使わしてくれるだ
ろう。そのように話を持ってゆくことができた。それが、ふたりの生涯
収入のように持たらされたからだ」
バニーはうなづいた。「彼女はウォリーにいつももっと夢を持って欲
しかった。しかし、ウォリーはそうしたくなかった」
アムはハットを脱いで、額の汗をぬぐった。彼はもはや涼しいように
は見えなかった。彼は言った。「まだ分からんことがある。バニー、そ
れは誰のアイデアか?あんたの?それとも、ウォリーの?」
バニーは言った。「正直に言うと、ウォリーのだ。彼は自分を殺して
欲しがっていた。さもなければ、オレは決してそんなことは考えなかっ
た。彼はつきまとい続けた。彼は最初から『オレを殺してくれ!』と言
ったわけではない。しかし、いっしょに飲み歩いているうちに、オレが
自分の店の開業資金を必要としていることを知った。そして、マッジが
好きで彼女もオレを。それでオレにつきまとい続けた」
バセットは言った。「つきまとい続けたとは、どういうことだ?」
「そう、彼はオレに、保険証書がどこにあるかしゃべった。仕事場のロ
ッカーの中。そして、それを誰も知らないと言った。彼はこう言った。
『マッジはあんたを好きだ、バニー。もしもオレになにかあったら』彼
は計画のすべてを話した。もしも彼になにかあったら、マッジが保険証
書の存在をすぐには知らないことが、彼女には都合がいい。それは、も
しも彼女がすぐにカネを得たら、カリフォルニアかどこかへ行って使い
果たしてしまう。彼が望むことは、彼女が安全に彼女のために投資して
くれる男と結婚するまでカネのことを知らないように仕組みたかった」
バセットは言った。「しかし彼は、自分を殺せとは言ってない。もし
も死んだらと言ってるだけだ」
バニーは頭を振った。「彼が言ったことはそうだが、それは、彼が言
いたかったことではない。彼はオレに言った。自殺したい願望はあるが
できない。誰かにそうしてもらうしかない」
バセットは訊いた。「その夜、なにがあった?」
「エドに話したように、12時半に、オレはマッジを家まで送った。1
時半ではなく。そのあとで、彼女は何時に帰ったか覚えてないだろう、
もしもオレが1時半だと言ったら、ふたりとも守れるだろうと考えた。
そのときまで、ウォリーを捜すのはあきらめていた。シカゴアベニュ
ーの川の近くに夜通しポーカーをやってる店を知っていた。オレはオー
リーンズ通りを歩いて、ほとんどシカゴアベニューまで来たとき、反対
方向から来るウォリーと会った。家を目指して、手にはビール瓶を4本
持って。かなり酔っていた。
彼は、いっしょに歩いて家まで送ると言ってきかなかった。運んでい
た4本のうち、1本をくれた。1本だけ。暗い路地を抜け道に選んだ。
街灯は路地の端までなかった。そこを通り抜けるあいだ、彼はしゃべる
のをやめた。オレの少し前を歩いた、ハットを脱いで、手に持った。そ
して、そう、彼はそうして欲しかった。もしもオレがそうすれば、マッ
ジと、そしてオレがいつも欲しがっていたオレ自身の店が手に入るのだ。
それで、オレはやった」
バセットは訊いた。「それで、なぜそんなことを━━━」
アムは言った。「口を閉じてろ、刑事!あんたは知りたいことすべて
知った。やつをひとりにしてやれ!今、すべてが分かった」
彼は歩いてドレッサーまで行くと、ボトルから何杯か注いだ。オレを
見たので、オレは頭を振った。3杯でやめて、もっともきついのをバニ
ーに渡した。バニーは飲むために立ち上がった。
バニーは、ごくごく飲むとバスルームに向かった。バセットがなにか
が起こってるのに気づいたときには、そこにたどり着いていた。「ヘイ!
ちょっと待て!」と、バセット。室を横切って、鍵がかかる前に、バス
ルームのドアノブをつかもうとした。
アムはバセットをつまづかせた。バスルームのドアはスライドして内
側から鍵がかかった。
バセットは言った。「なんてことだ、彼は━━━」
「ああ、フランク」と、アム。「いいアイデアでも?行こう、エド。外
に出よう!」
オレもすぐに外へ出たかった。
ほとんど走るようにして、階段を降りて、歩道に出た。
急いで歩いた。ギラギラした午後の太陽の下で。アムがオレがついて
来ていることに気づく前に、数ブロック歩いた。
彼は歩く速度をゆるめ、オレを見て、歯を見せて笑った。
彼は言った。「ポイントは2つあっただろ、エド?オオカミ狩りに行
って、ウサギ1匹!」
「もう、狩りには行きたくないね」
彼は言った。「オレも同じ。オレが間違えていた、エド。1時間前に、
あのメモを見て、バニーがやったことを知った。しかしそれまで気づけ
なかった。彼には会ったことがなかった。しかしなんだって、謝らなけ
ればならない?ひとりで会いにゆくべきだった。しかし、見世物のよう
にしてしまった。バセットといっしょに」
オレは言った。「メモがどうかした?あ!今、なにかに気づいた。バ
ニーは、名前のスペルを正しく書いていた。そのこと?」
アムはうなづいた。「そう、Anderz。アンダーズという名前を、
電話でエドから聞いただけで、エドはスペルも言ってなかった。その存
在も知らないと言っていた保険証書を見てなかったら、Andersと
書くだろう」
オレは言った。「メモは見たが、気づかなかった」
アムはオレの声が聞こえなかったのか、言った。「それは自殺でなか
ったことは分かってる。前にウォリーの心理的ブロックについて話した。
彼は自殺することができなかった。しかし、このような離れ技をするよ
うなところまで坂道をころげ落ちていたとは、夢にも思わなかった。ま
た思うのは、これが彼の人生だったら、エド、ちょうどよかったんじゃ
ないか?バニーにこのようなトリックを演じてもらって━━━」
「おやじは、バニーに良かれと考えていた」
「そう考えよう!良くなることは知っていたんだ」
オレは訊いた。「どのくらい前から、おやじはこれを計画していた?」
「5年前にゲーリーで保険の契約をした。レーノルズから弟の無罪に投
票するよう買収されて、有罪に投票した。レーノルズの手下にそのため
に殺されると考えたに違いない。
しかし、その当時、彼の心のなにかが変わったか、あるいは、気まぐ
れで、ゲーリーから逃げ出して姿をくらませた。レーノルズがシカゴに
いたことは知らなかった。知っていたら、バニーの手をわずらわせはし
なかっただろう。レーノルズのところへ行って、仕事を安上がりに済ま
せられただろうから」
「つまり、5年前から、そうしたかったと?」
「心では考えていたに違いない、エド。だからこそ、保険を契約した。
エドが卒業して良い職につくまでは、それで乗り切ろうと思っていただ
ろう。エドがエルウッドで働き始めたころに、たぶん、バニーに働きか
けを始めたのだろう」
オレたちは、信号が変わるのを待っていた。ミシガンブルバードを渡
ろうとしていることに気づいた。かなり歩いてきたことになる。オレが
思っていたより、ずっと先まで来ていた。
信号が変わった。「歩け!」オレたちは渡った。
アムが言った。「ビールは、エド?」
オレは言った。「マティーニを1杯だけやりたい!」
「それなら、いいとこを知っている。行こう!見せたいものがある」
「なに?」
「その周りには小さな赤い柵のない世界がある」
エピローグ
オレたちは、ミシガンブルバードの東側を2ブロック、アラートンホ
テルまで歩いた。中に入ると、特別なエレベータがあった。長時間、上
昇していた。何階まであるのか知らないが、アラートンは高いビルだっ
た。
最上階は、とてもシャレたカクテルバーになっていた。窓はオープン
で、涼しかった。このくらい高いと、風は涼しく、灼熱とはかけ離れて
いた。
南側の窓際のテーブルについた。ループ街まで見渡せた。明るい陽射
しがきれいだった。高くて細いビルは、空に向かっていくつも伸びる指
のようだった。サイエンスフィクションの表紙のように。実際に見ても、
まったく信じられないだろう。
「どうだ、エド?」
「地獄のように、美しいね」と、オレ。「しかし、ここはクリップジョ
イント」
彼は歯を見せて笑った。小さな笑いのしわは、目尻のしわになった。
彼は言った。「ここは、ファブロスクリップジョイント、略して、フ
ァブクリップさ、エド!ここでは、ありえないことが起こる。すべてが、
悪いこととは限らない」
オレはうなづいて、言った。「クレアのように」
「カウフマンを恐怖の底に、突き落としたエドのように。ワウパカのカ
ネがどこにあるか話すエドを見ている、バセットのうろたえた目のよう
に。彼は残りの人生を、エドがどうやって知ったのか、あれこれ悩みな
がら過ごすことだろう」
彼は声を出さずに笑った。「数日前、エドは年齢ゆえ、ビクビクして
いた。ウォリーは1対1の決闘をして、編集長の妻と情事を持った。エ
ドは自分はそれほど悪いことはしてないと思っているだろう。しかし、
オレはエドより少し年上だが、銀行強盗を12オンスの火かき棒で殺し
たことはないし、ギャングの女といち夜をともにしたこともない」
「もう終わったことだ」と、オレ。「すぐに仕事に戻らなきゃならない。
アムもカーニバルに戻る?」
「そうだな。エドも印刷工に?」
「たぶん」と、オレ。「ダメなことでも?」
「ダメな理由はまったくない。いい仕事だ。カーニバルにいるよりずっ
といい。カーニバルには保証がない。たまにカネが入っても、すぐ使い
果たす。遊牧民のようにテント暮らし。家を持たない。食事はまずく、
雨でも降れば気が変になる。生きる地獄だ」
オレは失望を感じた。もちろん、アムといっしょには行かないが、ア
ムといたいと思う分、アムもオレといたいと思っていて欲しかった。お
ろかなことだが、正直な気持ちだった。
彼は言った。「そう、それは生きる地獄だ、エド。しかし、エドがそ
れをやってみたいと思うなら、いっしょに行こう。エドががんばれば、
なにかが得られる」
「サンクス」と、オレ。「しかし、やはり━━━」
「オーケー」と、彼。「エドを言いくるめる気はない。ホーギーに電報
を打ってくる。そして、ワッカー街に戻ったら、荷物を詰める」
「ソロング」と、オレ。
握手して、彼は出て行った。オレはまたテーブルについて、外を見た。
ウェイトレスが他に注文があるか訊きに来たので、いらないと答えた。
巨大なビルの影が長くなって、湖の明るいブルーが暗いブルーになる
まで、そこにいた。冷たい風があいた窓から入ってきた。
それから、オレは立ち上がった。アムがオレなしで行ってしまったこ
とが、急に怖くなった。電話ブースを見つけて、ワッカー街を呼び出し
た。アムの室番号を言った。アムはまだそこにいた。
「エドだ」と、オレ。「いっしょに行く」
「待ってたぞ。オレが考えていたより、少し長くかかったな」
「家に走って帰って、スーツケースを詰める」と、オレ。「それで駅で
会える?」
「エド、オレたちは貨物列車で戻らなきゃならない。文無しだ。途中で
食事したので、数ドルしか残ってない」
「文無し?」と、オレ。「まさか!数時間前に200ドルあったのに?」
アムは笑った。「それが芸というものさ、エド。カーニバルのカネは
長くは続かない。聞いて!1時間後にクラーク通りとグランドアベニュ
ーの角で落ち合おう。そこから、貨物列車に乗り込めるところまで、路
面電車に乗る」
オレは急いで家に帰って、スーツケースを詰めた。おふくろとガーデ
ィがいなかったことが、うれしくもあり、残念だった。ふたりのために
メモを残した。
オレが着いた時には、アムはすでに角にいた。手にはスーツケースと
トロンボーンのケースを持っていた。新品だ。
オレがそれを見た様子を見て、アムは声を出さずに笑って、言った。
「出発のプレゼントさ、エド!カーニバルで、練習ができる。カーニバ
ルでは、騒音を出せば出すほど、みんな喜んでくれるんだ!そして、い
つの日か、カーニバルを出て、自分の演奏をしろ!ハリージェームズの
最初の仕事はサーカスバンドだった!」
アムは、ケースをそこで開けさせてくれなかった。路面電車に乗り込
み、そして降りた。それから、貨物列車の操車場まで歩いて、貨車の間
を突っ切った。
アムは言った。「オレたちは今、浮浪の民だ。ごった煮を食ったこと
は?あした1つ作ってやる。あしたの夜、カーニバルのみんなに会える」
列車は貨物を積んでいた。空いている貨車を見つけて乗り込んだ。
黄昏。貨車の中は薄暗かったが、トロンボーンケースを開けた。
◇
低く口笛を吹こうとした。なにかが喉までこみ上げて来て、そこに突
き刺さった。アムの200ドルになにが起こったのか知った。
それは、手に入る最高に近いプロの使うトロンボーンだった。それは、
金メッキされていて、マイナーの曲を吹こうものなら、明るく輝くだろ
う。それは、軽量モデルだった。それは、ティーガーデンやドーシーが
使うようなトロンボーンだった。
それは、次元を越えていた。
ケースからうやうやしく取り出し、手に持ってみた。持ったかんじと
バランスはすばらしかった。
ゲーリーの高校で習ったトロンボーンの演奏で、まだ覚えていたのは、
Cスケールの指使いだった。ワンセブンフォースリー。唇を触れて、最
初のノートが見つかるまで吹いた。ぼやけてだらしがないのはオレのせ
いで、トロンボーンのせいではなかった。注意深く音を見つけながら、
音程を上げた。
機関車のエンジンがかかり、連結器が引っ張られる振動がここまで伝
わってきて通り過ぎた。まるで、ひとつながりの爆竹が次々に爆発する
ように。貨車はゆっくり動き出した。
オレはふたたび低い音程に戻り、それぞれの音をもっと信頼できるも
のにしていった。演奏できるようになるまで、長い時間はかからない。
そのとき誰かが「ヘイ!」と叫んだ。見ると、オレのセレナーデがト
ラブルを引き起こしたようだ。貨車の制動手が横についてきて、叫んだ。
「そこから出るんだ!」貨車の床に手をついて飛び乗ろうとしていた。
アムは言った。「そのトラムを貸してくれ、エド!」オレの手から奪
い取った。出入り口の近くに行ってトラムを口に当てると、制動手の顔
めがけて、最悪のブロンクスやじの右下がりの音を鳴らした。
制動手は悪態をついて手を離した。数歩追ってきたが、列車が速度を
上げ、後ろに姿を消した。
アムはトロンボーンを返した。ふたりとも笑っていた。
オレは笑うのをやめて、マウスピースをまた口につけた。明るい音を
吹いた。クリアで地獄のように美しく、鈴のように、鳴り響く音、何年
も練習がいる音が吹けたのは、とてもラッキーだった。
それから音は割れ、アムが吹いた音よりもっとひどい音になった。
アムは笑い出した。オレはまた吹こうとしたが、できなかった。オレ
も笑い出したからだ。
少しのあいだ、オレたちは互いを見て笑っていた。笑いはさらにひど
くなって、止まらなくなった。そうして、貨物列車はオレたちを乗せ、
シカゴを出て行った。どちらも笑っていた。まるで白痴のふたりが笑い
ころげているかのように。
(終わり)