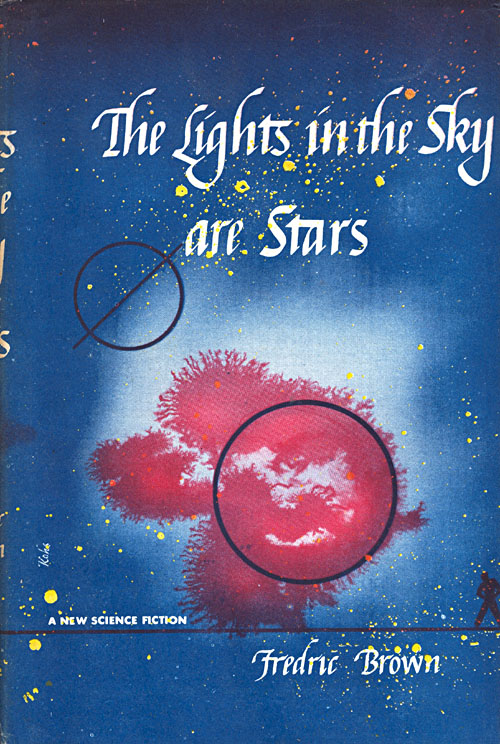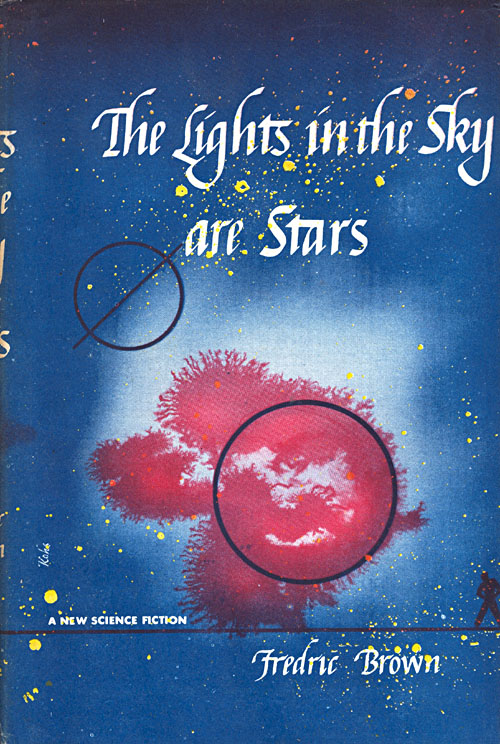ライトインスカイスター
原作:フレドリックブラウン
アランフィールド
1997
∨
1998
∨
1999
∨
2000
∨
2001
∨
エピローグ
∨
プロローグ
もう数日滞在する予定だったが、なにかが気を変えさせた。弟のビル
のバスルームの鏡に、自分のからだを映した。骨ばったからだ、水が
滴っ
て、片足で立っていた。オレは、立ち上がるにはもともと1本足しかな
い、背後でバスタブから水が大きな音をたたて
溢れ出ていた。オレは、
まさにその夜、出発することに決めた。
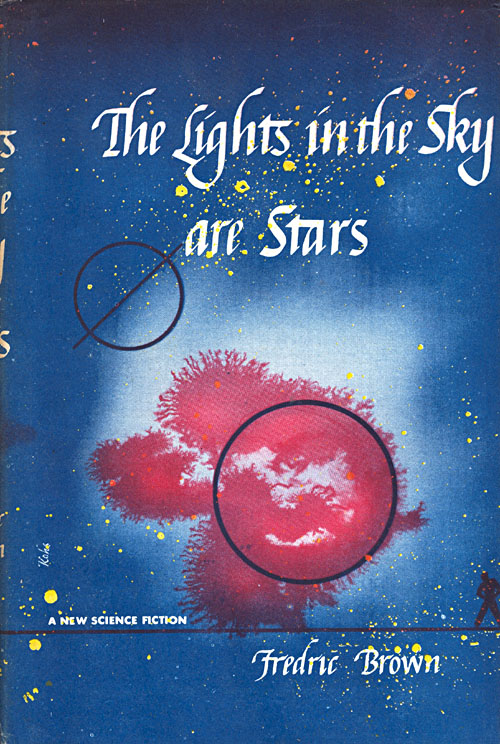
登場人物
マックスアンドリュー:ロケット技師、57才、片足が義足。
ビル:マックスの弟、安定した仕事、シアトルに住む。
マーリーン:ビルの妻。ふたりの子ども、イースターとビリー。
ロリーバースティダー:トレジャーアイランドの主任技師。
ベスバースティダー:ロリーの妻。
エレンガラハー:ラルフガラハーの未亡人。木星計画を推す。
ムバッシ:マックスの友人、神秘主義に取り憑かれている。
クロッカーマン、クロッキー:マックスの上司。
1997
バスタブから水が溢れ出るように、時間もオレから流れ出て行った。
ドアの長い鏡で自分を見てみれば、すべてはあまりに明らかだった。
鏡は、あんたにウソはつかない。もしも鏡に、あんたは57才に見え
ると言われたら、神かけて、そうなのだ。もしもなにかしたいこと、行
きたいところがあったら、すぐに始めて、出掛けた方がよい。残された
時間を使い始めた方がよい。なぜなら、流れ出て行くものを、あんたは
止めることはできないからだ。水ならバスタブの蛇口を締めれば止めら
れるが、あんたから流れ出て行く時間を止める蛇口はない。そう、それ
をゆっくりさせることはできる。規則正しく生活することで。高齢医療
を受ければ、世紀を越えて生きられるかもしれない。しかし、兄弟、あ
んたはすぐ70の老人だ。
あと13年で70、とオレは考えた。たぶん、普通よりもっと早く年
寄りになる、オレの時間の過ごし方では、片足だけの生活で、そう、オ
レの片足はヒザまでしかない、すでに、おごそかに暮らしている。
バスルームのドアに全身が映る鏡を置くのは、失礼だし非人間的だ。
若者にはナルチシズムを生じさせるし、老人には、不幸を与える。
からだを拭いてから、義足を付ける前に、体重計に乗った。126パ
ウンド。それほど悪くはない、とオレは考えた。失った14のうち、7
パウンドを取り戻した。自分をうまくケアできたのなら、数週間で残り
も取り戻せるだろう。すべて取り戻すまで、ここに留まる必要はなかっ
た。
また、自分の姿を鏡で見た。今度は、そんなに悪くなかった。からだ
に、長期の重力トレーニングしたよりもいい、鋼のような力強さがあっ
た。そして、磁力の足は、からだに一体となって、1つに見えた。
服を着て、下へ行ったが、みんなにまだ話してなかった。食事が終わ
って、マーリーンがイースターとビルジュニアを寝かすために上へ行く
まで待った。議論になると分かっていたから、子どもたちがいっしょに
いて欲しくなかった。
ビルシニアとマーリーンは、なんとかなる。オレは、ふたりの言うこ
とはなんでも賛成できる。しかし、ふたりに、オレは出発することを伝
えなくては。マックスおじさんは、どうしたらいいだろう?どうか子ど
もたちのそばを離れないでくれ!
ビルは、座って、テレビを見ていた。
オレの弟のビルは、髪はグレーで、中央は禿げていた。想像力がない
が、いいやつだった。晩婚だったが、幸せな結婚をした。良い安定した
仕事をして、良い安定した意見を持つ。
味はどうでもよかった。カウボーイ音楽が好きで、今も、座って聞い
ている。
宇宙から、それは来た。テレビ番組。地球の2番目の人工衛星、なに
もない宇宙に2万2千マイル離れた通信ステーションから、地球を1日
に1回周遊し、カンサスの上空にいつもとどまって、背の高いトウモロ
コシの上空2万2千マイルにいつもいる、そこからテレビ放送は送られ
てくる。
フルカラーで3次元で宇宙から地上へ。そこには、カウボーイハット
をかぶって、ギターをかき鳴らす男が、テキサス訛りで歌っていた。
孤独な祈りを
種馬のように猛り、自由に━━━
彼は種馬というより去勢馬に見えた。うるさい以外の印象はなかった。
ビルは、それが好きだった。
窓のところへ行って、夜の外を眺めた。美しいシアトルの夜景だった。
ビルは昔、窓に顔をすりつけて見ていた、30マイル離れた丘の上から
も。美しい夜景は、特に、今夜のような澄み切った夜に、美しく、暖か
く、明るい夜に、秋に見られる、そうした夜の1つだった。
下には、シアトルの街の灯、上には、夜空の光。
背後で、カウボーイが歌っていた。歌は終わり、ビルはイスの肘掛け
にあるスイッチを押して、コマーシャルのあいだ音をミュートにした。
突然のうれしい静けさの中で、オレは言った。
「ビル、オレは出発する」
彼は、そうしないで欲しいと思っていたことをしたが、そうするだろ
うことは分かっていた。歩き出して、テレビを完全に消した。
カウボーイの歌をあきらめた。オレと議論して、少しでも長く滞在さ
せようとした。
悪いことに、ちょうどそのとき、マーリーンが室に戻った。子どもた
ちは、議論を見ることなくベッドへ入ったに違いない。ビルは、彼を応
援するためにマーリーンが下に来るまでに、疲れ切っているとオレは計
算していた。しかし、今、ふたりを同時に相手にしなくてはならなかっ
た。マーリーンは、オレが言ったことが聞こえていた。
「だめ!」と、彼女。きっぱりと。ソファに座って、オレを見た。
「大丈夫」と、オレ。穏やかに。
「マックスアンドリュー、あなたはここに来てから、3週間にもなって
ない。あと2週間はここで静養しなくてはならない。そう、あなたも知
ってるはず」
「全部、休んではいられない」と、オレ。「しばらくは、軽い仕事から
始める」
ビルは、イスに戻った。「聞いて、マックス」と、彼。オレは彼の方
を向いたが、彼は、口ごもって、マーリーンの方を向いたので、オレも
そうした。
「あなたは、ここを去るほど回復してない」と、マーリーン。「よく分
かってるはず」
「それなら、オレは間違いなく外で倒れるわけだ。そうなったら、ここ
へ引きずり戻して、滞在させればいい。オーケー?」
彼女は、オレを見ていた。ビルは、咳払いをしてから、オレを見た。
「聞いて、マックス」と、彼。また、口ごもった。
「あなたと」と、マーリーン。「その、かゆような足」
「ちょうど1つが、かゆい」と、オレ。「さて、子どもたち、この議論
がまだ続くなら、いちいち話し手の方に向いて、目を回さなくていいよ
うに、いっしょのソファに座ってくれる?ビル、ソファの奥さんの隣り
に移動してもらえる?」
彼は、立ち上がって、移動した。まったく、優美でなかった。もとも
と、優美さは、ビルの長所ではなかった。反対にマーリーンは、結婚す
る前までバレリーナをしていて、あらゆる動きが優美だった。彼女は、
イースターの紙おむつケーキから発想を得て、あたかもバレーの一部で
あるかのように無意識に踊って見せた。それを見ていただれもがすばら
しさを感じた。
「どうか、分かって、マックス」と、マーリーン。「みんな、あなたに
いて欲しいし、好き。あなたは、迷惑でもなんでもない。それに、あな
たの気が済むように支払いもして、家計の助けになっている」
「家計の助けになんかなってない」と、オレ。指摘した。「オレの費用
を、1ペニーまで詳しく計算しているけれど。もしも週ちょうど50ド
ル支払わせてくれるなら、提案通りなら」
「あなたの好きな額を支払って、あと、2週間だけ滞在して!」
その誘いに乗りそうになった。「いや、だめだ、ダーリン、すまない」
オレは反撃した。「聞いて!あんたたちはふたりで、こっちはひとり。
しかし、あんたたちは援軍を呼べる。オレはイースターとビリーに夢中、
そして、ふたりともまだ、眠ってない。ここへ連れて来て、オレが去る
と言えば、ふたりは泣き出して、塩っ辛い子供たちの涙でオレの気が変
わるかも?」
マーリーンは、オレをにらみつけた。「あなたは、あなたは」
オレは、ビルにニヤリとした。「彼女がなにもしゃべらない理由は、
そうすることも考えていたからだ、しかし、それはできない。子どもた
ちを下に連れてくるために同じ口実を考えていたんだ」オレは、マーリ
ーンを見た。「しかし、それはまったくフェアじゃない。それは重要で
ないと、自分にも言えない。感情的には子どもたちをゆすぶれるかもし
れない。目的もなく。どんなに子どもたち、あるいはオレを、ゆすぶろ
うとも、オレは今夜、出発する。そう決めた」
ビルは、ため息をついた。座ったまま、オレを悲しそうに見ていた。
おでこが、グレーになりかけた弟。「そう思ってなかった」と、彼。
「ユニオン運送会社の仕事を、手配できそうだと言うつもりだった。良
い仕事」
「オレは、ロケット技師だよ、ビル。ユニオン運送会社ではロケットは
使わない」
「運行管理の仕事さ、マックス。その意味では、ロケットとジェット機
に違いはない」
「ジェット機は好きじゃない。それが違い」
「ロケットは、過去のものだ、マックス。それに、マイゴッド、生涯の
あいだずっと、メカニックのままでいることはできない」
「なぜできない?それに、くそっ、ロケットは、過去のものではない。
もっといいものを作り続けている限り」
ビルは、笑った。「ミシンのように?」
ミシンのエピソードを述べることはしない。
けれど、オレはビルに笑い返した。今までは、オレにとっても楽しか
ったからだ。たぶん、当時でさえ楽しかった。2週間の期間と、100
0ドル近いカネが掛かったが、ほんとうに良いジョークは、少なくとも、
それだけの価値はある。
ビルは、また、咳払いをした。しかし、マーリーンがオレを制して、
言った。「うう、彼をひとりにしてあげて、ビル。みんながなんと言お
うと、彼は出発する。だから、最後の夜をだいなしにしないで!」
オレは、室を歩いて行って、彼女の肩を軽く叩いた。「オレの天使」
と、オレ。「それを祝して、飲もう!」
一瞬、彼女は疑わしそうに見えた。オレは、辛抱強く言った。「大丈
夫、ダーリン、オレはアルコール中毒じゃない。ふつうの社会的な飲み
方ができないとか、かつては、それなしではなにも始まらなかったとい
う意味では、少なくとも。さぁ、オレの差し迫った出発のために、みん
なの分のマティーニをカクテルさせてくれ!」
彼女は、跳び上がった。「わたしが作る、マックス」彼女はキッチン
へ向かった。その足取りは、ダンスのようだった。ビルの目もオレの目
も、彼女を追った。
「いい女だ」と、オレ。
「マックス、なぜ、結婚して落ち着かない?」
「この年で?落ち着くには若すぎる!」
「まじめに」
「まじめだよ」
ビルは、ゆっくり頭を振った。そう、それが、オレが彼と彼の生活に
感じてるものだった。
マーリーンは、飲み物を運んで来た。みんな、グラスを手にした。
「マックスの幸運に!」と、マーリーン。「どこに行くつもり?」
「サンフランシスコ」
「また、トレジャーアイランドのロケット技師?」
「たぶん、しかし、すぐじゃない。つまり、最初に少し休んでから」
「しかし、なぜ、仕事に就けるまでここで休まないの?」
「なにかがそこで起こっていて、観察していたい、たぶん、手助けとか。
昨夜、テレビのニュースで言っていた」
「オレも聞いた」と、ビル。「上院に顔のきくヘンな女が、木星にロケ
ットを送るらしい。なんと、木星!火星や金星はどうなる?」
オレのかわいそうな弟、カネはあるがビジョンがない、目の見えない、
盲目の弟。
「聞いて、子どもたち!」と、オレ。「午前中のジェット機に乗るつも
り。8時だから、あと6時間しかない。提案がある。オレがここにいた
あいだは、優秀なベビーシッターを持つアドバンテージがあったわけだ
が、もうそれもなくなる。これが最後のチャンス。なぜ、ヘリを吹かし
て、シアトルじゅうを夜通し走り回らない?ナイトクラブやら、ライブ
パフォーマンスを見たり。1時半までに戻って来れれば、ビルがオレを
空港まで送ってくれて、飛行機の時間までたっぷり時間がある」
マーリーンは、非難するように見えた。「あなたの最後の夜は、ここ。
なにをすべきか分かってるはず」
「すべきことがなんであろうと」と、オレ。「あんたのするようにする。
する計画はいくつか考えてある。荷物を詰めたり。あんたたちがいなく
ても」
ふたりを説得して、そうさせた。
◇
オレのスーツケースは、用意ができて、ドアのそばに置かれていた。
重くはなかった。オレの旅行は軽く、軽く生きた。五体満足なことは、
あんたに結びついていて、それがなくなればオレたちは倒れることも、
神は知っていた。
オレの寝室の階段に戻った。あるいは、この3週間はオレの寝室だっ
たが、すべてのオレの私物が運び出された今は、また、客室に戻った室
に。そのとき、オレは電気を消さなかった。静かに室を横切り、静かに、
荷物を詰めた。隣りの室には、ビリーとイースターが眠っていたからだ。
窓を開けて、ベランダに出た。
美しい夜だった。暖かく、大気が澄んでいた。遠くのラニア山がすぐ
近くに見えた。
頭の上、遥か遠くの夜空の光は、星だった。その星に、オレたちは決
してたどり着けなかった。なぜなら、あまりに遠いからだ。星がいる場
所に、しかし、いつかはたどり着けるだろう。ロケットではだめでも、
なにか別のものではきっと。
答えはあった。
月には、たどり着けた?火星や金星にも。
オレはこの時代にいたことを神に感謝する。人類が突然宇宙に乗り出
した栄光の60年代に。最初のステップは踏み出した。人類が星へ向か
う、最初の3ステップは。
オレはそこにいて、それに参加していた。宇宙飛行士、第1クラス、
マックスアンドリュー。
そして今は?星にたどり着くためになにを?
星は━━━教えて!あんたが、星について知ってることは?
オレたちの太陽は、星だ。夜空の星は、すべて太陽だ。そのほとんど
が、周りを回る惑星を持つことを知っている。地球や火星、金星や、ほ
かの太陽系の惑星は、オレたちの太陽の周りを回っている。
そして、とんでもなく多くの星がある。
それは、神を汚すことにはならない。過少評価ではある。天の川銀河
には、だいたい、1千億の星がある。1千億の星、それぞれに惑星があ
る。平均で、1つの惑星としても、1千億の惑星がある。それらの惑星
のうち、10万に1つが、地球タイプとする。つまり、呼吸できる大気
があって、太陽からの距離が地球とだいたい同じで、温度も重力も同じ
くらいとする。すると植民地化して、普通の生活ができ、豊かで子孫を
増やせる惑星が、天の川銀河に100万あることになる。
100万の世界が、オレたちが到着し、降り立ち、生活するのを待っ
ている。
しかし、それは、ただの始まりに過ぎない。それは、ただ、この太陽
系が属する天の川銀河の話に過ぎない。
とんでもなく多くの銀河がある。天の川銀河にある星の数よりも、も
っと多くの銀河がある。つまり、少なくとも、1千億×1千億の星があ
る。
つまり、100万×100万の人類が居住可能な惑星があることにな
る。数字を導き出せただろうか?男、女、子どもを含めた全世界人口を
400億とすると、各自に25づつの惑星だ。ひとりでは増えないので、
カップルで考えると、50の惑星。平均の人口密度で考えて、惑星ごと
に30億とすれば、掛ける50、これはもちろん、最初の数で、その後、
それぞれの世界で人口を増やして行く。そうして、人類は、それぞれの
世界で、幸せに暮らして行ける?
あるいは、もしかしたら、ある惑星では、すでに別の人類が暮らして
いるかもしれない。それもまた、興味深いところだ。そのとき、どのよ
うにして子孫を増やして行く?
◇
サンフランシスコ、朝の3時15分。ジェット機の到着は遅れた。い
つものこと。エンジェルアイランドでタブロイド紙を買い、ユニオンス
クウェア行きのヘリタクシーに乗った。そこは、ダウンタウン近くで、
ヘリが着陸できる唯一の場所だった。がんばって、ノブヒルのマークの
あるところまで歩いて上った。少し疲れたが、それほどではなかった。
マークは、古いホテルで、ボロボロだが安かった。シングルなら1泊
15ドルで泊まれた。子どもの頃は、そこは港と橋が見えることで有名
だった。今は、もっと背の高いビルで周りを囲まれていた。しかし、7
階より上の室に泊まれば、カリフォルニア=メイソン交差点から、中華
街の低いビルを越えて、北東方面やロケット基地になっているトレジャ
ーアイランドを見ることができた。今夜も、たぶん、発着するロケット
があるだろう。遠くからだとしても、暗闇でロケットが離陸したり着陸
するのを見るのは、美しいシーンだ。オレは3か月間ロケットを見てな
かった。それを見ることが恋しかった。あまりに長く、そこから離れて
いた。ビルの右隅の高い階の室を頼んだ。
受付の男は、そのような室はないと言った。しかし、10ドル見せる
と、また調べてくれて、夜の間、1時間前にチェックアウトした室が1
つあって、その室で良ければ、まだ、入れると言った。オレは、その室
をとった。
その室は、散らかっていたが大丈夫だった。チェックアウトしたばか
りのだれかは、カップルらしく、さんざん酒を飲んで、ベッドを使って
一戦交えたらしく、タオルも数枚使っていた。夜の半分しかいなかった
としても、その客は、じゅうぶん元は取っただろう。
しかし、オレは、いやな気はしなかった。窓の近くにイスを引いて、
座り、トレジャーの光と上空を注意しながら、エンジェル空港で買った
タブロイド紙を読んでいた。興味のある特別選挙が含まれない記事は、
みんな読み跳ばした。
しばらくして、新聞は置いた。ロケットだけに集中した。そして、多
くのことを考えた。ビルの息子のビリーのことを考えた。6才で、彼に
は、まだ、夢があった。宇宙飛行士になりたがった。星に憧れていた。
そのことを手助けしてあげられるか、疑問だった。テレビのスペースオ
ペラのようなものも。しかし、それは重要でないと思った。彼が夢を持
ち続ける限りにおいて。星に憧れるスターダスター以上のなにか。変人
以上のなにか。オレたちのひとりひとりにも当てはまる。じゅうぶんな
時間があれば。
空に夜明けが近づいて、グレーになると、港の上空に霧が掛かり始め
た。ロケットが一度離陸し、着陸したら、もう見れなくなることを知っ
ていたので、オレは眠った。そのイスの上で。シワくちゃの散らかった
ベッドには、中でも上でも、横になりたくなかった。しかし、いびきを
かいて眠った。
メイドがオレを起こした、ドアをがたがた言わせて。
明るい太陽の光が窓に射していた。腕時計は、11時だった。7時間
も眠ったようだ。イスから立ち上がるとき、からだが堅かった。
オレは、メイドが行ってしまう前にドアを開けて、しばらく室を出る
ので、そのあいだに室をきれいにそうじしてくれるとありがたいと言っ
た。からだが堅く、汚れて、ヒゲも剃らないまま、朝食を食べに下へ降
りて行った。からだを洗って、ヒゲを剃るのは、バスルームがきれいに
なって新しいタオルになるまで待った。メイドは、オレが室をあれだけ
散らかしたと思っただろうか?しかし、彼女がなにを考えようと、重要
ではないと思った。
室に戻ると、きれいになって、整理整頓されていた。タオルを取って、
ヒゲを剃った。からだの堅さはなくなって、かなりいい気分だった。
トレジャーアイランドに電話して、主任技師のロリーバースティダー
をお願いした。彼の声が聞こえると、オレは言った。「マックスだ、ロ
リー。うまくやってる?」
「マックスって?」と、彼。
「マックスだけ」と、オレ。
ロリーはうなった。「マックスアンドリュー!ソノファビッチ!去年
はどこに?」
「あっちこっち。ほとんどは、ニューオリンズ」
「どこから電話を?」
オレは伝えた。
「ここへ早く来て、仕事を始めれば?」
「まだ、あと1週間は」と、オレ。「仕事に就きたくない、ロリー。ま
ず、ここで見守りたいものがある」
「選挙のこと?」
「ああ、それを昨日聞いた、シアトルで。スコアは?」
「ここへ来れば、話せる。あるいは、ちょっと待って、今夜は予定は?」
「ない」
「なら、いっしょに食事しよう、オレとオールドレディで。オレたちは、
まだ、バークレイに住んでる。ここは、あんたのとこから途中だ。6時
に引けるから、ゲイトまで来てくれれば、残りの道をいっしょに帰れる」
「いいね」と、オレ。「しかし、聞いて!今日の午後、離陸と着陸はあ
る?」
「1回だけ。パリのロケットが、5時15分に離陸する。オーケー、あ
んたを5時に迎えに行くとゲイトに伝言しておく」
◇
ロリーの妻のベスは、料理がうまかった。ビルの家の料理も、まずか
ったわけではなかったが、マーリーンは、料理については、ファンタス
ティックなところがあって、どんな味がするのか心配だった。ベスバー
スティダーの料理は、古風なドイツ料理だったが、彼女はプディングを
とても軽く作ったので、皿から流れ出たりしないように、濃い豊かなグ
レイビーソースをたっぷりかける必要があった。肉料理は、とてもやさ
しく、コーカサス地方の女性伝来のものに違いなかった。
エールビールといっしょにみんなで味わうと、ゆったり座って、リラ
ックスした。立ち上がりたくても、立ち上がれなかった。
「では」と、オレ。「選挙のことは、ロリー?」
「そう、フェアな選挙には見える」
「オレの言ってるのは、そのことでなく、それも聞きたくはあるが。聞
いて!聞いたところでは、昨日のニュースに数行出ていたらしい。カリ
フォルニア出身の上院に顔のきくガラハーという女が、木星を周回する
探査も可能にする法案を準備しているらしい」
「その通り」
「しかし、それがオレが知りたいこと。その詳細は?最初に、特別選挙
の行方は?州知事が、任期途中で死んだ上院議員の残りの任期を引き継
ぐために、だれかを指名できるはず」
「それは10年前までのこと。1987年に法規が改正されて、上院議
員の任期がその死によって中断された場合は、残りの任期が半分以上な
ら、つぎの会期が始まる前に、特別選挙を行わなくてはならない」
「うう、それが答え。それなら、ガラハーってどんな女?」
「エレンガラハー、45才、6・7年前、ロサンジェルス市長のときに
死んだラルフガラハーの未亡人。その後、彼女自身の政治活動を始めた。
以前から政治には関わっていたが、彼女の夫の興味あるものだけに限定
されていた。カリフォルニア議会で2期務め、そのあと今は、上院議員
になろうとしている。つぎの質問は?」
「彼女をかり立てるものは?彼女も、スターダスター?」
「いや、違う。しかし、技術研究所のブラッドレイの友人だ。彼を知っ
てる?」
「彼の書いたものをいくつか読んだ。少し難解だが、いい本だった」
「技師のひとりで、限界を設定している。アインシュタインの相対論の
信奉者で、光速を越えることはできないと考えている。しかし、とにか
く、彼はガラハー女にジュピターの飛行計画を売り込んだ。しかし、彼
女は当選するまでは、それに対して関わらないようにしている。カリフ
ォルニアのかなりな保守層が彼女の選挙を応援している」
「それなら、当選しないようにしなくては。対抗馬は?」
「レイトンという男がいる、ドワイトレイトン、サクラメント出身。そ
この元市長。出身と同じに曲がっている。保守主義者」
オレは肩を震わせた。「それだけ?」
「彼はテレビの時間をたくさん買って、しゃべりがうまい。彼が言うに
は、人類はもっとも貴重な資源、ウラニウムを無駄に捨てている。死ん
だ月や火星の上の価値のない植民地を維持するために膨大な量のウラニ
ウムを消費することによって。地球は、長期にわたって証明された非現
実的な夢を実現するために無駄な努力を続けることによって、地球自身
をだめにしている。火星だけで、1千億ドル以上を費やして、火星にい
ったいなんの価値がある?砂漠とわずかなコケだけだ。人間生活を維持
するじゅぶんな大気もないし、ひどく寒い。だが、年間、なん百万ドル
も使って、数十人の生活を支えようとしている、まったく正気の沙汰と
は思えない」
「分かった!」と、オレ。「それでじゅうぶん」
ベスが言った。「手伝って、ボーイズ!テーブルを片付けたいの」
オレたちは彼女を手伝った。あとで、リビングでエールを飲んでから、
ロリーに言った。「分かった、だいたいの状況は見えた。なにかできる
ことは?」
彼は、ため息をついた。「そう、手始めに、あんたは投票できる。今
すぐに、ここで登録すれば。明日が最終期限。バークレイにまた行って、
投票する前に1年間いた住所を申請しなくてはならない。ここの住所を
提出すればいい。その間、この家で間借りしていたと、オレたちは証言
する」
「いいね」と、オレ。
「今夜、湾を横断して戻って」と、ベス。「また、明日投票のために、
ここに戻るなんて無駄。今夜はここへ泊まって、朝、戻るときに投票す
ればいいわ」
「いいね、ベス、サンクス!」
「オレもそれを考えていた」と、ロリー。「それじゃ、あんたが投票で
できることに戻ろう。あんたは、サンフランシスコに多くの友人がいる。
そう、あんたは、ここ以外に、いくつかの地域でも登録できる。来週の
火曜日には、たぶん、3つか4つの投票に参加することができる」
「そう?5つか6つでは?」
「あと、あんたの友人たちが登録しているか確かめておいて。オレたち
は。彼らがだれに投票するか、あるいは、あんたの友人でなかったかは、
心配はしない。すべての投票が助けになる、マックス」
「確かにそう、すべての投票が助けになる。しかし、20人の投票を動
かしたところで、些細な力に過ぎない。くそっ、もっと強力な方法は?」
「くそっ、1つあるよ、マックス。あんたは、発言して来なかった。も
しも今、あんたがCMに出たり、テレビの時間を買い取って発言したら、
みんなを刈り立てて、熱狂に近いものを引き起こせる、あんたがどちら
の側だろうと、たぶん、思っていた人数より多くの者を遠ざけることに
なるだろう」
オレは、ため息をついた。「そのことでは、あんたが正しい。しかし、
まだ、なにかあるだろう。ガラハーに会って、頼もう。とにかく、彼女
に会いたい」
「町にいるとは限らない。しかし、彼女の広報マネージャーには会える。
リチャードシェアラー。広報室のあるセントフランシスのスウィートビ
ルへ行け!オレは昨日、電話で話した」
「なんの用事で?」
「彼が、トレジャーアイランドの昼休みに、技師たちと話しをするため
に、部下をひとり送ったと聞いたので。部下の時間を無駄にするな、と
言ってやった。彼は、トレジャーアイランドの投票を確実なものにした
かった。それで、部下を送れば、助けになると考えたのだ」
「なるほど」と、オレ。「木曜は、最初に彼と会って来る。明日は、自
分を登録したり、友人がほんとうにそうか確かめて来る」
◇
木曜は、3時半に目覚ましをセットした。リチャードシェアラーにそ
んなに早く会うためでなく、モスクワロケットが3時40分に着陸する
からだ。これは最初の着陸で、離陸は夜になるので、オレはそこで見れ
る。夜のロケットの着陸は、比較的まれで、それは、1回のフライトで
地球を半周し、大気圏外を数時間飛行するとき、夜の着陸が多少リスク
があるからだ。しかし、夜の着陸を見るのは、美しい。
室の窓のところに立って、暗闇の中で、それを見た。あんたも座って、
火炎の尾を見たことがあるだろう。説明の必要はない。もっともすばら
しい花火だし、その花火が、オレたちを月に、火星に、金星へ連れて行
って来れる。ほかの惑星にも、そのうち。
ロケットは、過去のものだ、とビルは言った。
それはそうだろうが、完全にそうはなってない。最初の1歩を踏み出
したが、そのあとガッツを忘れた。一時的に、一時的に違いない、自分
の方向を見失った。ほとんどの者が。
全員でない、このことを神に感謝する。オレたちの数百万が、オレを
含めた数百万が、星に憧れている。しかし今、なん百万が、オレたちの
生涯のあいだでは、それは不可能で、挑戦するだけの価値はないと考え
ている。
最悪なことは、反動主義者や保守主義者たちは、ビジョンがまったく
なく、けちで近視眼的にしか物事を見れず、今までやって来たことのす
べてが、なんの金銭的見返りのない時間と労力の無駄と考えていること
だ。
もちろん、そうだったが、それは、ステップ、最初のステップであっ
て、宇宙飛行士たちになにか発見を期待しているときでさえ、そうだっ
た。しかし、ジーザス、室の階段を上っているときに、宇宙の宝でいっ
ぱいの無限の室、最初の1段や2段で、宝が見つからなかったからとい
って、上るのをやめるだろうか?
保守主義者たちは、なん百万もいるが、オレたちのことを変人とかス
ターダスターと呼ぶ。彼らが心配なのは、税金であり、カネだ。借金生
活に入れば、彼らは言う、なぜその先を目指す?惑星は価値がなく、星
は、到達できたとしても、なん千年もの時間が掛かる。
一歩譲って、なん千年も掛かるとしよう。オレたちが今までの収穫で
満足して、その先に挑戦しない限り、それで終わってしまう。しかし、
挑戦し続ければ、あるとき突然なにかが起こりうる。火星へは、196
5年に、月に到達する計画より4年も早く到達できた。突然、Aドライ
ブが発見され、今までの化学燃料は使われなくなった。今オレたちは、
粗末なボートで太平洋を横断しようとしている男のようなものだ。海岸
から数マイル行ったところで、突然、超音速の飛行機を、粗末なボート
の代わりに与えられた。
星に挑戦しようとすることも、たぶん、それと同じで、恒星間距離に
挑戦するとき、Aドライブロケットは粗末なボートのようなものだ。A
ドライブが惑星間飛行を可能にしたように、恒星間飛行を可能にするな
にかを発見するかもしれない。しかし、残念なことに、オレたちが挑戦
し続けない限り、発見もない。今までの成果を全力で使って。これは、
月に挑戦し続けたことと同じだ。今までの化学燃料を使って、全力で月
に挑戦していたときに、Aドライブが発見された。
◇
9時に、オレは歩いて、セントフランシスのスウィートビルの131
5室へ行った。ドアには、『ガラハー選挙本部』と読めた。ブロンドの
受付嬢が、デスクの周りに書類を広げていた。オレが入って行くと、彼
女は顔を上げ、だれにでも笑顔で接するかのように、笑顔を見せた。
オレは、先にロリーの情報、候補者は町にいないことを確かめること
にした。「エレンガラハーは在室?」
「ミセスガラハーは不在。州北部の演説旅行に出ている、ソリー」
「なぜ、ソリー?リチャードシェアラーは?」
「しばらくしたら戻る。座ってお待ちを━━━ああ、今来た、この方が
待っている、ミスターシェアラー」
入って来た男は、ムーンフェースで背の高い赤毛だった。オレは自己
紹介をして、彼は握手をした。「なにかできることは、ミスターアンド
リュー?」彼の声は低く、ゆっくりで、ものうげなしゃべり方だった。
「エレンガラハーの選挙応援できることは?」
「オレのオフィスへ」彼は、内部オフィスへとオレを案内し、イスを勧
めて、自分はデスクに座った。デスクは、古い自動タイプのオールプラ
スティック製だった。
「あんたは、ミセスガラハーの友人、ミスターアンドリュー?」
「そう」と、オレ。「会ったことはないが、木星へのロケット計画をバ
ックアップしてくれるなら、オレは彼女の友人」
「ああ、スターダスター」彼は、ニヤリとした。「そう、スターダスタ
ーからのサポートを受けたいし、実際、候補者は、そのロケット計画に
執着している」
「どちらを認めてない?」
「オレは、ロケット計画を認めている。つぎの段階に進むときだと思っ
ていた。しかし、彼女が、選挙の直前にも関わらず、新聞社に語ったこ
とは、彼女を勝たせる以上の票を失わせることにつながる政治的なミス
だったと思っている」
「彼女は、選挙に敗れると?」
「分からない、ミスターアンドリュー。しかし、オレたちには、そのこ
とに関わった以上、しっかりしたスターダスターの票が必要だ」
「スターダスターの票は、心配いらない」と、オレ。「少なくともいく
つかのケースでは、数倍の票が得られる」
彼はかすかに笑った。「その真意を訊くのが怖ろしい、そのことを忘
れてもらうか、聞かなかったことにしよう」
「いいとも、オレは言ってない。しかし、あんたは、彼女が勝つかどう
か分からないと言った。その意味は?」
彼は長いこと黙ったままだった。彼のために、オレはこう言った。
「ときがたてば、彼女は負けるということ?」
「そうなることを、怖れている。予想外のことが起こるのでない限り」
「ドワイトレイトンが突然、予想外の事故にあうとか?」
彼は、デスクに向かって前のめりになっていた。それから突然、だれ
かに背中を押されたかのように、背筋を伸ばした。
「あんたは別に提案してない」と、彼。「クライストにより、あんたを
信じ、なにか計画してくれると」
「仮の質問だが、答えて!ガラハーのチャンスを手助けしたい?」
彼は立ち上がり、オフィスをゆっくり大股で歩き始めた、考えながら。
5往復してから、立ち止まり、オレを見た。「だめだ、それは彼女にと
って最悪なことになる、レイトンがほんとうの事故にあっても」
「なぜ?」
「なぜなら、レイトンはどうしようもないヘソ曲がりだから。だれも証
明できないが。しかし、人々の多くが、彼の側の団体でさえ、彼の言う
ことに疑問を抱いている。それが、票を失わせる。多くはないが、エレ
ンの不運な言動は、票を失わせることを怖れるが、逆に、後押しもして
くれる。エレンのほかの対立候補も、大衆が予想もしなかった方法で。
エレンの票を奪って最後の瞬間まで走り出すかもしれない。そのうえ、
レイトンが事故にあえば、熱狂的なスターダスターが仕組んだのではな
いかという遠い憶測が生じる。この国では、どこにいても、原因も分か
らないことでダメージをこうむって、エレンに及ぶこともある」
「そう」と、オレ。「さっきのことは、忘れて!レイトンがどうしてヘ
ソ曲がりだと?彼がなにをした?」
「サクラメント市長の時、突然、彼はものすごく金持ちになった。うわ
さでは、公共事業発注でキックバックがあったそうだ。しかし、それは、
うまく隠された。所得税官が、うわさに後押しされて、彼の前年の所得
を調査したが、良好の診断結果だった」
「正当な会計だったと?」
「彼の会計は、良好だった。政界入りの前、その分野でトップに近かっ
た。頭が良く、彼に反対するものなどいなかった。密接でも、徹底的に
追及した」
「密接なものとは?ガラハーの宣伝と無関係に、オレのカネでテレビの
時間を買い取る?オレが彼に公衆の面前で謝り、追及されても意に介し
ない?」
彼は、頭をゆっくり振った。「エレンに対して、反動が来る。ほかの
候補に影響を与えることなく、ある候補を攻撃できない。だめだ。あん
たにできることは残念ながらない、ミスターアンドリュー、益より害の
方が大きい。大規模なことであっても。もちろん、あんたの投票には感
謝している。知り合いのなかでゆれる、どんな投票であっても」
彼は、面会の終わりを告げるように、オレの手を握った。
◇
オレは、考えながら、歩き回っていた。なにかを考えたかった、ほか
のいくつかの投票でゆれながら、いくつか投票するような弱い行動を開
始する前に。なん百の投票でさえ、大きな助けにはならない。彼女の広
報マネージャーが最終的にオレのレベルに合わせて言ってくれたように。
ユニオンスクェアを過ぎたことに気づいた。中央に台があって、男が
演説していた。声は増幅されて、スクェアのどこにいても聞こえた。
「木星」と、男。呪いの言葉を吐くように。「この女は、オレたちのカ
ネを使おうとしている。少なくとも、10億ドルを。木星を回るロケッ
トを打ち上げるために。10億ドル、オレたちが支払う、ポケットから
出して、口にできるパンの代わりに!
10億ドル、それでなにが買える?別の価値のない惑星?それでさえ
買えない。ずっと近くの別の価値のない惑星。ロケットは着陸もしない。
着陸もできない」
台の周りは、少人数の群衆しかいなかったが、脇を通りすぎるスクェ
アじゅうの人々が、自分の仕事に急いでいたとしても、聞こえ、耳に入
った。
オレは台に向かって歩きながら、台に上って、やつをアホのように殴
ってやろうと考えていた。そうしたくて、両手がうずうずした。しかし、
それは助けにならない。そんなことをしても、投獄されるだけだったの
で、自分に票を入れることはできなかった。
なにもしなかった。一度だけ、イライラしただけ。
「惑星、木星は、4億マイル離れている、火星の8倍、人が立つことも
できない惑星。メタンとアンモニアの有毒な大気、あまりに濃厚な大気
のため、底では圧力で液体になっている。圧力がとても高いため、どん
なに強力なロケットさえ、卵の殻のようにつぶれてしまう。大気は数千
マイルの深さがあり、常に対流している。大気の下は?数千マイルの大
気層の下は、ものすごい圧力にさらされる。望遠鏡で、木星についてこ
こまで分かっている。人類にそぐわないことも。さらに、この巨大な惑
星は、強い引力に引っ張られて、宇宙船は接近さえできず、近づけば、
つぶれてしまう。あるいは、跳ね返されてしまう。木星の月は、地球の
月と比べて、もっと不毛で、冷たく、まったく人が住めない。しかし、
ミセスガラハーは、オレたちのカネを10億ドル、無駄にしようとして
いる」
ポケットの中で両手を丸めて、そこに立って、静かに聞いていた。エ
レンガラハーを選挙で勝たせる唯一の方法は、オレの決めたことをがん
ばることだけだと信じて。
◇
サクラメントに着いたのは、正午だった。空港は混んでいた。それは、
ある種の慣例に思えた。ヘリタクシーで町に入るのにも、いくつか難し
い問題があったが、1時半には、ドワイトレイトンのオフィスのあるK
ストリートのビルの前に着けた。
1分後に、オフィスの前にいた。
受付嬢は、タフだった。しかし、それほどはタフでなかった。最初に、
オレの仕事はとても個人的で、選挙キャンペーンにも関わり、レイトン
氏の選挙にも影響が大きいと話した。彼の広報マネージャーや秘書には
関係がなく、レイトン氏のみに関係する。
彼はそのとき忙しかったため、27分間待たされたが、中へ入れてく
れた。
オレは偽名を伝えると、スターダスターは、みんな、彼のキャンペイ
ンに反対しているという一方的な側の意見を興奮してまくしたてた。興
奮してしゃべりながら、1分もしないうちに追い出してくれと思ってい
た。
オレはもっと長くしゃべれたが、1分は途方もなく長く感じられた。
そのあいだ、オフィスのレイアウトを観察した。内側のオフィスにも外
側のオフィスと同様、鍵が付いていた。金庫の形とサイズも。それは大
きくて頑丈そうだが、古いタイプの鍵で、いい道具を使えば、10分も
あれば開けられそうだった。
オレは、必要な道具と、それを運ぶブリーフケースを買った。9時ま
で時間を潰し、それから、レイトンのオフィスに盗みに入った。
泥棒用の警報はなかった。唯一のチャンスだった。
金庫を開ける必要はなかった。デスクを最初に見た。1つだけ鍵の掛
かった引き出しがあって、そこには1つのものしか入ってなかった。赤
の台帳だった。
中の項目は、レイトンの手書きだった。それを確かめるために、デス
クにあるほかの書類と比較した。名前、日付、数量、パーセンテージを
示すサクラメント市への売上げ数字さえも。彼を、6回は監獄へ送り込
めるだけのじゅうぶんな証拠があった。
奇妙さと体系的なことは、会計士の心情だった。
金庫にはカネがあり、それを盗んでも、良心は痛まなかったが、リス
クは負いたくなかった。オレはすべきことをしに来て、それは、カネよ
りもっと重要だった。幸運に溺れたくはなかった。
台帳を簡単に包んで、セントフランシスのリチャードシェアラーのオ
フィスに郵送した。
サンフランシスコに戻ると、すぐにベッドに入った。
◇
正午直前に、シェアラーに電話した。
「小包は届いた?」と、オレ。
「ああ。どちら?」
「それを送った者。ここでは名無し、特に電話では。それをどう扱う?」
「一番いい方法を決めかねている。不安を感じる」
「不安を感じる必要はない!」と、オレ。「州警察に持って行け!それ
だけ!しかし、オフィスの周りに新聞記者が集まって来るから、もっと
も興味のありそうな数ページのコピーを手渡すだけ」
「しかし、どこで手に入れたと言えばいい?」
「どこで手に入れた?簡単な包みでサクラメントから、あんたに郵送さ
れて来た。包み紙も警察に提出すればいい。そこには指紋はない。住所
も、新聞の切り抜きで作ってある。あんたは、レイトンの部下で、彼の
やり方を憎むやつがいると予想する。台帳は、重要なものは、レイトン
本人が書き込んでいる。盗まれた証拠はない。たぶん、今でも盗まれた
ことに気づいてない」
「聞いて!あんたは、これで、なにが欲しい?こっちはなにをすれば?」
「2つできることがある。1番目は、オレに飲み物をおごること。2番
目は、そのとき話す。オレは15分後までに、ビッグディッパーバーに
いる。オレが分からなくても、オレの方は分かる」
「分かる気がする。昨日、オレのオフィスに来なかった?複数回、投票
するとか言って」
「しっ!」と、オレ。「複数回投票することは違法なことは知ってる?」
タクシーにビッグディッパーと言って、そこへ行った。通り過ぎたこ
とはあったが、入ったことはなかった。しかし、静かでいいところだっ
た。ブース席に座って、数分して、シェアラーが来た。
彼は、興奮してるようにも心配してるようにも見えた。「あんたの提
案を考えていた」と、彼。「記者たちに見守られながら、州警察に行く
という、それは最高の賭けだ。それも考えるが、明日まで待つ。土曜の、
しかも午後遅くまで。土曜の夜のニュースで放送されて、日曜の新聞に
載る。それがベストな公表のしかた。見ものだし、ワクワクする」
「そこまで遅らす理由は?郵便の消印から、受け取ったのは今日と分か
る」
「それは簡単、レイトンのものかどうか分からなかったことにすればい
い。レイトンの手書きかどうかも知りようがない。オレを窮地に追い込
むために、だれかが一杯食わせようとしているのかもしれない」
オレは顔をしかめた。「あんたはほんとうに、オレがあんたをかつご
うとする可能性があると考えている?」
「まったくない。しかし、冷静になって考えると、それも考えておく必
要がある。オレ自身に、多くの容疑が掛かって来る。とにかく、明日の
午後まで、確認のために待つ。いくつかのコピーも、その過程で取るか
もしれない。それを、記者たちに手渡す。オーケー、ドリンクをおごっ
た、つぎにして欲しいことは?」
「選挙のあとまで、待ってもらう。エレンガラハーは、それまで忙しい。
しかし、彼女に台帳を送ったのはオレだと告げて、彼女と会う約束を取
って欲しい。彼女は、オレと会って話してくれる?」
「会って話す?たやすいこと、オーケー、ほかには?」
「それだけ、約束できることは。ガラハーに頼んでくれたら、うれしい。
オレが戻って来たと、彼女に知って欲しいので」
彼はドリンクをすすってから、オレを見た。「あんたはロケットには
乗れない。それは分かっているはず。たとえ、エレンがそうして欲しく
ても。高齢のパイロットは」
オレは、手で彼を制した。「オレがおかしいと考えてる?高齢のパイ
ロットについては、オレの方がよく分かっている。オレは、57だ。そ
う、オレは乗ることはできない。しかし、後押しはできる。そして、そ
れがオレがやりたいこと」
彼は、うなづいた。「エレンは、あんたにふさわしい宇宙計画のベス
トな仕事に推薦してくれると思う。ふつうなら、もちろん、10に1つ
もチャンスがないところでも」
「あの台帳を手に入れたことで、エレンガラハーが当選する確率は増え
る?」
「同じことだが、会議を通して請求書を得ることで、別のなにかが出て
来る。あんたは、すべての対立候補のオフィスを盗みに入ることはでき
ないだろう?」
オレは、彼にニヤリとして、言った。「できるかも」
◇
選挙は、見ものだし、ワクワクした。そのニュースは、ちょうどよい
ときに暴露され、テレビも新聞も、そのほとんどを伝えた。レイトン側
は、最後の絶望的な努力を続けた。レイトン本人も、汚名を晴らすため、
テレビで無実を訴えたが、名前を明かさぬ誰かからの指示で、選挙レー
スから撤退することを発表した。最後の数分で、サクラメントの6つの
地域で勝敗が逆転し、エレンガラハーがすべての地域で優勢となった。
◇
その夜の8時、ベスとロリーとオレは、対立候補が負けを認めるのを
見ていた。テレビをつけて、音は小さくして、なぜなら、オレたちはみ
んな、エレンガラハーの顔を見たかったし、なにを言うのか聞きたかっ
たからだ。彼女は、ロサンジェルスからサンフランシスコ行きのフライ
トに乗り、8時37分に、エンジェルアイランドに着いたらインタビュ
ーを受ける予定だった。
ベスは、冷蔵庫にシャンパンボトルをしまっていた。選挙が正式に終
了したら開けるつもりで。
みんなのグラスに注ぎ、勝利を祝った。
シャンパンを飲んで、みんなでしゃべった。8時35分に、テレビを
見ていると、ジェットポートのインタビューアにカメラが切り替わった。
それで、オレはボリュームスイッチをオンにした。
「たいへん濃い霧」と、彼。「この敷地内の視界は、ほとんどゼロ、ガ
ラハー上院議員がここへ来るのを待っているが、ジェット機が着陸する
のを見ることができない。レーダーのみの助けで着陸することになりそ
う。今、やって来た、時間通り、音が聞こえる」
「ああ、なんてこと」と、オレ。「ジェット機は、レーダーだけで着陸
するらしい、もしも」
クラッシュオ音が聞こえた。
そこへ行こうとして立ち上がったが、ロリーがオレを制して、言った。
「ここでニュースを見た方が早い!」
だんだんと、時間ごとに分かって来た。飛行機は、かなりクラッシュ
して、多くの乗客と乗組員が即死し、傷を負ってだれも助からなかった。
副操縦士は助かって、救助されたとき意識があった。レーダーも無線も
同時に故障し、地面から数ヤードのところだったので、やり直しができ
なかったと言った。エレンガラハーの広報マネージャーのリチャードシ
ェアラーは死亡。技術研究所のドクターエメットブラッドレイは死亡。
「ひどいジェット機」と、ロリー。
ガラハーは生きていた。意識がなく重傷だったが、生きていた。すぐ
に、エンジェルアイランドの救急病院に運ばれて、容体について、でき
るだけ報告された。
霧の中で、救急車のサイレンがもの悲しく響いた。ひどいサンフラン
シスコ、ひどい霧、ひどいジェット機、すべてがひどかった。
オレたちは、座って、待った。シャンパンは、温まって、気が抜けた。
ロリーは、それをシンクに流し、代わりに、冷たいビールを出した。オ
レは、自分のグラスに手を出さなかった。
11時過ぎになって、ガラハー上院議員の容体の報告があった。彼女
は生きていて、助かりそうだったが、ひどい重傷だった。緊急手術が2
回行われた。なんか月も入院することになるだろう。しかし、回復する
ことは、ほぼ確実だった。
リチャードシェアラーは、彼女に、台帳を送ったのはだれか、ほんと
うのことはまだ話してないだろうとオレは思った。そうに違いない。彼
女は、たしかに、それを訊いただろうが、彼女にすぐに伝えなければな
らない理由はない。彼女とふたりだけになる時間があって、どうしても
それをまず伝えようとしたのでない限り。
そう、そんなことは簡単にはありそうもなかった。彼女の広報室は、
彼女も含めて7人いて、シェアラーを除いた5人は、ロサンジェルスに
いるあいだ、ブラッドレイもいっしょに行動していた。彼女とシェアラ
ーが、ふたりだけになる時間はあり得そうになかった。
ついに、オレは、ロリーが注いでくれたビールのグラスに口をつけた。
それは、シャンパンのように温まって、気が抜けていた。
つぎの朝、オレは、ロリーの下で、トレジャーアイランドで働き始め
た。
1998
ロケットの仕事。ロケットの仕事は、なくなりつつあるが、なくなる
のは、ずっと先の話だ。これらのロケットは、数百マイルだけ宇宙に出
て、すぐまた、地球に戻って来る。運行しているロケットは、ニューヨ
ークとパリ、モスクワ、東京、ブリスベン、ヨハネスブルグ、リオデジ
ャネイロ。サンフランシスコで製造されたロケットは、月や火星を目指
す予定だが、まだない。これらの真のロケットは、ニューメキシコやア
リゾナから離陸する。それらを運用する政府は、ロケット技師に対して、
おかしな考えを持っている。ロケット技師は、50を越えてはならない
という。政府はまた、ロケット技師は、両足が本来のものでなければな
らないとも考えている。オレは、2番目のルールを満たさないが、惑星
間の仕事をもらっている。
(つづく)
1999
ワシントンのエレンから、1月末。「おお、マイダーリン、今夜、こ
こにいて欲しかった。でなきゃ、わたしがそこへ。
この疲労感と鈍い頭痛がなくなって欲しい。そうすれば、少しはハッ
ピーにリラックスできるのに。しかし、頭痛はなくならない。今日達成
できたことを伝えたい」
(つづく)
2000
千年!お祝いしよう!ほんとうにお祝い!イェーイ、ハッピーニュー
イア!ハッピーニューミレニアム!バーは、人々でごった返し、3重に
も4重にも輪ができていた。オレは進もうとしたが、できなかった。ド
リンクは、通過して行った。だれかが追加のドリンクを持って、連れを
捜していた。肩をすくめて、オレに渡した。「運がいいね、おっさん!」
ほかの人に買ったドリンク、買われたドリンク、世紀の終わりのお祭
り騒ぎ、世紀末の躁状態。背中を叩かれ、背中を叩き、意味もなく握手
をし、中や外に焦点が移る。そのとき、群衆は薄くなり、溶けてゆき、
最後のオレたちは閉店で追い出され、夜の外へ、今はワイルドな夜へ、
寒く、澄んで、静かな。どこかへよろよろ歩き、通りを上がったり、下
がったり、公園と思われる芝生を横切った。
プールを渡る橋、まだ静かで暗いプール。
橋まで行くと、黒の水の下にある低いレールを見下ろして立った。水
はとても静かで、とても黒く、反射する星が見えた。静かな暗い水面の
下で、光がいくつもやさしくダンスしていた。水、そこで生命は進化し
た、水の中でオレたちは誕生し、進化し、そこで泳ぎ回って、空中へ這
い出し、陸上へ、動物の目で見上げ、夜空の光を見ていた。そう、今、
酔いながら、水の光、反射する星を見ていた。
空に向かって落ちて行った、星に向かって。
◇
また、白の室、しかし、今度は、悪夢ではない、ただの夢。あるいは、
本物?だれかが、オレの方に身をかがめている。栗色の髪のだれか。し
かし、目や心に焦点が合って来ると、それはエレンでなかった。看護婦
だった。白の制服に、エレンのような栗色の髪、しかし、エレンでなか
った。
声もエレンでなかった。オレに言っているのではない。「意識が戻っ
た、ドクターフェル」
ドクターフェル、ベルが鳴った。あんたが好きじゃない、ドクターフ
ェル。この古代のリズムはなんだ?あんたが好きじゃない、ドクターフ
ェル。理由は、言えないが。しかし、オレが正しいことはよく分かって
いる。あんたが好きじゃない、ドクターフェル。
看護婦は後ろに下がって、オレは首を回して、彼を見た。大きな男で、
鉄のようなグレーの髪、澄んだグレーの目、顔は、折れた鼻を除けば、
オレをホテルまで連れてきた宇宙飛行士の顔によく似ていた。
「しゃべれる?」と、彼。声は低く、反響した。信頼できる男の声だっ
た。
「あんたのことが好きだと思う、ドクターフェル」と、オレ。
彼は、オレにニヤリとした。「患者はみんな、そのリズムのことをあ
れやこれや言う。名前を変えた方がよかったかも」と、彼。肩越しに
「あんたは、もう、行っていい、ミスディーン」
「気分は?」と、オレに。
「まだ、分からない。なにか悪いことでも、外で?」
「露出、肺炎、栄養失調、精神錯乱、それだけ。なにか覚えてる?」
「プールに落ちた、それだけ。自分で出た?」
「そう、泳いでいたが、深さは、ヒザまでしかなかった。しかし、あん
たは、端の近くに横たわって、濡れて、凍えていた。どのくらい経って
から救出されたか、神のみぞ知る。1つ言っておく。もしも、それが3
0分遅かったら、あんたはここにはいない。あと1つ、別のことだが、
そんなふうにもう一杯と飲み続けたら、その1杯があんたの最後になる、
どこかへ落ちなくても。分かった?」
「ええ」と、オレ。
「ラッキーなことに、あんたはアルコール中毒にはなってない。だから、
普通の飲み方、社会的な飲み方に反しないように警告する必要はない。
しかし、もしもそのような飲み方をしたら」
「分かってる。オレがアル中でないと、どうやって知った?」
「あんたの弟や友人のクロッカーマン氏から。ふたりとも、ここにいる。
あんたの弟は近くにいる。午後の面会時間に来る」
「ふたりが、海岸からここへ来てると?ちょっと待って、ここはワシン
トン?」
「ここはデンバー。あんたは、デンバーのカーリー記念病院にいる」
「どのくらい長く?今は、なん日?」
「11日間いる。あんたは、新年最初の日の午前5時に運び込まれた。
今は、1月11日火曜」
「なん年の?」オレは、彼の口から聞きたかった。
彼は、奇妙な顔でオレを見た。それから、言い方を工夫して言った。
「2千」と、彼。「2千年」
◇
ニューミレニアム、とオレは考えた。オレは、また、ひとりだった。
21世紀、3番目のミレニアム。(21世紀が2001年から始まるな
んて言ったのはだれだ?)
未来。2千年のことをいつも考えていた、未来のこととして。195
0年代、オレが、まだ、十代だったころ、それは信じられないくらい遠
い未来だった。それまでの日々がなんの意味もない、特別な1日だった。
今、それが来て、そこにオレはいる。
ここで今、生活して行くなら、自分と仲良くしなければならない。真
実と向き合わなければならない、なんの隠し事も痛みもなしに。あまり
に痛い目にはあいたくない。
もう年寄りだということを認めなければならない。宇宙に出て行くに
は、年を取り過ぎている、惑星までだとしても。若いころに、オレはチ
ャンスをつかみそこなった。50代後半に、どんなにわずかだとしても、
奇跡的な2回目のチャンスがあったが、それもつかみそこなった。そし
て、オレは実際、今60だ。もうつぎのチャンスはない。だから、なに?
多くの人が、宇宙おたくで、ふつうに生活している、宇宙へ行けなくて
も。みんな生きているじゃないか?
それを受け入れろ、とオレは自分に言った。ここからなにかを目指せ
ばそれでいい。ほんとうに悪いことなんて、もう起こらない、なぜなら、
失望するようなことには2度と近づかないからだ。エレンを愛したよう
な。彼女の愛ほどすばらしいものがほかになければ、彼女の死ほど悲し
いことは2度と起きない。
思い出せ、決して忘れるな、あんたは決して地球から出発しなかった
し、今後も出発できない。この先は丘を下り降りるだけだということを
思い出せ。
あんたは、期待が大き過ぎた。ひとりの男が持てる期待より多くを持
ち過ぎた。あんたが望めるよりもっと多くを、人類が達成すると期待し
過ぎた。
人類は、このミレニアムのあいだには、星に到達するだろう。その前
のミレニアムの最初には、1000年には、どこにいた?十字軍が誤っ
た戦いは、剣にやりに弓矢で戦った。そのミレニアムの最後には、地球
を出発し、一番近い惑星に到達した。
このミレニアムの最後の前は、どこまで行ってるだろうか?
いや、あんたはそれを見れない。しかし、あんたは人類の一部だから、
その到達の一部でもある。手助けはできる。あんたは乗ることはできな
いが、生きてる限り、押す手伝いはできる。ロケットを押すことを助け、
人類が星に到達する助けになれる。
◇
栗色の髪の看護婦が、ランチを運んで来た。かなり体が弱ってること
に気づいた。しかし、食べることはできて、少し食べた。
看護婦がトレイを片づけるときに、面会時間はなん時からか訊いた。
ビルが来るまでに昼寝したいと思ったが、あと30分だったので、眠ら
ないことにした。
代わりに、ムバッシのことを考えた。チャンムバッシ。
もしもオレでなく、彼の考えが正しければ、どうする?そう、それも
あり得る。不可能なことはなにもない。今ここで、だれかが人類の限界
を決められるとして、物事は、今、あるいは、究極的に彼の心にあるす
ばらしくも神秘的なものによって実現されうる?
今ここで、だれが、心と物のあいだの関係を正確に知っている?人間
は、物のかたまりの中に、心を囚人として捕らえている。一方が死ねば、
とオレは考える、もう片方も死ぬ。しかし、体が心を動かせる、として
も、今あるいは究極的に、心の力が体を動かせるとも言えるのではない
か?
それが、正しい道なら、とオレは考えた、ムバッシにもっと力を与え
られるし、彼は道を発見するひとりになれる、少なくともそれを踏み台
にしてさらにステップアップできる。
しかし、それはオレのすることじゃない。それをあえてやろうとした
ら、オレは自分をからかうだろう。今まで、じゅうぶん自分をからかっ
て来た。ロケットは、オレのラケットだった。ロケットに執着する。ロ
ケットを押し改良するのを手助けし始めよう。
◇
「ハイ、マックス!」と、ビル。「戻って来てくれてうれしい!」
オレは握手をして、言った。「全部、戻って来た」オレがなにを言っ
てるのか気づいて、オレの心配をするのはやめようと思うだろう、もし
も心配していたら。
彼は、イスを引いた。
「まず」と、オレ。「ここの明細は?だれがカネを立て替えた?」
「大丈夫、クロッカーマンがあんたの手助けをしてる。彼が立て替えて、
銀行残高を調べて、ここの請求分はじゅうぶんあると言っていた。後で
返済すればいい」
「どうやって、銀行の残高を調べた?」
「確かに。あんたから2回カネが必要という電報をもらって送った。そ
れは想定内、あんたが仕事に復帰するとき、オレたちのいずれかに、2
00ドルくらいの借金があるが、心配はいらない」
「いいね」と、オレ。「もう1つ、フェルと話したが、どのくらいここ
にいなければならないのか訊くのを忘れた。彼とは話した?」
「今、ちょうど来るときに彼に会って訊いた。彼が言うには、あと10
日で旅行もできるそう。しかし仕事に戻るには、その後、少なくとも1
か月。シアトルに来て、いっしょに過ごそう?マーリーンも子どもたち
も大喜びする。オレももちろん」
「すぐ決めないとだめ、ビル?」
「もちろん、そんなことはない。強いるつもりはない。選択の余地があ
ればと言ってるだけ。クロッキーもムバッシもロリーも、みんなあんた
のためにしている。いい友人を持ったもんだ、マックス」
「それに、いい親戚も、ビル」顔を彼に向けて、まっすぐ見た。「聞い
て、ビル!シアトルに行くと決めた場合、1つだけ言いたいことがある、
みんなに聞かれる前に」
「いいとも」
「ビリーのこと。もしもオレがビリーに」オレは言い始めた。ビリーに
夢を与えたら、しかしこれはビルの言葉じゃない。「もしもオレが宇宙
の話をして、彼をスターダスターにさせようとしたら、気にする?」
「マーリーンとオレは、すでに話し合った」と、彼。静かに言った。
「答えはノー、気にしない。ビリーがなにをして、なにになりたいかは、
彼の問題」突然、ニヤリとした。「成長して気が変わらない限り、あん
たから押される必要はない。彼は、あんたがそうだったのと同じくらい、
すでにそうなってるよ、マックス」
「いいね」と、オレ。「それなら、ビル、1か月の1部は、たぶん、い
っしょに休養のために過ごせる。最初の2週間でなく、たぶん、良くな
ってからの2番目の2週間、強くなった方が子どもと過ごすのに都合が
いい。子どもたちは、病み上がりの身にはかなり手ごわい」
「すばらしい!マーリーンにも、2番目の2週間、いっしょに過ごせる
と言っておく。ほかの友人は?最初にだれと過ごしたい?オレから伝え
ておけば、書く手間が省ける」
「まだ、決めてない。しかし、代わりに知らせてくれたら、感謝する、
ビル。電報なり電話で、3人ともに、オレは退院して元気だと伝えて!
手段は任せる。やってくれる?」
「もちろん」
「電報代や電話代のレシートは残しておいて!あと、ここまでの旅費も」
彼は、笑った。「電報や電話代はいいが、旅費までは心配いらない。
うちの家族の休暇だし、オレは前から、デンバーまでドライブしたかっ
たんだ。マックス、ここは昔、カウボーイの町だったそうだ。もっとも
大きな町だったと思う。古き良き西部ミュージアムに展示されてる。オ
レがどこのホテルに泊まってるか当てられない方に、賭ける」
「う〜ん」と、オレ。「気取った大牧場のようなところだとは言わない
で!」
彼はどこかに泊まって、人生の時間を楽しんでる。オレが意識と一貫
性を回復したことをすまないと思う。なぜなら、彼は、ふたたび大人に
なって、家族の元に帰らなければならないからだ。
オレの弟は、馬に乗り、カウボーイになって、過去に生きている。オ
レの驚くべき弟。
◇
手紙がなん通か来た。1つは、マーリーンからで、オレと会えること
が彼女にも子どもたちにとっても、うれしい、ビリーは特にオレが来る
ことで大喜びしていたと書いていた。
ベスバースティダーからの手紙。「ロリーがひどく忙しいので、代わ
りに、わたしが書いている。彼は仕事を変えようとしている、マックス。
トレジャーアイランドの仕事でここしばらく、楽しくないことがある。
それは、監督たちと多くの点で意見が合わなくなっている。それで、別
の仕事に変えて、週末にここへ引っ越してきた。まだ、主任技師だが、
小さなロケットポートの方で、給与もかなり下がった。しかしそれは問
題ない、彼が仕事していて楽しければ、そして、彼がそうしたければ。
技術的な点では、すべての権限が与えられている。だれを雇い、だれを
クビにするか、各仕事の時間配分をどうするかといったことに制限はな
い。ここのポート監督たちとはうまく行っている。彼らは数ドル節約す
るために、角を削ったりしている。
わたしたちが、どこに引っ越したか知ったら、喜ぶと思う。シアトル
だから。今から、あなたは2羽の鳥を放てる、ロケットの発射とともに、
あなたの訪問を祝して、あなたの弟とその家族と同じ町に住めるので。
その方たちと知り合になれたらと思う。あなたの義理の妹さんにも会え
てよかった。ロサンゼルスのパーティで、あなたの学位所得のお祝いで、
覚えてる?
家は買わなかった、見て回る時間がなかったので。先週末にここで捜
して、しばらくのあいだ住むアパートを借りた。あなたのための客室付
き。引っ越しは土曜と日曜の予定で、支払も済ませて、あなたを迎える
準備もできている。あなたは来る、その点を争わないで!ちょっと待っ
て、ロリーが肩越しに覗いて、なにか付け足したいそう。彼にバトンタ
ッチするので、ベスがサインする」
ロリーのずんぐりした手書きに変わった。「いっしょに来てくれると、
うれしいマックス。LAの前の仕事に戻るつもりだとしても、戻りたく
ないなら、シアトルでいつでも仕事に就けるよう1つ取っておいてある。
ベスの、仕事の割り当ては自由に決められると書いてある通り。アゴを
上げて」
オレは、アゴを上げた、手紙にあるように。そして、シアトルの仕事
の方に決めた。
もう1通は、つぎの日届いて、決められなくなった。ムバッシからで、
簡単な走り書きだった。それは、病気が完全に治るまでのあいだ、なに
がなんでも、彼のところへ行って、そこで過ごすべきと書いてあった。
「マックス、オレが思うに望むのは、オレは成功間際にいる、助けがい
る、ここへどうか来て」
違う物事についてのようにも見える。
言ってることは、成功間際にいること、その意味は、テレポートでき
るようになったか、あるいは、すぐにできると思っているかだ。
いったい、どうやって助ける?
あるいは、暗いマントをはおって、好奇心を煽って、驚かそうとして
いる?
しかしジーザス、いったい?
そう決心するのは難しかった。2日後に、クロッキーから手紙が来た。
「マックス」と、彼。「ムバッシのことが心配だ。彼は、神秘的戯れの
1つに毒されている。断食して、ドラッグもやっている。危険な組み合
わせだ。あまりにやせて、影が映らなくなった。オレが話す常識に耳を
貸さない。こんなことを長く続けていられない。
もしも、退院するまでに、心配なら、そうしなくても、咎めることは
しないが、招待に応じて、彼を訪問して欲しい。あんたなら彼といっし
ょにいて、まともに戻せるかもしれない。彼は、トライしたいことすべ
てを、トライしようとしている。餓死してなければ、ドラッグもやめら
れると思う。いや、彼はそうすることの意思が強すぎるだけなのだ。し
かし、やってることが危険なら、同じことだが。
なぜそうなのかは、神のみぞ知る。しかし、仏陀を除いて、あんたは、
だれよりも、彼に影響力がある。彼はあんたが必要だと思う。
もしも彼を訪問すると決めたら、いつ来るのか知らせて!オレのヘリ
で送る、そのあいだ、着くまで話ができる」
それが、オレに決心させて、フェル医師の予想の10日より3日早く、
退院した。どんなに元気で力が余ってるか、誇張し過ぎたかもしれない
が、それで退院できた。
◇
クロッキーは、最後に会ったときと、まったく変わってなかった。な
ぜそれが驚きなのか、分からない、たった2か月なのに、それは驚きだ
った。たぶん、その2か月は、数年の2倍に思えたからだろう。
彼は、オレの手を痛いほど握って、言った。「戻って来てくれて、う
れしい。会いたかった。ちょっとカフェで、ヘリのところへ行く前に話
そう」
クロッキーは、ヘリの運転中に話すことは決して好きじゃないことを
思い出した。地上で車を運転しているときも。オレは、うなづいた。
コーヒーを飲み終えてから、ムバッシのことを訊いた。
「新しいことはなにもない。2日間、彼と会ってない。しかし、聞いて!
ムバッシのところへ行く前に、あんたのことを少し話そう。オレといっ
しょの仕事に戻るんだろ?」
「ま、まだ分からない、クロッキー。考えてない」
「仕事は空いている、不在のあいだ、あんたのために取ってある。あん
たが必要だ、マックス」
オレは、ニヤリとした。「それは、オレが去った日のことを言ってる
んじゃない。まじめな話、オレは、またしばらくは、メカニックに戻り
たいと思う。それは、オレが必要とするものだ、とにかく、しばらくは。
グリス、オイル、砂、煤で汚れた手、肉体労働」
「マックス、もう若くはない。一生、メカニックではいられない」
「あと数年は、できる。そのあとは、分かった。オレのために、仕事を
空けておかなくていいよ、クロッキー」
彼は、肩をすくめた。「それはあんたの問題だ。しばらくは空けてお
く、気が変わったときのために。そして、しばらくは、メカニックの仕
事もあげられる、しかしなんだって」
オレは、頭を振った。「LAでなく、クロッキー。あんたの前の助手
が、グリスだらけのサルとして働いていたら、お互いにとってすばらし
いことじゃないか?自分がどこで働くか分かっている」オレは、ロリー
が仕事を変わったこと、彼からオファーを受けていることを話した。
「オーケー、そうしたいんなら」オレが、LAポートでメカニックを希
望しなかったので、彼がホッとしたことが分かった。
「クロッキー」と、オレ。「最近新聞を読んでなかったが、なにか契約
が公表された?」
彼は、なんの契約が知っていた。うなづいて、言った。「クリーガー、
チャーリークリーガー」
名前は、記憶になかった。しかし、クロッキーは知っているように見
えた。「いいやつ?」と、オレ。
「まぁまぁ」
それは、オレが聞きたいことで、その話がしたかった。実際になにが
起こっているのか、その詳細をクロッキーはどこまで知っているのか分
からない。訊きたくもなかった。その話については、木星ロケットの製
造に関する驚愕の事実を知ることになって、オレの心が警鐘を鳴らした。
「ムバッシについては?」と、オレ。
「考えてなかった、マックス。話すようなことは、なにもない。彼に会
えば、すぐ分かる。たぶん、ここで話すよりもっとよく」
「なら、時間を無駄にしないで、そこへ行こう」
◇
ノックしても、返事はなかった。ドアの下から、ピンクの四角い包み
がはみ出ていた。引っ張り出して開くと、ピンクの電報の包みだった。
それは、オレがおととい送った、オレが行くことを伝える電報だった。
遅くとも24時間前には、彼の室に届いていたわけだ。
ドアは、鍵が掛かってなかった。オレたちは中へ入った。オレたちは
どちらも、来るのが遅すぎた、なにが起きたか知るのには遅すぎたこと
を知っていた。
中は、滑らかな表面に、埃が薄く積もっていた。
小さな室のドアは、室に家具はなく、小さな室があって、中からボル
トで締められていた。1回だけノックした。すると、クロッキーがオレ
を見たので、オレはうなづいた。彼は、オレより50パウンドは重い。
彼は、バックステップしてから、肩から体ごとぶつかった。ボルトは、
外れた。
ムバッシは、笑いながら、そこに横たわっていた。背中を下にして、
シーツの上に、腰布だけで。あばら骨は、鳥カゴのようだった。目は、
大きく見開き、上のだれかをピンポイントで凝視していた。
緊急電話ルーチンの前に、チェックルーチンを行った。しかし、オレ
たちはどちらも、外側のドアをノックして返事がなかったときから、遅
すぎたことを知っていた。
ムバッシはそこにはいなかった。体はあったが、ムバッシはどこに?
ムバッシは、どこか別の場所へ行ったと信じたい、単に行ってしまっ
たのではなく。
◇
オレは、死すべき運命でなく、生まれ変わりや個々の不死を信じたい。
別の体で、また、よみがえったらと思う。神がオレを救ってくれるとか、
天国のフワフワの雲の端から見守ってくれているとか、呪われた家の汚
い窓枠からでもいいし、ふんころがしの鈍い目を通してでもいい、どん
な手を使ってでも、神に見守られていたい。どんなことをしても、オレ
は見て回りたいし、いろんな場所に行きたいし、歩き回りたいし、星に
も行きたい、宇宙を抜けて、いくつもの宇宙を抜けて、オレたちが神に
なったら、それまでは、神が存在することを信じてなかったし、オレた
ちが彼になるまでは、存在もしてなかったが故に、それさえも信じられ
ないだろう。
しかし、オレは間違っていて、今も間違っている。間違っていると言
ってくれ!あんたが示してくれ、オレは間違っていると。ムバッシは笑
っていた原因はなんなのか、教えてくれ!
あんた自身が、神よ、あんたがオレに間違っていると示してくれ!
2001
「そう、ここにしよう、ビリー」と、オレ。
オレは、ヘリを丘の後ろに停めた。それからふたりで、サイトをリン
グのように囲む丘の1つへ登った。10月の晴れた夜の5時だった。太
陽は、低いところにあった。木星ロケットの離陸まで、あと3時間あっ
た。しかし、オレたちより早く、いい場所を取ろうといくつかの丘に人
々がいた。8時3分の離陸時間までには、丘は人々で埋め尽くされるだ
ろう。
「そう?マックスおじさん、フェンスまで降りる?」
「大丈夫、信じてくれ!」オレは、少年に、ニヤリとした。「近づきた
いのは分かるが、心配しないで!離陸サイトの端で見たときよりも、も
っとロケットに近い」
43フィートの高さで、それは立っていた。美しかった。なんという
美しさ。細身でスラリとして、輝いている、おお神よ、これ以上、言葉
が出て来ない。新しいひとり乗りロケット、今までのロケットでは行け
なかったところまで行ける、別世界へ、さらにその先へ。行こうとして
いる場所に、さらに近づいて。
ビリーのそばかす顔に、失望の色が浮かんだ。「オーケー」と、オレ。
「時間は、たっぷりある。フェンスまで降りて、ロケットを見て来てい
い!ただし、見たらすぐ戻ってくること。離陸は、ここからの方がよく
見える」
オレは、彼が丘を駆け下りて行くのを見ていた。今、10才だった。
なんて早く、4年が経ってしまったことか!このロケットのことを知っ
てから、最初に、エレンガラハーのことを聞いてから。おお神よ、目的
に近づこうとして、なんて早く、月日が経ってしまうことか!落下する
物体のように、一定の加速。エレン、あんたとともにすぐに、とオレは
考えた、2年だったのか、30年だったのか?フラッシュのように過ぎ
去った。光の速さ?時間にも速度がある?
オレは、ブランケットを広げて、そのうえに座った、ロケットを見な
がら、ビリーを見ながら。彼は今、高い鉄網のフェンスに立っていた、
なるべく近くで見ようと顔を押しつけながら。
1960年に戻って、オレの10才のころは、惑星間ロケットはなか
ったが、もしも1台でもあって近くで見れたら、すぐに好きになっただ
ろう。
今、1台を目の前で見ている。大声で泣き出したい気分だ、なぜなら、
木星へ旅立つときに、それに乗っていないからだ。しかし、61才は、
年を取り過ぎて、大声で泣くことができない。あんたは今では、でかい
少年さ、と自分に言い聞かせた。
日が沈み始めた。息子は成長する、オレの息子ではないが、今まで持
った息子のなかで一番近い、丘を登って、オレの方へとぼとぼ歩いて来
る、目を星くずのように輝かせて、オレの隣りのブランケットの上に座
った。
失われたものを、彼の目が憧れて見ている。地球出身の宇宙飛行士の
顔だ。ケージに囲まれた顔。
埃、多くの人々が集まって来る。沈黙、ほとんどの人が。これから起
こることに驚く。沈黙。
埃、明るい流体の光が下へ流れていた、下へ、これから始まろうとし
ているところへ、下へ、ビリーの目の中の光が、地球を離れる準備がで
きてるように、目に光を宿す男のところへ、地球というちっぽけな2次
元の表面から脱出して、3次元の存在として泳ぎ出すために。
脱出、オレたちは、なんと、このちっぽけな場所から、脱け出したか
ったことか!その必要性は、物理的欲求を満足させる方向とは別のある
方向でなにかをしたいというあらゆることから動機づけられている。そ
れが、奇妙だがすばらしい道へ導く。芸術や宗教、禁欲主義や占星学、
ダンスしたり酒を飲んだり、詩や大騒ぎ。これらすべてが脱出だ。なぜ
なら、外への脱出の真の方向が最近分かった。無限へ、永遠へ、このち
っぽけな平面、オレたちが生まれ死んで行く、丸い表面から逃れて、太
陽系にあるこの埃、銀河系にあるこの原子。
遠い未来、そこでの生活を思い描く。オレの荒っぽい推測は、不適当
なら無視してくれ。不死?19世紀のクロスリアリティで達成されたも
のは、23世紀には無視される。なぜなら、それはもはや必要でないか
らだ。逆エントロピーで宇宙を退化させる?ノラニズムと同時進行型デ
カールの技法で陳腐化したもの。ワイルドなサウンド?量子力学、ある
いは物質とエネルギーの変換サウンドを、どうネアンデルタール人に聞
かせる?オレたちは、みんな、ネアンデルタール人だった、今から10
万年前は。彼らがこれからなにをして、なにになって行くのか、ワイル
ドに予想することは、主要テーマになるかもしれない。
星は?そう、彼らは、星に憧れるかもしれない。
エピローグ
今は暗かった。「なん時、マックスおじさん?」
「4分たっただけ、ビリー」
流体の光は消えた。息をひそめて無言だった。なん千もの人々が息を
ひそめて無言だった。
おおゴッド!エレンがオレといっしょに、ここにいたら、オレたちの
ロケットが離陸するのを見れた。オレたちのロケット。しかし、オレよ
りもっと、あんたのものだった。あんたは、そのために死んでしまった。
ここの暗闇の中で、息をひそめて待ちながら、オレはその前に屈辱を
感じる、あんたの前に、人類とその未来の前に、人類がひとつになる前
に神がいたとしたら、神の前に。
(終わり)